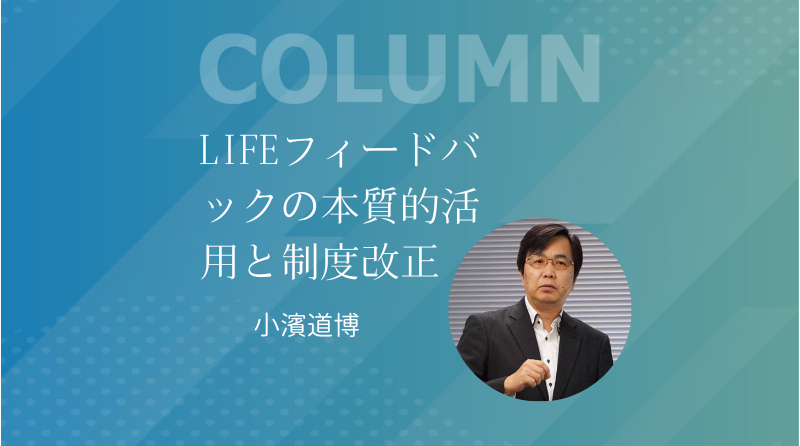LIFEの現状のシステムには問題も多いが、活用の仕方によって利用者の見方が変わり、職員のスキル向上ひいては介護業界全体のサービスの質の底上げにつながる。今後の制度改正との関係を交えながら、実践的なLIFEの活用についてお伝えしよう。
1,LIFEシステムの現状について
5月30日から提供された事業所フィードバックを見ると、現在は科学的介護推進体制加算の状況だけが分析されている状況だが、今後は各区分の集計グラフが提供されて行くだろう。
しかし、服薬や誤嚥性肺炎、褥瘡などの集計においては、中間月の送信データが、直近月の集計に反映されるなどによって、あり得ない数値になっている。そのため、LIFE関連の加算の算定要件であるPDCAサイクルへの活用については、「各事業所において、可能な範囲で御活用ください」と集計条件留意事項に記された。
ただし、PDCAサイクルへの活用を行わないと、今後の運営指導において加算の返還指導を受けることになるので注意が必要だ。PDCAサイクルへの活用とは、Plan(計画の策定)Do(サービスの提供)Check(LIFEへのデータ提供)Action(検討)のプロセスを廻し続けることである。LIFEに関連する全ての加算は、このプロセスを廻し続けるプロセスを評価する加算である。
また、LIFE活用のモデル事業が訪問サービスと居宅介護支援で2021年10月から実施され、その経過が報告された。次期介護報酬改正での加算創設を念頭においたものである。
(*関連記事:訪問系・ケアマネ事業所でのLIFE活用に向けモデル事業を実施へ)
このモデル事業は、さらに実施事業所数を増やして継続されている。また、24年度以降は、LIFEと医療データベースの連携も予定されている。それに伴って、23年度より新システムの開発が始まり、24年度から稼働の予定だ。つまり、現システムでのLIFEの運用は、あと2年を切っている。
そう考えると、集計に反映されるなどで、あり得ない数値になっている問題は、新システムでは修正されるとしても、現システムでは放置される可能性が高いとも言える。LIFEを活用する場合は、それらの問題があることを認識した上での活用が求められる。
2,LIFEは定期的な評価指標で評価することが神髄
現状では、単にLIFE加算を算定するだけの介護施設、事業所も多いのが現実だ。一年以上に渡って、フィードバック票が不十分であったために、致し方ない部分があることは理解できる。しかし、長い時間介護を提供する中、利用者への新たな気づきが減り、サービスを提供する時間だけ利用者に向き合っている施設や事業所も多い。これでは利用者の“正面”しか見えてこない。
LIFEの登場で、科学的介護提供体制加算を算定するために、少なくても半年に一度は、全利用者に対して、Barthel IndexでADLを評価し、DBD13で認知症ケアを測定し、BMIや口腔ケアを評価することになった。これまでは、これらの評価を定期的には行って来なかった事業者も多かった。すべての利用者に対して、定期的に一定の評価指標を用いて評価する習慣が付くことは、担当する職員のスキルを確実に向上させる。それは、施設全体のケアの質を向上させることに繋がっていく。長期スパンで見ると、介護業界全体の底上げに繋がるだろう。
また、担当者が、直接にLIFEに入力することで、新たな気づきが生まれる。今までは、利用者の正面しか見えていなかったものが、側面だったり、後ろから、上から、下から、いろいろな方向から利用者に向き合うこととなる。
例えば、利用者のAさん、Bさん、Cさんが居たとする。3人とも、非常に似たような状況にあるが、Aさんは、他の2人より若干、肌がカサついていることが気になっていたが、乾燥肌かなと思う程度であった。個人の評価数値をLIFEに入力するようになって、Aさんは、他の2人よりもBMIが低い事が判明。肌のかさつきの原因の一つが、低栄養状態であったことに気づき、栄養改善プログラムを入れることにした―。
このような事が、LIFEを導入して以降、起こっているだろう。職員のスキルの向上と、施設全体のケアの質を向上させることで、利用者満足が高まり、職員満足も高くなる。結果として、稼働率が高くなり、職員の定着率も良くなる。それこそが、LIFEを活用する意味であるし、神髄である。現時点でフィードバック票が不十分であっても、LIFEには、多くのプラス効果があると言うことだ。
3,ICT推進の意義は、職員が楽になること
LIFEを活用し、介護記録ソフトを導入するなどのICT化を進めることで、職員が、情報を時系列に沿って読み解くことができ、家族などに根拠をもって語ることができるようになる。しかし、ICTの活用は目的では無く、あくまでも手段であって、その先にケアの品質の向上、職員の生産性の向上があることを理解しなければならない。
例えば、オンライン研修の普及とビデオによる後日配信によって、職員への時間の拘束が無くなり研鑽の自由度が増した。平日午後からの集合研修に、夜勤者が眠い目をこすって参加する必要がなくなっている。これだけでも効率化は、確実に実現出来ている。職員が、楽になった、仕事がしやすくなったという実感があって初めてICT化は成功と言える。職員に選ばれなければ無用の長物であり、逆に職員の離職原因になるのだ。
LIFEについても、定期的に情報を提供することで、周期的に栄養、リハ、排泄、褥瘡、自立支援などの評価を介護現場、専門職が協働で行う事は良いことである。LIFE導入時のスタンスは、やってみて、ダメなら止めれば良いという程度でスタートすべきだ。結果として、多職種間のコミュニケーションがよくなり、共通のルールの元で情報共有がスムーズになり、ケアに反映できるといったメリットを実感することとなる。そのためには、上からの押しつけでは無く、職員の理解が重要となる。
4,LIFEのフィードバック票の読み方
そうはいっても、フィードバック票の読み方や活用の仕方が分からないという方も多いだろう。フィードバック票の読み方のポイントは、BMIが何点とか、ADLが何点とか、ピンポイントで数字を見るのでは無く、複数の評価指標を重ねて、トータルで見ていくことが重要だ。
例えば、ADLの点数が横ばい、または低下で、リハビリの効果が出ていない。このポイントだけ見ると、成果を上げるために、リハビリ・プログラムの見直しという対策になる。しかし、同時並行で、BMIを見ると、19以下で低栄養に近い。さらに食事摂取量の項目を見ると、平均よりかなり低いとする。この利用者は、食事量が少なく、低栄養状態で、体力も筋力も衰えているから、リハビリの成果が出にくいと判断できる。
この場合に必要なのは、リハビリ・プログラムの見直しでは無く、食事量を増やして頂く方法を皆で検討して、栄養改善を行うことが先決となる。事業所フィードバック票であれば、他の項目は、全国平均より優れているが、口腔ケアの項目では、全国平均の倍以上、歯、入れ歯が汚れている割合が高かった。口腔ケアに問題がある場合の考えられるリスクは、誤嚥性肺炎である。誤嚥性肺炎の発生割合は、全国平均の5倍であった。当施設の緊急の課題は、口腔ケアの早急な見直しであることが明らかに判明した。このように、多数提供される項目別の情報を、関連付けて読み取って行くことで、抱える問題や現状を把握できるようになる。
こういった対応には経験の積み重ねが重要で、それがLIFEに早期に取り組む理由だ。今はまだ、利用者個人別のフィードバック票の提供は始まっていない。事業所フィードバック票だけである、今のうちに、フィードバック票の読み方に慣れて頂き、来るべき個人別のフィードバック票の提供に備えて頂きたい。