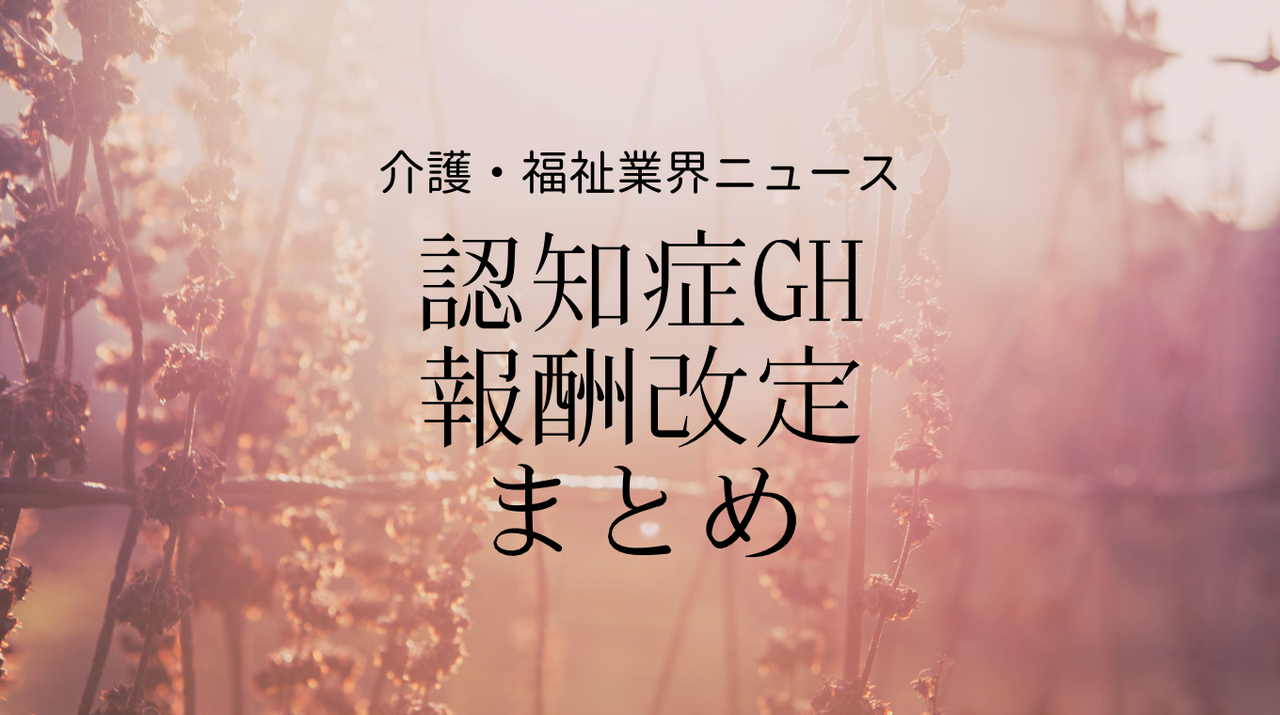2021年度介護報酬改定に向けて、全22回に渡り議論されてきた介護給付費分科会。その審議報告が、2020年12月23日に厚労省のホームページで公表されました。本記事では【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】に関する「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」の内容について、加算や報酬に関わる詳細部分をまとめて整理していきます。
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
関連記事:審議報告案、取りまとめへ 2021年度介護報酬改定に向けた年内の議論が終了 厚労省・分科会(第197回分科会)
認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し
1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされているグループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、以下に示す一定の算定要件を満たした場合のみ、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとする見直しが行われます。
<算定要件>
利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていること。
人員配置の緩和については、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする点も明記されています。併せて、3ユニット2人夜勤とする場合の新たな報酬設定も行われます。

看取り介護加算の見直し・新たな評価区分の創設
グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下2点の見直しが行われます。
①看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
②算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があることを踏まえ、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。

医療連携体制加算の要件を見直し
医療連携体制加算について、医療ニーズのある入居者への対応を適切に評価し、医療ニーズのある者の積極的な受入れを促進する観点から以下の見直しが行われます。
・医療連携体制加算Ⅱ・Ⅲの医療的ケアが必要な者の受入実績要件(前12月間において喀痰吸引又は経腸栄養が行われている者が1人以上)について、喀痰吸引・経腸栄養に加えて、医療ニーズへの対応状況や内容、負担を踏まえ、他の医療的ケアを追加する。

緊急時の宿泊ニーズへの対応に関する要件緩和
利用者の状況や家族等の事情により、ケアマネジャーが緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする「定員を超えての短期利用の受入れ(緊急時短期利用)」について、以下3点の見直しが行われます。
①「1事業所1名まで」とされている受入人数の要件について、利用者へのサービスがユニット単位で実施されていることを踏まえ、「1ユニット1名まで」とする。
②「7日以内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」とする。
③「個室」とされている利用可能な部屋の要件について、「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認めることとする。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し・処遇改善加算Ⅳ・Ⅴの廃止
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである「職場環境等要件」について、介護事業者による職場環境改善の取り組みをより実効性が高いものとする観点から、以下2点の見直しが行われます。
①職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
・ 職員の新規採用や定着促進に資する取組
・ 職員のキャリアアップに資する取組
・ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
・ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・ 生産性の向上につながる取組
・ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、
職員の勤務継続に資する取組
②職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。

また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止へ。その際に、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。
事務局からは、「介護職員処遇改善加算取得促進事業」において、上位区分への引き上げを強力に進める予定です。
介護職員等特定処遇改善加算の見直し
スキル・経験のある職員の処遇改善を目的とした介護職員等特定処遇改善加算について、「リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行う」といった趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、以下の見直しが行われます。
・平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする。
つまり、「2倍以上」という制限がなくなり、より柔軟な配分が可能となります。

口腔機能向上の取り組み充実に向けた新たな加算の創設・現行の口腔機能向上加算に新区分
利用者の口腔機能の低下を防ぐことなどを目的に、介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算がされます。その目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う必要があります。

栄養ケア・マネジメントの充実に向けた新たな加算の創設
栄養改善の取組を進める観点から、以下の見直しが行われます。
・管理栄養士(外部との連携を含む)が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する新たな加算を創設する。
サービス提供体制強化加算の見直し
サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、各サービスにおいて、財政中立を念頭とした見直しが実施されます。以下には「グループホーム」に関わる記載のみを抜粋しています。
①介護福祉士割合や介護職員等の勤続年数が上昇・延伸していることを踏まえ、各サービス(訪問看護及び訪問リハビリテーションを除く)について、より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。
②勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する。

認知症専門ケア加算の見直し
認知症専門ケア加算について、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、人員配置要件に関する見直しが行われます。
・認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について、認知症ケアに関する専門性の高い看護師(認知症看護認定看護師、老人看護専門看護師、精神看護専門看護師及び精神科認定看護師)を、加算の配置要件の対象に加える。

なお、上記の専門研修について、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行うことも、審議報告案に盛り込まれています。
生活機能向上連携加算の見直し
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、介護事業でのICTの活用も審議報告案に含められています。生活機能向上連携加算もこれに該当しており、算定率が低い状況を踏まえたうえで、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下2点の見直しが行われます。
①訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。
②外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

今後のスケジュール
2020年12月18日の分科会にて年内の議論は終了。12月23日の「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」をもとに、年明けから諮問・答申へと進み、新加算の単位数や見直し後の単位数など、詳細が明らかになっていきます。
引用:第193回社保審・介護給付費分科会「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の報酬・基準について」、第196回社保審・介護給付費分科会「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の報酬・基準について②」、第197回社保審・介護給付費分科会「審議報告案にかかる参考資料(令和2年12月18日)」より