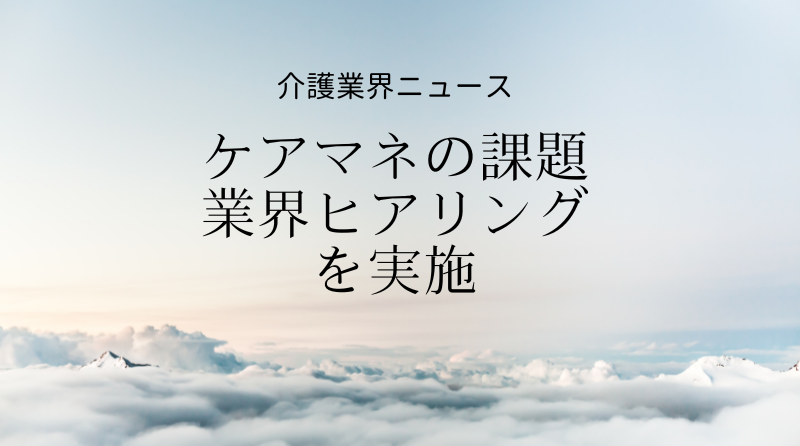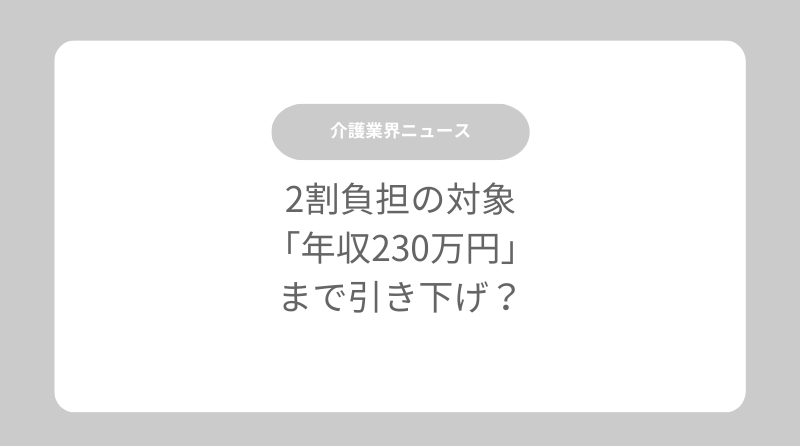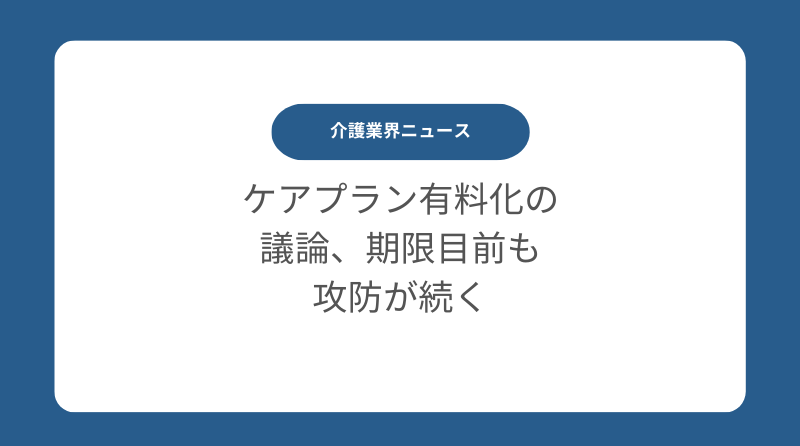厚生労働省老健局は5月9日、「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」の第2回会合を開催しました。この日は、事業者やその団体からヒアリングが実施されています。
介護支援専門員実務研修受講要件の緩和や、更新研修の見直しなどについて意見が交わされたほか、居宅介護支援事業所の管理者を主任介護支援専門員とする要件を撤廃するよう求める意見もありました。
ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会とは?4つの議題と顔ぶれ
「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」は、人口構成の変動や社会情勢の変化を受けて、ケアマネジャーの
- 業務の在り方
- 人材確保・定着に向けた方策
- 法定研修の在り方
- ケアマネジメントの質の向上に向けた取り組み
について包括的な検討を進める場として、2024年度に老健局が設置した検討会です。
メンバーは、相談支援に関わる事業者や研究者、専門職団体(日本介護支援専門員協会、日本医師会など)、利用者団体等で構成されています。
第2回会合では、居宅介護支援やその事業に関わるメンバーからヒアリングが行われました。
ヒアリングの参加メンバーとその主張
検討会メンバーからのヒアリングに対して意見陳述したメンバーは、事業者団体など5団体の代表者です。
ケアマネジャーがやりがいに感じていることや悩み、島しょ部での連携の実情、人材確保のための取り組みなど幅広いテーマでプレゼンが行われました。
このうち、人材確保に深くかかわる介護支援専門員実務研修の受講要件や有効期間の更新のための研修について明確に言及したのは、『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会理事の板井佑介氏と全国介護事業者連盟理事長の斉藤正行氏です。
その主張について、主な内容をまとめます。
実務研修受講要件や更新研修の見直しに関する意見
| 発言者 | 介護支援専門員実務研修 受講試験の受講要件について |
更新研修等について |
| 「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会・板井佑介理事 | ・職種を特定した年数制限は不要。実務経験期間は3年程度に緩和すべき ・複数の資格(国家資格、認定資格等)を持っている場合、受験可能期間を短縮すべき |
・研修は必要の立場 ・期間内選択制(単位制)として知識を習得する時間の余裕を作るべき 一時的に離職していた者、失効者に対しては Eラーニング等で随時研修が受けられる仕組みを整えるべき |
| 全国介護事業者連盟・斉藤正行理事長 | ・介護福祉士等の有資格者の実務経験年数について柔軟化を図ること、介護職員初任者研修取得者で喀痰吸引等研修の受講者等に限定し、一定の実務経験年数による受講要件の追加等を検討してほしい ・安易な廃止や簡素化については慎重な議論が必要 |
・安易な廃止や簡素化ということについては慎重姿勢 ・研修を実施する講師に対する評価制度の導入と講師へのフィードバックの実施の検討を求める ・高評価を受けた講師を活用した全国共通のオンライン研修の開催、アーカイブ化による動画研修の導入に向けた検討を求める ・研修から事例検討の時間を減らし、最新の制度改正、報酬改定への対応等を趣旨としたカリキュラムへの見直すよう検討を求める ・全国的な法定研修受講に対する補助事業創設の検討を求める |
現場従事者らから負担の大きさを指摘する声がある更新研修については、研修の実施方法や内容を見直すべきという意見は出ているものの、研修の実施そのものを無くすべきという意見はありませんでした。
特に介護事業者連盟の斉藤正行代表は、「安易な廃止や簡素化ということについては慎重姿勢」との立場を明示しており、「研修自体の中身を、意義ある研修にしていくことが重要だと主張しています。
管理者の主任ケアマネ要件「撤廃」を求める意見も
民介協の板井佑介理事はこの日、提出資料の中で、居宅介護支援事業所の管理者を主任介護支援専門員とする要件の撤廃も訴えています。
これは、主任介護支援専門員の専門性(は地域との関係性、スーパービジョン)と、事業所の管理者に求められる専門性(労務管理や事業所運営管理などチームマネジメントに関わるスキル)が異なることなどを根拠とするものです。
この着眼点については、検討会の構成員からも「すごく重要」(東京経済大学現代法学部准教授・常森裕介構成員)との認識が示されました。
なお、介事連の斉藤理事長も居宅介護支援の管理業務と主任ケアマネジャーの役割に「ずれが生じている」と指摘している点は同様ですが、「専門性を有する主任ケアマネジャーの配置には意義がある」とコメントしています。
次回の同検討会会合は6月に予定されています。
*初回会合のレポート記事:介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務範囲明確化や法定研修の在り方について集中議論―専門の検討会がスタート