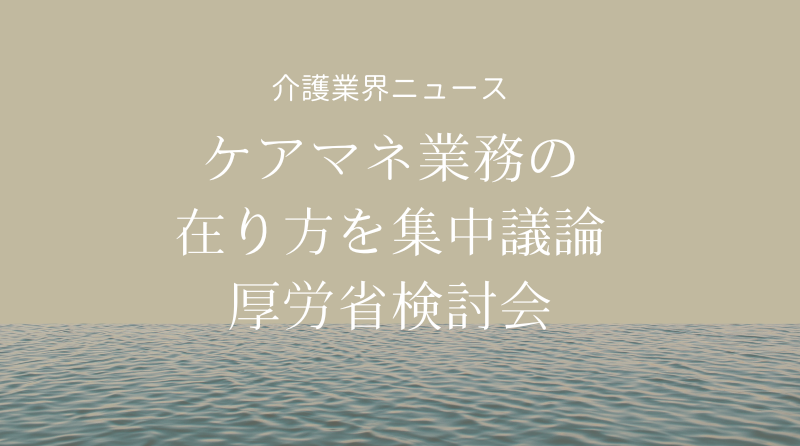厚生労働省は介護支援専門員(ケアマネジャー)の確保・定着策や役割、業務の範囲等について集中的に話し合う検討会を立ち上げ、4月15日に初会合を開きました。
資格試験の受験者数の増加策や研修の受講費用の負担軽減も検討事項として扱われています。
意見交換では、居宅介護支援事業所の代表として参加している構成員が「ケアマネジャーが本来業務として捉えていることと、周囲からの期待に大きな乖離が生じている」と訴える一幕もありました。
ケアマネジャーによる本来業務への自己認識と周囲からの期待に乖離?
介護支援専門員の業務については、2024年度介護報酬改定でも業務効率化を図ることで担当件数の引き上げたり、介護保険外の制度に関する知識の充実を促したりする施策が盛り込まれています。専門性を広く発揮するよう期待が高まり続ける一方で、介護職員を対象とした処遇改善施策などの影響によって近年は人材不足が指摘されています。
2024年1月にまとまった「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」でも、「介護支援専門員の業務内容について実態把握を進めるとともに、業務効率化や働きやすい環境の整備、質の向上を図るために必要な対応について引き続き検討していくべき」 と指摘されていました。
今回立ち上げられた「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」はまさにこうした対応を検討するための場です。
初回の会合で厚労省は検討の範囲を以下の通り整理しています。
- ケアマネジャーの業務の在り方について
- 人材確保・定着に向けた方策について
- 法定研修の在り方について
- ケアマネジメントの質の向上に向けた取り組みの促進
検討会の構成員(主に大学教授や専門職団体の代表で構成)のうち、青い鳥合同会社の相田里香代表社員は唯一、事業者の立場を代表するメンバーです。その相田構成員は1について、「ケアマネジャーが本来業務として捉えていることと、利用者、家族、他職種、多機関が求めている役割に大きな乖離が生じている」などとし、役割を明確化することの重要性を指摘しました。また、現場からの負担感が指摘される法定研修については更新までの5年間に必要な単位数の履修を各自のペースで進める方法を提案しました。
「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」今後のスケジュール
検討会は今後、秋ごろにかけて月に1回程度開催される予定です。
次回会合は5月9日、事業者団体、現場の実践者等からのヒアリングが予定されています。
現段階で示されているスケジュール案は以下の通りです。
| 日程 | 議事 | |
| 第1回(今回) | 4月15日 | ケアマネジメントに係る現状・課題 |
| 第2回 | 5月9日 | 構成員プレゼン・ヒアリング ※事業者団体、現場の実践者等を予定 |
| 第3回 | 6月目途 | ケアマネジメントの質の向上 及び人材確保に向けた方策の検討 |
| 第4回 | 7月目途 | (議論を踏まえて議事内容を検討) |
※第5回以降の進め方は、第4回までの議論を踏まえて検討。
(【表】「第1回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」資料3を基に作成)
*関連リンク:第1回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会