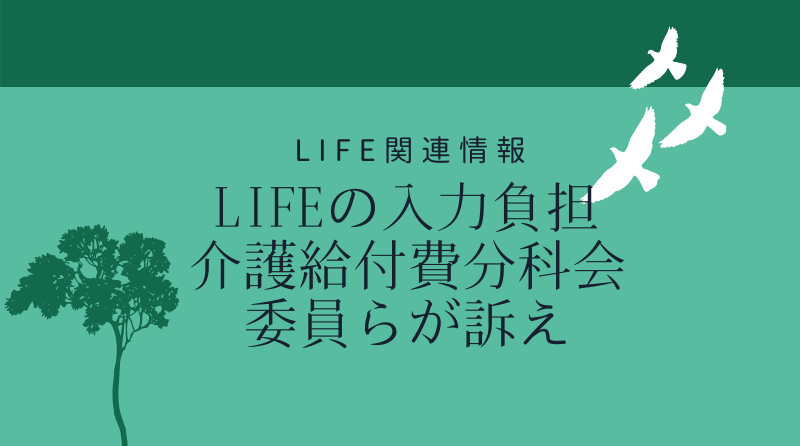2021年度の介護報酬改定の効果や、それにまつわる課題を把握するべく厚生労働省が動き出しています。LIFE(科学的介護情報システム)の導入効果や現状の課題について把握するための調査研究では、介護事業所を対象としたアンケートが11月5日までの間に実施される予定です。そこで得られた結果は2024年度介護報酬改定の検討材料となります。
調査について最終的な検討を行った9月27日の社会保障審議会・介護給付費分科会では、LIFEにまつわり顕在化してきた課題として、データ入力にかかる負担が大きく「ほとんどの施設で時間外労働が強いられている」といった状況や実地指導への不安の訴えがありました。
LIFE実態調査の概要とこれまでの議論
2021年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査のうち、改定の目玉と受け止められているLIFEの活用については、
(1)事業所の取組状況とその効果・課題の把握
(2) 訪問系サービスや居宅介護支援事業所での活用可能性の検証
の大きく2つの目的が定められています。
まず、(1)の導入効果や課題についての調査概要は以下の通りです。
【調査対象】
・LIFE に関連した加算を算定している施設・事業所(約5,000カ所)
・2021年 9 月までに LIFEシステムへの登録がない事業所・施設(LIFE へのデータ登録が 1,000 件以上あるサービスの中から抽出。約2,500箇所)
※いずれも2021年度介護報酬改定でLIFEへのデータ提出やそのフィードバックの活用が算定要件となっているサービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション)
【調査方法】
・対象事業所それぞれにアンケートを実施するほか、「効果的にLIFEを活用している」事業所・施設と「LIFEの活用に介して課題を感じている」事業所・施設にそれぞれヒアリング。
また、(2)の調査概要は以下の通りです。
【調査対象】
・訪問介護、訪問看護、居宅介護支援各事業所(約10カ所ずつ)
【調査方法】
・モデル事業所を募集し、LIFE へのデータ登録(科学的介護推進体制加算の項目)を実施し、フィードバック票の提供と、調査検討組織による「技術的助言」等を行った上で、ケアの質の向上に向けた取り組みを実施してもらう。
※居宅介護支援事業所は、通所介護などのサービスでLIFEにデータ提出を行っている利用者を担当するケアマネジャーがいる事業所が対象
・その後アンケートやヒアリング調査で活用の具体的なユースケースや課題を把握する。
*関連記事:訪問系・ケアマネ事業所でのLIFE活用に向けモデル事業を実施へ
このほかに、(1)(2)にまたがって介護保険総合データベース(介護給付費明細書や要介護認定などの情報)やLIFEへの登録データの分析も行われ、その結果として得られた知見が公開され、介護給付費検分科会でも共有されます。
介護給付費分科会に先立って開かれた介護報酬改定検証・研究委員会の議論では、同調査で介護事業所の請求ソフトの導入やICT化の状況を把握する必要性などが指摘されていました。
こうした意見を受けて介護給付費分科会で示された調査票案は、質問項目が一部変更されています。


【画像】第203回社会保障審議会介護給付費分科会資料より調査票案の一部を抜粋(訪問系サービス事業所票)
なお、21年度改定の影響や課題の調査は、同時期に「介護医療院におけるサービス提供実態」「文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減」「福祉用具貸与価格の適正化」についても実施されます。
課題は入力負担作業の負担、実地指導への不安も業界団体が表明
介護給付費分科会では、事業者を代表する委員らからLIFEの入力負担を訴える意見が目立ちました。
小泉立志委員は、自らが所属する全国老人福祉施設協議会の会員にLIFEの導入状況などを調査し、その結果で、会員の介護福祉施設等が主に下記を課題に感じていたことが判明したと報告しました。
・手入力でLIFEへの入力作業の負担が大きい
・LIFEへ入力するための体制を整えるのが難しい
・LIFE記入項目に対する実地指導への不安
・LIFEを活用するイメージがわかない
・(介護記録)ソフトの入力からLIFEへのデータ転送の負担が大きい
(※「LIFEの活用において『課題』だと感じている点」上位5項目。全国老施協のLIFE導入状況調査より)
また、こうした状況を踏まえて、報酬改定の効果検証では現場の課題の解決につながる調査を実施するよう求めました。
この点については、全国老施協と同じ調査票を使って調査を実施した、全国老人保健施設協会の東憲太郎委員も言及しています。
具体的には、
・導入している介護記録ソフトがLIFEに対応している場合であってもデータ提出に大部分、及び一部において手入力が必要と回答した施設が併せて56.1%を占め、老人保健施設でも同様に、半数以上の施設で手入力が必要な状況になっていること
・老施協の調査結果によると、LIFE対応加算のデータ提出状況について、「業務時間内で対応できる」と回答した施設は37.9%に留まること
・業務時間内で対応できると回答したの老健施設では14.5%だったこと
などを挙げ、加算算定に当たって「ほとんどの施設で時間外労働を強いられており、(ICT等を利用することで現場に大きな負担をかけずにデータ収集するという)当初目指したものとはかけ離れている状況」だと訴え、厚労相に丁寧な対応を要求しました。
今後のフィードバックの在り方は、専門家「改善は5年くらいかけて」
また、訪問系サービスや居宅介護支援事業所を対象とする調査の目的は、モデル事業所にLIFE活用に関する「技術的助言」の提供などを通じて、2024年度介護報酬改定での加算創設等の運用に向けた具体的なユースケースの検討を行うことにあります。ここでは、実運用の中で活用されるフィードバック帳票の在り方も検討事項になります。
一方で、新設された加算でLIFEの活用が要件化されている施設や通所系サービスでも、事業所に提供されているのは全国からの提出データの集計結果であり、「本来のフィードバックはなされていない状況」(日本医師会・江澤和彦委員)です。
今後、フィードバックデータをケアの向上につなげられるような形で示していくには、蓄積されていく各データを「ケアに紐づけていかないと難しい」「そのための下地を、今は作って行く必要がある」(江澤委員)といった考え方が示されました。
議論の最後に介護報酬改定検証・研究委員会委員長を務める松田晋哉委員(産業医科大教授)は、今後、LIFEのデータを使ったフィードバックについて、集まったデータを分析し、その結果を公表し、それに対する意見を求め、仕組みに反映させていくという一連の取り組みを、「5年くらいかけてやっていかなければいけない」との認識を示しました。
その上で、「良い制度をつくるためには広くデータを集める必要がある」として各団体に調査への協力を求めています。