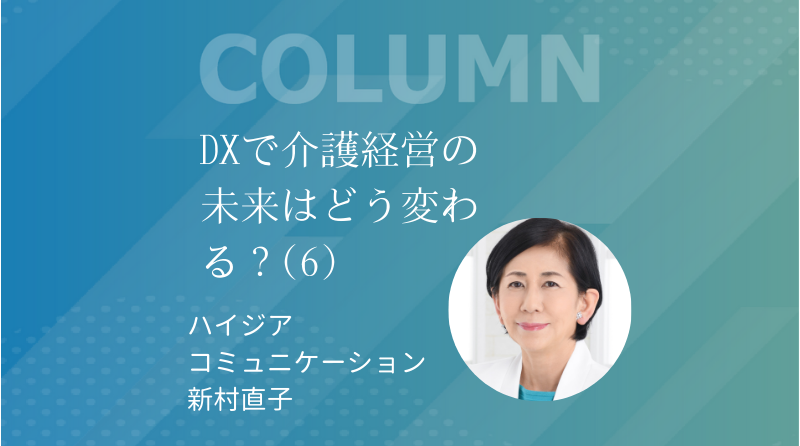北九州市は全国に先駆け、介護ロボット等の導入を前提とした先進的介護のモデルづくりに動き、その集大成として「北九州モデル」を完成させました。モデルの活用により、職員の全業務時間を35%削減できたほか、利用者さんとの会話など直接介護の時間を2割増やすなどサービスの質向上も実証しています。本連載の最終回となる今回は、北九州市介護ロボット等導入支援・普及促進センター長の樽本洋平さんに取材。前半では同モデルの実証と成果を紹介しつつ、後半は実践編として、介護DXで失敗しないための4つのポイントについて解説します。
政令指定都市で最も高齢化率が高い北九州市の挑戦
 【画像】樽本洋平氏
【画像】樽本洋平氏
北九州市は2016年から介護ロボット等を活用した先進的介護の実現に向け、実証事業に取り組んできました。その理由は明快。15年における高齢化率は実に29.3%と、政令指定都市の中でも最も高齢化が進んでいたからです。
この課題に向き合うため規制緩和の突破口である国家戦略特区制度の認定を受け、同市は「高齢者の活躍や介護サービスの充実による人口減少・高齢化社会への対応」に取り組み始めます。このうちのテーマの一つが「介護ロボット等を活用した先進的介護の実証実装」で、特区を活用した先進的介護の実証実装は全国で初の試みでした。
現在、北九州市介護ロボット等導入支援・普及促進センターでセンター長を務める樽本さんは16年の事業スタート時点から、理学療法士のバックグラウンドを生かし、事業に参画してきました。
北九州モデルの構築・普及までの歩み
2016 介護作業の課題の洗い出し、見える化
2017 介護ロボット等の導入・実証
2018 北九州モデルの仮説づくり
2019 北九州モデルの実証
2020 北九州モデルの普及
「スタート時は、まず課題を洗い出そうということで、直接介護と間接介護の切り分けや、ICT化が可能な作業を見極め、可視化する作業を進めました。その上で、17年から、5つの施設(いずれも特養)を公募で決め、複数の介護ロボット・ICT機器を各施設に導入して、どのような効果が出るのか、どうしたら効果を出しやすいのか、実証を行いました」。
翌18年はこれを踏まえた北九州モデルの仮説を作り、19年には仮説の検証のために、1つのユニット型特養を選定。見守り(映像による予測型見守りシステム/バイタルセンサーの2種、全室に各1台)・記録(介護ソフト、1ユニットに1セット・端末は1人1台)・情報共有(インカム、施設全体で10台)・移乗(移乗介助アシストロボット(2ユニットに1台)・浴室リフト(4ユニットに3台))の介護ロボット・ICT機器の導入のみならず、高齢職員の配置見直し、間接介護のアウトソーシングなどまでフルパッケージ化したモデルを実証した上で、生産性を高める働き方と弾力的な人員配置を包含する業務改善方法「北九州モデル」を確立したのです。

【画像】北九州モデルのイメージ:資料出典(北九州市)を基に編集部で作成
「業務仕分け」「ロボット導入」「業務オペレーション整理」の3Stepが特徴
北九州モデルでは一体どんな手順で介護ロボット等を導入していくのでしょうか。樽本さんは、その実践プロセスとして、「Step1:業務仕分け」、「Step2:ICT・介護ロボット等の導入」、「Step3:業務オペレーションの整理」という3段階のステップを踏むことが大きな特徴だと説明します。
「Step1では、準備を含めて1カ月ほどかけて介護施設の負担を見える化し、直接介護と間接介護などを分解し、ICT化できる攻めどころを探します。Step2では、1を踏まえ設定された目標に対し、どんな利用者・業務に機器を選定するのかなどを検討。さらにStep3では、誰が何を行うのか、業務オペレーションの見直しについて、アウトソーシングも含めてアドバイスしていきます。Step2・3で3カ月ほどかけるのを目安としていますが、施設によっては半年かかる場合もあります」。
北九州モデルを活用することで介護の様々な業務を効率化させ、職員の身体的・精神的・時間的な“ゆとり”を生み出し、介護の質の向上と職場環境の改善を目指すことが大きな目標。“時間を生み出す介護”の実現が、このモデルの最大のメリットだと言います。
業務時間は35%削減、2.87対1介護を実現
実際、19年の実証で、地域密着型の特養29床とショートステイ10床の39床でまるまる2日、全職員の時間の使い方の変化を検証したところ、業務時間が総量で35%削減できました。それまで、2対1だった人員配置は、2.87対1になるなど、およそ1.4倍の生産性向上効果も。一方で、利用者の生活の質(QOL)、精神的健康状態には変化がなく、ケアの質は低下しなかったことも確認されています。
「映像による見守りだけではなく、コストはかかりますが、心拍数や呼吸数などバイタルデータをモニターできる機器も併用することで、特に、夜勤帯の人による見守り時間は約62%と大幅に短縮できました。間接介護を削減できた分、直接介護の時間を2割程増やせています。職員の身体的精神的負担を減らしつつ、安全性やコミュニケーションの観点から介護の質を向上できたと評価しています」。

 【画像出典】:「北九州モデル導入・実践ガイドライン」(北九州市)
【画像出典】:「北九州モデル導入・実践ガイドライン」(北九州市)
記録時間はおよそ半減に。スマホで記録できるタイプの介護ソフトを導入し、利用者さんと話しながら、見守りもしつつ、記録もできる、いわゆる“ながら記録”ができるようになったためです。
導入した施設からは、「業務が軽減したことで気持ちが利用者のケアに集中できて、1日を丁寧に過ごすことができるようになったという職員が増えた」、「新しいことに取り組んだことで現場の士気が上がり、チームワークが向上した」といった声が届いています。
実践編:介護DXで失敗しない4つのチェックポイントとは?
こうした実証を踏まえ、21年4月には北九州モデルの普及を目的に、同センターが開設されました。自らもアドバイザーとして、介護ロボット等の導入支援に奔走する樽本さんですが、様々な支援事例を通して気づいた、介護DXを失敗させないためのチェックポイントがあると指摘します。ここからは実践編として、4つのチェックポイントを紹介していきます。
【1】「ゴール設定の共有」で生まれた時間を無駄にしない
樽本さんがDXの推進で最も重要視しているのが、「ゴール設定の共有」です。介護ロボットを導入しても、それによって生まれた時間を何に使いたいのか、そこに明確な目標を定めておかないと、いつの間にか時間に追われる日々に戻っていたということになりかねないからです。
「例えば、従来は業務時間外で行っていた研修を時間内に行う、利用者さんとしっかり話す時間を増やす、入浴時間を長くする等、導入後のゴールイメージを明確にしておいて、せっかく“生まれた時間”を無駄にしないようにする意識が重要です」と樽本さん。
ゴールを決める際は、経営陣の問題意識を踏まえ、施設としてありたい姿や目標を明確にしながら、解決策を検討していくのも大切。経営陣だけでゴールを決めてしまうのはもちろんNG。現場の多職種スタッフを含めて、全員が目指すべきゴールについて考え、意思統一を図っておくことが大切です。
【2】リーダーの選定、チームづくりでつまずかない
プロジェクトを引っ張る人材の選定も重要。前回のシルヴァーウイングの事例にもあったように、ロボット等の導入にあたり、現場も含めて、プロジェクトチームや委員会を立ち上げる例も多いでしょう。そのチームで誰をリーダーに据えるのか、この人選を間違えると、いざ動き始めてもなかなか現場をまとめられないという事態に陥ることも。
「例えば、主任さんクラスだと、その方が所属するチームのことはわかるけれど、別のチームや別の部署のことまで把握できていないことも多いもの。リーダーとしては、もう一段上の管理職クラスで、施設全体を俯瞰して見ることができるポジションの方がベター」と樽本さん。
かといって、管理職クラスばかりで固めると現場の目線が抜け落ちてしまう可能性も。若手や外部のコンサルタントなどの客観的な目線を入れることも忘れずに。また、現場には介護士、看護師、理学療法士、作業療法士など様々な職種の方がいますが、初期段階からこうした多職種の方々に漏れなくメンバーになってもらうことで、業務の仕分けや、業務オペレーションの整理が効率的に進みます。
【3】施設ハード・インフラ・利用者との適合など、機器の選定は慎重に
介護ロボット等の導入の“要”とも言えるのが、機種の選定。意外に見過ごされがちなのが、ネットワークインフラの調整を含め、施設のハード面と機器とのマッチングが適切であるかどうかという点です。例えば、対象となる機器は施設のフロアや壁等と適合するのか、Wi-Fiは適切に増強できるのか…といった細かい検討は、施設内の職員だけでは判断しにくいもの。メーカー、コンサルタントなど外部の専門家のアドバイスを受けつつ検討していくことも必要です。
利用者さんと機器とのマッチングも熟慮しましょう。把握すべきなのは、機器の活用を想定している利用者さんにはそもそもどんな身体機能、精神機能があり、その方の残存能力に対して機器はどういう効果をもたらすのか、ということ。「例えば移乗支援機器で、座っている状態から立つことを支援するタイプの機器があります。利用者の方の身体機能をうまく評価できていないと、本来はある程度自立して立てる機能があるのに、移乗支援機器を使ったばかりに、その方の自立の機会を奪ってしまう可能性もあります」。
補助金が入ったからと、慌てて機器を購入するのもNG。いざ導入してみたら、ハイスペック過ぎてその施設には使いこなせず、結局、倉庫にしまい込むという例も。「補助金があるから考えよう、では遅いのです。最近は、機器を比較検討できる展示会場や、公的機関での機器の無料貸し出し等もあるので、機器選定にはしっかり時間をかけることをお勧めします」と樽本さん。
 北九州市介護ロボット等導入支援・普及促進センターの展示エリア
北九州市介護ロボット等導入支援・普及促進センターの展示エリア
【4】人材教育は段階を踏んできめ細やかに
最後のチェックポイントが人材教育。同センターでは、「外部講習」「メーカーからの操作指導」「施設内研修」の3本柱で研修を行っているそう。外部講習で活用しているのが、北九州市が介護ロボット等の活用を推進する専門人材の育成を目的に開催している「介護ロボットマスター育成講習」です。
講習内容は、「入門編」「実践編」「管理編」の3コース。立場や役職で果たすべき役割は異なってくるので、それぞれに合わせて受講コースを選べるようになっています。入門編では機器等を活用する意義の理解及び基本的な知識の習得を目指し、実践編では適切な機器選定及び効果的に活用する知識を学ぶとともに、見守りや移乗支援など分野別に実機を使った実習まで行います。管理編では機器等の導入・運用を管理し、職場全体の作業効率を高めるノウハウを学べるようになっています。実践編、管理編を修了した人には、修了証も交付されます。
「そもそも介護ロボットを知らない人に関心を持ってもらうのは大変なこと。トップのリーダーシップはもちろん重要ですが、一人よがりに進めるのではなく、様々な外部講習を活用して現場スタッフの理解を促し、時にはチームを組んで介護ロボット・ICT機器に触れる展示会場等に視察に行くなど、様々な方法で現場のスタッフを巻き込み、目線を揃えて士気を高めていくことが大切です」と樽本さんはアドバイスします。
樽本洋平(たるもと・ようへい)
北九州市介護ロボット等導入支援・普及促進センター センター長
九州介護ロボット開発・実証・普及促進センター センター長
理学療法士、所属:麻生教育サービス株式会社
1979年、福岡県生まれ。理学療法士として医療法人に勤務し、急性期、回復期、在宅でのリハビリテーションに従事した後、2016年より公益財団法人北九州産業学術推進機構にて介護ロボットの導入支援、開発支援・実証等(国家戦略特区事業)に携わる。2021年4月より現職。