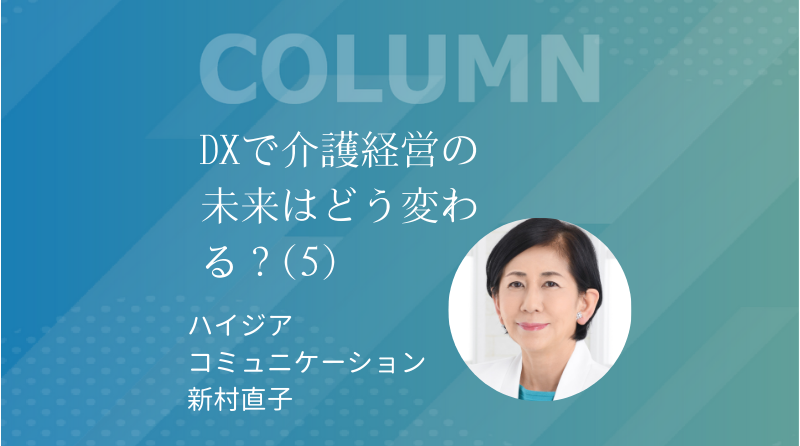小池百合子東京都知事、英国労働党のダン・ジャービス氏、米国保健省長官(当時)のトーマス・プライス氏・・・・。国内外の著名政治家がこぞって視察に訪れ、英国の日刊新聞「The Times」も取材に訪れた特別養護老人ホームが東京の下町・新富町にあります。社会福祉法人シルヴァーウイングが運営する「新とみ」がそれ。職員の負担軽減を目的に30種類以上もの介護ロボットを導入、新しい介護の在り方を追求し続けています。理事長の石川公也さんに介護ロボットの活用法、今後のビジョンについて伺いました。
政治家、海外メディアが視察に訪れる特養とは?

【画像】石川公也氏
社会福祉法人シルヴァーウイングは、東京都中央区新富町の特養「新とみ」のほか、練馬区の特養「みさよはうす土支田」、練馬若年性認知症サポートセンター、新宿区の特養「みさよはうす富久」など計5つの施設を運営、常勤116名、非常勤71名のスタッフを抱えています。
前述の名だたる政治家や海外メディアが視察に訪れる目的は一つ。シルヴァーウイングが採用している介護ロボットの使用実態を知ることです。実際、同法人では移乗支援を目的とした装着型の「HAL」(CYBERDYNE)や「マッスルスーツ」(イノフィス)、移動支援を目的とした搭乗型の「スカラモービル」(アルバジャパン)、リハビリ支援の免荷式リフト「POPO」(レイマック)、コミュニケーション支援の「PALRO」(富士ソフト)、「Pepper」(ソフトバンク)など、実に幅広い領域で30種類以上の介護ロボットを活用しています。
理事長を務める石川公也さんが介護ロボットの導入推進に舵を切ったのは2013年。東京都産業労働局「課題解決型雇用環境整備事業」に採択されたことがきっかけでした。この事業で、まずは介護記録の電子化に着手。リアルタイムでバイタル情報、介護サービスの記録等を共有できるようにして、朝、夕の申し送り等の情報も社内メールで全職員に周知するようにしました。職員にとっては、記録などの間接業務に労働時間の約3割を割いていましたが、この部分の業務負担を合理化できたと言います。
移乗支援ロボット導入で、腰痛で休職する職員がゼロに
「介護ロボットには、大きく分けて、排泄・移乗・見守りなどの業務負担を軽減するタイプ、利用者の歩行など自立を支援するタイプ、利用者のコミュニケーションや癒しに役立つタイプの3つがありますが、当法人ではこれらを併用しながら、新しい介護の在り方を模索してきました」と石川さん。
例えば、移乗支援型ロボットの「HAL腰タイプ」は装着しながらでも比較的動きやすいので日中の排泄介助や体位交換などに活用し、腰の負担を軽減する効果に特化したハイパワーの「マッスルスーツ」は主に夜間に集中的に活用するなど、現場のニーズに合わせた使い分けも行っています。

【画像】HAL腰タイプを装着して利用者を介助する職員

【画像】マッスルスーツは夜間の業務に集中的に使用する
これらの移乗支援タイプ・ロボットの導入により、利用者のアシスト業務が楽になり、排泄介助、体位交換、移乗などの腰痛リスクの高い業務への不安を払拭できました。「以前は腰痛で休職する職員が少なからずいましたが、今や休職者はゼロ。『ロボットを使うのと使わないのでは疲れ方が全く違う』、『慣れると手放せない』という声も挙がっています。さらに、導入後は、介護ロボットをより効果的に活用するための介護技術や、自立支援の在り方について職員間で意見交換する機会も増えました。今後は、介護環境が整っていない訪問介護の現場に持って行けるタイプの移乗支援型ロボットの開発なども期待したいと職員らと話し合っています」。
下肢機能支援型の免荷式リフト「POPO」(下写真)についても、導入したことで1名の理学療法士での歩行訓練が可能になり、職員の負担軽減に繋がりました。それだけではありません。POPOを使うと、平行棒を使う一般的な訓練に比べて一度の訓練中に歩ける距離が大幅に延長されるため、歩行訓練の効果も上がり、利用者のモチベーションアップにも貢献していると言います。

「PALRO」「PALO」などコミュニケーション系ロボットも活躍
さらに、コミュニケーション支援型ロボットについても、これまで国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)による大規模実証実験に参加するなどして、いち早く導入。その一つが、介護コミュニケーションロボット「PALRO」(下写真)です。

コミュニケーションのほか、歌やダンス、体操、ゲームなどの機能を搭載。職員らからも、「PALROを通して利用者とのコミュニケーションが取りやすくなった」、「話題提供の機会が増え、利用者のコミュニケーションが活発になった」という声が多く挙がっています。実際、AMEDの実証実験全体では、使用前後で34.1%の被験者に生活機能改善効果が認められています※1。
※1 AMEDシンポジウム2017開催レポート成果報告⑤ コミュニケーションロボットの効果(3)
「私たちの施設でも、『今何時です』、という声掛けをPALROで続けていった結果、失っていた時間の感覚を取り戻した認知症の方もいました」(石川さん)。現在、同法人ではPALROを20台保有。今後は、有料での個別利用者向けの貸し出しサービスを始める予定です。
もう一つ、シルヴァーウイングでは、頭をなでると本物のアザラシの鳴き声で反応する、非言語型のセラピー用アザラシ型ロボットの「PALO」も活躍しています。高齢の利用者がPALOと触れ合うことで、ストレス軽減や元気付けなどの効果が認められ、「イライラしている利用者も落ち着いてくれる」と職員の反応も良好です。

PALOを抱っこしてゆったりした時間を過ごす利用者さん
ロボット委員会、技術系職員の採用によって土台作りを
とはいえ、介護ロボットの導入当初は現場からの反発もありました。「いきなり使ってくださいと言われても、かえって現場の負担になるし、困ります」という職員の本音が届いたことも。こうした状況に、石川さんはどんな対策を打ったのでしょうか。
「まずは、『ロボット委員会』を立ち上げ、介護職がリーダー的な役割を担い、理学療法士や事務局スタッフ、施設長などの管理職などで課題や解決方法について検討するムードを作りました。導入当初は全員が慣れるように、シフト表の中にロボット利用を組み込んだり、そこで出てきた意見をメーカー側にフィードバックしたりしながら、介護ロボットを活用する土台作りを続けました」。
産業用ロボットのように工場で決まった工程のもとに使う例とは大きく異なり、介護現場でロボットを活用する際には、利用者の反応なども含め、“想定外”のことが起きる場面が多々あります。「現場では、様々な不測の事態が起こり得ることを職員に理解してもらった上で、一連の介護業務をいかにスムーズに行っていくかを追求していく姿勢が重要です。職員間には好き嫌いもあり、中にはシフトに組み込まれなければ使わないという職員もいなくはないですが、全体としては、どのロボットも諦めずに使っていって慣れていこう、ロボットを活用してより安全で負荷の少ない介護技術を生み出そうという空気が生まれています」。
さらに、文系の石川理事長ら現場の助けとなったのが、ロボット導入にあたって新たに採用した技術系職員たちでした。ちょうど半導体不況の時期に重なったこともあり、大手技術系企業で働いていた職員を4名雇用。機器類のベンダーと文系の介護職員とのインターフェースとして活動しています。これら職員の活用により、IT環境の整備やロボットのメンテナンス、機器の効果測定、安全性確認などへの目配りができるようになったと言います。
新人でもベテランでも数クリックで的確な記録付けが可能に
同法人が数年前から取り組んでいるのが、介護記録データ分析の高度化を目的とした介護AI入力予測ツールの実証実験です。
当初進めた、介護記録の電子化によって入力された記録内容を分析したところ、石川さんは新たな課題に気づきます。「介護記録には自由記述が多い。例えば同じ『アズノール軟膏を塗布した』という内容でも、『継続塗布する』『厚めに塗布した』『塗布して経過観察した』など表現方法が様々。こうした表現をパターン化することで、業務の効率化、質向上が図れないかということで、三菱電機ITソリューションズの介護AI入力予測ツール『記録NAVI』のプロトタイプ製品を活用するようになりました」。
「記録NAVI」は、あらかじめ介護記録に必要な典型的な文例を作成しておき、記録する際にはサンプルに表示された文例をクリックして選ぶだけというタイプの入力ツール。現在、石川さんは三菱電機ITソリューションズと共に記録内容を分析中で、「記録者による内容の癖やパターンなどもわかってきたため、さらに入力データを増やすことで改善を重ね、どのような介護場面でも、ベテラン、新人、外国人などどんな職員でも的確な介護記録を作成できるようにしていきたい」と話します。
AIを活用した介護リスク予見システムの構築へ
その上で、今後の構築を目指しているのは、AIを活用した介護リスク予見システムです。「介護現場で日々蓄積された看護記録、介護記録に加え、各種のセンサー機器類のバイタル情報などを合体させることで、従来は予見できなかった褥瘡などの介護トラブルや認知症や誤嚥性肺炎などの容体悪化についてのリスクを予測し、早期受診などの予防的措置を行っていこうというイメージです」。要介護者のQOL向上と介護者の業務負担軽減の両立を実現しつつ、様々なデータから疾病発生リスクを把握して疾病予防に繋げたい考えです。

【図版資料】:シルヴァーウイング提供
石川さんは介護領域の未来について、こう語ります。「現在、私は66歳。自分が将来どういう介護を望みたいかを考えれば、やはりいつまでも自立した生活を送れる自分でありたい。介護ロボットによって、自分一人でできなかったことができるようになれば、生きがいを持って働ける期間も長くなるでしょうし、AI予見システム構築が実現できれば、健康状態をより長く維持し、多くの高齢者が自立的に暮らせる社会がつくれるでしょう」。
“人とロボットの協業によって、人間の可能性はまだまだ広がる──”。石川さんがロボットとの協業で挑む、介護DXの先には、こんな力強いメッセージがありました。
石川公也(いしかわ・きみや)
1956年生まれ。大学卒業後は一般企業に勤務していたが、父親が福祉系の公務員の仕事をしていた影響から、1981年1月1日、老人ホームの寮父として福祉の仕事をスタート。「快適なシルバーライフの支援」を目指し、2001年1月に設立された社会福祉法人シルヴァーウイングの常務理事に就任。2017年12月、事務局長に就任。2017年1月から現職。2016年、「介護老人福祉施設の変革(生産性革命)実現のためのロボット利活用の推進」が認められ、経済産業省及び一般社団法人日本機械工業連合会が幹事を務める「第7回ロボット大賞」審査員特別賞を受賞。