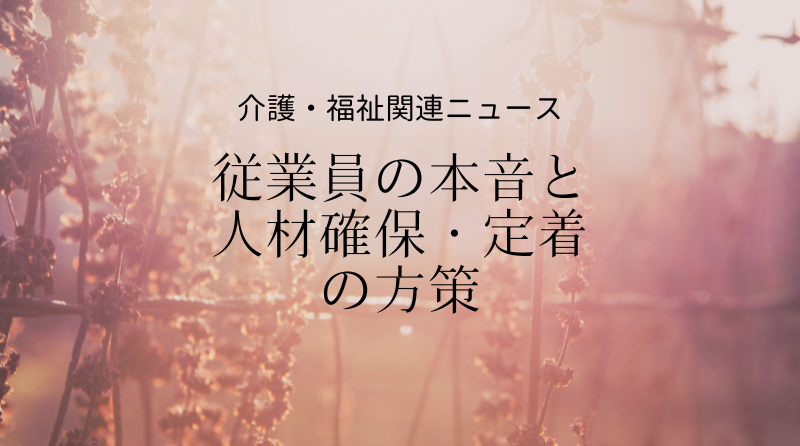介護業界で働く人の間で、「健康面の不安」を感じている人が顕著に増加している―。 介護労働安定センターが8月末に公表した2021年度介護労働実態調査により、こうした結果が明らかになりました。
また、同時期に公表された別の調査からは、不満により離職を考えたことがある人の割合は約6割にのぼるということも分かっています。
介護業界で働く従業員の就業意識についての動向と、介護事業者の採用における工夫や早期離職防止のための方策を整理しました。
調査結果から分かる介護業界で働く従業員の不安と不満
新型コロナの影響か「健康面の不安」が顕著に増加
介護労働安定センターは毎年、「介護労働実態調査」で介護業界で働く人の就業実態や意識調査を実施しています。
2021年度の結果によると、労働条件や仕事の悩みについては、「人手が足りない」が最多で52.3%。次いで「仕事のわりに賃金が低い」が38.3%となっています。
前年の2020年度と比べて大幅に増加しているのは「健康面(新型コロナウイルス等の感染症、怪我)の不安がある」で、28.1%です。20年度より8ポイント近く増えており、長引く新型コロナ禍の影響によるものと推察されます。

(介護労働安定センター 令和3年度「介護労働実態調査」結果の概要についてより引用)
不満により転職を考えたことがある従業員は6割
また、日本介護クラフトユニオンが同時期に公表した2022年度「就業意識実態調査」では、別の切り口から介護業界で働く人の就業意識について調べています。
これによると、月給制従業員の働く上での不満は「賃金が安い」が約3割、「仕事量が多い」が約2割となっており、それらの不満によって離職を考えたことがある人の割合は約6割にのぼっています。
離職を考えた理由の内訳(複数回答可)を見ると、「やりがいがない」「上司、先輩、同僚が仕事を教えてくれない」が約9割、「子育て・介護の支援策が充実していない」「悩み・不満などの相談体制が充実していない」は約8割で、「賃金が安い」「仕事量が多い」の約7割を上回る結果となりました。
| 月給制従業員が離職を考えた主な理由 | |
| 「やりがいがない」 | 92.6% |
| 「上司、先輩、同僚が仕事を教えてくれない」 | 87.5% |
| 「子育て・介護の支援策が充実していない」 | 80.0% |
| 「悩み・不満などの相談体制が充実していない」 | 77.5% |
| 「賃金が安い」 | 70.0% |
| 「仕事量が多い」 | 66.8% |
(日本介護クラフトユニオン 2022年度「就業意識実態調査」を参考に編集部作成)
調査結果から分かる介護人材確保・定着のための工夫
ここまで従業員が働く上でどのような不安を感じ、どのような時に離職を考えるのか見てきました。そのうえで、人材確保・定着のために事業所ができることは何か、調査結果から考えていきます。
人材採用において事業所が行った工夫
まずは採用の手段についてです。介護労働実態調査によると、無期雇用職員の採用において利用した手段・媒体は、「ハローワーク」が55.2%で最も高く、次に「知人等からの紹介」が45.2%、「民間の職業紹介」が26.3%です。
法人格別でみると、民間企業は「ハローワーク」が51.9%で、「知人等からの紹介」は45.2%、「民間の職業紹介」は25.6%となっています。社会福祉法人は「ハローワーク」が72.4%で、NPOは「知人等からの紹介」が55.2%で最も高いです。比較的採用コストが低い「ハローワーク」や「知人等からの紹介」が主流となっているようです。

(介護労働安定センター「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」より引用)
次に、職員の採用において工夫した点を見ていきます。
「介護資格や介護経験の有無にこだわらないようにしている」が42.2%と最も高く、次いで「新規学卒者や若手にこだわらないようにしている」が36.9%、「求人に際し、仕事そのものの魅力や労働条件を掲載する等求人内容を工夫している」が35.7%となっています。
介護人材の獲得競争が激しさを増す中、業界の経験値や年齢にこだわらず採用を実施している事業所が多いことが伺えます。
サービス種別でみると、訪問系は「職員や知人と連絡を密にとり、人材についての情報の提供を受けている」が44.9%と最多。施設系(通所型)では「介護資格や介護経験の有無にこだわらないようにしている」が54%、居宅介護支援は「職員や知人と連絡を密にとり、人材についての情報の提供を受けている」が21.7%で最多となっています。

(介護労働安定センター「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」より引用)
人材定着や早期離職を防ぐために効果のあった方策
最後に、人材定着のための方策について見ていきます。
早期離職の防止や定着促進のために最も効果のあった方策は、「本人の希望に応じた勤務体制にする等の労働条件の改善に取り組んでいる」が22.9%で最多。次いで「残業を少なくする、有給休暇を取りやすくする等の労働条件の改善に取り組んでいる」が18.1%となっています。
上記の方策に比べると割合は少ないですが、「職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている(定期的なミーティング、意見交換会、チームケア等)」は8.8%、「賃金水準を向上させている」は7%と、1割弱の事業所が効果のあった方策として挙げています。

(介護労働安定センター「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」より引用)
人材育成のための方策については、「教育・研修計画を立てている」が56.3%で最も高く、次いで「職員に後輩の育成経験を持たせている」が35.1%、「教育・研修の責任者(兼任を含む)もしくは担当部署を決めている」が34.1%となっています。
サービス種別で見ていくと、訪問系は「採用時の教育・研修を充実させている」が34.4%、施設系(通所型)は「能力の向上が認められた者は、配置や処遇に反映している」が32.6%、居宅介護支援は「自治体や、業界団体が主催する教育・研修には積極的に参加させている」が31.9%と2番目に多くなっています。

(介護労働安定センター「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」より引用)