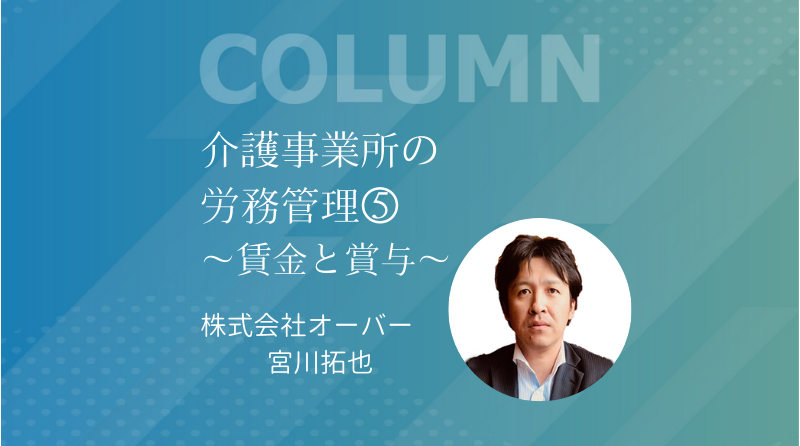介護事業所が働き方改革に対応するための労務管理のポイントについて、第5回目は「賃金・賞与のポイント①介護事業所における賃金、賞与の経営的視点」を取り上げます。
賃金は経営者と労働者が仕事の成果を共有するバロメーター
賃金とは、使用者(会社側)が労働者に対して、労働に対する報酬として支払う対価のことをいいます。
労働基準法では「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義されています。
これまでもお伝えしてきた通り、私は、人事労務コンサルティングの場面で職員の「労働時間」「賃金」「利益への貢献」についてかなりの時間を要して検証します。
具体的には、「事業所の経営的数値(売り上げ、利益)」と「賃金」の関係についての検証です。
労働者側からすると、賃金や賞与をはじめとした「報酬」を「労働の対価」として受け取ります。
会社の求めに応じ(=貢献)10時間労働したので、その対価として報酬を受け取るのです。
労働者は、この報酬について、自身の貢献に見合うものを受け取れているかどうかを重視します。
例えば、職場で事業所の利益に一番貢献しているにも関わらず、貢献度合いが低い職員と報酬が同じであると、モチベーションに影響しますし、法律や制度で定められているルールを逸脱している報酬(例えばサービス残業)であると、会社に不審を抱き、然るべき行動に移すことに繋がります。
私自身、賃金は、経営において、労使共に結果を示す1つのバロメーターであり、企業の精神であると考えています。
だからこそ、会社側においても、労働者においても賃金に対する“在り方”がとても重要なのです。
人件費を制するものは、介護事業所経営を制する?
介護事業所における人件費率(売り上げに占める人件費の割合)は60〜70%、中には80%近くの事業所もありほかの産業と比較して高くなっています。
賃金は、経営改善を図る上でアプローチすべき数字の中でも、蔑ろにできません。
そのため、その賃金には、経営状況が反映された数字と、会社の思い、経営方針、行動指針などの実践と達成の要素が盛り込まれていることが重要です。
「世間相場の賃金を払っていれば大丈夫」という考えでは、いずれ経営は行き詰まります。
そもそも、保険者の指定を受けている介護サービスにおいては、売り上げを伸ばすことには、ある種の限界があります。
まず、事業運営において定員が決まっている事業があります。その場合は、定員に達すれば、それ以上の売り上げの向上は望めません。
またサービスの供給量を増やそうとしても、労働時間の限度があります。
売り上げは、「単価回数」と考えた時、介護事業では、この単価も、介護保険制度に依存しています。加算等の考慮も必要ですが、大局的には、単価は変わらないと言えます。
一方、賃金については、事業所の利益への職員の貢献度(ここでは勤続期間の長さも含めます)が増えると、昇給等により支給額を増やすことになります。
雇用が定着すると、その分、一人当たりの支給額が増える要素となり、売り上げに対する人件費が高くなります。
賃金における人事労務マネジメント3つのポイント
では、これらを踏まえ、どのような人事労務マネジメントを行えばよいのでしょうか?
大前提は、事業所に貢献している、頑張っている人材が報われる仕組みであることです。
この前提に立ち、今回、3つのポイントをお伝えします。
1つ目は、就業規則、給与規程など規程、ルールにはこだわりを持つことです。
筆者が支援させていただく介護事業所の中には、インターネット等で雛形をダウンロードし、そのまま活用されている場合があります。その多くは、一通りの項目は定められているのですが、実際の経営と照らし合わせた時、無理が生じていたり、実態とかけ離れていたりするものがあります。
特に賃金規程については、少なくとも5年後を想像した時、その運用が功を奏しているかを、しっかりとイメージできていることが重要です。
例えば、管理者手当について、その役職への手当として支給するだけなく、未来に繋がる要素を盛り込んだ運用になっているかを確認しましょう。具体的には、管理項目数に応じた管理手当額を設定する等が考えられます。賃金は、職員にとって生活を支えるという側面だけなく、精神的にも大きく影響します。
職員の貢献と賃金が連動していることで、労働や研鑽の結果が報いられているという感情と、未来に向かう前向きな感情を抱くことができると考えます。
2つ目は、明確で誠実な「区別」をすることです。
同一労働同一賃金への対応として、均等均衡待遇が成されているか事業所の多くがどうか不安を抱えています。この不安を解消するには、職員間に生じている賃金差について、論理的に説明できる設計が必要です。
また、一人一人の働き方に対応する意味でも、経営者は、賃金においてもその多様化に合わせた運用が重要です。そのためには、支給について明確で主体性が見える運用基準の設定が重要です。
職務手当ひとつを考えても、各職務にもレベルがあり、成果として求めている内容は異なると思います。
筆者の場合、事業所によっては、職務手当を5段階ほど設けることもあります。その中には、事業所の売り上げや利益が手当て額に影響を与えるものもあります。売り上げが下がっているにもかからず、固定的な支給で経営が成り立つのかどうかは考慮すべき事項です。
3つ目は評価基準の在り方です。
どれほど円滑な運用ができる規程を設けても、どれほど優秀な人材を雇用していても、評価が適切に行われていない職場は安定しません。評価には、賃金や賞与における査定という目的(数字的要素)もありますが、それだけではありません。
評価の目的には、労働者が自身の働きと成果が経営者にしっかりと伝わっているということを確かめる側面(感情的要素)もあります。それゆえ、事業としての目標、個人としての目標、行動指針等の設定が個人の評価指標においては必要不可欠です。
賞与の設定と従業員とのコミュニケーション
賞与については、それぞれの会社ごとで運用が異なるものです。筆者は以前までは、「基本給の2ヶ月分」といった規程をよく目にしていきましたが、今は業績も勘案した支給をされている企業が多いように感じます。
私は賞与の設定について、介護事業者からのご相談に乗るときに、従業員がどれぐらいの収入を目的として労働しているかをお尋ねします。例えば「年収400万円は稼ぎたい」という思いがあるなら、自社でどのような働き方をするとその希望が実現できるのかを確認します。それを実現する要素は、売り上げなのかもしれませんし、勤務における責任や一定の休日労働や時間外労働が許容できるかどうかということも考えられます。
時間外労働は悪か?残業時間を職員と見直すための視点
昨今では、長時間労働の是正をはじめとした時間外労働のあり方が注目されています。
賃金の視点から、この時間外労働について考えてみましょう。
先述しましたが、介護事業所において月の売り上げには、一定の上限が生じます。
職員が介護サービスを提供する時間分の働きについては、介護報酬が支給されますが、それ以外の時間について介護報酬は支給されません。
例えば、訪問介護で、職員が1日5件訪問したとします。平均の報酬単価約5,000円/時間(身体介護や家事援助の単価を勘案した参考単価)で考えるとその日の売り上げは、2万5,000円。
その訪問した従業員の1時間あたりの時給が、1,300円とします。
その職員がもし、1日8時間労働すると、日給は1万400円となります。さらに、この従業員が2時間残業すると、2時間分の時間外手当は3,250円、その日の賃金は約1万4,000円となります。
しかし、もしも介護職員が提供していたのがこの参考単価より低い、家事援助を中心とした訪問だった場合は売り上げにおける人件費率は高くなります。
語弊を恐れずに申しますと、この報酬を生み出さない時間の扱いを検討することが、人件費率を是正する上で重要となります。

とはいえ、サービスを提供する時間以外にも事務作業や翌日の準備など必要な業務はあります。
また、報酬が支払われない時間には、移動時間も含まれます。
このような背景を踏まえつつ、時間外手当を見直し、人件費比率を改善する方法として、次の取り組みをお薦めします。
(1)会社が認める、想定する時間外労働数を伝える
(2)時間外労働の内容を見える化する
(3)改善することで生じる時間外手当の削減額を見える化する
(4)経営状況を鑑みながら、削減された時間外手当の一部を成果として別の手当として支給する
(5)時間外労働を否定せず、貢献を認める。
私自身、報酬を生み出さない時間も、非常に尊いもので、この時間があるから人と人の関係が潤滑にいく、深まる時間となることを幾度となく経験しています。
例えば、1日の訪問が終わり、終業後、会社の休憩室や雑談をする、そこで自分の悩みが解決されたり、業務について自信を持てるようになったりする。かしこまらない、このような瞬間が、仕事に対する感謝の気持ちをもったり、仕事を継続したりするきっかけとなるものです。
第6回目は、「賃金・賞与のポイント①賃金・賞与におけるトラブル対策」をお届けします。
※この記事は、難しい用語を極力削減し、わかりやすさを重視しています。
この記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。