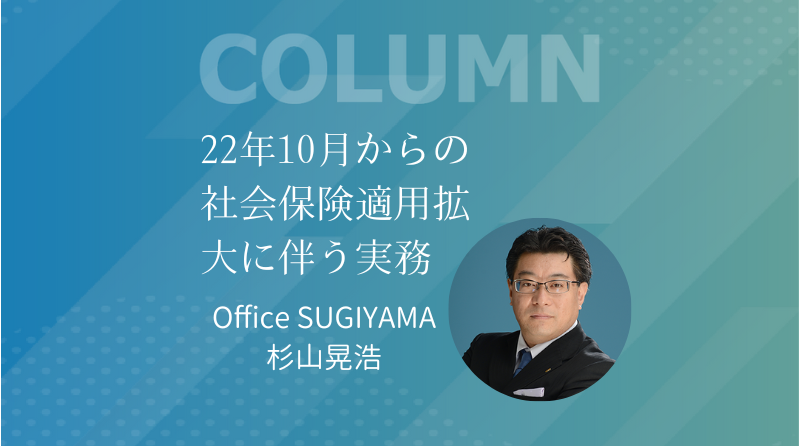社会保険の適用が拡大され、アルバイトやパートといった短時間働く人にも厚生年金に加入する条件が広がることをご存知でしょうか。こうした短時間勤務の労働者を雇用している企業には、新たに対応が求められることになります。中小企業にもこれから段階的に対象が広がるため、どのような影響が考えられるかを知り、必要な対応を確認しておきましょう。
1.社会保険適用拡大の具体的な内容
知っていますか?パートタイマーやアルバイトの雇用に関わる法改正の内容
現在、厚生年金被保険者の総数が常時500人を超える事業所は、「特定適用事業所」と呼ばれています。一定基準を満たすパートタイマーやアルバイトを、社会保険被保険者とする手続きをしなければなりません。
2022年10月からは、年金制度に関する法律の改正によって特定適用事業所の規模要件が引き下げられ、厚生年金被保険者の総数が常時100人を超える事業所は、一定基準を満たすパートタイマーやアルバイトを社会保険被保険者にする手続きが必要となります。
「常時100人を超える」とは、厚生年金被保険者の総数が、1年間のうち6カ月以上100人を超えることが見込まれる場合のことを意味しています。
24年10月からは規模要件がさらに引き下げられることになり、厚生年金被保険者の総数が常時50人を超える事業所も同様の取り扱いとなります。
なお、特定適用事業所に該当するか判断する場合の従業員数は、社会保険適用事業所に使用される厚生年金被保険者の総数です。基準よりも短い時間働いている労働者や70歳以上の健康保険のみに加入されている高齢者は、今回の適用拡大に関わらず、特定適用事業所の判断に関係しません。
厚生労働省や日本年金機構では、社会保険適用事業所の調査を実施しながら、社会保険適用拡大の啓蒙活動を行ってきました。
ところで、社会保険料は事業所と従業員がそれぞれ半分ずつ負担します。負担方法は、従業員の給与から天引き後に事業主が日本年金機構に支払う形で行います。
これまで社会保険の対象外とされてきたパートタイマーやアルバイトが社会保険の対象になれば、企業にとって大きな負担となります。特にパートタイマーの比率が高い介護事業所においては、人件費が大きく上昇することとなります。また、パートタイマーやアルバイトの立場に立つと、給与から社会保険料が天引きされるため、手取りが大きく減少します。可処分所得の減少による生活苦から離職を選択する者の発生も予想されます。
22年9月30日まで十分に時間があります。従業員が22年10月1日以降に社会保険被保険者になりたいのか、なりたくないのか、事前に対象となるパートタイマーやアルバイトと話し合っておくことが大切です。社会保険被保険者になりたくないと意思表示した対象者には、労働条件の変更を速やかに行います。事業所によっては、就業規則の変更整備が必要になることもあるでしょう。
法改正に伴う具体的なアクション
ここからは、今回の法改正で新たに社会保険の適用拡大の対象となる事業所のことを、「特定適用事業所」と呼びます。
21年10月から22年7月までの各月のうち、厚生年金被保険者総数が6カ月以上の期間100人を超えていることが確認できる事業所には、22年8月ごろに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が届きます。このお知らせが届いた事業所には、10月ごろに「特定適用事業所該当通知書」が年金機構から送られてきます。ですから、「特定適用事業所該当届」の提出をする必要はありません。ただし、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいるときは、該当者の「被保険者資格取得届」を年金事務センターに届け出る必要があります。
厚生年金被保険者総数が5カ月以上の期間100人を超えていることが確認できる事業所には、22年8月ごろに「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が届きます。
さらに、22年9月にも同様の確認を行うこととなっており、21年10月から22年8月までの間で、5カ月以上の期間100人を超えていることが確認できる事業所にも同様の通知が届きます。
特定適用事業所に該当する可能性がある事業所が、特定適用事業所に該当したときは、「特定適用事業所該当届」を年金事務センターに届け出る必要があります。この点には、注意が必要となります。
【お知らせの種類による手続き一覧】
| お知らせの種類 | お知らせを通知するタイミング | 必要となる手続き |
| 「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」 | 直近11カ月のうち、使用される厚生年金被保険者の総数が5カ月100人を超えたことが確認できた場合(5カ月目の翌月ごろ送付予定) | ・その後特定適用事業所に該当した場合は、特定適用事業所該当届の提出が必要です。
・また、適用拡大に伴い新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、被保険者資格取得届の提出が必要です。 |
| 「特定適用事業所該当通知書」 | 「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」は送付され、5カ月目の翌月も被保険者の総数が100人を超えたため特定適用事業所に該当したにもかかわらず、特定適用事業所該当届の提出がなかった場合(5カ月目の翌々月ごろ送付予定) | 適用拡大に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、被保険者資格取得届の提出が必要です。 |
2.適用拡大により新たに被保険者となる従業員
社会保険加入の適用対象となる4つの条件
現行の制度では、フルタイムで働く従業員とフルタイム従業員の4分の3以上働いている従業員が社会保険被保険者です。
今回の適用拡大により、短時間労働者が新たに社会保険被保険者として追加されます。
具体的には次の4つの要件を満たした短時間労働者が新たな対象となります。
【1】週の所定労働時間が20時間以上あること
【2】雇用期間が2カ月以上見込まれること
【3】賃金月額が8万8,000円以上であること
【4】学生でないこと

週の所定労働時間の算定方法
週の所定労働時間の算定方法は、次のように決まっています。
「週の所定労働時間」とは、就業規則や労働条件通知書などによって定められた通常の週に勤務すべき時間です。これは、雇用保険被保険者の該当基準と同一です。
「通常の週」とは、祝祭日や夏季休暇などを含まない週のことです。
短時間労働者の雇用形態によっては、所定労働時間が週単位で定まっていないことがあります。このような場合には、次のように労働時間を算定します。
●1カ月単位で定められている場合
1カ月の所定労働時間を12分の52で除して算定する
●1年単位で定められている場合
1年間の所定労働時間を52で除して算定する
●1週間の所定労働時間が短期的かつ終期的に変動する場合
平均により算定する
なお、週の所定労働時間が20時間未満であっても、実際の労働時間が直近2カ月で週20時間以上となっている状態が続くことが見込まれるときは、「週の所定労働時間が20時間以上ある」と判断されます。
2カ月を超える雇用期間の判断
2カ月以内の期間を定めて雇用されている者が、定められた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、その日から被保険者となります。
賃金月額の判断
賃金月額は、時間給、日給、週給を月額換算し、諸手当などを含めた所定内賃金の額で判断します。
賃金制度によって、月額換算の方法が異なりますので、注意してください。
月給、週給など一定の期間で定められる場合は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た金額の30倍に相当する額を報酬月額とします。
日給、時間給、出来高給または請負給の場合は、被保険者の資格を取得した月前1カ月間に同一の事業所において、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を法主月額とします。
「所定内賃金」には、次の賃金は対象とはなりません。
●臨時に支払われる賃金および1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
例.結婚手当、賞与など
●時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
例.割増賃金
●最低賃金法で算入しないことを定められている賃金
例.精皆勤手当、通勤手当、家族手当など
なお、所定時間外労働が常態化している場合には、残業を含んだ実際の労働時間を所定労働時間とみなされます。よって、8万8,000円に含まれる賃金となります。ただし、法定労働時間内の残業に限定されます。
学生の判断
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)などに在学する制度または学生は、社会保険被保険者の適用対象外となります。これは、雇用保険被保険者の該当基準と同一です。
ただし、次に該当する場合は、社会保険被保険者の対象となりますので注意してください。
●卒業見込証明書を有し、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定がある者
●休学中の者
●大学の夜間学部および高等学校の夜間などの定時制の課程に在学する者
●社会人大学院生など
3.想定されるトラブル
配偶者に家族手当を支給されている短時間労働者がいる場合
人事院の調査によると、家族手当制度がある企業は78%となっています。そのうち、配偶者に家族手当を支給する企業は81.2%です。トラブルが発生する可能性が高いのは、配偶者の状況によって家族手当の支給の可否が決まる支給規定が存在するときです。
人事院の調査では、配偶者の収入制限にフォーカスしています。確かに、収入制限によって家族手当の支給の可否が存在していることが分かります。しかしながら、各種手当の支給基準の決定権は各企業にゆだねられています。例えば、配偶者が社会保険の被扶養者であることを支給要件としていれば、今回の適用拡大によって配偶者が社会保険被保険者となれば、家族手当の支給は当然に停止されます。
実際のところ、自社の短時間労働者の配偶者の勤務先における家族手当の支給基準など把握できる術はありません。だからこそ、事前に自社の短時間労働者と面談し、社会保険被保険者になることの可否判断をさせなければなりません。
仮に、自社の短時間労働者が、社会保険被保険者となることを望まないときには、雇用契約を見直し、労働時間を週20時間未満とするなどの手続きが必要となります。
このような見直しは、社会保険の適用拡大がスタートする前に終えておく必要があります。つまり、22年9月30日までには一連の手続きを終えるようにしてください。

引用:人事院民間給与の実態(2019年(平成31年)職種別民間給与実態調査の結果)より
70歳以上の労働者の在職老齢年金が支給停止される場合
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。
要するに22年10月以降は、70歳以上の労働者で社会保険被保険者資格取得要件を満たした場合は、在職老齢年金が支給停止される可能性があります。支給停止となるか否かは、個人の年金受給額が大きく影響してきます。70歳以上で、適用拡大の4要件を満たす従業員には、早目に年金事務所に相談に行かせるなどの対応が必要です。
◆社会保険適用拡大解説動画のプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
社会保険適用拡大には、細かい取り決めが多く存在しています。わかり易く解説した動画を作成していますので希望者全員に無料プレゼントします。
お気軽に下記からお申し込みください。