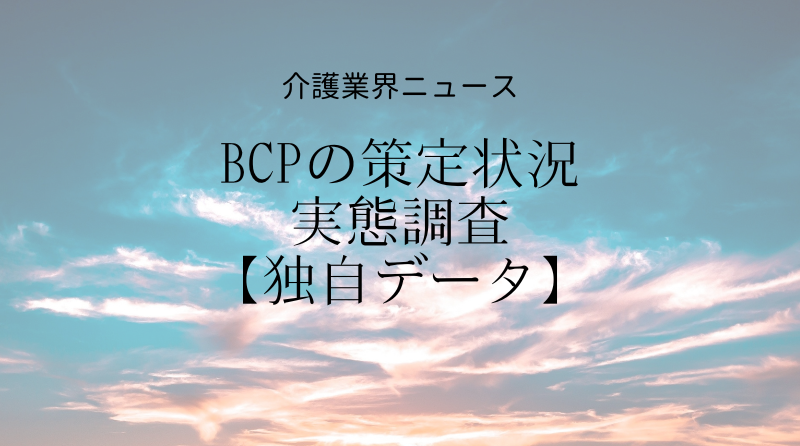感染症や災害が発生した場合にもサービス提供を続けるために、全ての介護保険施設・事業所に策定が義務付けられている業務継続計画(BCP)。
2024年度介護報酬改定では、これを策定していない施設や事業所に減算が適用されることになりました(居宅療養管理指導や特定福祉用具販売を除く。25年3月31日までは一定の適用除外措置あり)。
そこで、株式会社エス・エム・エスでは介護事業者を対象に、BCPの策定状況についてアンケートを実施しました。
既に「策定した」事業所は41.8%ありましたが、そうした事業所でも不安を抱えているケースがあるようです。
アンケートの概要と回答者
アンケートは6月2日に同社の持つ全国の介護事業者及び障害福祉事業者のリストから12万3,591名にメールで回答用のフォームを送信し、6月9日までに1,177件の回答を得ました。
回答者の属性は以下の通りです。


策定途中が43.8%「策定していない」も1割弱
まず、事業所でのBCPの策定状況について紹介します。
4つの選択肢から回答を求めたところ最も多かったのが、「策定の途中」で43.8%。続いて「策定した」が41.8%。以下、「策定していない」9.6%「わからない」4.8%でした。
事業種別に見ると、訪問看護や居宅介護支援で「策定した」と「策定の途中」が概ね拮抗していました(居宅介護支援のみを運営する法人で「策定した」が46.7%、「策定の途中」が42.9%。訪問看護のみ展開している事業者で「策定した」が32.6%、「策定の途中」が35.5%)。
また、通所介護では「策定した」の割合が他のサービスと比べて高くなっています(通所介護を含む複数サービスを展開している法人の64.0%、通所介護のみを運営する法人の66.1%。いずれも地域密着型を含む)。


「内容に不安」「作成方法がわからない」など策定のネックに
アンケートではBCPを「策定した」と回答した人(492名)に対し、策定にかかった期間や策定担当者の人数も尋ねています。
以下はそれぞれの結果です。
策定時間のボリュームゾーンは「1カ月以内」(25.0%)または「2〜3カ月」(31.5%)、策定担当者については1名で対応した事業所(50.0%)と、2~4名体制を取った事業所(44.9%)であるようです。


なお、BCPは策定だけでなく研修や訓練の実施までが施設・事業所に課せられた義務となっています。
また、計画を実行性あるものにするためにはその内容を定期的に見直す必要があります。
今回の調査結果では、既に計画を策定した事業所のうち研修や見直しまで実施できている事業所は3割程でした。

一方、「策定の途中」(515名)や「策定していない」(113名)を選んだ回答者にはその理由もそれぞれ尋ねました。
選択肢は、「今作成している内容で問題ないのか不安なため、策定の途中としている」(※「策定の途中」選択者のみ)「忙しい」「作成の方法がわからない」「運営指導(実地指導)が来るまで、まだ余裕があると思うため」「BCP策定が義務化されたことを知らなかった」「その他」「わからない」です。
それぞれ最も多かった回答は「今作成している内容で問題ないのか不安なため、策定の途中としている」(「策定の途中」を選んだ回答者のうち63.9%)、「作成の方法がわからない」(「策定していない」を選んだ回答者のうち69.9%)でした。


なお、計画の内容や実効性について不安を抱えている状況は、「策定した」を選んだ回答者も同様でした。
「策定した」を選んだ回答者に、自由記述形式で計画を策定するうえで大変だったところや失敗したポイントを尋ねたところ、
- 公開されている情報では自事業所にあった計画策定を完結させるに不十分である
- 小規模事業所で対応が困難だったという意見
- 策定内容の実効性に不安が残る
といった意見が目立ちました。
具体的な記載の一部を以下に紹介します。
公開されている参考情報が不十分だったという意見
「都と市で公開している情報が一律で(事業所で策定する)BCPに欲しい情報として掲載されていない」
「自社の一存で完結しにくいものがあるにも関わらず、その判断材料となる情報が国や都や市から出されていない」
「参考になる資料は施設(向けのものが)が主で少人数の居宅向けの資料が無く困った」
小規模事業所で対応が困難という意見
「ひとりケアマネのためいろいろわからないことが多かった」
「一人(で運営している居宅介護支援)事務所で、対応地域の範囲が広く、海に面するところ、川、山など様々なところがあり、かなり苦労している。現在は自分にもしもの時があれば、他の一人ケアマネと連携をとって対応連携できるように、書式を作成しているところ」
「実際に発災時に規定通りの連携となるのか訓練を自社だけでやっても具体性に欠ける」
「居宅単独のためどうしたらいいかよくわからかった」
策定内容の実効性に不安が残る
「策定したBCP指針が正しいか分からない」
「非常時でなくても人員ギリギリなので、現実との差、実効性が果たしてあるのか疑問」
「実際役立つないようになっているかわからない」
「一人ケアマネで他市の利用者様も担当しているため、どこに訊いても解決せずじまい。とりあえず、策定はしたという感じ」