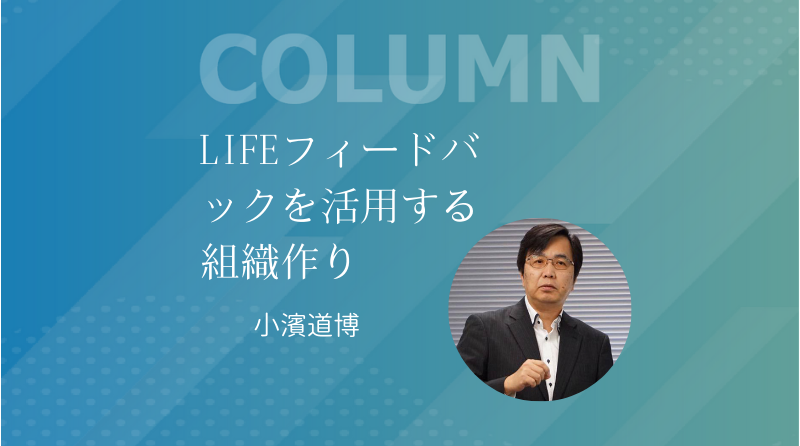1.トラブル多発のLIFEの船出、フィードバックデータの有効活用が今後の課題
4月から運用が開始された科学的介護情報システム(LIFE)は、初日からシステム障害で運用がストップした。その原因は、想定以上のアクセスが集中したためとされている。システムがパンクするほど、多くの介護施設、事業所がLIFEに取り組んでいることを意味する。
今後の焦点は、フィードバックである。LIFEから提供されるフィードバックデータをいかに有効に活用するかが重要な課題となっている。
2.LIFE活用のレベル格差が事業所間格差に―多職種連携でLIFE委員会の編成を
LIFEのフィードバックの活用次第で、介護施設、事業所間のケアの質の格差が拡大していく。
しかし、フィードバックの分析と活用は容易ではない。特に小規模な事業者には専門職が少ないこともあって困難を極めるだろう。
フィードバックの基本的な構成としては、ADL値などの項目毎に、提出データの時系列での変化をグラフで示される予定だ 。そこにLIFEの全国平均値が比較対象として提示される。
介護事業所では、この漠然としたデータを職員で共有して、その活用を検討することになる。各部署の専門職が、それぞれの立ち位置でフィードバックされた情報を用いて、その変動要因の分析と今後の対応策を検討するという流れだ。一連の流れを上手く機能させるためには、多職種が連携して、利用者の更なる状態の改善に取り組むための「LIFE委員会」の編成と定期的な委員会の開催が必要となる。
このLIFE委員会のレベル格差が、将来的に事業者間格差となっていく。しかし、委員会には相当の時間が取られる。現在の業務を見直して、効率化を実現した上でLIFE委員会を編成することになる。その効率化のためには、ICT化の促進や見守りセンサーの導入なども検討すべき時期に来ている。

3.LIFEフィードバックデータの中身と活用のポイント
LIFEのフィードバックは、ADL値点数の改善推移などでは、時系列の利用者データを棒グラフで表し、LIFEでの全国平均値が折れ線グラフで表されることになっている。
排尿・排便などの施設全体の状況では、全介助・一部介助・見守り・自立の割合を、全体を100とした棒グラフで、時系列の横並びで表し、左側にLIFEでの全国平均値が棒グラフで表される。
このグラフを、各専門職の立ち位置で分析して検討委員会に持ち寄る。
例えば、4月では全介助が20%、7月が15%、10月が20%とした場合、この変動の原因を探求して改善に繋げていく。また、全国平均値は23%とすると、全国平均より全介助は少ないという結果であることがわかる。すなわち、LIFEの活用のポイントは、この時系列の推移グラフなのである。利用者毎、施設毎の時系列の推移の積み重ねが、財産であり、独自のエビデンスとなっていく。
このフィードバックを利用者・家族に渡して、改善の成果を確認頂く事も可能であり、リハビリテーション会議での活用も想定される。
この時系列データの積み重ね期間が長いほど、他の施設との差別化に繋がる。ケアの質が向上し、成果や結果が伴うことで利用者満足が向上する。利用者満足が向上することで、職員のモチベーションも上がり、職員満足度が向上する。特に、フィードバックによって、その成果が見える化される。職員は、自分のサービスの成果を、データを通して実感出来る。職員満足度が上がることで、定着率がアップし、人材募集も容易になる。LIFEを活用することのメリットは大きいものがある。

出典:居宅・施設系サービスにおけるCHASEを介した科学的介護に資するデータの収集・活用に関する調査研究事業 報告書 三菱総合研究所
4.依然として暫定版で運用されるLIFEに募る不信感
LIFEが提供するフィードバックデータの様式は、半年以上に渡って全国集計値だけの暫定版となっていて、PDCAサイクルを廻して活用が出来ない状況が続いている。
暫定版で提供されているのは、全国集計値の数字の羅列に過ぎない。そんな状況で多くの介護施設が抱える問題は、担当職員のモチベーションの維持である。LIFEの活用で、自分たちの提供する介護サービスをランクアップすると意気込んでいた職員の多くがここに来て疲弊しており、LIFEに対する不信感を増大させている。
5.訪問サービスと居宅介護支援のLIFEモデル事業と今後の活用
令和3年度介護報酬改定では蚊帳の外であった、訪問サービスと居宅介護支援事業所については、LIFE を活用した介護の質の向上に資するPDCA サイクルの推進についてのモデル調査を実施する。
具体的な活用事例の検討を行い、LIFE 導入の課題について検証を行う。実地調査については、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業所のサービスごとに10事業所ほどを対象に実施する。
訪問サービスでは、LIFE からフィードバック票を提供して、ケアの質の向上に向けた取り組みを検証する。居宅介護支援では、LIFEに対応している通所介護のフィードバックをケアプランの見直しに活かす取り組みをテストして課題の洗い出しを図る。
6.LIFE活用の基本は科学的介護推進体制加算
厚生労働省はLIFEのインターフェースの変更を12月から行うことを アナウンスした。いよいよ、フィードバックの暫定版から正規版への移行がカウントダウンされる状況だ。
LIFE活用の基本は科学的介護推進体制加算にある。その他の加算は、その上乗せに過ぎない。効果的なリハビリテーションの成果を得るためには、ADLやIADLの推移だけを検討するのでは無く、栄養改善や口腔ケアなどの幅広い情報を活用しての原因分析や解決策を検討する必要がある。
例えばLIFE関連加算において、個別機能訓練加算やリハビリテーションマネジメント加算を算定してフィードバックされる資料は、ADLとIADLの時系列の比較と項目別のレーダーチャートだけである。これだけであれば、なにもLIFEを活用する必要は無い。BMIや栄養状態、口腔、DBD13などのデータと総合的に検討することが大切だ。
それらの情報は、科学的介護推進体制加算を算定することで得られる。同加算でもADL値の分析結果は提供されるが、さらに個別機能訓練加算などを算定する事で、IADL関連情報が追加されることとなり、更に深掘りした解析が可能となる。他の加算も同様で、栄養改善加算などを算定する事で、食事量や栄養状態の情報が上乗せされる。すなわち、LIFEの基本的な活用は、科学的介護推進体制加算の項目だけで可能ではあるが、他の加算を算定し、任意項目を提供する事で更に深掘りした活用が可能となる。
7.LIFEというエビデンスが確立することによる介護事業への影響
LIFEへの提出と活用が、今後の加算算定には必須となってくる。LIFEというエビデンスが確立することのメリットも大きい。
今までは全国標準のエビデンスが無かったために、自分たちの提供する介護サービスの評価が主観的で比較対象が無かったために、その施設、事業所の言い分を受け入れるしか無かった。
LIFEが軌道に乗ると、全国標準の比較対象が出来る。それによって介護サービスの評価の標準化が進む事が期待出来る。利用者、家族も優良なサービスを提供する施設、サービスを提供する事業所を選ぶことが出来るし、標準に届かないサービスを提供する施設、事業所は淘汰されていくだろう。