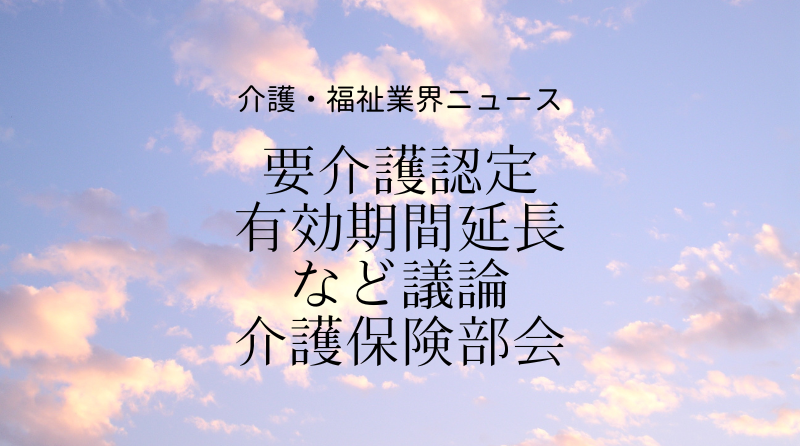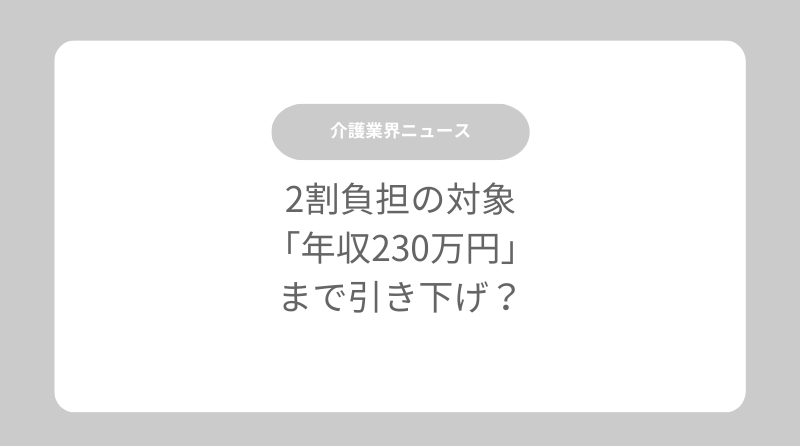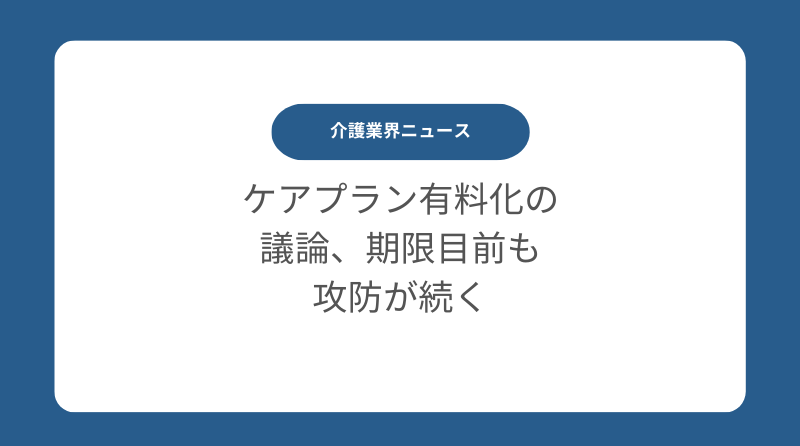9月末に開かれた第98回社会保障審議会介護保険部会では、次期介護保険制度改正に向けて、要介護認定の在り方の見直しが議論の俎上に上がりました。
具体的には、
- 更新申請の有効期間のさらなる上限拡大、新規申請および区分変更申請の有効期間の上限延長
- 介護認定審査会の簡素化による業務効率化を進めるための方策
について検討が進められています。
要介護認定の有効期間延長をめぐる厚労省の提案
要介護認定を行う保険者の業務負担が課題に
まずはじめに、要介護認定の有効期間の上限拡大や認定審査の簡素化がなぜ検討されているのか、その背景について見ていきます。
要介護認定を受けている高齢者は、2000年の約218万人から21年の約684万人と約3.14倍になり、増加傾向が続いています。

(厚生労働省第98回社会保障審議会介護保険部会参考資料より引用)
このように認定申請件数が増加する中、認定を行う市町村の業務負担が課題となっています。負担を軽減するために、これまでも更新申請の有効期間の拡大や介護認定審査会での審査の簡素化などの見直しが行われてきました。
しかし、要介護認定の申請から認定までの平均期間は36.2日で、依然として長い状態が続いているのが現状です。

(厚生労働省第98回社会保障審議会介護保険部会参考資料より引用)
この問題について、市町村の事務負担を軽減するため、令和3(2021)年度地方分権改革提案では以下のような提案がなされました。
これに対して政府が「新規認定および区分変更認定の要介護認定有効期間の延長について、社会保障審議会の意見を聞いた上で検討し、令和4年度中に結論を得る」と閣議決定したことから、介護保険部会で議論がなされることになりました。
新規申請・区分変更申請の有効期間の上限を24カ月に
こうした経緯を経て、今回、新規申請・区分変更申請の有効期間を原則12カ月・上限24カ月に延長する提案が厚生労働省からなされました。

(厚生労働省第98回社会保障審議会介護保険部会参考資料より引用)
更新申請の有効期間の上限については、18年度からは36カ月に拡大、さらに20年度からは48カ月に拡大(前回認定時と要介護度が同じ場合)されてきました。
認定から一定期間後に軽度化しているケースに注目してみると、更新申請の場合は12カ月後に軽度化している人の割合は約2〜5%と低いです。しかし、新規申請および区分変更申請の場合は12カ月後に軽度化している人の割合は12〜16%と、更新申請と比べると高いことが分かります。こうした差があることをを考慮しつつ、新規申請や区分変更申請の有効期間も、更新申請のように上限を拡大するべきかどうか、意見が交わされました。

(厚生労働省第98回社会保障審議会介護保険部会参考資料より引用)
介護認定審査会の簡素化をめぐる厚労省の提案
なぜ介護認定審査会の簡素化は進まないのか
次に介護認定審査会について、これまでにどのような簡素化がされてきて、どこに課題があったのか見ていきます。
厚労省は、18年4月1日以降の申請について、以下の6つの要件すべてに当てはまる場合は認定審査会の簡素化を可能としてきました。
- 第1号被保険者である
- 更新申請である
- コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
- 前回認定の有効期間が12カ月以上である
- コンピュータ判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定されている
- コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内」ではない

(厚生労働省第98回社会保障審議会介護保険部会参考資料より引用)
しかし、実際に認定審査会を簡素化して行った件数を以下の図から見てみると、21年上半期は12万301件で、簡素化対象数のうち44.5%にとどまっていることが分かります。

(厚生労働省第98回社会保障審議会介護保険部会参考資料より引用)
厚労省がアンケート調査で、簡素化を実施していない自治体に対して「簡素化を行っていない理由」を聞いたところ、「審査会で詳細に審査しないことが、申請者の不利益・不公平につながる可能性があるため」との回答が4割近くになりました。
また、簡素化を実施している自治体に対して「簡素化に関して、不都合に感じている点」を聞いたところ、「審査会に通知が必要であるなど、事務の簡素化につながっていない」との回答が3割を占めました。
したがって認定審査会の簡素化が進んでいない背景には、以下の2点があると考えられます。
- そもそも2018年に行われた取り組みが簡素化につながっていないこと
- 簡素化により要介護認定の適正性を担保できないのではないかという懸念ががあること
これらが課題となる中、令和3(2021)年度地方分権改革提案では、以下のような提案がなされました。
この提案に対して政府は「介護認定審査会における審査および判定に関する事務については、市社会保障審議会の意見を聴いた上で市区町村の事務負担を軽減する方策を検討し、令和4年度中に結論を得る」と閣議決定しました。
そして今回、要介護認定の適正性を確保しつつ、認定審査の簡素化による業務の効率化を進めるためにどのような方策が考えられるのか、介護保険部会で検討がなされました。
要介護認定の有効期間延長に慎重な判断求める声も
要介護認定の有効期間延長については、全国町村会行政委員・東京都瑞穂町長の杉浦委員が「高齢者の介護状態は短期間で変わることもある。有効期間の延長をするならば、短期的な状態変化にどのような対応をするのか着眼するべき」といった指摘をするなど、委員からは慎重な意見が多く見られました。
そのほか、保険者の事務負担軽減の取り組みとしてAIやICTで効率化を進めるなど簡素化できるところから進めていくべきという意見や、介護認定審査会の簡素化は必要だがエビデンスに基づく必要があるという声もあがりました。