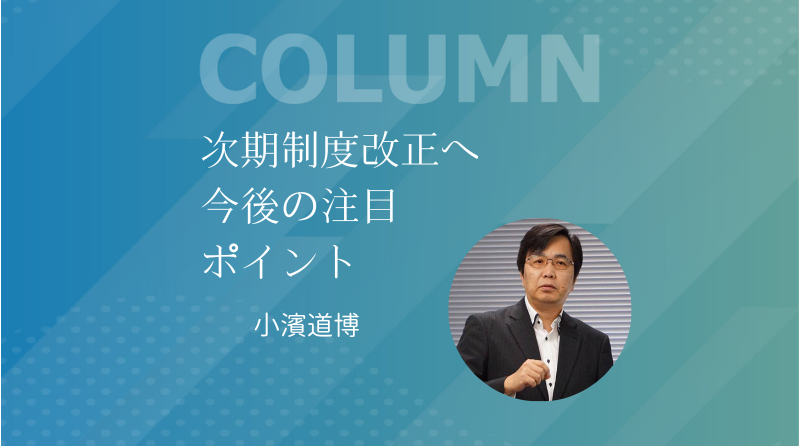いよいよ1年後に迫った次期介護保険制度改正・介護報酬改定。この1年間で介護施設・事業所の運営に大きくかかわる制度や施策の概要が明らかになってくる。今回は、3つのトピックに沿って今年度の動きなど、着目しておくべきポイントを解説したい。
1.ケアプランデータ連携システムがもたらす変化
介護業界の人材不足は、日本全体の問題であり、背景には出生率の低下や労働人口の減少がある。特に、介護を必要とする高齢者の増加に伴い、介護職員の需要は今後も高まっていくと考えられる。このような状況において、ICTの活用は介護業界における人材不足の解決策として期待されている。
介護業務の効率化やケアマネジメントの改善策として期待されるのが、2023年4月20日からスタートするケアプランデータ連携システムだ。これによって、介護サービス提供の記録や請求のやりとりが紙ベースから電子データに移行する。ケアマネジャーは、毎月、利用者の提供票を作成し、担当事業所へ紙に印刷して渡している。一方で担当事業所は、毎月末に提供票にサービス提供実績を記載して担当のケアマネジャーに紙媒体で戻す。結果、ケアマネジャーに机の上には、月初に提供票が100枚近く積み上がることになる。例えば、利用者が30人、各利用様に3つの事業所を位置づけていたら90枚の提供票が戻ってくるわけだ。この100枚の提供票を給付管理ソフトに手入力している。この作業だけでも2~3日かかっているのが現状だ。
連携システムを使う事で、ケアマネジャーはPCの画面上で提供票を入力して電子データで提供票を送るようになる。担当事業所は画面上で実績を打ち込み、電子データで戻す。ケアマネジャーはこのデータを給付管理ソフトに落とし込むだけで作業を完了する。従来の手入力作業が不要となることで圧倒的に業務が簡素化され、月初業務が1日もかからなくなるのだ。
ただし、このようなICTシステムの導入には、費用対効果を考慮する必要がある。また、導入に伴う管理業務の変革、さらには利用者やスタッフのトレーニングと意識改革も必要となる。
ICTの活用は、サービスの質の向上や負担軽減、コスト削減などの効果が期待できるが、適切な導入・運用が必要となるのが常である。
こうしたICT化が進められることで、ケアマネジャーの手間が削減されることが期待されている。また、ケアマネジャーの一人あたりの担当件数が増え、収入が確保されることが見込まれる。これは、介護業界における人材不足の問題を解決する上で重要な点であり、ケアマネジャーの処遇改善にもつながると考えられている。ケアプランデータ連携システムによって浮いた時間を活用して、逓減制の特例である担当件数44件への転換も可能となるだろう。
経営者には、ICT化を進めることで人材不足の問題を解決し、業務効率の向上や処遇改善を図ることが求められる。その先に、業界の慢性的な課題解消の道筋が見えてくる。

【画像】国民健康保険中央会説明資料より引用
2.12年ぶりの新たな介護サービスの創設の詳細
2024年度の制度改正の注目ポイントに、在宅サービスでの新型サービス創設がある。12年改正で創設された、定期巡回随時対応型訪問介護看護と複合型サービス(現在の看護小規模多機能型居宅介護)以来、12年振りのことだ。
居宅要介護者の選択肢が増え、より柔軟な介護ニーズへの対応が期待されている。特に都市部は、人口密度が高く介護需要も高いため、このような複合型サービスが必要とされているだろう。
新サービスの詳細や指定要件、報酬体系については、23年度に社保審・介護給付費分科会で検討されることとなっている。厚生労働省の審議時点での説明からは、「訪問介護と通所介護の複合型である可能性が高い」とされているが、詳細はまだ未確定のようだ。ほかに複数の組み合わせが検討される可能性もあるので、今後の情報に注目したい。
訪問介護と通所介護の複合型として新たに創設されるサービスは、小規模多機能型居宅介護とは異なる特徴を持つ可能性がある。地域密着型のサービスになるかもしれないし、訪問介護や通所介護のように、より幅広い地域でサービスを提供することも考えられる。また、新たなサービスに施設ケアマネジャーの配置が求められるかどうかは未定であり、今後の審議で検討されることになる。
訪問サービス担当者については、小規模多機能型同様に、初任者研修修了者などの医療福祉関連の資格が求められない可能性が高い。訪問サービス担当者に医療福祉関連の資格を求めないという制度上の転換は、介護職員の人材不足問題に対する解決策として有効なアプローチの一つであると言える。しかし、資格を持たない担当者がサービス提供に参加する場合には、適切な教育・研修等が必要となるだろう。また、介護職員の資格を持たない担当者が訪問介護サービスを提供する場合、そのサービスが居宅に密着した地域密着型のサービスであることが重要となる。地域住民との信頼関係を築き、利用者のニーズに合わせた柔軟なサービス提供が求められるためである。
コロナ禍の特例における通所介護の介護職員による訪問サービスの取り組みは、新たなサービス創設に向けた参考となる。訪問介護と通所介護の複合型サービスの提供にあたっては、介護保険制度の枠組み内で、利用者のニーズに合わせた適切なサービス提供が実現できるよう、検討が進められることが期待されている。
3.LIFEの活用が介護事業の将来の分かれ目に
LIFEは、24年度から訪問サービスと居宅介護支援が位置づけられる関係で次期バージョンに移行する予定だ。23年度には、利用者別フィードバック票の提供もスタートする。それまでの間、加算だけを算定してLIFEを全く活用していないケースも多い。
LIFEは、介護保険制度の改善を目的として、介護保険制度の趣旨に沿ったサービスの実施状況を把握するために行われている評価調査である。その目的は、介護保険サービス利用者、介護サービス事業者、介護保険制度関係者などから情報を収集し、その結果を分析・評価することで、介護保険制度の運営改善につなげることにある。現状、フィードバック票が暫定版であることやデータ集計に関する諸問題が報告されていることから、フィードバック票だけでLIFEを活用するのは難しいかもしれない。LIFEを真に活用するには、フィードバック票以外にも、公開されている報告書や調査結果などのデータを活用することが必要となる。また、LIFEを活用することで得られた情報を、介護サービスの改善や運営に役立てることが大切であり、それが事業者の差別化に繋がる。
つまり、LIFEが介護現場に新たな視点を示すことで、利用者への対応が多角的になれば、より質の高い介護が提供される。
科学的介護推進体制加算を算定するためには、定期的な評価が、求められる。この制度の狙いは、利用者の機能や状態を客観的に評価して、介護の質向上につなげることである。定期的な評価を実施していれば、利用者の状態が変化しても早期に気づき、サービス提供内容を変更することができる。
日常業務の中に気づきが生まれ、利用者の状態に適したサービスを提供することができれば、確実に担当職員のスキルはレベルアップする。それは、ゆっくりと、しかし確実に介護施設全体のケアの質の向上に繋がっていくだろう。
すなわち、フィードバック票が無くても、LIFEに取り組む意義は大きいのだ。フィードバック票は、あくまでも結果を表したグラフ・ツールにすぎない。LIFEに取り組むことの意義は、フィードバック票だけに限らず、介護施設全体のケアの質向上に貢献することにあると言える。
グラフ化されたフィードバック票が不完全な状態でも、活用の術はある。フィードバック票や評価結果のデータを時系列に横に並べることで、個人別の評価の変化を把握し、多職種で検討することができる。データを適切に蓄積・管理して、それを活用するための情報共有や検討を行うために、定期的な会議やコミュニケーションの場を設けることが重要だ。
他の介護施設・事業者に先行して活用ノウハウを構築することができれば、それは強みとなる。
この1年でLIFE活用においての事業所間格差が大きく拡大するだろう。

【画像】利用者フィードバックのイメージ厚生労働省ウェブサイト「科学的介護情報システム(LIFE)について」上の資料より引用