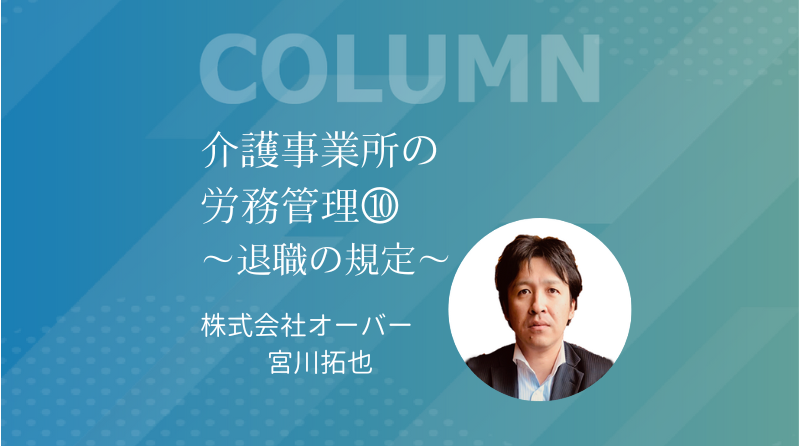介護事業所における働き方改革を進める観点から、労務管理のポイントについてお伝えしてきました。最終回として、今回は退職のルールと事業所の対応を取り上げます。
退職を巡るルールとコミュニケーション
これまでの記事では、就業規則には、会社を成長・発展させるための経営者と従業員のコミュニケーションツールとしての側面があることなどをお伝えしてきました。
ただ、就業規則にある規定が着目されるのは、やはり、労使間で、何か交渉事や調整の必要性、トラブルなどが起きた時です。スムーズな労務運営のためには、一定の道筋を定めておく必要があります。
代表的なものが、退職に関する規定です。

筆者に頂く退職に関するご相談の多くは、法律では定められていない部分について、どのように対応すれば良いかというものです。
筆者としては、現代における職場の就業規定は、分かりやすさ(納得性)と、メリハリが大切と考えています。その上で、細かなルールは日々のコミュニケーションや共有事項で浸透して頂くことが良いかと感じます。
退職は労働者の生活にも影響するデリケートなできごとです。
全ての労働者が気持ち良く、スムーズな退職を迎えられれば良いのですが、そうはいかないものです。
一定の判断基準を設けることで、そのような状況でも、論理的に事を進めることにつながります。
退職に至る前のリスク管理としての採用・試用期間に関する定め
退職について考える前に、就業規則における「採用」、「試用期間」に関する規定が重要です。
「面接の時には、そのような性格、仕事への考え方とは気づかなかった」という声を多く聞きますが、これを防ぐためにできることはなんでしょうか。
面接でその人の能力や性格を全て見抜くことは難しく、実際に働く中で、一人ひとりの特性が見えてきます。
それゆえ、「面接時の印象・評価と実際の労働時の印象・評価にはズレが起きる」という前提の中で、採用を進める心構えが大切です。
だからこそ、試用期間の定め、本採用の判断基準、試用期間の延長の定めは明確にしておく事が大切です。
また、試用期間について、どのような仕事に携わってもらうのか、それによって実践の場面で性格や能力を見抜けるのかを検討し、採用された側は会社側にとってまだ試されている期間であるという相互認識を育むことが大切です。
それでは、以下では労働者が退職する場面について、4つのパターンを考えます。
【1】従業員の業務遂行能力不足、勤務態度が会社(職場)に合わない場合
【2】従業員の怪我や疾病により業務の継続が難しい場合
【3】外部的な要因(育児や介護)で業務の継続が難しい場合
【4】定年に至った場合
能力不足や勤務態度が悪い従業員と社内ルールの関係
仕事に成果が出ていない、勤務態度が悪いからやめてほしい…。こうした場合の退職はどう考えるべきでしょうか?
勤務状況が著しく不良で改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないときは解雇ができるという規定を設けることは可能ですが、解雇の有効性は、簡単には認められません。
このような状況においては、就業規則の規定内容や日々の労務実践が重要となります。
まず、就業規則に解雇に関する規定があること、服務規律や懲戒に関する内容がどのように書かれているか。さらに、これを前提として、人事や労務として勤務不良の基準を定めているか、実際に生じている問題を把握しているか、会社として改善に向けた指導を行っているか、その内容はどうか、他の労働者との比較ができているか。つまり、「就業規則で解雇等について定めていたうえで、実際に会社はできる限りのことを把握し教育、改善、配慮した」事が重要となります。
退職を促すことは非常にデリケートな問題で、大きなトラブルにも繋がります。
会社として丁寧に、誠実な対応を行ってください。
怪我や疾病により業務継続が難しい場合~休職に関する規定~
自身の怪我や疾病により業務の継続が難しい場合、通常、まずは休職することとなります。
そこで、経営者には「いつまで休職を認めたら良いか」という悩みが生じます。
こういったときのために、就業規則に休職に関する取り扱いを定めておきます。
下記の例では、入社後1年経過したものが休職した場合は休職期間の上限は6カ月で、万一6カ月で復職できない場合は、「休職期間満了での退職」となります。
【例】
第●条 従業員が、次の各号のいずれかに該当したときは、休職とする。
(1)業務外の傷病により欠勤が、継続又は断続を問わず日常業務に支障をきたす程度に続くと認められるとき。
(2)精神又は身体上の疾患により労務提供が不完全なとき。
(3)その他業務上の必要性又は特別の事情があって休職させることを適当と認めたとき。
2前項の休職期間(第1号にあっては、書面により会社が指定した日を起算日とする。)は次のとおりとする。ただし、休職の事由又は程度を勘案し、会社は、その裁量により、休職を認めず、又はその期間を短縮することができる。
(1)前項第1号及び第2号のとき…6か月(勤続期間が1年未満の者については、1か月以上3か月未満の範囲でその都度会社が定める。)
(2)前項第3号のとき…会社が必要と認める期間
・
・
・
休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職期間満了の日をもって退職とする。
(※規定例は筆者作成)
育児や介護など外部の要因による退職
現代、労働者を取り巻く状況は変化し、仕事と育児、仕事と介護など仕事と個人的事情を両立する時代になりました。
このような外部的な要因で仕事が継続できない事態は、労働者のみならず、企業にとって想定外であることも多く、最悪の場合、事業運営が立ちいかなくなくなることもあります。
では、企業として何をすべきか。基本的には、育児・介護休業法には休業や休暇等の制度が定められており、その制度を利用しながら雇用の継続を図る方向になります。
一方で、法律には定められていない内容は、会社が独自に検討し、ルールなどを定めておく必要があります。
会社は労働者に対して、入社時に定める労働条件を示して対価として報酬を支払います。
この労働条件が外的要因によって達成できなくなる場合は、労働条件の見直し、雇用関係の継続を検討することになります。
筆者は、このような事態の備えとして、「個人的事情で仕事が継続できない場合、労働者はできる限り早く会社に相談する事。」という文言を盛り込むことを提案しています。
育児や介護を含む外的要因による退職は、労働者が悩みを抱え、一人で結論に至るケースがあります。一方で、経営者や人事・労務管理担当者の適切な介入によって退職まで至らずに済む場合もあります。
労働者が、「会社に働き方を相談できる」ということを知っていることが重要です。
定年による退職に関する規定
定年による退職は、就業規則に準じて運用することになります。
定年とは、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度をいいます。
その年齢を会社は就業規則等の規定で定めます。
なお、定年を定める場合は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、60歳を下回ることはできません。また、定年を65歳未満に定めている事業主には65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務付けられています。
定年の定めをしている事業主は、(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入及び(3)定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。
例えば、以下のような定めです。
(定年等)
第49条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
3前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。
(1)過去○年間の人事考課が○以上である者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者
(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者
(引用:厚生労働省 就業規則ひな形)
現在は、介護事業所以外にも多くの企業で、60歳を超えた方々が活躍されています。定年後継続雇用されておられる方もおられますし、再就職で活躍されている方もおられます。
年齢問わず活躍できる方はいつまでも来てほしい。そのような考えの経営者も多いのではないでしょうか。
弊社でも60歳を超えた方々が現場を支えてくださっており、日々感謝しています。
とはいえ、「いつまでも働いてほしい」と、「働くことができること」は別の問題です。
企業として労働して頂く以上、心身の状況に応じた雇用の在り方、安全への配慮は重要です。
弊社でも一定の基準を設けています。
高年齢者の雇用では、労働者の心身状況を踏まえた安全への配慮がより強く求められます。
生き残る介護事業者になるために戦略的な働き方改革を
介護事業所での人材の獲得・定着を取り巻く環境は厳しい状況が続きます。しかし、工夫次第で改善できる事も多くあります。
今後、生き残る企業になるためは、「戦略に基づいた働き方改革」が重要となります。
近年は、評価制度や貢献度に応じた賃金制度の構築に関するご相談が多くなりました。
会社が評価する項目と、現場の従業員が評価して欲しいと考える項目は一致するものではありません。
現場の評価も十分に参考にしながら、経営状況に応じ柔軟に運用できる制度を構築することが喫緊の課題であると私自身、強く感じているところです。
介護事業の成長において、人事労務の適切な運用は大きな力を発揮します。
上手くいかないことがあっても、1つずつ改善を進めて頂くと貴社に適した仕組みが実現します。
これまでに執筆させて頂いた内容が、皆さまにとって、少しでもお役に立てていたら幸いです。
ありがとうございました。
※この記事は、難しい用語を極力削減し、わかりやすさを重視しています。
この記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。