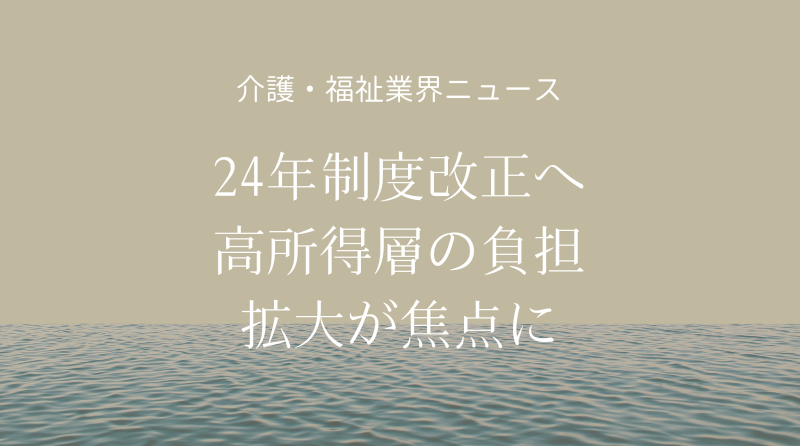次期介護保険制度改正(2023年の介護保険法などの改正)の方向性を巡る論点の中でも、大きな争点となっている「給付と負担の見直し」について、社会保障審議会・介護保険部会の議論が大詰めを迎えています。
要介護1・2の人に対する通所介護・訪問介護を市区町村の事業に移行するかどうかについて、改革の是非を含めた検討を進めるため、厚生労働省は、より詳細についての現状把握が必要だと認識しているようです。
一方で、支払い能力のある高齢者の負担拡大は、具体案の検討が進められようとしています。支払額が2倍になる利用者の範囲が拡大されれば、事業運営にも影響を及ぼす可能性があります。
改正に向けた焦点は応能負担の強化に
介護保険部会では、12月末に次期介護保険制度改正に向けた提言をとりまとめます。ここで明文化された内容は、今後提出される介護保険制度に関する法律の改正案や介護報酬改定の方向性に大きな影響を与えることになります。
「給付と負担の見直し」は、今の仕組みを維持したり、さらにサービスを拡充しようとすれば避けられません。しかし、事業や利用者の生活に直結する論点であるため、平行線が続いています。
こうした中、厚労省が一歩踏み込んだ提案をしたのが、65歳以上の高齢者の負担拡大についてです。
切り口の一つが、”2割・3割負担の対象範囲の拡大”(「『現役並み所得』『一定以上所得』の判断基準」の見直し)についてです。厚労省は、部会としての提言とりまとめが差し迫った11月28日の会合で、このラインをどのように見直すか、意見を求めていました。
2割・3割負担の対象範囲を拡大することについては、サービスの利用控えにつながることなどが一部から懸念されています。これに対し、厚労省は、
- 2割負担や3割負担の導入時(それぞれ15年8月、18年8月)にはサービス利用傾向に顕著な差は見られていない。
- 2割負担や3割負担の導入以降も利用者の実質負担率は増えていない
ことを明示しました。



(【画像】第103回介護保険部会資料(22年11月28日開催)より(赤枠を編集部で追加))
ただし、近年は医療保険制度でも高齢者の負担拡大が続いていること、介護サービスは一般的に長期間利用されることといった要素もあることから、実際に2割負担や3割負担の対象拡大が行われた場合の影響は測りきれていません。
もう一つの切り口が、65歳以上で所得が多い人(単身で年収340万円以上であることなどが要件)の介護保険料の引き上げ(「高所得者の1号保険料負担の在り方」の見直し)についてです。こちらは、低所得者の保険料引き下げとセットで提案されています。
現在は、年間の所得が320万円以上の人の保険料が最も大きくなる仕組みですが、この基準を見直すことが提案されています。
この利用者負担や保険料における応能負担の強化については、24年度の制度改正事項になる公算が大きいと既に一部で報道されています。
要介護1・2の人への訪問介護・通所介護の総合事業への移行などは決着つかず
「給付と負担の見直し」を巡る検討では、
- 保険料の徴収やサービス給付の対象年齢を引き下げるかどうか(被保険者/受給者範囲の見直し)
- ケアマネジメントに利用者負担を導入するかどうか
- 要介護1・2の人への訪問介護と通所介護を介護予防・日常生活支援総合事業に移行するかどうか
といった抜本的な改革テーマが議論の俎上に載っていましたが、意見の対立や「これまでの施策の効果計測が不十分である」といった指摘が相次ぎ、合意形成は進んでいません。これらの論点は、実現を検討するための実態調査や分析を行うなどして、26年の法改正(27年度から運用開始される制度)に向けた検討で引き続き、議論が深められていくことになりそうです。