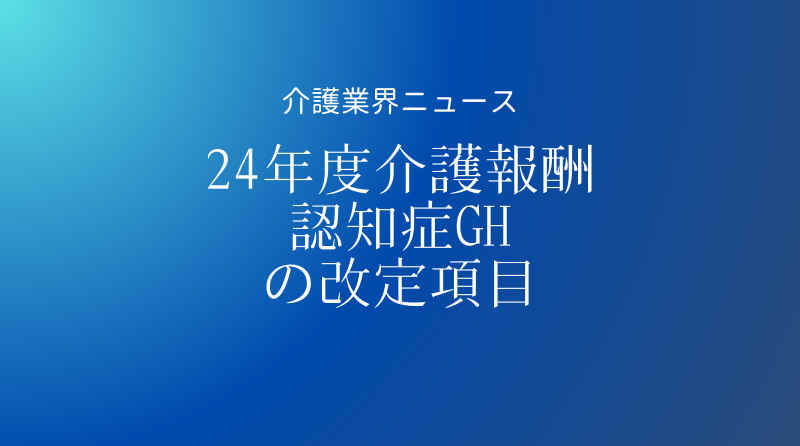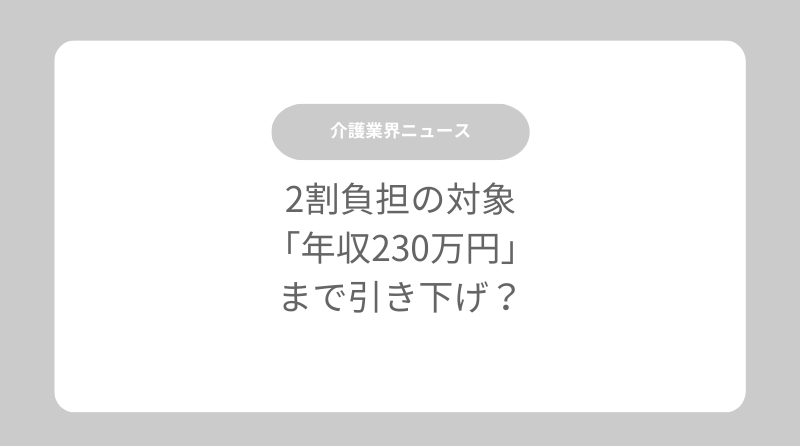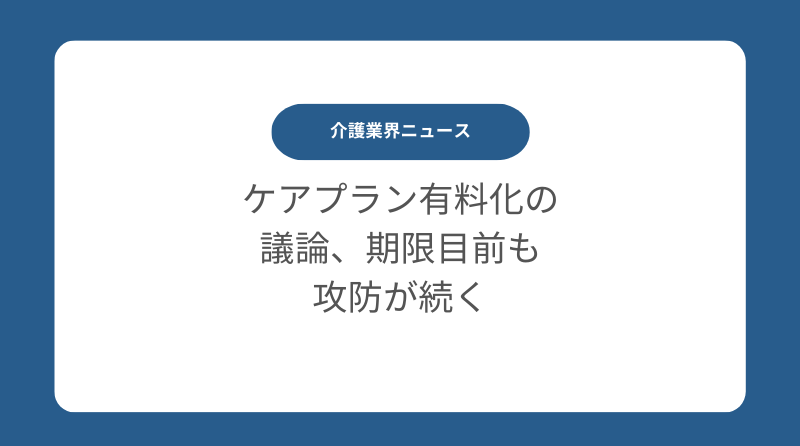社会保障審議会の介護給付費分科会は、2024年度介護報酬改定に向けた審議報告を12月19日にとりまとめました。【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】では、協力医療機関との連携強化を目的とした加算やBPSDの出現時などに早期の対応を促すための加算などが新設されるほか、夜勤体制加算の要件が緩和される方針となっています。
本記事では【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】に関する「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」の改定事項について、内容を整理して解説します。
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
医療連携体制加算の見直し(受入れ要件の拡大)
医療連携体制加算について、体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的ケアが必要な者の受入要件について、対象となる医療的ケアを追加する見直しが行われます。
夜間支援体制加算の見直し(要件の緩和)(予防を含む)
夜間支援体制加算について、現行の要件に加え、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護従事者が最低基準「0.9人以上」を上回っている場合にも算定を可能とする見直しが行われます。
ア)利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の10%以上に設置していること。
イ)事業所内に利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること。
協力医療機関との連携体制の構築【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護共通】(予防を含む)
高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しが行われます。
ア)以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めること。
ⅰ)利用者の病状の急変が生じた場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
ⅱ) 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
イ)1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認する。協力医療機関の名称等について、事業所の指定を行った自治体に提出しなければならない。
ウ)利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入居できるように努めること。
協力医療機関との定期的な会議の実施を評価する加算新設【認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院共通】
入所者・入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、定期的に入所者・入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を開催することを評価する新たな加算が設けられます。
入院時等の医療機関への情報提供を評価する加算新設【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護共通】 (予防を含む)
入所者・入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算が設けられます。
感染症対応力の向上を評価する加算新設【居住系・施設系サービス共通】(予防を含む)
施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者・入居者への感染拡大を防止するため、以下の取組みを評価する新たな加算が設けられます。
ア)新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関(協定締結医療機関)との連携体制を構築していること。
イ)上記以外の一般的な感染症(※)について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。
※ 新型コロナウイルス感染症を含む。
ウ)感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関や地域の医師会が定期的に行う感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること。
また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることを評価する新たな加算が設けられます。
施設内療養を行う高齢者施設等への対応【居住系・施設系サービス共通】(予防を含む)
新興感染症のパンデミック発生時等に、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行う取組みが新たに評価されます。
なお、対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定することとなります。
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携【居住系・施設系サービス共通】(予防を含む)
入所者・入居者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等の対応を取り決めるよう努めることが求められます。
また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことが義務付けられます。
平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進【認知症対応型共同生活介護、介護保険施設共通】(予防を含む)
認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を推進するため、以下を評価する新たな加算が設けられます。
ア)BPSDの予防に資する認知症介護に係る専門的な研修等を修了している者を配置し、事業所内において、BPSDの予防に資するチームケアの指導を実施していること。
イ)評価指標を用いてBPSDの評価を行い、BPSDの予防に資するチームケアを提供していること。
ウ)BPSDの予防に資するチームケアに関する計画を作成するとともに、チームケアの実施について計画的な評価・見直し、事例検討等を行っていること。
「利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減」検討委員会の設置の義務付け【短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス共通】(予防を含む)
現場における課題を抽出・分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられます。その際、3年間の経過措置期間が設けられます。
介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進【短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス共通】(予防を含む)
介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、以下の事項を満たす取組みを評価する新たな加算が設けられます。
- 利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の開催や、必要な安全対策を講じている
- 見守り機器等のテクノロジー(※1)を1つ以上導入している
- 生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行う
- 一定期間ごとに、業務改善の取組みによる効果を示すデータの提供を行う
上記の要件をすべて満たした上で、さらに以下の事項をすべて満たす取組みを評価する区分が設けられます。
- 提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認できる
- 見守り機器等のテクノロジーを複数導入している(※2)
- 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っている
※1)見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア)見守り機器
イ)インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
ウ)介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
※2)見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器はすべて使用すること。
その際、アの機器はすべての居室に設置し、イの機器はすべての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ ースアップ等支援加算の一本化
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件と加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
※経過措置期間:2024年度末まで
また、以下の見直しが実施されます。
ア)職種間の賃金配分について、引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつ、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
イ)新加算の配分方法について、 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合に、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
ウ)職場環境等要件について、生産性向上や経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し【通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス共通】
就労開始から6月未満のEPA介護福祉士候補者・技能実習生(以下「外国人介護職員」)について、現行では人員配置基準への算入が認められていません(日本語能力試験N1またはN2に合格した者を除く)。
就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態などを踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しが行われます。
具体的には、事業者が以下の事項を踏まえて、人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合、「就労開始直後」から人員配置基準への算入が可能となります。
- 外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況
- 管理者や指導職員等の意見等
その際、適切な指導・支援を行い、安全体制を整備する観点から、下記の要件が設けられます。
ア)一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ)安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。
併せて、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修・実習のための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の修得・学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導・支援体制の確保が必要であることが改めて周知されます。
科学的介護推進体制加算の見直し(様式の再検討、要件の緩和)
科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行うこととなります。
ア)加算の様式について、入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
イ)LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
ウ)初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入
感染症・災害に対応するための業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算となります。その際、感染症の予防・まん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されません。
※経過措置期間:2025年3月31日まで
高齢者虐待防止の推進【全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く) 】
虐待の発生や再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬が減算となります。
テレワークの取扱い【全サービス(居宅療養管理指導を除く)共通】(予防を含む)
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示すことが求められます。
※このほか、全てのサービスに共通する改定事項(短時間勤務制度を導入する場合の「常勤」配置の緩和、管理者の兼務範囲の明確化、重要事項等のウェブサイトでの公表)が加わります。