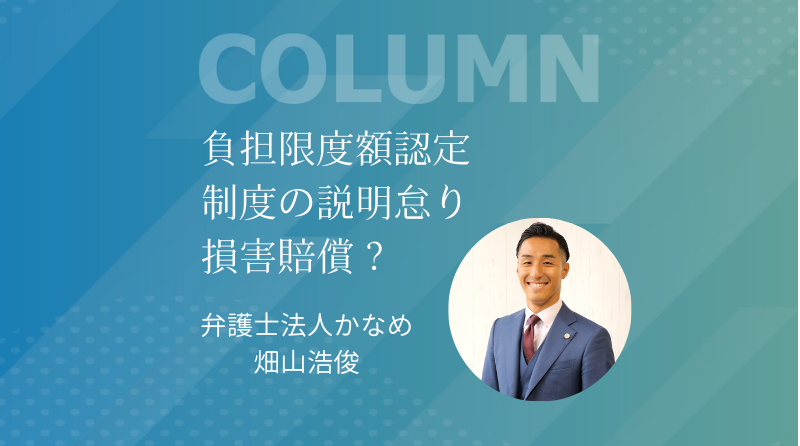施設に所属しているケアマネジャーや介護職員の皆さまにとって、介護保険負担限度額の認定制度は馴染み深いものですよね。
サービスの利用開始時の重要事項説明を通して、介護保険負担限度額認定制度を利用者やご家族に説明している施設や事業所が多いと思います。
しかし、サービスの利用開始後に、「介護保険負担限度額認定制度の説明を受けていない。もし最初にきちんと説明を受けていたら、もっと安く施設を利用できたのに。この差額はどうしてくれるのだ」などと、トラブルになったことはありませんか。
今回の記事では、このようなトラブルが実際に裁判にまで発展したケースをご紹介します。
1.介護保険負担限度額認定制度をめぐるトラブル
裁判例の紹介に入る前に、介護保険負担限度額認定制度の基本知識を改めて説明します。
介護保険サービスを利用した場合、サービス費用の1~3割が利用者の自己負担です。しかし、在宅における介護保険サービスの利用者との「負担の公平性」の観点から、介護保険施設(介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイの施設利用では、食費や居住費は保険給付の対象外であり、全額自己負担が原則です。
介護保険負担限度額認定制度は、低所得者の食費と居住費が一定額を超えた場合に、各市区町村の窓口に認定希望者が申請し、申請を受けた各市区町村が認定をすることで、超えた部分について介護保険から給付が受けられる制度です(図参照)。

2.およそ180万円の賠償を争った裁判例の紹介
それでは、裁判例の紹介に移ります。こちらは、東京地裁2021(令和3)年3月12日の判決です。
本事例は、老人保健施設のケアマネジャーが入居者に対して、介護保険負担限度額認定制度の説明を怠ったとして、原告である当該入居者が、被告である老人保健施設を運営する医療法人に対し、説明義務違反を理由として、施設利用開始時から負担軽減を受けていた場合の負担額と実際に支払った負担額との差額等、合計約180万円の賠償を求めた事案です。
原告は、介護施設側の方が情報を多く持っているのだから、「費用がもっと安くならないのか」という問合せを受けた際に、介護施設の運営法人及びその職員であるケアマネジャーが、介護保険負担限度額認定制度を用いればどのような効果が生じるかや、どのような要件に該当すれば費用が安くなる可能性があるかについて丁寧に説明する義務があると主張しました。
もっとも、裁判所は、運営法人及びそこに勤務するケアマネジャーには、入居者に対して介護保険負担限度額認定制度の説明をする法的義務はないと判断し、原告の主張を退けました。
具体的には、以下のような点を認定しています。
まず、前述のとおり、本件制度は、認定希望者が各市区町村の窓口に申請し、申請を受けた各市区町村が認定をする制度で、介護保険法にその根拠がありますので、入居者と老人保健施設の契約の内容となるものではありません。施設で勤務するケアマネジャーもこの手続きに関与しません。
また、介護保険法96条1項は、介護老人保健施設の開設者は、「常に介護保険施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない」と定めていますが、これは、介護老人保健施設の設備、運営等について定めたものです。
そのため、ケアマネジャーに対し、介護保険負担限度額認定制度の説明を行う義務を基礎づけることはできず、その他、介護保険法の定めるケアマネジャーについての各規定に照らしても、ケアマネジャーにおいて利用者に対して介護保険負担限度額認定制度の説明を行う義務を導くことはできないと判断されたのです。
3.施設利用時の説明で気を付けるべきポイント
以上のとおり、上記裁判例では、ケアマネジャーには介護保険負担限度額認定制度の説明を行う義務はないと判断され、事業所側の勝訴となりました。
しかし、だからと言って安心という訳ではありません。
この事例から学んでいただきたいことは、ケアマネジャーには法的な説明義務がない制度や手続きであっても、「説明を受けていない」ということを理由に裁判にまで発展するケース」があるということです。
問題の本質は、「丁寧に説明をしていたのかどうか」という施設サービスの質の問題だと思います。
ケアマネジャーや運営法人からすれば、「市区村長が実施している制度の説明を行っていないことの責任追及をこちら側にされても困る」と感じるでしょうが、利用者やご家族側は、通常、介護保険制度については素人であって、施設側と利用者側とでは介護保険制度に関する情報量に圧倒的な差があることは事実です。
ですから、施設側としては、「丁寧すぎるほど丁寧に情報提供しておくこと」を基本スタンスに据えておくことが無難だと思います。
法的な説明義務がないということと、丁寧な説明を心掛けることで顧客満足度を高めるということは別次元の話です。
制度の詳細まで説明する必要はないと思いますが、例えば、重要事項説明書の内容を説明する際に、各市区町村が作成している介護保険負担限度額認定制度の説明用リーフレットを合わせて配布したり、同制度を説明している各市区町村のHPをQRコードに変換して重要事項説明書に掲載したりする一手間を加えることで、それ以後の利用者との信頼関係の構築に繋がります。
今回紹介した裁判例のケースは、どの介護施設でも発生する可能性がある事案ですので、これを機にサービス利用開始時の説明方法を見直してみて下さい。
4.最後に:介護現場の法務対応力を向上する書籍の紹介
弁護士法人かなめ著で2冊書籍を執筆しました。
弁護士法人かなめでは、管理者・施設長の方々から日々法律相談を受けています。
過去の膨大な相談内容の中から「管理者・施設長の方々にこれは抑えておいて頂きたい」というトピックを中心に執筆しました。是非、現場法務の向上にお役立て下さい。
介護現場を運営していると「想定外」の問題がたくさん発生します。
そんなときに慌てないようにリスク管理体制を向上させるためには実際のトラブル事例から学ぶことが最も近道です。
そこで弁護士法人かなめでは、令和3年に判決が言い渡された裁判例を可能な限りピックアップし、それを実務的な目線から分析した書籍を執筆しました。
リスクマネジメント対策の一環にお役立て下さい。