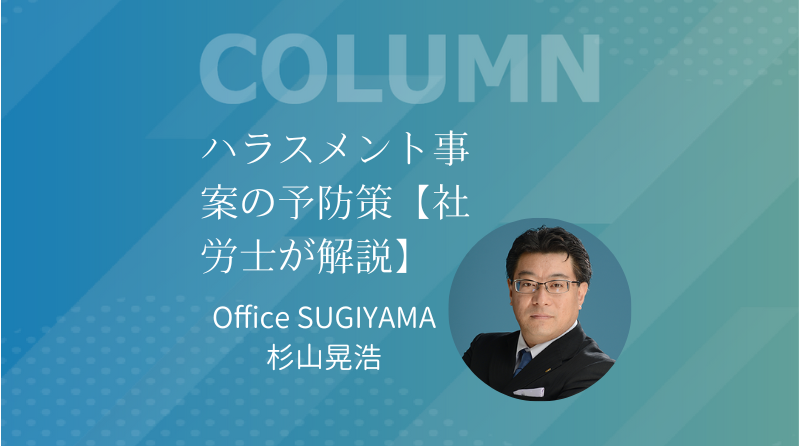1.増え続けるハラスメントと介護現場におけるリスク
介護事業所の管理者をしていると、ハラスメントに関する相談を受けたことは一度や二度ではないと思います。昨年発表された厚生労働省の「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況 」によると、民事上の個別労働紛争のうち「いじめ・嫌がらせ」に関するものがに関するものが24.4%となっています。2位の「自己都合退職」は11.5%と比べても断トツで多いことが分かります。
さらに過去10年間を振り返ってみると、「いじめ・嫌がらせ」が増加傾向にあることは、誰の目にも明らかです。ハラスメントが世の中に認知されてきていることに加え、毅然とした対応を取る人が増えてきていることの現れでしょう。

また、JOB総研が公表している「2023年 ハラスメント実態調査 」からは、81.5%と断トツでパワーハラスメントの被害が多いことが分かります。

調査からは、ハラスメントが頻繁に発生していることもわかります。あなたの職場でもいつ発生してもおかしくない状況下にあるという認識で、ハラスメント対策をすすめることが有効です。

特に介護事業所においては、利用者や利用者の家族からのカスタマーハラスメント対策も重要となってきます。カスタマーハラスメント防止のための啓蒙活動や契約書の見直しなど、併せて行いたいものです。
ハラスメントがある職場では、良い人材ほど見切りをつけて転職してしまいます。未曽有の採用難時代においては、せっかく採用できた人材が離職しないように、ハラスメントのない環境を作ることが求められています。

2.ハラスメント防止対策と事前準備
企業には、ハラスメント防止措置が義務付けられています。
しかしながら、何をどこまですれば良いのか分からないというのが現実ではないでしょうか。
そこで主なハラスメント防止措置を以下のようにまとめてみました。
皆様の職場に合うように、自由にカスタマイズして、対策を講じてください。
| 防止措置 | 具体的な内容 |
| ハラスメントポリシーの明確化 | ハラスメントを絶対に許さない方針を明文化し、そのポリシーを全ての労働者に周知すること |
| 教育研修の実施 | 定期的にハラスメントに関する教育や研修を行い、その定義、形態、影響、報告の手順などを明確にします。
新入職員にはオリエンテーションの一部としてハラスメント防止対策と対処法を研修メニューに加えます。 管理職および管理職予備軍には、ハラスメント発生時の具体的な訓練を研修メニューに加えると効果的です。 |
| 就業規則の整備 | ハラスメントが発生した場合の報告手順、調査手続、処置、懲戒処分などを明確にし、それらを就業規則に明記しスタッフに周知します。
就業規則の変更となるので、スタッフ数が10人以上であれば、労働基準監督署へ届出が必要となります。 |
| チラシ、ポスターの掲示 | スタッフが容易に気づく、見やすい場所に、ハラスメント防止対策や注意喚起となるチラシやポスターを掲示します。
目につきやすいところに掲示することで、サブリミナル効果を期待します。 |
| 定期的な啓発活動 | 会議やメールなどを通じて定期的にハラスメント防止対策を強調し、スタッフの意識を高めるようにします。
毎回、会議のアジェンダに「ハラスメントについて」などと議案として上程するのも有効です。 |
| 相談窓口の設置 | ハラスメントに関する相談や報告を受け付ける窓口を設置しスタッフに周知します。
その際には、相談者の秘密は必ず守られるという安心感を与えてください。 窓口担当者には、ヒアリング技術向上のための研修を実施し、ヒアリングシートなども準備しておきます。 なお、組織内のスタッフに相談できない、相談しにくいというシチュエーションも考えて、社外相談窓口の設置もご検討ください。 |
| ハラスメント対策会議の設置 | 労使が一体となり、ハラスメント防止からハラスメント発生時の対応、処置、再発防止策を決するようにします。
ハラスメント対策会議と併せて懲戒委員会の機能を持たせておくと、懲戒の程度の決定や懲戒スピードが速まるなどの利点があります。 当然のことですが、必ず議事録を作成して下さい。 |
| 利用者との契約書の見直し | カスタマーハラスメント発生時には、利用者の退去や契約解除を実現できる内容に変更しておきましょう。
重要事項なので、確認の署名をもらえるようにしておきます。 利用者やその家族に説明するためにも、わかり易いリーフレットなどを作成しておくのも良いです。 |
介護事業所においては、カスタマーハラスメント防止の観点を含めて、厚生労働省から 「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル 」が公表されています。厚労省がわざわざ個別にマニュアルを作成するほど、介護スタッフにとってハラスメントは大きな問題であることが伺えます。
3.ハラスメント発生時の介護事業所での対応
介護事業所でハラスメント事案が発生したときは、初動が肝心です。
我々の事務所には『スタッフからハラスメントの相談を受けたのですが、どう対応したらよいでしょうか。』といった質問が関与先の担当者から寄せられます。普段からハラスメント発生時の対応を明確にしていないため、対応が後手後手に回り、事態が急激に悪化することもしばしばあります。
あらかじめハラスメントが発生したときの対処フローを見える化し、関係者間で共有しておくことが重要となります。
以下に、発生時からの業務フローの例を挙げておきます。みなさまの事業所の実態に合うようにカスタマイズして導入いただければ幸いです。
| 業務フロー | 具体的な内容 |
| 即時対応 | 職場の同僚や上司、ハラスメント相談窓口担当者が、ハラスメント被害やハラスメント被害のおそれの相談や報告があったらすぐに対応します。
被害者の安全を確保し、概要を確認します。 詳細ヒアリングにつなぐべく、速やかに関係者に連絡を取り次ぎます。 |
| 詳細ヒアリング | 事案の詳細を把握するためにヒアリングを行います。
被害者、加害者、そして可能なら目撃者から事実関係を聞き取ります。 ヒアリングの際には公平かつ中立的に対応してください。 なお、被害者、加害者、第三者でヒアリングすべき内容が異なることから、あらかじめそれぞれの立場に応じたヒアリングシートを準備しておき、記録を残します。 |
| 裏付け調査の実施 | ヒアリングの結果を基に、ハラスメント対策会議が裏付け調査を行います。 |
| 結果報告 | 調査結果を基に、事案がハラスメントであったかどうかを結論付け、その結果を関係者に報告します。 |
| 処分の実施 | ハラスメントが認定された場合、加害者に対する適切な処分を行います。
懲戒委員会が、就業規則に従って、妥当な懲戒処分を決定し、加害者に通知します。 |
| フォローアップ | 被害者のケアを継続します。
カウンセリングの実施や職場環境の改善など、被害者が再度同様の事案に巻き込まれないような措置を取ります。 |
| 再発防止策の検討と実施 | 具体的な事案を受けて、ハラスメント防止のための教育や研修を再検討・強化します。
ハラスメント防止委員会が主導権を握り、確実に再発防止策を実施してください。 |
ところで、ハラスメント事案が発生した際に最も重要なことは、適切にヒアリングを実行することです。中立性や公平性を保たなければならないことは頭では分かっているものの、実際に実行しようとするとなかなか難しいものです。ヒアリングを実施するスタッフは、先入観を持たず平常心で聴き取りするように心がけましょう。
とはいえ簡単に実践できるものではありません。なのでヒアリングを実施するスタッフには、特別な教育が必要となります。特別な教育といっても、特に身構える必要はありません。基本的な質問を口に出して、ロールプレイングをしてください。繰り返しロールプレイングをすることで、イメージが湧きやすくなり、その結果より深く聞き取ることができるようになります。つまり、深掘り質問ができるようになれば、事案対応力が格段に高まることにほかなりません。
以下に、いくつか入口の質問の事例を挙げておきます。参考にしていただければ幸いです。
①事案の詳細について
- ハラスメントが発生した日時はいつですか?
- ハラスメントが行われた場所を教えてください?
- どのようなことを言われましたか(されましたか)?
- それは一度だけですか?それとも何度も繰り返されていますか?
②関与者について
- あなた以外に目撃者はいましたか?
- あなた以外にハラスメントを受けている人はいますか?
- このハラスメントについて知っている人はいますか?
③影響について
- 今回の事案は、あなたの仕事や心にどのような影響を与えましたか?
- その後、眠れない、食欲がない、頭が痛いなどの体調変化はありましたか?
④証拠について
- 今回の事案に関する写真、メール、メモなどの証拠となるようなものはありませんか?
⑤その他
- 今回の事案について、誰かに話したことはありますか?そのときの相手の反応はいかがでしたか?
- あなたはこの問題をどのように解決したいと考えていますか?
◆「被害者、加害者、第三者専用ヒアリングシート(エクセル版)」のプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
被害者、加害者、第三者とそれぞれからヒアリングする内容は異なります。
それぞれに合ったヒアリングシートをA4サイズのエクセルで作成しています。エクセルデータでお渡ししますので、加工が自由にできます。ロールプレイングをしながら、追加したい質問項目や削除したい質問項目を消すなど、自由にカスタマイズしてください。
必要な方はお気軽に下記からお申し込みください。