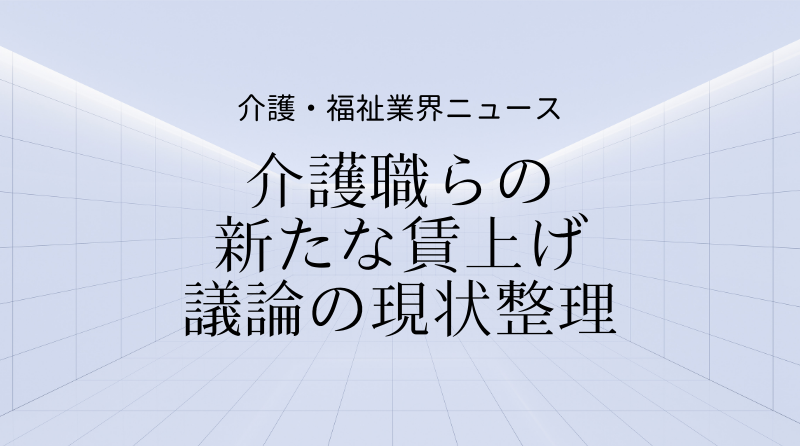政府は11月9日、「全世代型社会保障構築会議」と、看護や介護、保育職の賃上げに向けてその目標や制度のあり方を検討する「公的価格評価検討委員会」の合同会議の初会合を開きました。介護職らの給与改善は、岸田文雄首相が掲げる「成長と分配の好循環」を実現する目玉政策として、業界の枠を越えて注目を集めており、これまでに様々な動きがありました。
本記事では介護職らの賃上げを巡る動きについて、現時点で明らかになっていることを整理します。
介護職等の賃金引上げを巡る議論とこれまでの政策との関係
介護職や看護師、保育士らの賃上げについて検討する公的価格評価検討委員会は、厚生労働省ではなく、首相官邸に立ち上げられました。これまでに社会保障制度の改革などを検討してきた全世代型社会保障構築会議の下部会議として位置づけられています。メンバーは、金融経済や財政、社会保障関連の法律の専門家らで構成されています。
この会議では、公的価格の制度について、看護・介護・保育現場における報酬・価格の決定方法や現行の処遇改善の仕組みなどが示されました。

*引用:全世代型社会保障構築会議(第1回)・公的価格評価検討委員会(第1回)合同会議資料4「公的価格の制度について」より
介護職員については、2009年度以降に介護職員の処遇改善加算の創設や順次の拡充等の取組が実施されており、その後創設された特定処遇改善加算も含めると2019年度までの10年間で月額7万5,000円相当の賃上げが実現されています(※これらの加算を算定している事業所の場合)。
しかし、これらの改善策は運用ルールが複雑で、煩雑な事務作業が発生することや、経営上の柔軟性にかけるなどといった問題点が事業者団体などから指摘されてきました。
また、介護職の賃金そのものについても、他産業と比較すると、依然として低い水準で推移しています。

*引用:全世代型社会保障構築会議(第1回)・公的価格評価検討委員会(第1回)合同会議資料4「公的価格の制度について」より
岸田首相は会議での議論の後、「看護・介護・保育・幼稚園などの現場で働く方々の収入の引上げは最優先の課題」と明言し、民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて前倒しで引上げを実施する方針を表明しました。
なお、この会議の翌日には、国の財政健全化などについて財務相が諮問する「財政制度等審議会・財政制度分科会」で社会保障費に関する課題が取り上げられました。ここでも同様に、介護現場の賃金水準の低さが指摘されています(※前に示したリンク先資料P24、25)。ただし、こちらでは、その対応について、介護報酬や診療報酬の「分配のあり方を見直す必要がある」と指摘されています。
介護職の賃上げに向けた今後のスケジュールと改善額
賃上げの実施に向けやスケジュールについて、岸田首相は合同会議に対し、「安定財源の確保と併せた道筋を考え、年末までに中間整理を取りまとめ」るよう指示をしています。
また、その後の動きとして、介護職全員の賃金を月額3%程度に当たる9千円程度引き上げるという方針が政府が19日に決定する予定の経済対策の中に盛り込まれていることと、複数の報道機関が報じています。
賃金引き上げを実施する方法や対象の職種など、詳細が決定次第、ご紹介してまいります。
*制作協力:フリーライター 南マイコ