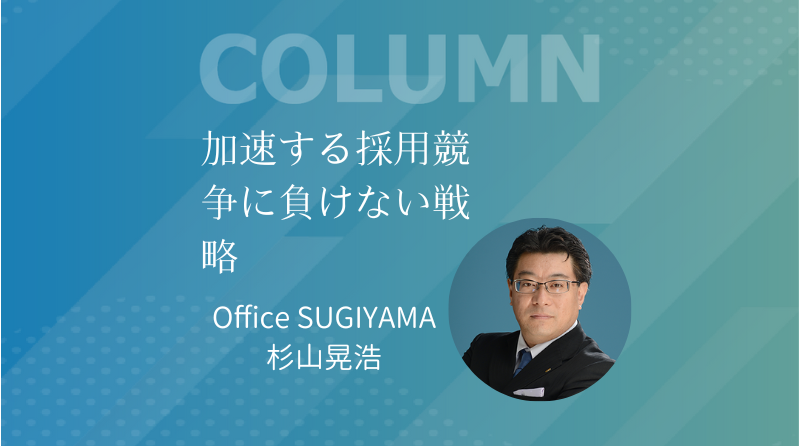リクルートワークス研究所が3月に公表したレポートによると、4年後には現在の15倍の働き手不足となるという衝撃のデータが示されています。
このレポートは、労働需給シミュレーションからいくつかの産業の未来を予測したものです。それぞれの産業に突きつけられた課題に対し、機械化や自動化で課題を解決に導くこと、新しい働き方を創造すること、ムダをなくすことなどを提言してくれています。
しかし、経営者を取り巻く環境を見渡すとコスト面、労働法規制、現実の現場、それぞれ一筋縄では解決することはできない課題ばかりです。
そこで、みなさんの介護事業所が2040年以降も存続するために、今何をすべきなのかを改めて考えてみました。
1.労働需給シミュレーションからみた介護・医療業界の未来
「未来予測2040労働供給制約社会がやってくる」で発表された労働需給シミュレーションでは、2026年から2027年にかけて労働供給不足が急激に酷くなることが読み取れます。
コロナが収束した現在、全ての産業で人手不足感が高まっているのが現状です。2023年時点の需給ギャップは12.8万人の労働者不足ですが、2027年には現在の15倍を超える192.8万人の労働者不足となります。たった4年後には、全ての産業で、今よりも激しい採用競争にさらされることが容易に想像できます。
産業別にもシミュレーションが紹介されています。

次に、介護事業所に関係が深い2つの職種別シミュレーションを示します。
まず、介護職員と訪問介護従事者を指す「介護サービス」職種について。

次に医師、看護師、薬剤師などの保健医療専門職です。

グラフが示す通り、どちらの職種も将来大きく人手不足になることが予想されています。しかも、年を追って供給不足が高まるばかりです。
だから、事業者にとって、『今が一番採用し易い』環境であると言えるのです。
介護サービスでは、現在でも労働力が不足しています。多くの介護事業所が、『採用が難しい』と声を上げている実態もあります。ここで気づかなければならないことは、「労働力不足=採用できない」という悩みは、日増しに強くなるばかりだということです。時間が解決してくれることはありません。
みなさんの介護事業所が自分ごとと捉え、将来さらに酷くなる労働力不足という課題に立ち向かわなければならないのです。
保健医療専門職では、介護サービスに少し遅れて人手不足感が増してきます。
資格取得までに時間を要するため、失業者を職業訓練してすぐに労働市場に供給するようなことができません。
すなわち、保健医療専門職の採用ルートの確立や離職防止環境の構築が急がれるところです。
なお、これらのシミュレーションは「ほとんど経済成長しない日本」が前提となっています。地域の状況によってはし、労働需給がより急激に悪化することも容易に考えられます。
例えば、熊本県では世界最大の半導体製造企業であるTSMCの企業誘致に端を発し、次々と誘致企業が増え続けています。このように県内の経済が成長することで、熊本県では労働者の採用競争が日増しに激しくなってきています。『採用競争が激しいのは製造業やIT系企業であって、介護事業所は関係ない。』などと甘く考えるのは止めましょう。採用競争は賃金や処遇の向上競争であり、賃金が低い職種や処遇が良くない企業から労働者が流出して行くのが自然の摂理です。
介護スタッフが退職しないような手立てが講じられているか、一度自社を省みる必要があります。
2.慢性的な人手不足下での採用戦略とは?
みなさんの職場ではどのようなタイミングで人材募集を行っていますか。
例えば、介護スタッフから『退職したい』との申し出が契機となって人材募集をする介護事業所と常時人材募集をしている介護事業所では、どちらの介護事業所が良い人材を採用できそうですか。
答えは簡単です。
常時人材募集をしている介護事業所の方が、良い人材に出逢える可能性が高いです。自社にぴったりと合う人材など世の中にそれほど多くは存在していません。当然、自社が人材募集をしているときに自社にぴったりと合う人材が応募してきて採用される確率を考えてみれば、それがとてつもなく低いことは容易に想像がつくはずです。
次に、人材募集を求人広告や人材紹介に頼っている介護事業所とそうでない介護事業所では、どちらの介護事業所が将来的に良い人材を採用できそうですか。
こちらの答えも簡単です。
求人広告などに頼らない介護事業所の方が、将来的に良い人材を採用できる可能性が高いです。なぜなら、求人広告も人材紹介も自社にとって最適な人材募集方法にたどり着くことが難しいためです。一方、自社で採用活動を行う場合は、人材募集のすべての過程が自分ごとです。さまざまな方法を試し、PDCAをまわし、結果として自社にとっての人材募集方法の最適解を見出すことができます。P
なお、求人広告や人材紹介に頼っていない介護事業所では、採用コストが大きく膨らみます。採用コストの上昇は、介護事業所の利益を削るだけです。利益が減れば、スタッフの賃金アップや処遇改善に使えるお金が少なくなります。いつまで経っても、社内留保は増えず、人材の自転車操業が続く未来が想像できます。果たして、そんな介護事業所で働きたいと思えるでしょうか。
最後に、人事担当者が毎年同じような方法で人材募集を繰り返している介護事業所と人事担当者が採用のための研修を毎年受講して採用に関する知識をブラッシュアップしている介護事業所では、どちらの介護事業所が良い人材を採用できそうですか。
正解は明らかですね。
人事担当者が採用の研修を毎年受講し、知識を磨いている介護事業所の方が、当然、良い人材を採用できる確率は高くなります。
人事の仕事はルーチンワークであり、毎年同じことの繰り返しです。ですから、法改正があればその知識を学ぶことはありますが、採用に関して毎年新しい情報を上書きしている担当者はほとんどいません。
ルーチンワークでは、誰でも同じレベルで結果を出すことが重要視されます。退職者の発生が確定すれば、ハローワークに求人原稿を提出し、媒体に求人広告を出し、人材紹介会社に連絡する。これだけの作業では、採用に関する知識は一向に深まりません。博打をしているような状況といっても過言ではないでしょう。
これらの観点から、慢性的な人手不足という環境下での採用戦略として、次の3つのポイントが導き出されます。
①常時人材募集をする
②自社で採用戦略のPDCAをまわす
③人事担当者の採用スキルアップをする
3.人事担当者のリスキリングで採用力を高める
リスキリングという言葉を聞いたことはありますか。
岸田文雄首相の肝入り政策のひとつで、労働者の学び直しを推進するものです。昨年12月には、厚生労働省が人材開発支援助成金の中に事業展開等リスキリング支援コースを新設しました。これは、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
助成金を利用するには、「新たな事業展開」、「DX化」、「グリーンカーボンニュートラル化」のいずれかに関わる教育訓練である必要があります。
ところで、人事分野においては、勤怠管理等のDX化がかなり進んでいます。しかしながら、採用についてはほとんどDX化されていません。一方で、求職者や転職希望者のDX化が進んでいる状況下にあります。
介護現場はどんどんDX化されていきますが、採用の現場はほぼアナログのままです。
このような現状を鑑み全ての介護事業所に「人事リスキリング」の推進をお勧めします。
人事リスキリングとは、文字通り人事担当者の学び直しです。採用に特化した体系的なプログラムを学ぶことによって、他の介護事業所との差別化ポイントが明確になり、介護事業所の採用力が大きく高まります。
最後になりますが、『今日が一番採用し易い日』です。今日より明日、明日より明後日は、確実に採用が難しい局面になっていきます。
介護事業所間の厳しい採用競争に勝つためには、人事リスキリング講座(リンク先:オフィススギヤマサービスページ)で最新の採用マーケットや求人原稿作成技術を学び、1日でも早く効果的な人材募集を始めることです。
採用に苦労しないよう、是非アクションを進めましょう。
◆「医療・介護系求人で3ヶ月間に50人以上の応募を集めた超バズリ求人原稿」のプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
実際に「医療・介護系求人で3ヶ月間に50人以上の応募を集めたバズリ求人原稿」を希望者全員に無料プレゼントします。実績のある原稿をしっかり読み込んで、採用担当者の頭の中をリスキリングしていただければ幸いです。なお、事業所が特定できないように、一部加工してお渡しいたします。
お気軽に下記からお申し込みください。