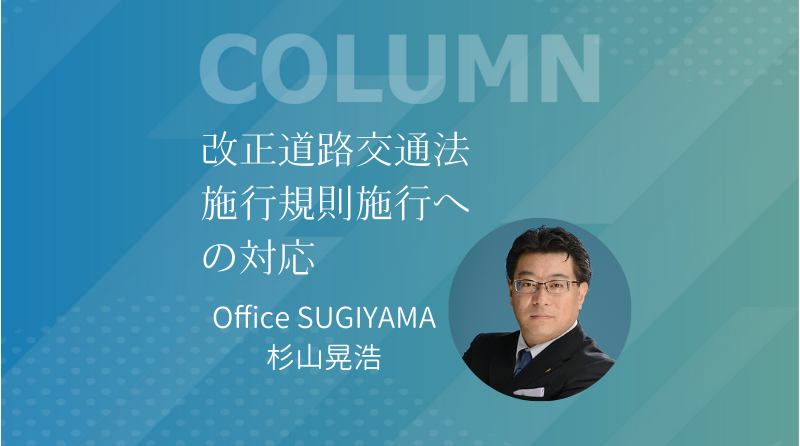送迎車両をはじめ、多くの介護事業所の業務遂行には欠かせない自動車。2022年4月1日から改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の選任が必要な事業所では、社有車を運転するスタッフにアルコール検査が義務付けられます。
【道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者の業務の拡充について(通達)】
1.アルコール検査が義務付けられる事業所とは?
自社の事業所で対応が必要かどうかは、安全運転管理者の選任が必要か否かで決定します。
そこで、先ず事業所が安全運転管理者の選任基準に該当するか否かをチェックしましょう。
事業所で使用している自動車の台数が次のAまたはBのいずれかに該当していれば、アルコール検査が義務付けられる事業所となります。
《安全運転管理者の選任基準》A 乗車定数が11人以上の自動車を1台以上使用している
B その他の自動車を5台以上使用している
事業所とは、自動車の使用の本拠地を意味しています。すなわち、会社全体の台数ではなく、本社や支店ごとに自動車が何台あるか確認する必要があります。
台数を計算する際に、原付バイクを除く自動二輪車は1台当たり0.5台としてカウントされます。社長車、従業員の持ち込み車両、リース車両を含み使用するすべての自動車が対象となります。つまり、社有車以外も対象となることがありますから、判断に迷ったら事業所を管轄する警察署で確認してみましょう。
なお、自動車を20台以上使用している事業所では、20台ごとに1名副安全運転管理者を選任しなければなりません。
ところで、今回は該当していなくても、施設定員の増加に伴い送迎車両を増車したり、訪問介護事業の拡大に伴い増車したり、営業や管理機能強化のために社有車を購入したときには、台数基準に該当するかもしれません。社有車管理リストや業務使用車管理リストに「5台になったら安全運転管理者選任しよう!」などと朱書きしておくと届出忘れが生じません。
2.安全運転管理者の届出方法
安全運転管理者や副安全運転管理者の選任を必要とする事業所が、選任を怠ってしまうと罰金5万円以下の刑罰に処せられることがあります。この点は十分注意してください。
安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に書類を整えて、事業所を管轄する公安委員会に提出します。
なお、添付書類として次の2つの書類を準備する必要があります。
①運転免許証の写し、戸籍抄本又は住民票(マイナンバーを省略しているもの。)の写しのいずれか
②運転記録証明書 (自動車安全運転センターで1ヶ月以内に発行された過去3年又は5年間のもの。)
運転記録証明書は窓口で申請してもすぐに受け取ることができないので、余裕をもって準備しておきましょう。業務を抜けられない方や窓口が遠方にある方には郵送でも対応してくれます。
3.安全運転管理者についての要件と業務内容
安全運転管理者や副安全運転管理者になることができる方は、「事業所に常勤し、ほかの事業所と兼務せず、使用者から必要な権限を与えられている者」に限られます。
この条件を満たしたうえで、次の資格要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。

安全運転管理者には、次の8つの重要な業務があります。
①交通安全教育
②運転者の適性等の把握
③運行計画の作成
④後退運転者の配置
⑤異常気象時などの措置
⑥点呼と日常点検
⑦運転日誌の備付け
⑧安全運転指導
安全運転管理者は、安全運転管理者等講習を年に1回受けなければなりません。この講習は、丸一日かかります。業務に支障をきたさないためにも、あらかじめ年間スケジュールをチェックしておくことをお勧めします。
4.アルコール検査のやり方
アルコール検査のタイミングは、運転前と運転後の2回実施します。そしてその結果を記録し、1年間保存します。
なお、具体的なアルコール検査の方法など事業所で必要な対応は、改正道路交通法施行規則日に応じて、次のようになります。
◆2022年4月1日~
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
②酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存すること
◆2022年10月1日~
①運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること
アルコール検知器については、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有することが必要です。とはいえ、通所販売されているアルコール検知器は、これらの機能を有していると思われるので、自由に選ぶことができます。
ただ気を付けるべきポイントは、アルコール検知器を常時有効に保持することです。検知器のセンサーが何回使えるかなど、購入時に確認しておかないと、買い替え時期が意外と早くなってしまうかもしれません。
また、数人で使いまわしするよりも、1人1台を使う方式をお勧めします。事業所のオペレーションによっては、直行直帰の発生が考えられます。1人1台持ちの状態であれば、どこでもチェックができる状態にしておくことが大切です。
記録については、紙で記録する方法とパソコンなどに記録する方法があります。記録の保存期間が1年間なので、パソコンやクラウドに保存できるアルコール検知器の利用をお勧めします。なお、紙で記録するときは、全日本トラック協会標準帳票がアルコール検知器使用義務にも対応しているため、自社用に真似して作るのも良いでしょう。
【全日本トラック協会標準帳票点呼記録簿記入例(公益社団法人全日本トラック協会)】
5.併せて確認しておきたい事項
事業所内に新たなルールが適用されることになれば、就業規則の見直しとスタッフへの周知が必要になってきます。
就業規則においては、次の項目条文への追加や見直しが必要となることが多いのではないでしょうか。
①服務
②遵守事項
③懲戒
④解雇
⑤安全衛生
就業規則の他にも、入社誓約書などにアルコール検査義務と罰則を明示しておくことで、より実効性を高めるものと考えます。
今回のアルコール検査義務化は、2021年6月、千葉県八街市で発生した下校中の児童5名が死傷する凄惨な交通事故が発端となっています。この事故が発生した原因には、トラックの運転者が飲酒していたことや運転者が勤務する事業所が安全運転管理者を選任していなかったことなどの問題がありました。
もしも自分の勤務している事業所でこのような事故が発生したら、経営者は使用者責任を問われ、多額の損害賠償の請求を受けることになるでしょう。
最後に、飲酒運転の防止を目的とした法改正ですが、自動車運転にまつわるトラブルにはあおり運転や無免許運転など、モラルの欠如が原因となるものが多数存在します。ぜひこの機会に、就業規則を見直すなどコンプライアンス遵守を徹底させ、良い職場づくりを目指していただきたいと考えます。
◎お知らせ
『アルコール検査規程』が必要な方は、無料でプレゼントします。
お申込みはこちらから ⇓
https://forms.gle/RyHaeuo5NV4MUyCf6
『就業規則診断』を希望される方は、無料で10ページ程度の診断レポートをプレゼントします。
お申込みはこちらから ⇓
https://forms.gle/wn6Jd6rwdr4ErDqS6