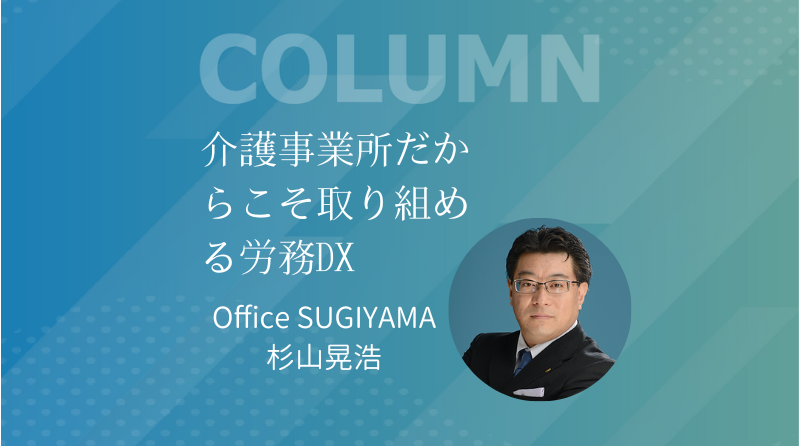1.介護事業所が労務DXに取り組みやすい理由
近頃では、DX(デジタルトランスフォーメーション)というキーワードが広く使われるようになっています。2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が、DXは「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」ものであると定義してから、既に18年の月日が流れました。
日本では、18年に経済産業省が作成した「DXを推進するためのガイドライン」では、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。
20年には、情報処理促進法に基づき経営者に求められる企業価値向上に向け実践すべき事柄が「デジタルガバナンスコード」として策定されました。対象は、企業規模、法人・個人事業主の別などにかかわらず広く一般の事業者とされています。当然に、介護事業所も含まれます。
また、22年には、「デジタルガバナンス・コード2.0」が発表され、改訂ポイントがわかりやすく示されています。私が注目しているのはDX認定・DX銘柄の認定において、「ITシステム・デジタル技術活⽤環境の整備に関する⽅策」として、「DX推進のための投資等の意思決定において、コストのみではなくビジネスに与えるインパクトを勘案すると同時に、定量的なリターンの⼤きさやその確度を求めすぎず、必要な挑戦を促進している」ことが重要視されている点です。
さて、みなさまの事業所ではDXの推進に取り組んでいますか。
実は、介護事業所は、とてもDX化が導入し易い業界だと考えています。特に労務DXに手を付けていない介護事業所は、今後より利益の確保が難しくなると断言できます。
DX化に着手しやすいという根拠は、次の3つです。
①勤務シフトが定形的である
②報告書類に記載すべき内容が決まっている
③小規模事業所が多い
①勤務シフトが定型的である
勤務シフトが定形的なので、出退勤の記録を簡単にデジタル化できます。その結果、勤怠集計や給与計算といった定型業務の処理時間を大きく減少させることができます。
例えば手計算で労働時間集計や給与計算業務をすることを考えてみてください。計算機の打ち間違い、文字の読み間違い、60進法に直す際の計算間違いなどなど、人の手が介在することでさまざまな間違いが発生するリスクがあることが分かります。間違いが発生する可能性は容易に予想がつくため、何度も検算する。事業所によっては、給与に関することだから間違ってはいけないと、二重チェックを二人で実施するなど、業務時間が大きく取られています。
勤怠集計や給与計算業務というのは、非生産的な作業です。一方で、定型的な作業なので、デジタル化が比較的簡単です。デジタル化した当初はプログラムミスやシステムのバグを確認するために、手計算と併せて行うことになり業務量が増えます。でも3カ月もすればミスやバグの対応は終り、大幅に業務時間の短縮ができます。
②報告書類に記載すべき内容が決まっている
介護事業所にはさまざまな報告書を作成する義務が課されています。
報告書の種類が多いということは、報告書を探す時間が必要になります。何かを探す時間もまた、、非生産的な時間であり、極力減らしたいですよね。でも報告書がデジタル化されていれば、検索機能を活用して探す時間をグッと短縮することができます。
それぞれの報告書には、記載しなければならない事項が共通のものも多いです。氏名などの基本データは、コピーアンドペーストで、入力時間を減少させることができます。
クラウドシステムを使えば、いくつ事業所があっても、どこでも情報共有できます。例えば無料で使えるスプレッドシートを使って、あらかじめ書類の体裁を整えておきます。書類作成の必要に応じて、必要な事項だけ入力すればよいですね。選択制の項目であれば、プルダウンで簡単に選択できるようにするなど、工夫すればいくらでも時間短縮が可能ですね。
③小規模事業所が多い
令和3年度介護労働実態調査によると介護事業所全体における、1事業所あたり平均人数は20.5人です。最も多い施設系では52.6人となっています。
つまり、多少時間がかかろうとも、一人一人に寄り添って丁寧に教えることができます。
「デジタルガバナンス・コード改訂のポイント」では「 組織づくり・⼈材・企業⽂化に関する⽅策」において「社員⼀⼈ひとりが、仕事のやり⽅や⾏動をどのように変えるべきかが分かるような、経営ビジョンの実現に向けたデジタル活⽤の⾏動指針を定め、公開している」ことを求めています。
あなたは「DX化にチャレンジしている介護事業所」と「できない理由を盾にDX化にチャレンジしない介護事業所」のどちらが未来に生き残る介護事業所だと考えますか。
介護事業所経営者のDX化が必要だと判断すれば、DX化を一気に進めることができます。
2.IT化ができない理由を疑う
労務DX化といいながら、介護事業所では”IT化”からスタートするのが一般的です。
DX化では、ビジネスモデルの抜本的な改革を目指します。いわば、質的変化です。IT化は、これまでの業務プロセスをデジタル技術によって効率化します。つまり、量的変化です。
例えば、セミナーなどで介護事業所経営者にIT化をお勧めすると、次のような回答が大半を占めます。
『職員が高齢者ばかりだからできません。』
『規模が小さいのでできません。』
『費用がかかることはできません。』
『ITが分からないのでできません。』
『紙で特に問題だと感じたことがないので、今のままで十分です。』
でも、本当にこのような考えのままで良いのでしょうか。
『職員が高齢者ばかりだからできません。』
今、高齢スタッフは何名いますか?たった1名高齢スタッフがいるだけで、IT化をあきらめてしまう経営者が多いことも事実です。デジタル機器を導入しようとすると、IT化についていけない高齢スタッフが退職してしまうのではないかというおそれが少なからずあるようです。
しかし、現実には、高齢スタッフであっても、デジタル機器を使っている人はたくさん存在しています。使い方が分からないのであれば、教えればよいだけです。介護事業所のみならず、全ての事業所に求められていることは、「リスキリングやリカレント教育など、全社員のデジタル・リテラシー向上の施策」を実行することです。
『規模が小さいのでできません。』
規模が小さいからこそ、IT化の導入がしやすいのです。新しいことを覚えてもらうスタッフが少ない方が浸透し易いですよね。一人一人に寄り添う時間が増えるので、技術が身に付くのも早いはずです。
規模が小さいからこそ、非生産的な業務を極力排除し、生産的な業務に集中できる環境を作らなければ、明るい未来を考えることができません。
『費用がかかることはできません。』
無料で利用できる勤怠管理システムを探してみたことはありますか。
労務DXを進めるのであれば、定形業務のデジタル化、IT化は基本です。
例えば電子タイムカードは月額1人300円程度のシステムであっても、十分利用できるものがあります。小規模事業所であれば、毎月数千円程度の投資で、勤怠管理から給与計算、給与明細の配布までがあっという間に終わってしまうケースも多々あります。
小規模事業所であっても、手計算であれば勤怠集計に相当な時間が必要です。手計算で給与計算をすれば、何度も検算を行うことでしょう。これらの時間は、売上に繋がらないどころか残業代などのコストになって介護事業所の利益を減らす原因となります。
ぜひ、必要な挑戦をしていただきたいと思います。
『ITが分からないのでできません。』
勤怠管理システムや給与計算システムの中には初期設定が難しいものが存在しているのも事実です。
初期設定の壁を破るには、ユーザーインターフェースが良いもの、すなわち自分で使ってみてわかり易いものを探すのがもっとも近道です。30日間無料で利用できるアプリなども多いので、実際に利用して試しやすくなっています。
費用は掛かりますが、専門家や販売店に設定をお願いしてしまうのも有効です。入力画面における入力項目や入力箇所などをマニュアル化しておけば、自社運用も簡単になります。
何もしないままでいると、IT化していく介護事業所と比較して利益体質が劣るようになります。利益体質が悪ければ、スタッフの給与アップができなくなり、低い給与で求人募集するしかなくなります。当然、離職者が増え、入職が少なくなるので、事業の継続にも大きな壁が立ちはだかることになります。
『紙で特に問題だと感じたことがないので、今のままで十分です。』
電子帳簿保存法の改正、インボイス制度の導入、マイナンバーカードの保険証利用など、行政は積極的にIT化、DX化を進めています。
現状、IT化、DX化についてこれない介護事業所に対して、救済措置的にアナログ管理、アナログ処理ができる余地が残されています。いつまでもこのままであれば、行政コストが高止まりしてしまいます。私は、デジタル管理、デジタル処理が義務化される未来は案外近いと考えます。その時になって、慌てないように、困らないように、今から準備を進めなければならないのです。
3.労務DXを実施する際の注意点
勤怠管理から給与計算を例にして、労務DXの4つの注意ポイントを解説します。
①事前準備
②システム運用
③データ活用
④スタッフの承諾
①事前準備
勤怠管理システムを運用するにあたり、複雑な勤怠制度は弱点となります。
仮に現在が複雑な勤怠制度であれば、シンプルな勤怠制度に変更し、就業規則の変更も行います。
勤怠システムを運用するのはAIではなく人間です。素人に複雑なプログラムは組めません。だから、『システムは人間よりも賢くない』と考えて、勤怠制度の整備から始めましょう。
②システム運用
勤怠管理システムの運用を始めると、打刻漏ればかりするスタッフが発生することがあります。
打刻漏れした場合の取り扱いについて、しっかりと情報共有するようにしてください。例えば打刻忘れしたら懲戒するなど、運用ルールも明確にしておきましょう。
《参考》労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
③データ活用
勤怠管理システムの設定を、給与計算システムに合わせて細かく設定しておきます。勤怠情報を締めた後にCSVデータでデータを抜いて、給与計算システムに簡単に取り込めるようにしておきましょう。システムによっては、API連携していて、簡単に給与計算ができるものもあります。
④スタッフの承諾
給与明細をスタッフに直接メールで送るなど、電子明細を利用する介護事業所が増えてきています。
ただし、あらかじめスタッフに対し、電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面による承諾を得なければなりません。
電子明細の導入を決めたら、先ずは全てのスタッフに同意書を配布するところからスタートします。
これらの注意ポイントに気を付けて、IT化を進めてください。
◆「給与明細電子化同意書(例)」のプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
「給与明細電子化同意書(例)」を希望者全員に無料プレゼントします。
お気軽に下記からお申し込みください。
「給与明細電子化同意書(例)」プレゼント希望