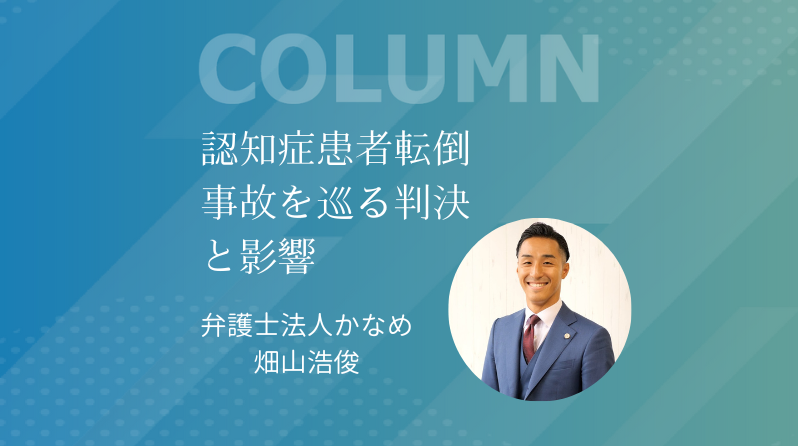昨年、介護・医療業界で注目を集めた判決があります。
兵庫県立西宮病院で平成28(2016)年4月2日に認知症患者の男性が廊下で転倒して重い障害を負ったことに対し、病院を運営する兵庫県に約532万円の賠償を命じたものです。
有名人によるSNSでの言及がきっかけで知った方も多いのではないでしょうか。
病院側に過失があったとする判断は、裁判所が事実関係や証拠関係を元に導き出したものですが、現場の感覚は乖離していると言えるでしょう。
この判決が下されたプロセスやその根拠について解説し、業界に与える影響などを考察します。
1.兵庫県立西宮病院で起きた転倒事故と判決に対する世間の反響
この判決に対しては様々な批判が出ました。
特に介護現場・医療現場で働く職員や看護師の方々から「やってられない・・・」「裁判官は現場を全く理解していない」というような絶望感に満ちた声も数多く出ています。
2ちゃんねる創設者で実業家のひろゆき氏が自身のツイッターで「認知症患者は、ベッドに縛り付けて動けなくするのが正解ということですね」とつづったこともあって、この判決はあっという間に世間の耳目に触れることになりました。
どのような事案であったのか以下に解説します。
2.転倒事故の概要―当時の病院の対応と認知症患者の男性が負った障害
(1)転倒した男性の当時の状態
転倒した男性は当時87歳で認知症に罹患していました。認知症の中でも前頭側頭型認知症と診断されていました。前頭側頭型認知症の特徴は抑制が効かなくなる、同じことを繰り返すなどといった症状がみられることです。実際、この男性も情緒不安定になっていたほか、生活は昼夜逆転しており、大声を出す、ひどい物忘れがあるなど、感情の不安定や易怒性があることが指摘されていました。ただ、自立歩行は可能な患者だったようです。これらの事実だけでも、介護困難な患者であったことが容易に想像できます。
離床を検知して知らせるキャッチセンサーが鳴り、ナースステーションから看護師が向かうと、男性は看護師の制止を聞かずに叫び、ふらつきながらも素早く起き上がろうとすることもあったようです。また、既に起き上がっている状態であることもあったので、病院側は転倒転落のリスクが高いと判断し、家族の了解を得て体幹ベルトを使用していました。
(2)転倒事故の発生
このような状況の中で転倒事故が発生します。
平成28年4月2日午前5時頃、男性はベッドから起き上がろうとしたためキャッチセンサーが鳴りました。看護師がすぐに病室へ向かったところ男性は「トイレに行く」と尿意を伝えます。先ほどもトイレに行ったことを伝えたのですが男性は言うことを聞かなかったため、看護師は体幹ベルトを外し、男性を誘導し、男性が便座に座ったことを確認してからトイレの扉を閉めました。その後、別室患者からのナースコールが鳴ったので、その看護師は別室に移動し別室患者の排便介助を行いました。その間に男性はトイレから出て病室前の廊下へ移動し、仰向けに転倒してしまったのです。この転倒事故が原因で男性は両上下肢機能全廃という後遺障害を負いました。
3.裁判所の判断が下されるまでのプロセス
裁判所の判断が下されるまでのプロセスを見ていきましょう。
(1)損害賠償責任が認められるための要件
損害賠償責任が認められるためには、
①過失②過失と結果との間に因果関係があること③損害が発生していることの3つを満たすことが必要です。当然、転倒事故の裁判では、争う原告側は、「病院側に過失がある」と主張することになります。
ここで重要になるのは①過失です。過失はさらに2つに分解されます。
【過失は2つの要件に分解される】
ア 結果を予見する可能性と結果を予見する義務
イ 結果を回避できる可能性と結果を回避する義務
(2)裁判所の判断
ア 結果を予見する可能性と結果を予見する義務について
裁判所は、転倒した男性が入院する前の状況や入院後の状況からすると、この男性をトイレ内に放置し、他の患者の元へ行けば、便座から勝手に立ち上がりトイレから歩いて出ようとして転倒するおそれが高いことは十分に予見できたと認定しています。
イ 結果を回避できる可能性と結果を回避する義務について
裁判所は以下のとおり結果回避義務違反を認定しました。
本件病室内のトイレの便座に亡B(男性のこと)を座らせたまま亡Bから目を離せば同人が転倒する危険性があったから、本件看護師においては、亡Bが排尿を終えて同人がベッドに戻るまで目を離さないか、他の看護師に見守りを依頼する注意義務があり、それにより亡Bの転倒の結果は回避できたといえる。それにもかかわらず、本件看護師はいずれの対応をとることもなく、亡Bをその場に残したまま、別室患者からのナースコールに応じてその場を離れたものであるから、本件看護師には結果回避義務違反が認められる。
※括弧内の記載、下線は筆者
病院側は、別室患者からのナースコールは緊急性が高い可能性等も考えられたこと、別室患者は高熱を伴う感染症に罹患する脳性麻痺患者であり、漏便による汚染でさらに悪化する可能性が高いことから、すぐに別室患者の排便介助に向かったのであってトイレ内の男性から離れたことに注意義務違反はないと主張していたのですが、裁判所は、別室患者の診療記録上、同患者がおむつを着用していたこと等を指摘し、トイレ内男性の排尿介助を優先することで直ちに別室患者の生命健康に対する重大な危険が生じるおそれが高かったとは認められない、と主張を退けています。
また、病院側は、当時の夜勤体制は3名体制であったものの、1名は休憩に入ったところであり、もう一名は別の患者のナースコールに対応中であった上、上記のとおり別室患者の緊急対応を要する可能性もあったため、休憩中の看護師を呼び出しても間に合わないと考え、休憩中の看護師に声をかけなかったのであるから注意義務違反はないと主張しました。これに対し、裁判所は、上記のとおり、上記の別室患者の状態に照らせば休憩に入っていた看護師にトイレ内男性の介助を引き継ぐか、別室患者のナースコールへの対応を依頼するだけの時間的余裕がなかったとまでも認め難い、と判断し、病院側の主張を退けています。
4.判決に対して思うこと
介護や医療の現場感覚とは乖離した判決が下される背景
上記のとおり、「過失」の有無は、裁判所が事実関係や証拠関係を元に法的に評価して認定します。この裁判所の評価や認定について、世間の反応は「介護現場の感覚から大きくずれている」と反発している状況です。
たしかに、裁判所はあくまで原告や被告から提出される事実の主張、証拠の提出を踏まえて、それらを裁判官室でじっくりと俯瞰し、評価することが仕事です。「理屈」を積み上げていく作業ですから、その作業の結果、導き出される結論が介護現場の感覚からずれてしまうことはある意味やむを得ないことであって、それこそ、司法の限界なのではないかと思う部分があります。
しかし、現実問題として、その判決が介護現場や医療現場に与える影響は計り知れません。現場で一生懸命に働く方々からすれば「ナースコールが鳴って、その瞬間にその人の緊急対応の可能性は現場に行ってみないとわからないし、休憩中に入ったばかりの人にすぐに声をかけるなんで無理だよ。」「別に現場の業務をサボって個人のスマホに夢中になっているときに起きたような業務怠慢の事故ではなくて、他の人の介助に急いで行ったときに発生した不慮の事故なのだから、何故これで法的に責任を負うの?」という判決に対する違和感を覚えることはやむを得ないといって良いでしょう。
「過失」の要件をどう判断すべきか
筆者が懸念するのは、実際にこのような判決が出ることによって、介護・医療現場で身体拘束が加速してしまうのではないかということです。身体拘束は原則として禁止されているのですが、介護・医療現場から見て、理不尽と感じられる判決が相次いでしまうと、「認知症で職員の指示を聞いてもらえず激しく動くような利用者・患者は身体拘束しよう」、「転倒してしまうと賠償責任を負ってしまうからこれもやむを得ないじゃないか」、という考え方が広がってしまうのではないかと思います。
国は高齢者虐待防止の義務付けをしていますが、一方で転倒して怪我を負わせたら司法判断で厳しい結末が待っています。現場の方々はこの状況を見て、「個人の尊厳を尊重した介護・医療なんて程遠いじゃないか」「個人の尊厳が大切と言うのであれば、生活の場や緊急性の高い医療の現場で起こる事故については、もっと現場に寄り添った司法判断をしてくれないと、肝心の介護・医療の現場を支える人がいなくなってしまって、個人の尊厳なんて実現できなくなるじゃないか」、と現場の方々は感じてしまいます。
筆者としては、民事訴訟のルールに則って裁判所が判断を下していくことは司法の仕組み上、正しいことであり、それ自体に問題は無いと思うのですが、裁判所が「過失」の判断をするときについては、もっと介護現場や医療現場のリアルに目を向けて判断して頂きたいと思っています。要するに、「過失」の要件は、わざと怪我をさせたというような「故意」に匹敵するような重大な注意義務違反、つまり「重過失」に限定して判断しても良いのではないかと思います。
たしかに今回取り上げた事案でも、休憩に入ったナースに声をかければ防げたのかもしれません。しかし、現場の感覚としては、「ナースコールが鳴ったらすぐにかけつけないといけない」、「トイレにいる患者と別室患者の距離は近く、すぐに行ける距離だったから自分がすぐに行かないといけないのではないか」、「別室患者は、気持ち悪いと思っているからナースコールを押したのだろう、早くオムツを交換してあげないと」、等と思って行動したのだろうと推測できます。
人として正しい感覚に基づいて働いている現場の方々の士気を低下させるような判決は、かえって日本の介護医療現場を人権侵害が蔓延するような閉塞感漂う空間にしてしまうのではないかと懸念します。
「過失」の要件の判断をどうすべきか、は国を挙げて議論すべきテーマです。
介護現場や医療現場から見たときに違和感を覚える判決が相次いでいる状況下では、早急に取り掛かるべき重要テーマだと筆者は考えています。