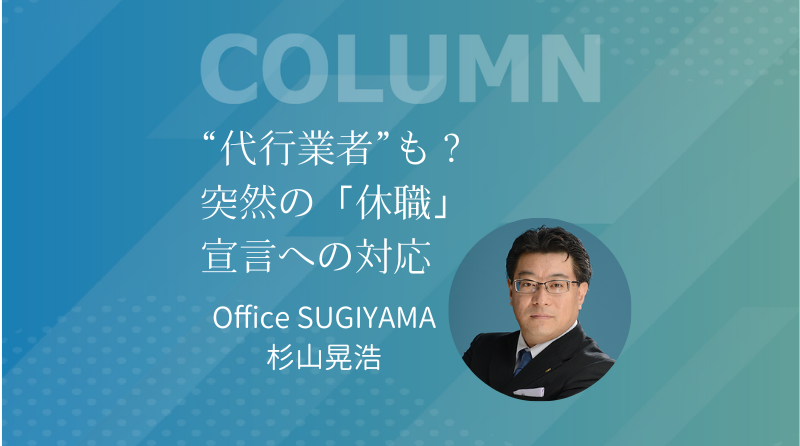「明日からこの職員は休職します。会社に診断書を送りますので対応してください」─。
こんな一方的な連絡を、見知らぬ“代行業者”から受けたらどうしますか?
近年、「退職代行サービス」が広く知られるようになりましたが、その派生として「休職代行サービス」も登場しています。
休職規定が整っていない介護事業所では、経営に影響を与えるケースもあり、注意が必要です。
休職は本人の一方的な意思表明だけでなく、就業規則に基づくルール運用と、会社の判断を伴って成立するため、事業所の取るべき対応は異なります。
にもかかわらず、休職代行業者は「本人が言いにくいことを代わりに伝える」だけという体裁を取りながら、実質的には条件交渉に踏み込むケースがあるのです。
これは弁護士法第72条が禁止する“非弁行為”にあたる可能性が高く、介護事業所がそのまま受け入れると大きな不利益を被りかねません。
この記事では、休職代行サービスの手法や休職を巡って介護事業所が直面しがちなトラブル、そして、事前の備えについて解説します。
1.「休職」とは?―労働基準法上に定めがないがゆえ介護事業にもたらすリスクを知ろう
まず、事業所で押さえておきたいのは、労働基準法には「休職」という言葉は登場しないということです。 休職は、法律で一律に定められた制度ではなく、各事業所の就業規則によって任意に定められる仕組みです。
つまり、その会社に*「休職制度」*があれば利用できますが、規定がなければそもそも休職はできません。
労働の現場では実際、
- 就業規則に休職規定がない
- 曖昧な表現で定められている(例:「必要に応じて休職を認める」)
- 休職期間や復職条件が不明確
- といったケースが非常に多いのです。
その結果、「休職開始日をめぐる争い」「期間延長の要求」「復職可否の判断をめぐる対立」といったトラブルが後を絶ちません。
2.スタッフ1人の離脱が命取りに…「休職」が介護事業所にもたらす経営リスクとは
介護事業所では特に、スタッフの休職が経営を揺るがす問題になりがちです。
代表的なリスクを整理すると以下のようになるでしょう。
人手不足の問題
介護業界の慢性的な人材不足により、介護事業所では1人の職員が長期休職に入るだけでシフトが崩れ、残された職員の負担が増します。精神疾患による長期化リスク
メンタル不調での休職は、復職の見通しが立ちにくく、数カ月から1年以上に及ぶ場合もあります。
職員が戻ってこられるのかどうかが見えないという事実によって、職場全体に不安が広がります。復職が定着しないケース
復職しても十分に業務がこなせず、再休職や再離職につながるケースもあります。その過程で他の職員との摩擦や不公平感が生まれ、チームの士気低下や離職に結びついてしまう可能性があります。利用者への悪影響
介護サービスは「人」そのものが提供価値となります。
休職を適切にマネジメントできないと、利用者やその家族からの信頼を損なうリスクがあります。
3.休職代行業者が入り込む“隙”を招く休職規定の曖昧さ
例えば、「休職期間は最長6カ月」としか定めていない就業規則の場合、「では、復職の判断は誰がどう行うのか?」という点で揉めやすくなります。
休職代行業者は、まさにそうした就業規則の“隙”を突いてきます。
- 休職開始日が曖昧だと… 「診断書が出たので、今日から休職します」と一方的に通知してくる。
- 休職期間の規定が不透明だと… 「まだ治っていないので、さらに休職を延長してください」と要求してくる。
- 復職基準が不明確だと… 「医師が復職可能と言っているのに、なぜ会社は復職を認めないのか」と食い下がる。
こうした主張を受け入れてしまうと、事業所側がコントロールを失い、代行業者や本人の主張に振り回されてしまうのです。
4.実務上介護事業所が取るべき対応のヒント
では、休職代行から連絡が来たとき、どう対応すればよいのでしょうか。
対応策1.「本人・医師の診断書」に基づく対応を徹底する:
代行業者からの一方的な連絡は参考程度にとどめ、必ず本人と医師の診断書を確認することが重要です。
対応策2. 就業規則の休職規定に従った判断を一貫して伝える:
「当社の休職規定に基づき対応します」と明確に伝えること。曖昧な対応はさらなる要求を招きます。
対応策3. 交渉を持ちかけられたら“非弁行為”を疑う:
「休職を延長してほしい」「復職を認めろ」といった交渉は弁護士以外ができることではありません。弁護士法第72条を踏まえ、毅然とした対応を心がけましょう。
対応策4.専門家との連携を欠かさない:
社労士や顧問弁護士に相談し、外部業者に流されないよう体制を整えておくことが肝心です。
5.休職代行に振り回されないための根本対策は「休職ルールの整備」
結局のところ、休職代行に振り回される背景には「就業規則の休職規定が曖昧」という問題があります。
- 休職の開始条件をどう定めるか
- 休職期間をどこまで認めるか
- 復職可否の判断基準をどう設けるか
- 再休職や復職失敗への対応をどう考えるか
これらをあらかじめルール化しておけば、外部の代行業者に口を出される余地はありません。
休職規定は単なる制度ではなく、介護事業所を守るリスク管理ツールです。 職員の数や業態、現場の実情に合わせて設計する必要があり、ここに社労士としての専門的な知見が求められます。
杉山事務所では、これまで多くの介護事業所で休職・復職トラブルを防ぐための規定整備を支援してきました。
「現場の実態に合った休職ルール」を作ることが、結局は職員と利用者双方を守ることにつながり、無用なトラブルを防止します。
6.まとめ
休職代行に振り回されるかどうかは、事業所が明確な休職ルールを持っているかどうかにかかっています。
- 曖昧な就業規則だった場合 → 代行業者(休職希望の職員)の一方的な主張を受け入れざるを得ない状況に陥ってしまう
- しっかりしたルールがあれば→ 「規定に従って対応します」で終わる
今こそ、自事業所の休職規定を見直すタイミングです。
今回、この内容に関連して、 「介護従事者のための復職可能診断チェックリスト」をプレゼントします。
復職判断の曖昧さを減らし、現場の混乱を防ぐための“最初の一歩”としてご活用ください。
◆読者プレゼント:復職可能診断チェックリスト◆
中小介護事業所でもすぐに活用できる「復職可能診断チェックリスト」を無料でプレゼント!
休職への対応で重要なのは、自社の復職判断基準を持つことです。
このチェックリストを使えば、確認事項の漏れがなくなります。自社向けにさらにアレンジを加えることも可能です。
希望者全員に無料プレゼントしますので、お気軽に下記からお申し込みください。