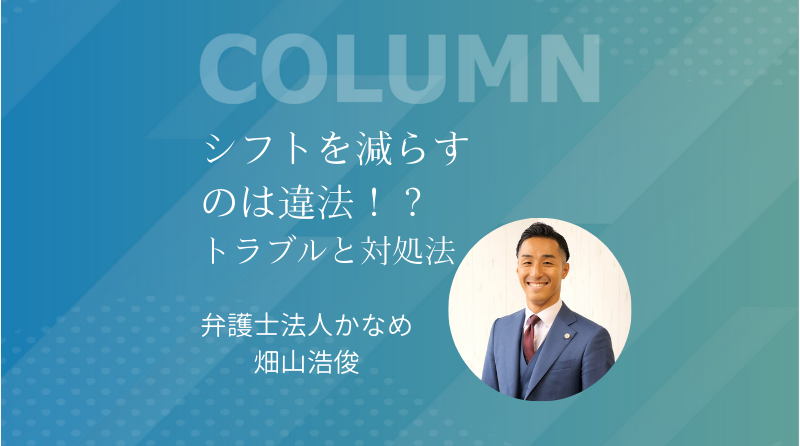1.介護現場のシフトトラブル事例
介護現場では 多くの場合 、「シフトにより勤務日を決定する」という内容で雇用契約を締結しています。シフトの組み方次第で勤務日数には変動があるものの、大体週3~4回などと人によって固定化していることも多くあります。
しかしながら、例えば、そのスタッフが資格を有していない関係で、特定の資格を必要とされる業務に配置できず、結果としてシフトが減ってしまった、もしくは、コロナ禍でシフトが減ってしまったという場面があります。
シフトが減るということは、当然給料が減ることを意味します。
実際に 、「シフトで週3日は入ることが確保されていたのに、そのシフトを入れてくれないのは違法だ。週3日分の給料を支払って欲しい。」といった トラブルに発展するケースがあります。
シルバーハート事件(東京地裁令和2年11月25日判決) は、この点がトラブルになっ た事例です。原告が主張したの は、「勤務時間は週3日、1日8時間、一週間で24時間と合意していたのだから、それに満たない分は未払いだ!未払賃金を支払え!」という内容 でした。法人側としては、「あくまでシフトは流動的なものなのだから、確実に週3日なんて約束していないじゃないか。」と 反論しています。
シフトを巡る トラブルに 対しては、雇用契約の内容をどのように考えるのかが非常に大切なポイントになってきます。
2.シフトと雇用契約の関係―事業者と職員のトラブルを防ぐために重要な視点
どの介護現場でも、職員との間で雇用契約を締結しています。
シフトの場合、「シフトによる」という記載をよく見かけますが、中には、「週3日」や「週3~4日」といったように、日数を記載しているパターンもあります。
雇用契約の内容は もちろん、雇用契約書にどのような記載があるのか、という点も大切なのですが、実態がどうなっているのか、という点が最も重要です。
例えば、雇用契約書には 「シフトによる」との 記載のみ があり、形式的には、日数に関する記載は ありませんでした。 しかし、採用面接時に、「必ず週3日は仕事できます。」と期待させた上で、なおかつ、入社から1年間、ずっと継続して週3日勤務の実態があるような場面で、突然、1年後、シフトを減らされたような場合であれば、週3日必ず働くという内容で雇用契約が成立していたと認定される可能性があります。実態がどうなっているか、という点を見落としてはならないのです。
シルバーハート事件では、原告は、勤務時間は週3日、1日8時間、週の合計は24時間との雇用契約を締結していたと主張しましたが、雇用契約書の記載内容や実際の勤務実態はどのようなものだったのか、見てみましょう。
原告は入社面接の際に、「週3日、1日8時間、週24時間」という希望を実際に会社に伝えていました。
しかしながら、雇用契約書の内容は、始業時刻午前8時、終業時刻午後6時30分、休憩時間60分の内8時間、という記載の他は、手書きで「シフトによる。」という記載があるのみで、雇用契約書からは週3日であることを窺わせる記載はありませんでした。また、勤務開始から約2年間の実績を見ると、1カ月の出勤回数は9 ~16回であり、週3日のシフトが固定で組まれていた訳ではありません。
さらに、この 現場では 、管理者、相談員、運転、入浴担当、アクティビティー担当等の役割を考慮して、各役割につき1人ずつ配置する必要がありました。そして、原告は、運転免許や相談員の資格を有していなかったので、アクティビティーか入浴のシフトにしか入れません。このような事情を加味すると、週3日のシフトを固定することは困難でした。
以上のような雇用契約書の記載や原告の勤務状況、介護事業所のシフトを組む上での実態を踏まえ、裁判所は、「勤務時間は週3日、1日8時間、週の合計は24時間」という内容の合意など無かったと事実認定しています。原告の請求は退けられました。
3.大幅にシフトを減らすことの問題点
このように一定の日数を必ずシフトに入れる点が雇用契約の内容になっていないとしても、会社側が一方的に何の理由もなく、シフトを大幅に減らすと違法になる場合があります。
シルバーハート事件で、裁判所は、「シフト制で勤務する労働者にとっては、シフトの大幅な削減は収入の減少に直結するものであり、労働者の不利益が著しいことからすれば、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり違法となり得る」と論じています。
例えば、運転業務において、頻繁に交通事故を引き起こす職員がいたとします。会社側は、利用者の生命身体健康に対する安全配慮義務を負っていますので、事故を何度も繰り返す職員を漫然と運転業務に従事させ続けると、それ自体が安全配慮義務違反と指摘されかねません。また、車両の修理費用や保険料のコスト増など、経費面の負担が増大すると会社経営がひっ迫する要因にもなりますので、この事態にも対処しなければなりません。このような理由から、当該職員を運転業務から外し、結果として、当該職員のシフトが大幅に減ってしまうようなケースでは、シフト大幅減に関する合理的な理由があると言えるでしょう。
これに対し、合理的な理由が無いにもかかわらず、シフトを一切入れないなどの対応をしてしまうと、シフト決定権限の濫用と判断され、一定額の賃金や賠償金を負担しなければならない結果になります。シルバーハート事件でも、合理的な理由がないシフトの大幅減が一部に認められるとして、会社側が一部敗訴しています。
介護事業所としては、仮にシフトを大幅に減らす事態が生じるとしても、必ず、何故そのような事態になるのか、その理由がどこにあるのか、を具体的に当該職員に説明するようにしましょう。その際、説明できる具体的理由が見当たらないのであれば、一旦立ち止まって、そのようなシフトを減らす処置をしても良いのかどうか、弁護士や社労士などの専門家に相談するようにしましょう。
4.介護現場のシフト調整にかかる膨大なコストを把握し解消を
ところで、シルバーハート事件では、シフトを調整する過程が記載されています。
簡単にまとめると、
【ステップ1 】
前月の中旬頃までに各従業員が各事業所の管理者に対し、翌月の希望休日を申告
【ステップ2 】
各事業所の管理者は希望休日を考慮して作成したシフト表の案を、前月下旬頃に開催されるシフト会議に持ち寄り話し合いを行う。
【ステップ3 】
各事業所の人員が適正に配置されるよう、人手が足りない事業所には他の事業所から人員の融通を行う等の調整を行った上で、シフトが正式に決定される。
という流れです。
介護事業所の読者の皆様は、このステップを読んでも、何ら違和感を覚えないと思います。
この「シフトを組む」という作業は、大勢の職員の予定調整、介護事業所が守らなければならない人員基準などをベースに実施する必要があるので、膨大な時間がかかっています。筆者が直接聞いた事例では、シフトを組むのに1週間から10日以上かかる介護事業所も珍しくなく、このコストをどのように削減するかはまさに経営課題と言っても過言ではありません。現在は、介護業界の経営課題を解決することを目指したICTツールが日進月歩で開発されており、シフト勤務表を自動作成する調整ツールを提供している企業も存在しています。
便利なツールも駆使しながら、介護現場で生じるトラブルが一つでも減少することを願います。