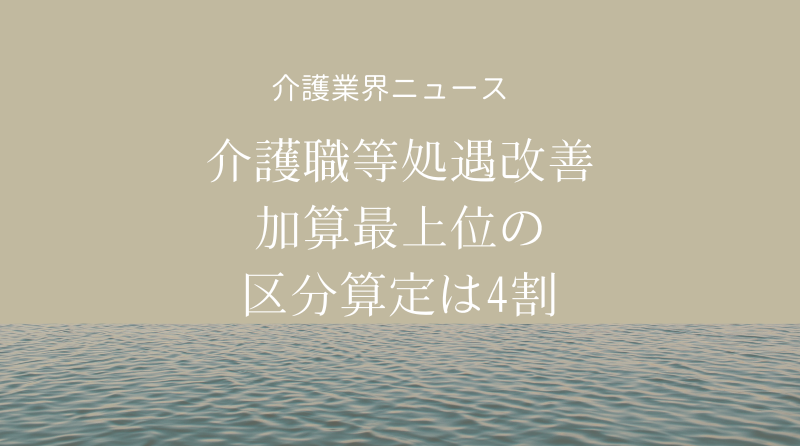従来の3つの処遇改善加算が一本化された「介護職等処遇改善加算」(新加算)の算定状況が明らかになりました。厚生労働省が示したデータによると、最上位区分である加算(Ⅰ)の算定率は約4割にとどまっています。
同じく算定状況を調査した福祉医療機構は、算定に必要な「キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)」のクリアに難しさがあるのではないかと分析しています。
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)の算定率が最も高いのは特養
12月23日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会では、処遇改善加算の今後の在り方が議題になりました。厚労省は、議論の参考にするため、2024年8月サービス提供分の介護職等処遇改善加算の算定状況をまとめています。

(【画像】第243回社会保障審議会介護給付費分科会【資料3】処遇改善加算等についてより)

新加算には上位から順に(Ⅰ)から(Ⅳ)の区分があります。算定にあたっては①キャリアパス要件②月額賃金改善要件③職場環境等要件の3つを満たすことが求められています。
(【画像】厚労省による処遇改善加算制度の一本化説明用リーフレット)今回示されたデータによると、最上位である加算(Ⅰ)の算定率は、サービス全体では42.3%にとどまりました。
このうち最も高かった特養では76.6%で、それに(Ⅱ)を合計すると93.1%に上ります。一方、特養以外での加算(Ⅰ)の算定状況は、在宅系サービス(訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等が36.9%(うち、訪問介護は35.7%)、介護老人保健施設は65.1%などと開きはあるものの平均すると42.3%で、これに(Ⅱ)を合計すると、7〜9割です。この差から、(Ⅰ)の要件を達成するには一定のハードルの高さがあることがうかがえます。
業歴が長い施設・事業所の方がキャリアパスⅤをクリアしているというデータも
介護職員等処遇改善加算の算定状況については、福祉医療機構(WAM)も独自に調査を実施しており、加算(Ⅰ)の算定率と(Ⅱ)の算定率には開きが見られました。
同機構は、加算(Ⅰ)の算定に必要な「キャリアパス要件Ⅴ」(介護福祉士等の配置)に難しさがあるのではないかと推測しています。キャリアパス要件Ⅴは既存のサービス提供体制強化加算などの算定有無で判断される要件で、これを満たすには勤続10年以上の介護福祉士の割合などを配置する必要があります。つまり、加算(Ⅰ)を算定するには、キャリアの長い介護福祉士の採用や、職場定着の取り組みを進める必要があります。
また、WAMの調査では、特養を対象に加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)とで開設年を比べたデータがあります。加算(Ⅰ)を算定できている特養の方が平均値で5年、中央値で8年、業歴が長いことが分かりました。

(【画像】福祉医療機構「2024年度介護報酬改定に関するアンケート調査(前編)」より)
同加算の算定には、業歴の長さもポイントであるといえそうです。
社会福祉法人は営利法人より算定率が高い傾向
さらに、WAMは、開設主体(社会福祉法人と営利法人)によって加算(Ⅰ)の算定状況に差があるかを通所介護と訪問介護に分けて分析しています。

通所介護では、社会福祉法人の算定率が73.1%だったのに対し、営利法人では31.9%と2倍以上の差がありました。
また訪問介護でも、社会福祉法人が68%、営利法人が50%と、社会福祉法人の方が高くなりました。

ただ特徴的な点では、訪問介護は通所介護より差が小さくなっています。訪問介護員には介護職員初任者研修を修了するなどの要件があり、その結果としてベテラン職員が多くなることや、厳しい人手不足により人材獲得のために処遇改善に特に力を入れていることが要因とみられます。
2025年度も要件の緩和は継続される方針に
社会保障審議会・介護給付費分科会に話を戻すと、介護職等処遇改善加算の上位区分の算定が進んでいないことなどを受けて、25年度中も算定要件の緩和を継続する方針が厚労省から示されました。
現在、緩和措置をとることに対して委員から反対意見は出ていませんが、本来は事業所で各要件を満たすべきであるという立場と、一部要件を廃止して賃上げを優先すべきという立場に分かれています。