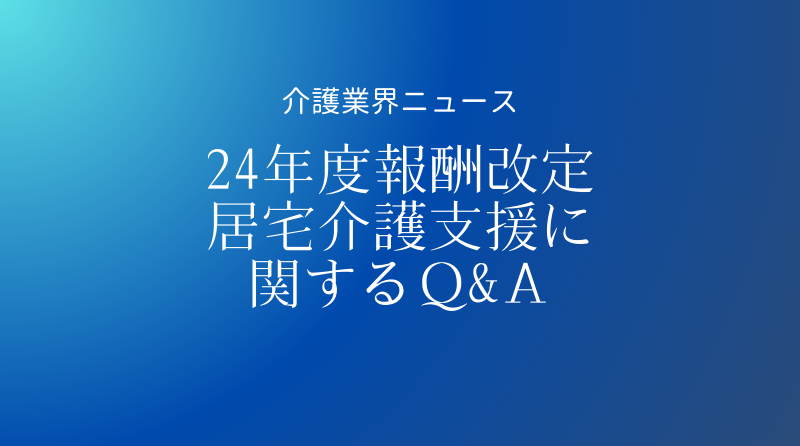2024年度介護報酬改定について、11月11日時点で厚生労働省からQ&Aが11回に渡って公開されています。
このうち、居宅介護支援に関するものとしては今改定で認められるようになった情報通信機器を活用したモニタリングや、選択制が導入された福祉用具に関する対応についての解釈などが示されています。
例えば、3月15日発出の”第1段”では、テレビ電話装置等のトラブルによってモニタリングが実施できなかった場合は月に1度のモニタリングが免除される「特段の事情」とは認められず、利用者宅への訪問を実施しなければならない旨を明示しています。
また、”第5弾”(4月30日発出)では選択制の対象となった福祉用具の中古品の販売の扱いなどが示されています。
居宅介護支援・介護予防支援に関するQ&A(vol.1【3月15日発出】、vol.3【3月29日発出】、vol.5【4月30日発出】)の内容
厚生労働省からのQ&Aは以下のページ下部に掲載されています。
※厚労省の特設ページ「令和6年度介護報酬改定について」
居宅介護支援及び介護予防支援に関連する内容を以下に整理します。
特定福祉用具販売種目の再支給等について (vol.1)
問98
特定福祉用具販売の種目は、どのような場合に再支給又は複数個支給できるのか。
(答)
居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合については、介護保険法施行規則第70条第2項において「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。」とされており、「その他特別な事情」とは、 利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合の再支給のほか、ロフストランドクラッチやスロープのような種目の性質等から複数個の利用が想定される場合も含まれる。
貸与と販売の選択制における令和6年4月1日以前の利用者について(vol.1)
問99
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94 号)第7項~第9項にそれぞれ掲げる「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」(以下、「選択制の対象福祉用具」という)を施行日以前より貸与している利用者は、施行日以後に特定福祉用具販売を選択することができるのか。
(答)
貴見のとおりである。なお、利用者が販売を希望する場合は福祉用具貸与事業者、特定福祉用具販売事業者、居宅介護支援事業者において適切に連携すること。
問100
施行日以降より選択制の対象福祉用具の貸与を開始した利用者へのモニタリング時期はいつになるのか。
(答)
施行日以後に貸与を開始した利用者に対しては、利用開始時から6月以内に少なくとも1回モニタリングを実施することとしているが、施行日以前の利用者に対しては、利用者ごとに適時適切に実施すること。
貸与と販売の提案に係る利用者の選択に資する情報提供について(vol.1)
問101
福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必要な情報とはどういったものが考えられるか。
(答)
利用者の選択に当たって必要な情報としては、
- 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
- サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し
- 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
- 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること
- 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
- 国が示している福祉用具の平均的な利用月数(※)等が考えられる。
※ 選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数(出典:介護保険総合データベース)
- 固定用スロープ:13.2ヶ月
- 歩行器 :11.0ヶ月
- 単点杖 :14.6ヶ月
- 多点杖 :14.3ヶ月
担当する介護支援専門員がいない利用者の選択制の対象となる福祉用具の対応について(vol.1)
問102
担当する介護支援専門員がいない利用者から福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所に選択制の対象福祉用具の利用について相談があった場合、どのような対応が考えられるのか。
(答)
相談を受けた福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所は、当該福祉用具は貸与と販売を選択できることを利用者に説明した上で、利用者の選択に必要な情報を収集するために、地域包括支援センター等と連携を図り対応することなどが考えられる。
貸与と販売の選択に係る情報提供の記録方法について (vol.1)
問103
福祉用具専門相談員は、利用者に貸与と販売の選択に資する適切な情報を提供したという事実を何に記録すればよいのか。
(答)
福祉用具貸与・販売計画又はモニタリングシート等に記録することが考えられる。
選択制の対象福祉用具の販売後の取り扱いについて(vol.1)
問104
選択制の対象種目の販売後のメンテナンス等に係る費用は利用者が負担するのか。
(答)
販売後のメンテナンス等にかかる費用の取扱いについては、利用者と事業所の個別契約に基づき、決定されるものと考えている。
問105
スロープは、どのような基準に基づいて「福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」、「住宅改修」に区別し給付すればよいのか。
(答)
取り付けに際し、工事を伴う場合は住宅改修とし、工事を伴わない場合は福祉用具貸与又は特定福祉用具販売とする。
テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて(vol.1)
問106
テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、訪問介護員が訪問している間に、テレビ電話装置等の準備をすることは可能か。
(答)
訪問介護の提供に支障が生じない範囲で、例えば ICT機器のOn/Off 等の協力などを行うことは差し支えないが、具体的な実施方法や連携方法等は、あらかじめ指定居宅介護支援事業所と訪問介護事業所とで調整すること。
また、協力・連携の範囲について、利用者の要望や目的によっては、適切ではない場合等もあると考えられるため、その必要性等については、状況に応じて判断する必要がある。
問107
居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成後、初回のモニタリングについてもテレビ電話装置等を活用して行うことは可能か。
(答)
要件を満たしていれば可能であるが、居宅サービス計画等の実施状況を適切に把握する観点から、初回のモニタリングは利用者の居宅を訪問して行い、その結果を踏まえた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが可能かどうかを検討することが望ましい。
問108
情報連携シートの項目はすべて記載する必要があるか。
(答)
テレビ電話装置等を活用したモニタリングのみでは収集できない情報について、居宅サービス事業者等に情報収集を依頼する項目のみを記載すればよい。
問109
サービス事業所に情報収集を依頼するにあたり、情報連携シートではなく、民間の介護ソフト・アプリの記録機能を活用する方法は認められるか。
(答)
情報連携シートは様式例であるため、必ずしもこの様式に限定されないが、介護ソフト・アプリの記録機能を活用する場合においても、情報連携シートの項目と照らし、指定居宅介護支援事業者と居宅サービス事業者等の連携に必要な情報が得られるかを確認すること。
問110
利用者に特段の事情がある場合には1月に1回(介護予防支援の場合は3月に1回)のモニタリングを行わなくてもよいが、利用者が使用するテレビ電話装置等のトラブルによりモニタリングが実施できなかった場合は特段の事情に該当するか。
(答)
該当しない。この場合は、利用者の居宅への訪問によるモニタリングに切り替えること。
問111
文書により利用者の同意を得る必要があるが、重要事項説明書等にチェック欄を設けるなどの対応でも差し支えないか。
利用者やその家族に対し、テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、そのメリット・デメリットを含め十分に説明した上で、チェック欄にチェックを入れることにより同意を得ることは差し支えない。
テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて(vol.3)
問5
テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月において、サービス利用票 (控)に利用者の確認を受ける方法としてどのようなものが考えられるか。
(答)
訪問によるモニタリングを行う月において、直後のテレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月の分もサービス利用票(控)を持参し確認を受ける方法や、電子メール等により確認を受ける方法等が考えられる。
福祉用具について(vol.1)
問112
選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に位置付ける場合、主治医意見書や診療情報提供書に福祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師に照会する必要があるか。
(答)
追加で医師に照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会は要しない。
問113
福祉用具貸与については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画作成後、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画等に記載しなければならないこととなっており、選択制の対象福祉用具の貸与を行った場合、福祉用具専門相談員が少なくとも6月以内にモニタリングを行い、その結果を居宅サービス計画等を作成した指定居宅支援事業者等に報 告することとされているが、居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載については福祉用具専門相談員のモニタリングと同様に6月以内に行う必要があるのか。
(答)
必ずしも6月以内に行う必要はないが、福祉用具専門相談員からモニタリングに関する情報提供があった後、速やかに居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載を行うこと。
福祉用具貸与に関するモニタリングの実施時期について(vol.5)
問3
福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う時期を記載することとされたが、計画に記載する事項として、モニタリングの実施を予定する年・月に 加え、日付を記載する必要があるのか。
(答)
福祉用具貸与計画における次回のモニタリング実施時期については、例えば「何年何月頃」や「何月上旬」等の記載を想定しており、必ずしも確定的な日付を記載する必要はない。一方で、利用者の身体状況や ADL に著しい変化が見込まれる場合等、利用者の状況に応じて特定の日に実施する必要があると判断されるときは日付を記載することも考えられる。
問4
福祉用具貸与計画に記載する実施状況の把握(モニタリング)の実施時期は、どのように検討すればよいのか。
(答)
利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及び ADL の変化等は個人により異なるものであるから、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要がある。
選択制の対象となる福祉用具の購入後の対応について(vol.5)
問5
選択制の対象となる福祉用具を購入したのちに、修理不能の故障などにより新たに必要となった場合、特定福祉用具販売だけでなく福祉用具貸与を選択することは可能か?また、販売後に身体状況の変化等により、同じ種目の他の福祉用具を貸与することは可能か。
(答)
いずれも可能である。なお、福祉用具の販売または貸与のいずれかを提案するに当たっては、利用者の身体の状況等を踏まえ、十分に検討し判断すること。
福祉用具の選択制の提案にかかる医学的所見の取得について(vol.5)
問6
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のリハビリテーション専門職から医学的な所見を取得しようとする場合、利用者を担当している福祉用具貸与事業所にリハビリテーション専門職が所属していれば、その職員から医学的所見を取得することは可能か。
また、利用者を担当している福祉用具専門相談員が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格を所持している場合は、当該福祉用具専門相談員の所見を持って医学的所見とすることは可能か。
(答)
選択制の提案に必要な医学的所見の取得に当たっては、利用者の身体状況や生活環 境等の変化の観点から、利用者の過去の病歴や身体状況等を把握している専門職から聴取することを想定しており、例えば、質問で挙げられている職員が、医師と連携のもと利用者の入院期間中にリハビリテーションを担当している場合や、利用者に訪問リハビリテーションも提供している場合等であれば可能である。
問7
選択制の検討・提案に当たって医学的所見の取得に当たり、所見の取得方法や様式の指定はあるのか?
(答)
聴取の方法や様式に特段の定めはない。
問8
一度貸与を選択した利用者に対して、一定期間経過後に、再度貸与の継続または販 売への移行を提案する場合において、改めて医師やリハビリテーション専門職から 医学的所見を取得する必要があるのか?
(答)
販売への移行を提案する場合においては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかから聴取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえる必要がある。
貸与の継続に当たっては、必要に応じて聴取等をするものとして差し支えない。
選択制の対象の販売品について(vol.5)
問9
選択制対象福祉用具に関しての中古品の販売は可能か。
(答)
今般の選択制の導入以前から特定福祉用具販売の対象になっている福祉用具は、再利用に心理的抵抗感が伴うものや、使用により形態・品質が変化するものであり、基本的には中古品の販売は想定していない。
また、選択制の導入に伴い、「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「多点杖」が新たに特定福祉用具販売の対象となったが、これらについても原則として新品の販売を想定している。これは、福祉用具貸与では中古品の貸出しも行われているところ、 福祉用具貸与事業所によって定期的なメンテナンス等が実施され、過去の利用者の使用に係る劣化等の影響についても必要に応じて対応が行われる一方で、特定福祉用具販売では、販売後の定期的なメンテナンスが義務付けられていないこと等を踏まえたものである。
問10
選択制の対象である福祉用具を貸与から販売に切り替える際、既に当該福祉用具の販売が終了していて新品を入手することが困難な場合は、同等品の新品を販売 することで代えることは可能か。
(答)
利用者等に説明を行い、同意を得れば可能である。
取扱件数による基本単位区分について(vol.1)
問114
利用者数が介護支援専門員1人当たり45 件以上の場合における居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)又は居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ)の割り当てについて具体的に示されたい。
(答)
【例1】
取扱件数80人で常勤換算方法で1.6人の介護支援専門員がいる場合
① 45(件)1.6(人)=72(人)
② 72(人)-1(人)=71(人)であることから、
1件目から71件目については、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)を算定し、72件目から80件目については、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)を算定する。
【例2】
取扱件数160人で常勤換算方法で2.5人介護支援専門員がいる場合
① 45(件)2.5(人)=112.5(人)
② 端数を切り捨てて112(人)であることから、
1件目から112件目については、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)を算定する。
113件目以降については、
③ 60(件)2.5(人)=150(人)
④ 150(人)-1(人)=149(人)であることから、113件目から149件目については居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)を算定し、150件目から160件までは、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ)を算定する。
※平成 21 年度介護報酬改定関係Q&A(Vol.1)(平成 21 年3月23日)問58の修正。
居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について(vol.1)
問115
事務職員の配置にあたっての当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等について具体例を示されたい。
(答)
基準第13条に掲げる一連の業務等については、基準第13条で定める介護支援専門員が行う直接的なケアマネジメント業務の他に、例えば、以下のような間接的なケアマネジメント業務も対象とする。
<例>
○要介護認定調査関連書類関連業務
・ 書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど
○ケアプラン作成関連業務
・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど
○給付管理関連業務
・関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど
○利用者や家族との連絡調整に関する業務
○事業所との連絡調整、書類発送等業務
○保険者との連絡調整、手続きに関する業務
○給与計算に関する業務 等
※令和3年度介護報酬改定関係Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問116の修正。
特定事業所加算について(vol.1)
問116
「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、自ら主催となって実施した場合や「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施」した場合も含まれるか。
(答)
含まれる。
問117
「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等 に参加していること」について、これらの対象者に対し支援を行った実績は必要か。
(答)
- 事例検討会、研修等に参加していることを確認できればよく、支援実績までは要しない。
- なお、当該要件は、介護保険以外の制度等を活用した支援が必要な利用者又はその家族がいた場合に、ケアマネジャーが関係制度や関係機関に適切に繋げられるよう必要な知識等を修得することを促すものであり、ケアマネジャーに対しケアマネジメント以外の支援を求めるものではない。
入院時情報連携加算について(vol.1)
問118
入院日以前の情報提供については、入院何日前から認められるか。
(答)
特段の定めは設けていないが、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には、入院の原因等も踏まえた上で適切に判断すること。
問119
入院時情報連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、入院したタイミングによって算定可能な日数が変わるが、具体的に例示されたい。
(答)
下図のとおり。

契約時の説明について(vol.1)
問120
今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、 利用者に、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスの、同一事業 者によって提供されたものの割合(以下、訪問介護等の割合等)の説明を行うことが努力義務とされたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。
(答)
- 例えば、以下のように重要事項説明書等に記載し、訪問介護等の割合等を把握できる資料を別紙として作成し、居宅介護支援の提供の開始において示すとともに説明することが考えられる。
- なお、「同一事業者によって提供されたものの割合」については、前6か月間に作成したケアプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数のうち(※同一事業所が同一利用者に複数回提供してもカウントは1)、同一事業所によって提供されたものの割合であるが、その割合の算出に係る小数点以下の端数処理については、切り捨てても差し支えない。
<例>
※重要事項説明書 第●条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである。
※別紙

※令和3年度介護報酬改定関係Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問111の修正。
※令和3年度介護報酬改定関係Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問112、問115は削除する。
初回加算について(vol.3)
問6
指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を提供していた利用者について、要介護認定を受け、引き続き当該事業所が居宅介護支援を提供する場合において、初回加算の算定は可能か。
(答)
指定介護予防支援事業所の利用実績は問わないため、算定できる(介護予防支援費の算定時においても同様である)。
介護予防支援に関するQ&A(vol.1【3月15日発出】、vol.3【3月29日発出】、vol.5【4月30日発出】)の内容
事業者の指定に係る条例について (vol.1)
問121
市町村が指定介護予防支援事業者の指定に係る条例を定めるに当たり、指定を受けられる事業者の要件を独自に設けることは可能か。
(答)
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)のうち、基準第1条第3号及び第4号に規定する「市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準」以外のものについては、「市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準」とされているため、当該基準を参酌した上で、独自の要件を設けることは可能である。
管理者について
問122
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の附則の規定により、令和9年3月31日までの間は、引き続き、令和3年3月31日における管理者である介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く)を 管理者とすることができるとされているが、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、上記の介護支援専門員を管理者とすることは可能か。
(答)
原則不可だが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
地域包括支援センターからの介護予防支援の委託について(vol.1)
問123
介護予防支援の指定を受けている指定居宅介護支援事業者が、地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けることは可能か。
- 可能である。
- 介護予防支援の指定は、介護予防支援の提供を受ける被保険者の保険者ごとに指定を受ける必要があるため、例えば、指定を受けていない保険者の管轄内に居住する被保険者に対し介護予防支援を提供する場合には、当該保険者の管轄する地域包括支援センターからの委託を受ける場合が考えられる。
初回加算について(vol.3)
問7
居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防サービス計画を作成していた利用者について、当該居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受け、当該利用者に対し直接介護予防支援を提供する場合、初回加算を算定できるのか。
(答)
算定可能である。
なお、初回加算は指定介護予防支援事業者として新規で介護予防サービス計画を作成する手間を評価するものであるため、お尋ねの事例においては、原則として改めてアセスメント等を行った上で介護予防サービス計画を作成する必要がある。
地域密着型サービス、介護予防支援に関するQ&A(vol.3【3月29日発出】)の内容
体制等状況一覧表について(vol.3)
問1
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日老発0315 第1号厚生労働省老健局長通知)別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する進達書を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届け出る場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。
(答)
当該様式については、市町村長から都道府県知事への進達書となっているが、事業者から市町村長への届出書と読み替えて、適宜使用して差し支えない。
なお、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業においても同様の取扱いとする。
※ 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)(平成18年4月21日)問21の修正。
全サービスに共通するQ&A(vol.1、vol.6、vol.7)
”vol.1”では、全サービスに関わる改定項目についても解釈が示されています。また、”vol.6”と”vol.7”でその内容の一部が微修正されています。
その内容を以下に記載しています。
業務継続計画未策定減算について
vol.6問7(※vol.1問164の修正)
業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
(答)
- 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、
かつ、や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 - なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。
vol1.問165
業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。
(答)
業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。
| 対象サービス | 施行時期 | |
| ① | 通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 | 令和6年4月 ※ただし、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 |
| ② | 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション | 令和6年6月 ※上記①の※と同じ |
| ③ | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防支援 | 令和7年4月 |
※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売には、業務継続計画未策定減算は適用されない。
問166
行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
(答)
業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。
例えば、通所介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和7年10月からではなく、令和6年4月から減算の対象となる。
また、訪問介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月から減算の対象となる。
高齢者虐待防止措置未実施減算について
問167
高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
(答)
減算の適用となる。
なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。
問168
運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
(答)
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。
問169
高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
(答)
改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。
虐待防止委員会及び研修について
問170
居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。
答
虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。
例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催することが考えられる。
研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。
なお、委員会や研修を合同で開催する場合は、参加した各事業所の従事者と実施したことの内容等が記録で確認できるようにしておくことに留意すること。
また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の企画と運営に関しては、以下の資料の参考例(※)を参考にされたい。
(※)社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備-令和3年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考例」令和3年度老人保健健康増進等事業、令和4年3月。
科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算について
問171
月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月(以下、「利用開始月」という。)の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。
(答)
事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開始した翌月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとしている。
ただし、加算の算定についてはLIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌月の10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はできない。当該月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。
また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までにデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。
なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。
問172
事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。
(答)
原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFEに提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。
なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。
ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合(※)を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出していない場合は、加算を算定することができない。
(※)「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」問4 /上部に記載あり
| 対象サービス | 施行時期 | |
| ① | 通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 | 令和6年4月 ※ただし、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 |
| ② | 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション | 令和6年6月 ※上記①の※と同じ |
| ③ | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防支援 | 令和7年4月 |
やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。
また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。
介護記録ソフトの対応について
問173
LIFE への入力について、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトからCSV 連携により入力を行っているが、LIFEへのデータ提出について、当該ソフトが令和6年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。
(答)
差し支えない。
事業所又は施設にて使用している介護記録ソフトを用いて令和6年度改定に対応した様式情報の登録ができるようになってから、令和6年4月以降サービス提供分で提出が必要な情報について、遡って、やむを得ない事情を除き令和6年10月10日までにLIFEへ提出することが必要である。
LIFEへの提出情報について
問174
令和6年4月以降サービス提供分に係るLIFEへの提出情報如何。
(答)
令和6年4月以降サービス提供分に係るLIFEへの提出情報に関して、令和6年4月施行のサービスについては、令和6年度改定に対応した様式情報を提出すること。
令和6年6月施行のサービス(訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、予防訪問リハビリテーション、予防通所リハビリテーション)については、令和6年4~5月サービス提供分の提出情報に限り、令和3年度改定に対応した様式情報と令和6年度改定に対応した様式の提出情報の共通する部分を把握できる範囲で提出するか、令和6年度改定に対応した様式情報を提出すること。
各加算で提出が必要な情報については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日)を参照されたい。
科学的介護推進体制加算について
vol.7問1(vol.1問175の修正)
科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも6か月に1回から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから少なくとも3か月に1回提出すればよいか。
答
科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和6年4月又は6月以降は、少なくとも3か月に1回提出することが必要である。
例えば、令和6年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年11月までに少なくとも1回のデータ提出が必要である。
※下線部が修正箇所
介護報酬改定の施行時期について
vol.1問181
令和6年度介護報酬改定において、
訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションに係る見直しは令和6年6月施行
その他のサービスに係る見直しは令和6年4月施行 ・ 処遇改善加算の一本化等(加算率引き上げ含む)はサービス一律で令和6年6月施行 とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。
(答)
本来、改定に伴う重要事項(料金等)の変更については、変更前に説明していただくことが望ましいが、4月施行の見直し事項については、やむを得ない事情により3月中の説明が難しい場合、4月1日以降速やかに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得ることとしても差し支えない。
6月施行の見直し事項については、5月末日までに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある。 なお、その際、事前に6月以降分の体制等状況一覧表を自治体に届け出た介護事業者においては、4月施行の見直し事項と6月施行の見直し事項の説明を1回で纏めて行うといった柔軟な取扱いを行って差し支えない。
また、5月末日までの間に新たにサービスの利用を開始する利用者については、サービス利用開始時の重要事項説明時に、6月施行の見直し事項について併せて説明しても差し支えない。
問182
4月施行サービス(右記以外)と6月施行サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)の両方を提供している介護事業者は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出を別々に行う必要があるのか。
(答)
事業者の判断で、4月以降分を提出する際に6月以降分も併せて提出することとしても差し支えない。
人員配置基準等に関するいわゆるローカルルール
問183
人員配置基準等に関するいわゆるローカルルールについて、どのような取扱いとするべきか。
(答)
介護保険法上、介護事業所・施設等が介護保険サービスを提供するためには、自治体が条例で定めた基準を満たすものとして、都道府県等からの指定を受ける必要がある。自治体が条例を制定・運用するに当たっては、①従うべき基準、②標準、③参酌すべき基準に分けて定められる国の基準(省令)を踏まえる必要がある。
このうち人員配置基準等については、①従うべき基準に分類されている。したがって、自治体は、厚生労働省令で定められている人員配置基準等に従う範囲内で、地域の実情に応じた条例の制定や運用が可能である一方、こうしたいわゆるローカルルールについては、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要がある。
そのため、いわゆるローカルルールの運用に当たり、自治体は、事業者から説明を求められた場合には、当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにする必要がある。
また、いわゆるローカルルールの中でも特に、管理者の兼務について、個別の事業所の実態を踏まえず一律に認めないとする取扱いは適切でない。
管理者の責務
問184
管理者に求められる具体的な役割は何か。
(答)
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日付け老企第25号)等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととしている。 具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。
≪参考≫
「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」(抄) (令和元年度老人保健健康増進等事業「介護事業所・施設における管理者業務のあり方とサービス提供マネジメントに関する調査研究」(一般社団法人シルバーサービス振興会))
第1章 第2節
管理者の役割
1.管理者の位置づけ及び役割の重要性
2.利用者との関係
3.介護にともなう民法上の責任関係
4.事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有
5.理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知
6.事業計画と予算書の策定
7.経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント
8.記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有