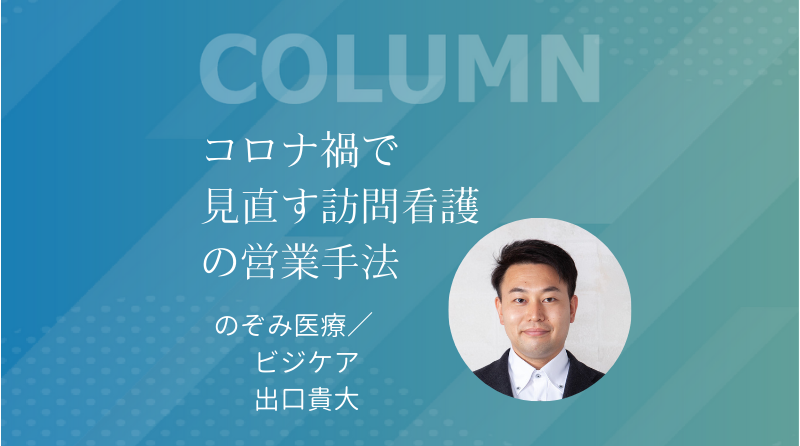地域によって緊急事態宣言やまん延等重点措置が発令されていた期間中は、「思った以上に営業ができなかった」、「ケアマネジャーやドクター、他のサービス関係者に会いに行きたくても行けていなかった」、という方も多いのではないでしょうか?私もこうした相談を数多く受けてきました。
流行が落ち着いてきた今こそ、新たな備えが必要です。
そこで、今回はアフターコロナ、ウィズコロナでの訪問看護ステーション(以降・訪看)の営業方法についてお伝え致します。
コロナによって営業活動にどれくらい影響がでましたか?
皆様は普段、どのように営業活動を行っていますでしょうか?
(1)社内のチラシを作りそれを持って会話しに行く
(2)実績や計画書・報告書を持って行くときに会話する
(3)利用者の状態変化時に報告をする
上記の取り組みは、多くの訪看が営業活動の主軸として行っているかと思います。
今回、緊急事態宣言が出たことなどにより、(1)と(2)は郵送、(3)は電話、というスタイルに切り替わった訪看も多いのではないでしょうか?
主軸として行っていた営業活動ができなかった経験から、他に良い方法がないか、と考えている方も多いと思います。
また、緊急事態宣言などが解除されたからといって、再度同じような状況を迎えた時にまた主軸の活動が出来なくなるようでは、営業戦略として残念です。
どんなことがあっても対応し、継続できてこその戦略です。
そのため今回はどんな状況に置かれても戦略的に動ける営業の考え方についてお伝え致します。
ケアマネジャー、ドクターらが訪問看護に依頼したくなる状況とは
まず、ケアマネジャーやドクター達が、訪看に依頼をしたくなる場面について考えてみましょう。
この視点を抜きにして、ただ自社のチラシを配って空き枠情報などを伝えたり、計画書や報告書を送ったりしているだけだと、 「新規の依頼が欲しい!!」という一方通行な想いを相手に押し付けることになってしまいます。
優しいケアマネジャーやドクターだと、頑張りを認めて依頼をくれることもあるかもしれません。しかし、1件だけでそれっきり、という結果になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それを打開する方法は「何をするか」ではなく、
「どういう状態を作り出すか」、言い換えれば「相手が助かった、お願いしてよかった、一緒に仕事していてやりやすい、一緒に仕事をしていて嬉しい」といった気持ちを持ってもらうことが重要です。
営業活動では、こうした状態に持って行くためにあの手この手でやり方を工夫していくことが大切なのです。
一緒に仕事がしたいと思われるステーションになるための2つのポイント
では相手に、自分の事業所に「お願いしたい」と思ってもらうためにどういう考え方をすればいいか。それは大きく2つの考え方があります。
1つ目は「相手の職種に応じて助けになるポイントにアプローチする!」という事です。
例えば、ケアマネジャーもドクターも毎日ご利用者様の訪問には行きません。
ではいつ訪問しているかというと、ケアマネジャーの場合は基本的に、月に1度のモニタリングの日だけです。
訪問診療の場合はご利用者様の状況によって変わりますが、多くの場合隔週1回や、毎週1回ペースで予定が組まれています。
ここで注目してもらいたいのが、ケアマネジャーもドクターも、自らが訪問に行けない間のご利用者様のしっかりとした情報を持っていないということです。
それを解消するためにケアマネジャーはヘルパーや訪問入浴などの他のサービスから様子を聞いていたりしますが、訪看に対して「どうでした?」とはなかなか聞いてきてくれないんです(笑)。つまり、医療面の事に関しての十分な情報は入手出来ていないとえます。
一方、訪問診療を行うドクターはご利用者様の状況や状態を知らないまま、居宅に向かうことが多いです。
言わば目隠しをして歩いているようなものなので、ご利用者様の居宅に行くまでに色んなことをシミュレーションしたり、居宅について初めてその場で状況を瞬時に判断したりすることを求められるため、大変苦労をされています。
そこでもし、ドクターがご利用者を訪問する前に、訪看から情報共有していたらどうでしょう?
利用者の状況・状態をある程度想定しながら、こういった事を聞いてこよう、こういう会話をしよう、など気持ちに余裕をもって訪問できますし、訪問先でも落ち着いた対応ができるかと思います。
私達訪看側が「いつケアマネジャー、ドクターが訪問するのか」を把握して、タイムリーに情報共有するだけで相手に与える影響はかなり大きいのです。
月末月初の計画書・報告書の時の情報共有では既に遅いのです。
連携相手について、職種別に週間、月間の訪問パターンを想定し、「どういうことに困るかな?」「どういう情報があると助かるかな?」と考えをめぐらすことが大切です。
2つ目は「相手がどういう性格であるか環境下に置かれているかを把握する!」ということです。
個々人によって、仕事がやりやすい、連携がとりやすい、助かる、と感じるポイントは違います。そのため、職種が同じだからといってそれぞれに同じやり方で関わっていてはいけません。
人によって直接顔を見て仕事をするのを好む方、業務量が多いためFAXでまとめて送ってもらった方が良いと感じる方、電話の方が気軽に話しやすい方、などそれぞれにやりやすい情報共有の仕方や連携の仕方があるのです。
また、相手が忙しい時に、直接会うスタイルを好む相手だからと、状況を気にせず会いに行くのは迷惑ですし、1人で事業を回している方にとっては、会ったり電話をしたりという方法だと、その時間中他の仕事を止めてしまうになってします。相手がどういう環境で仕事をしているか、今どういう状況にあるのかをしっかりと把握し、相手にとって一番いい方法で情報共有していく事が望ましいでしょう。
相手の立場に立った営業活動を行うためのコミュニケーション
ここまで読んでいただいたら、「情報共有の考え方も、相手に合わせてその手段を変えることも分かった。でも実際にどうやったらいいか」、と悩まれるかもしれません。
しかし、それを解決するシンプルで一番いい方法があります。
それは、直接ケアマネジャー、ドクターに聞いてみることです。
「どういった情報共有の仕方の方が嬉しいですか?」
「どういったタイミングで情報をもらえると助かりますか?」
「1カ月のうちでどのタイミングが一番忙しくて、どのタイミングが落ち着いていますか?」
など、相手に関心を持ち、相手の状況や気持ち・考え方を聞きながらイメージすることが大切なのです。そして怖がらずに勇気を出して直接聞いてみることが大切です。
相手のために「良い連携が取れるようになりたい」、相手に「仕事をしやすいな」と感じてもらえるようにするにはどうすればいいか、そういった事を相手の状況に合わせてタイミングや手段を変えていく、その方法や考え方がこれから更に求められる営業方法ではないかと実感しています。
あなたの事業所では、まず何から始めてみますか?