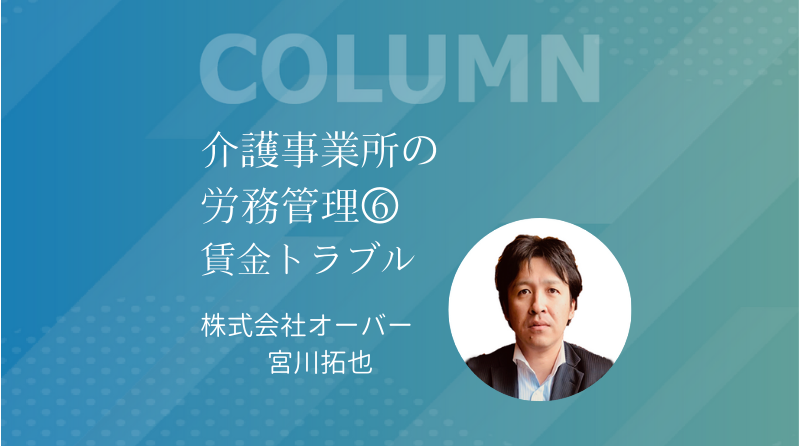今回は介護従事者への賃金・賞与におけるトラブル対策についてお伝えします。
「労働時間」と「賃金・賞与」に関するトラブル
人事労務や職場づくりに関するご相談で多いのが、「労働時間」と「賞与・賃金」に関するものです。
賞与・賃金を巡っては、「言った、言ってない」「賃金が上がらない」「賞与が低い、支給されない」…。トラブルに至る背景はそれぞれ異なりますが、揉め事の内容はこのあたりになります。
・残業代の不払いに関するトラブル
・労働法の理解不足に関するトラブル
・労働者の賃金格差によるトラブル
・賞与についてのトラブル
残業代の不払いに関するトラブル
まず、言及したいのが、残業代不払いや未払い残業の相談についてです。
残業代に関するトラブルは、経営者の「意図的な運用によって引き起こされているもの」と「無意識に引き起こされているもの」の2つがあります。
「意図的」とは、その運用が違法であることに気付いていながら、経営者の「そういうものだ」という認識から生まれるトラブルです。
例えば、
・業務終了後の申し送り時間が労働時間にカウントされていない。
・訪問介護員の移動中の時間が労働時間にカウントされていない。
・定時になると、とりあえずタイムカードを打刻して残業させる。
というものです。
労働時間を適切に管理されておられる方は驚かれるかも知れませんが、このようなご相談は実際にあります。
では、こうした運営をされている経営者の皆さんが、「法律なんて関係ない!」という感覚で運営されているのか、というとそうではありません。「今までこのようにやってきた」「介護の仕事はこういうものだし、このようにしないと経営できない」という感覚をお持ちの方がおられると感じています。
介護等の福祉や支援に熱い経営者は時に、自身の生活は二の次三の次で仕事に取り組まれることもあるでしょう。
とはいえ、労働者として働いてもらう以上は、労働基準法をはじめとした法律を遵守する必要があります。
時代と共に新たな規制が生まれる事に対しても対応していく必要があります。
労働法の理解不足によるトラブル
残業代に関するトラブルのうち、無意識に引き起こされているものもあります。それは、経営者が法律等への理解が浅いまま運用していた事が原因で起こるトラブルです。
例えば、
・管理監督者に該当しない役職にも関わらず残業代を支払っていなかった。
・管理監督者職なので深夜割増を支払っていなかった
・15分に満たない労働時間は1日の労働時間からカットしていた
などがあります。
このように記載しますと、労働法の中でも、一歩踏み込んだ部分の取り扱いがもとでトラブルが起こっています。
これらを回避するには、意識をして改善していくしかありません。今は、インターネット等をはじめ、労働に関するルールについて誰もが理解し得る時代です。労働者から疑念を抱かれないように努める必要があります。
労働者の賃金格差によるトラブル
労働者間の賃金格差もトラブルを引き起こしています。
例えば
「前に、〇〇手当が上がったとAさんから聞いたのですが、なぜ私は上がらないのですか?」「なぜ、私には残業をするなと言うのにBさんには言わないのですか?」などといった訴えがあります。
賃金に関する情報が職場内に漏れる事はあってはならないですが、それでも日々のコミュニケーションの中で伝わったり、勘付かれたりする事で、職員の不満が噴出する事があります。
特に「格差」については、同一労働同一賃金(※)もあり、労働者の意識は高まっています。
※参考:同一労働同一賃金
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止
施行 2020年4月〜(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日〜)
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらやる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
●均衡 待遇規定不合理な待遇差の禁止
①職務内容②職務内容・配置の変更の範囲③ その他の事情の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要があります。
●均等 待遇規定差別的取扱いの禁止
① 職務内容②職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合、待遇について同じ取扱いをする必要があります。
派遣労働者については、次のいずれかを確保することを義務化します。
① 派遣先の労働者との均等・均衡待遇② 一定の要件※を満たす労使協定による待遇
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります
賞与についてのトラブル
賞与は法律上の支払い義務はなく、定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるもの、支給額があらかじめ確定されていないものと規定されています。
就業規則等でその支給について規定した場合は、その通りに支給する必要があります。
では、賞与においてどのようなトラブルが生じているのでしょうか。
筆者が遭遇するトラブルとしては、「評価」に対する部分が多い印象です。「業績は上がっているのに、賞与は変わらない」「従業員間で納得できない差がある」「約束していた額が支給されない」などといったものです。
これらを回避するには、過度な確約をしない事、評価は客観的な数字や行動等を評価する事、(感情ベースで評価する場合も、その感情を言葉として伝えられる事)が重要です。
労働者にとって「賃金とは労働の対価」であり、経営者にとって「賃金とは貢献の対価」であるというギャップ 故に、この部分のバランスを考えることが事業所の安定的な運営に影響します。
会社側にとっても、労働者にとっても「賃金」「賞与」の在り方を考え、共有することがキーになります。
トラブルを回避する3つのポイント
賃金トラブル対策のポイントは「不条理をなくす」「正直に話す」「思い込まない」の3点です。
1点目の「不条理をなくす」についてですが、もし、自社に不条理な部分、つまりは法律を遵守していない、筋が通っていない運用が為されている場合は早急に改善してください。今はトラブルとして表面化していなくとも何らかのタイミングで表面化し対応に迫られる事が予測されます。
実際に筆者が支援に当たった事例でも、ふとした事がきっかけで「実は・・・」と職員から今までの不条理な部分についての訴えがあり、解決に相当な時間と労力を要した事があります。
「今までこうだったから」で不条理が認められる時代ではありません。法律等への適合は、理路整然と行ってください。
また、時間外労働について、「時間外労働を支給したくない」「その時間は時間外労働とは認めない」という感情で不条理を招くことなく法律に、法律に準じて対応いただく事が重要です。
2点目の「正直に話す」については、基本給や手当について、会社側の思いを伝える必要があります。「〇〇の実現」、「〇〇の業務を●●のような形で進めてほしい」ということを伝え、手当はそれに対する対価である事を伝えます。その手段は口頭に限りません。
総支給額に囚われて支給していては、ある種不条理です。また、職員一人一人への期待や役割と実際の貢献度について正直に話し、定期的に認識を揃えていく事が重要です。
例えば、部門会議等で、それぞれの労働者の働き方についてヒアリングし、事業所運営に貢献している労働者を経営者と労働者で共有する方法も考えられます。
経営者や一部の労働者の視点のみで評価する事は、実際とのズレを生じます。
例えば、「会社は私たちをしっかり見ていない、なぜAさんよりBさんの評価が高いのか、個人的な感情で評価しないでください」といった労働者の声は実際に生じています。
3つ目は「思い込まない」ことです。
「この時間は労働時間ではない」「休憩時間は取れないのが当たり前」「うちは残業を一切認めていないから残業代は支給しなくても良い」「従業員はうちの状況について理解してくれているから何も言ってこない」等、思いこみをしない事です。
事業所の思いを職員に理解してもらうと同時に、フレキシブルな働き方、均等均衡の取れた働き方を実現させていくという観点からも法律やルールを認めたうえで、筋道の通った運用が必要となります。
第7回目は、「就業規則のポイント①なぜ就業規則が重要なのか」をお届けします。
※この記事は、難しい用語を極力削減し、わかりやすさを重視しています。
この記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。