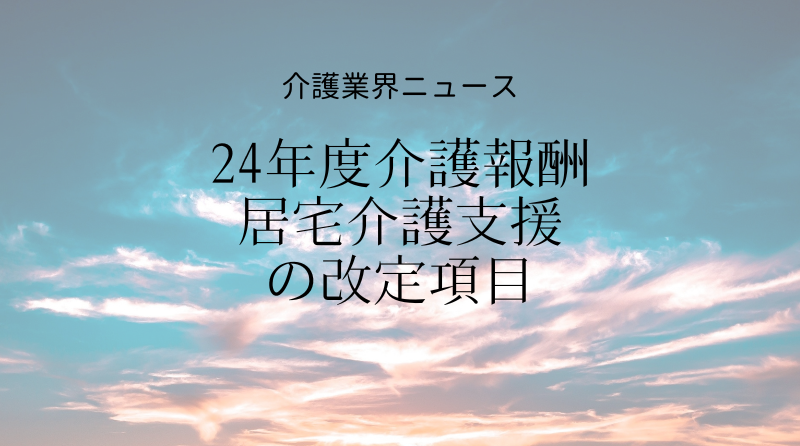*24年度報酬改定の情報収集はこちらから!【無料オンラインセミナー申し込みページ】
12月18日に社会保障審議会の介護給付費分科会は2024年度介護報酬改定に向けた審議報告をとりまとめました。【居宅介護支援】では、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が緩和されるほか、基本報酬の算定要件にケアプランデータ連携システムの活用が組み込まれるなど、重要かつ多岐にわたる見直しが実施されます。
【介護予防支援】も含め、改定項目を網羅して紹介します。
*参考:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(社保審・介護給付費分科会)
サービス利用割合の説明に関する要件の緩和(公正中立性の確保のための取組の見直し)
事業者の負担軽減を図るため、居宅介護支援事業所の義務となっていた過去6カ月間のサービス利用の割合を説明する規定(以下の内容)が努力義務に緩和されます。
ア)前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
イ)前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスについて、同一事業者によって提供されたものの割合
介護支援専門員1人当たりの取扱件数の見直し(逓減制の緩和)
居宅介護支援の基本報酬見直しについてです。
ICT機器等の導入に関わらず逓減制の適用ラインが緩和されるほか、上位区分の(Ⅱ)については、「ケアプランデータ連携システムの活用」が要件となっています。
また、予防プランの人数の計算方法も緩和されています。
ア)(事務職員の配置やケアプランデータ連携システムの活用がない場合)
- 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数:現行の「40未満」を「45未満」へ見直し
- 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数:現行の「40以上60未満」を「45以上60未満」へ見直し
イ)
- 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件:ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に改める
- 居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数:現行の「45未満」を「50未満」へ見直し
- 居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数:現行の「45以上60未満」から「50以上60未満」へ見直し
ウ)
居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出について、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。
介護支援専門員1人当たりの取扱件数(基準)の見直し
基本報酬の見直しに合わせ、居宅介護支援事業所に常勤する介護支援専門員の配置要件(人員基準)が、以下の通り見直されます。
ア)原則として、要介護者の数に、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44、またはその端数を増すごとに1とする。
イ)指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合は、要介護者の数に、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が49、またはその端数を増すごとに1とする。
特定事業所加算の見直し
居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件が、以下の通り見直されます。
ア)「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとともに、評価の充実を行う。
イ)(主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。
ウ)事業所での毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。
エ)介護支援専門員が取り扱う一人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直し(※)を踏まえた対応を行う。
※)介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)の内容
市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の規定
2024年4月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになるため、以下の見直しが行われます。
ア)市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することが運営基準上で義務化となることを踏まえ、これに伴う手間やコストを評価する新たな区分を設ける。
イ)以下のとおり運営基準の見直しを行う。
ⅰ) 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。
ⅱ)管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合は兼務を可能とする。
(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者であり、介護予防支援事業所の管理に支障がないときに限る。)
他のサービス事業所との連携による遠隔でのモニタリング(予防を含む)
以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置やその他の情報通信機器を活用したモニタリングが認められるようになります。
介護予防支援も対象です。
ア)利用者の同意を得ること。
イ)サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。ⅰ)利用者の状態が安定していること。
ⅱ)利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
ⅲ)テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。
ウ)少なくとも2カ月に1回(介護予防支援の場合は6カ月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。
入院時情報連携加算の見直し(要件の厳格化)
入院時情報連携加算について、入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、以下の見直しが行われます。その際、事業所の休業日等に配慮した要件設定を行うこととなります。
現行:「入院後3日以内」または「入院後7日以内」に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合を評価
2024年4月以降:「入院当日中」または「入院後3日以内」に病院等の職員に対して利用者の情報提供した場合を評価
通院時情報連携加算の見直し(算定対象の拡大)
通院時情報連携加算について、「医師」の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が「歯科医師」の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合も、同加算の対象となります。
ターミナルケアマネジメント加算等の見直し(算定対象の拡大)
ターミナルケアマネジメント加算について、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、対象疾患を末期の悪性腫瘍に限定せず、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者」を対象とする見直しが行われます。
併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件も見直されます。
ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化(予防を含む)
介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことが明確化されます。介護予防支援の場合も同様です。
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直されます。
業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入【訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】
感染症・災害に対応するための業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算となります。
※2025年3月31日まで適用除外。
高齢者虐待防止の推進【居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く全サービス共通】
虐待の発生や再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬が減算となります。
身体的拘束等の適正化の推進【訪問系、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援 共通】(予防を含む)
利用者や、他の利用者等を保護するために緊急・やむを得ない場合を除き、身体的拘束等が禁止されます。身体的拘束等を行う場合には、その態様や時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録することが義務付けられます。
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化【訪問系、通所系、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなし規定が適用されている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化します。
特別地域加算の対象地域の見直し【訪問系、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援共通】
人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められ、特別地域加算の対象と告示で定める地域について、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域について、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行うこととなります。
テレワークの取扱い【居宅療養管理指導を除く全サービス共通】
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示すことが求められます。
※このほか、全てのサービスに共通する改定事項(短時間勤務制度を導入する場合の「常勤」配置の緩和、管理者の兼務範囲の明確化、重要事項等のウェブサイトでの公表)が加わります。