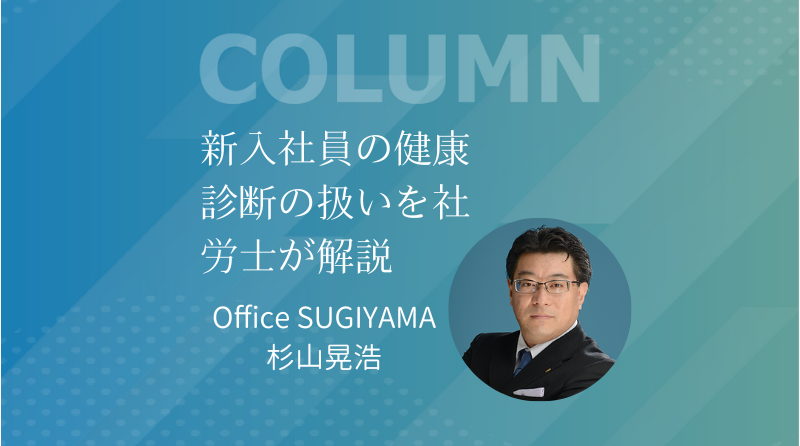新年度が近づくと新入社員の健康診断の扱いに関する質問が増えてきます。みなさんの職場においても、話題に上ることが増えているのではないでしょうか。そこで、今回は健康診断をテーマとして取り上げてみました。
健康診断の制度は、福利厚生制度としての価値が高く、事業所ごとに捉え方が異なります。欠勤にはいたっておらず勤怠管理上は表に出てこないが、健康問題が理由で生産性が低下している状態である”プレゼンティーズム”を防止するために健康経営に取り組んでいる事業所もあります。
今一度、健康診断の基本を確認し、健康診断への対応が問題なくスムーズにできるようになります。
1.健康診断実施に関する3つの義務
健康診断の目的は、労働者の健康の保持増進、疾病の早期発見・予防のみならず、労働者の就業の可否・適正配置・労働環境の評価などを判断することにあります。そうした目的から事業者には定期健康診断等の実施が義務づけられています。したがって、労働者に対する安全配慮義務を果たすためには、健康診断は必要不可欠と言えるでしょう。
実施が義務付けられている主な健康診断は以下のとおりです。
①雇入時の健康診断
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときに健康診断を実施しなければなりません。
入社オリエンテーションの際に実施するようにプログラムしておくと、確実です。
入社後に時間が取れない中小零細企業では、入社前に雇入時の健康診断をしておくことも可能です。
また、実は、入社前3カ月以内に実施された健康診断結果書の提出を受けて雇入時の健康診断に変えることもできます。 実際に、内定者に対して、入社時に健康診断の結果報告書の提出を義務付けている会社もあります。内定者が入社前3カ月以内に健康診断を受診していれば、費用負担についてトラブルが発生する可能性がありません。
この、雇入時の健康診断の費用負担についてですが、実は会社負担か、労働者負担か明確に定めている法律はありません。
ただ、健康診断の実施義務が会社にあるため、一般的には雇入時の健康診断の費用は、会社負担とするのがトラブルの防止策となります。
一方で、内定者の費用負担で健康診断を受診させ、健康診断の結果報告書を雇入れの際に提出させることも可能です。ただし、この場合には、内定者の理解と承諾が必要となります。もしかしたら、この費用負担を発端にして、『ケチな会社だ。これだと将来給与も上がりそうにないから、内定を断ろう』などと、内定者が入社拒否してくることも考えられます。
自社にとって、どのような取り扱いが良いのか明確にしておくと良いでしょう。
内定者から提出された健康診断結果に関して注意すべき点として、重要なものがあります。
それは、健診結果の提出は、雇入時の健康診断で検査すべき項目についてのみ代用できるため、必要な診断項目が網羅されているのか確認する必要があるということです。1項目でも実施されていないものがあれば、入社後速やかにその項目に該当する健康診断を実施する必要があります。
②定期健康診断
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければなりません。
会社に実施が義務付けされているため、雇入時の健康診断と異なり、会社が費用負担すべきです。
この定期健康診断では、次の2つのケースについて相談を受けることが多いです。
1つ目は、健康診断を拒む従業員の取り扱いについての相談です。
会社は、定期健康診断を受けさせる義務があります。仮に『営業が忙しくて健康診断の時間が取れない』等の理由で従業員が受診を拒み、結果として受診しなかったときは、50万円以下の罰金刑になる可能性があります。
2つ目は、健康診断結果に異常があったときの取り扱いについての相談です。
近頃は産業医の選任が不要な中小企業において、労働基準監督官から「健康診断結果の意見聴取がされていない」といった指摘が増えています。
会社は、健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。更に、医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。
また努力義務とされてはいますが、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導をすすめる必要があります。会社が、安全配慮義務を果たすためにも、保健指導は必ず実施しておきたいところです。
余力があれば、近年注目を浴びている健康経営を取り入れて、従業員が健康に働ける職場づくりを目指したいですね。

出典:厚生労働省
③特定業務従事者受診
特定業務への配置替えの際および6カ月以内ごとに1回、定期的に指定された項目について実施しなければなりません。注意すべきは、配置替えの際に受診させることを忘れているケースが多いということです。
介護事業所においては、「深夜業を含む業務」に従事するスタッフが特定業務従事者に該当します。常態として深夜業に従事しているスタッフの判断基準は、次のように通達で示されています。
「常態として深夜業を1週1回以上又は1ヶ月に4回以上行う業務をいう」(昭和23 年10 月1 日基発第1456 号)
特定業務従事者受診は、業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断です。したがって、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。
他方、雇入時の健康診断および定期健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものです。業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための時間は労働時間とはされず、健康診断時間中の賃金の取扱いについてはあらかじめ明確化しておく必要があります。ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を会社が支払うことが望ましいでしょう。
2.定期健康診断を受けさせなくても良いスタッフとは?就業規則を確認してみましょう
定期健康診断の対象となる従業員は、次のいずれかに該当する従業員です。
①正社員
②1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上で、1年以上継続して雇用される予定のパートタイマーやアルバイト
③1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上で、1年以上継続して雇用される予定の契約社員
前記①~③に該当しない従業員には、定期健康診断を受診させなくても会社は罪に問われません。
なお、非正規従業員のうち特定業務に該当する夜勤をする職員なら、6カ月以上の雇用予定があれば、特定業務従事者受診の対象となるため注意が必要です。
また、①~③に該当しない非正規雇用の従業員であっても、社内制度があれば、健康診断の対象とすることができます。厚生労働省では、助成金を活用して、対象外の従業員の健康診断の実施を進めてきました。そのため、一般的には健康診断の対象外とされる従業員が、健康診断の対象者となっていることもあります。今一度、就業規則を確認してみましょう。
ところで、前記以外にも定期健康診断を受けさせる必要のない従業員がいるのをご存じでしたか。
それは、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の従業員です。ただし、職場復帰後は速やかに定期健康診断を実施する必要があります。
例えば、育児休業期間中に従業員から定期健康診断を受けたいとの申し出があったときは、どのような対応をとるべきなのでしょうか。
原理原則通りの対応としては、『休業中の従業員には、定期健康診断を受ける義務はありません』と伝えて受診をさせません。
しかし、定期健康診断を福利厚生制度として捉えている事業所であれば、受けさせても問題ありません。ただし、受診費用は会社が負担するのか、従業員が負担するのかを明確にしておきましょう。
健康診断は自費診療に該当するため、医療機関によって費用が異なります。会社負担で受診させたら、他の従業員よりも高額な請求が来ることもあります。無用なトラブルの種を作らないためにも、費用負担については、休業中の従業員に説明しておきましょう。
3.健康診断をめぐるトラブルの未然防止策
健康診断をめぐるトラブルは案外多いものです。些細なトラブルであっても、一度発生してしまうと、何かと時間を取られてしまいます。だからこそ、未然防止が大切なのです。
主な対策を以下に明示しておきますので、あなたの職場に合った内容で書類等を整備し、計画的に社内教育の機会を確保しておくとトラブルの未然防止に繋がります。
【基本となる対策】
①就業規則の整備
②従業員への説明会
【内定者向け対策】※入社前3カ月以内に実施した健康診断結果を会社に提出させる場合
①健康診断結果通知提出依頼書
②内定者向け説明会
【定期健康診断拒否者対策】
①懲戒レベルの明確化
②警告書
③上司への通告書
④管理職勉強会
【異常所見者向け対策】
①再検査実施・検査結果提出依頼書
②従業員への説明会
③上司への通告書
④就業措置決定通知書
【休業者向け対策】
①休業中の健康診断にかかる確認書
②休業者説明会
③管理職勉強会
今月は、健康診断をめぐるトラブルを事前防止するための文書例を以下の3種類作成しています。
みなさんの職場の実態に合うようにカスタマイズしてご利用ください。
①入社予定者に対する健康診断結果通知書の提出依頼書
②健康診断拒否者に対する警告書
③産前産後休業および育児休業取得前の健康診断にかかる確認書
◆健康診断をめぐるトラブルを事前防止するための文書例」のプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
オフィススギヤマグループ版「健康診断をめぐるトラブルを事前防止するための文書例」を希望者全員に無料プレゼントします。
お気軽に下記からお申し込みください。
「健康診断をめぐるトラブルを事前防止するための文書例」プレゼント希望