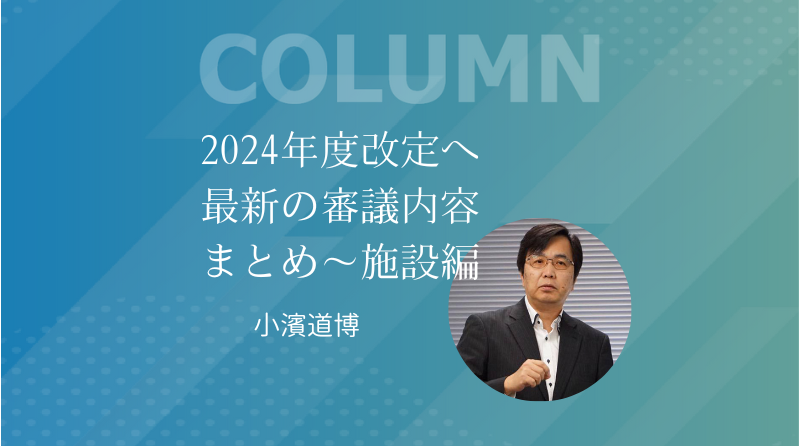令和6年度介護報酬改定に向けた審議は現在、サービスごとの課題とその解消に向けた対応について2巡目の検討が行われたところだ。
今回は、明らかになってきた改定の方向性について介護老人保健施設、介護福祉施設、特定施設入居者生活介護それぞれの項目と施設・入居系サービス共通する対応について1つずつ確認していきたい。
介護老人保健施設:在宅復帰・在宅療養支援指標の見直しでマネジメントのレベルアップが必要に
1.多床室料の自己負担化
介護老人保健施設では加算などの見直しのほかに、多床室料の自己負担化の問題がある。これは、3年前の審議で先送りされた論点だ。先送りされた理由は、介護療養型医療施設の令和6年3月の廃止に伴う介護医療院などへの転換手続を優先させたことにある。しかし、特養では多床室料は全額自己負担であり、次回改正後には介護療養型医療施設も廃止されて存在しないことになる。
もはや、老健の多床室料自己負担導入を進めるに当たって支障が無いのだ。
多床室の自己負担化が実現した場合、確実に長期滞在型の老健の経営を直撃する。長期滞在型とは、基本報酬で、「その他型」あるいは「基本型」を算定する施設である。これらの老健に長期滞在している入所者は、多床室料が全額自己負担となった場合、割安感の増した特養に移動するだろう。
老健の介護報酬単価が明らかに特別養護老人ホームより高いに関わらず、長期滞在型の事業運営が維持されているのは、多床室に介護保険が適用されている現状では実質的な支払金額の格差が少ないためだ。該当する老健は、早期に長期滞在型から脱却して、「加算型」まで引き上げることが急務だ。最終的には「超強化型」を目指すべきである。
2.在宅復帰・在宅療養支援機能の強化
老健の基本報酬は、「その他型」から「超強化型」まで5段階ある。その階段は、在宅復帰・在宅療養支援指標の点数の積み上げで決定される。
直近の検討ではこの指標のうち、「入所前後訪問指導割合」及び「退所前後訪問指導割合」の基準を引き上げる方向が示された。その結果、最上位区分の超強化型を算定する為のハードルは一層高くなるだろう。マネジメントにもレベルアップが求められる。
また、「支援相談員の配置割合」に係る指標においては、“社会福祉士の配置を評価する”とされた。特養の生活相談員は社会福祉士資格などが求められており、ハードルが高い。しかし、老健の支援相談員の資格基準は、“有る程度の実務経験”程度である。この部分で、社会福祉士資格が必要となれば、かなりの意識改革が求められるであろう。
これらの見直しに合わせて、「各類型間における基本報酬において、更に評価の差をつける」とされたことから、下位区分の「その他型」から「基本型」の基本報酬が引き下げられ、上位区分の「強化型」、「超強化型」の基本報酬が引き上げられる可能性が高まった。特養化した老健にとっては、多床室料の自己負担化と合わせてダブルパンチであり、経営の存続が危ぶまれる事態を想定しなければならない可能性がある。

(【画像】第231回社会保障審議会介護給付費分科会資料2より※今回見直しが検討されている指標を編集部が赤枠で強調)
3.加算関係の見直し
個別の加算についてはまず、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算を、新たな加算区分を新設する方向だ。
その要件は、リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進する観点から
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
- 実施計画等の内容について、リハ・口腔・栄養の情報を関係職種間で一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFE提出情報を活用すること。
- 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行った上で、見直しの内容について関係職種に対しフィードバックを行うこと。
である。
また、短期集中リハビリテーション実施加算は、原則として入所時及び月1回以上の頻度で、ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション計画を見直すとともに、その評価結果をLIFEに提出した場合の加算区分を新設する。さらに、既存の区分の報酬単位を引き下げる方向だ。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、認知症を有する利用者の居宅を訪問して、生活環境を把握することを要件とする。利用者の居宅を訪問しない場合は、報酬単位を引き下げる方向だ。
ターミナルケア加算について、死亡日から期間が離れた区分における評価を引き下げ、死亡直前における評価を引き上げることで、安易に病院に移さず、最後まで老健で看取ることを求める方向である。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)では、現在の算定要件である入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合に加え、施設において薬剤を評価・調整した場合に報酬を引き上げる。その上で、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合には、さらに高く報酬を引き上げる。
なお、算定要件には以下の三点を新たに加える方向だ。
- 処方を変更する際の留意事項を医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有し、処方変更に伴う病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて総合的に評価を行うこと
- 入所前に6種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること
- 入所者や家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。
介護医療院と共通の論点として挙げられた退所時情報提供加算は入所者が医療機関へ退所した際に生活支援上の留意点等の情報を提供した場合についても新たに評価する。また、居宅に退所した場合も、生活支援上の留意点等の情報を適切に提供することとし、医療機関への退所の場合の評価との整合性がとれるよう見直しを行う方向である。

介護老人福祉施設:緊急時の対応や透析が必要な入所者への対応が論点
1.緊急時等の対応方針の見直し
配置医師の対応が困難な場合の緊急対応においては、施設・配置医師・協力病院の3者でその役割分担等を協議し、緊急時等の対応方針(いわゆる緊急時等対応マニュアル)に反映することとする。その上で施設には、配置医師・協力病院の協力を得て、定期的な見直し(1年に1回程度)を行うことを義務づける方向である。
2.配置医師緊急時対応加算
配置医師緊急時対応加算については、配置医師が、日中であっても、通常の勤務時間外に急変等に対応するために駆けつけ対応を行った場合に報酬を引き上げる方向性が示された。
3.透析が必要な入所者の送迎・付き添いの評価
透析が必要な入所者の送迎・付き添いでは、定期的かつ継続的な透析を必要とする入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある入所者の場合で、施設職員が月一定回数以上の送迎を行った場合について、新たな加算などが創設される方向である。
特定施設入居者生活介護:医療的ケアへの対応巡る2つの論点
夜間看護体制加算については、「夜勤・宿直の看護職員を配置している」場合と「オンコールで対応している」場合の評価に差を設け、オンコールの場合で報酬を引き下げる方向である。
入居継続支援加算は、たんの吸引等の医療的ケアを必要とする者の占める割合の計算に於いて、「膀胱留置カテーテル」「在宅酸素療法」「インスリン投与」についても新たに追加して、看護職員がこれらのケアを行うことを評価する方向である。
介護施設共通の対応:協力医療機関を定めることを義務化に向けた検討
特養・老健・介護医療院においては、1年間の経過措置を設けた上で、以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化する。
(1)入所者の急変時等に、医師又は看護職員が夜間休日を含め相談対応する体制が確保されていること。
(2)診療の求めを受け、夜間休日を含め診療が可能な体制を確保していること。
(3)当該施設での療養を行う患者が緊急時に原則入院できる体制を確保していること。
この場合、複数の協力医療機関を定めることにより①~③を満たすとする方向である。特定施設と認知症グループホームについては、上記の①と②について努力義務とする。また、定期的(年1回以上)に、協力医療機関と緊急時の対応等を確認して、医療機関名等について指定権者(許可権者)に提出することを義務とする方向である。
さらに特養、特定施設、認知症グループホームについては、医療機関へ退所した場合の情報提供にかかる加算も創設される方向で検討が進んでいる。
情報連携に関連する評価としては、老健の空床情報を地域医療情報連携ネットワーク等のシステムでの定期的な情報共有や、急性期病床を持つ医療機関の入退院支援部門に対する定期的な情報共有等を行っている場合、入院日から一定期間内に医療機関を退院した者を受け入れた場合については、初期加算の報酬を引き上げる方向性も示されている。
なお、地域連携診療計画情報提供加算及び認知症情報提供加算については、算定率が著しく低いことを踏まえて、廃止される方向だ。