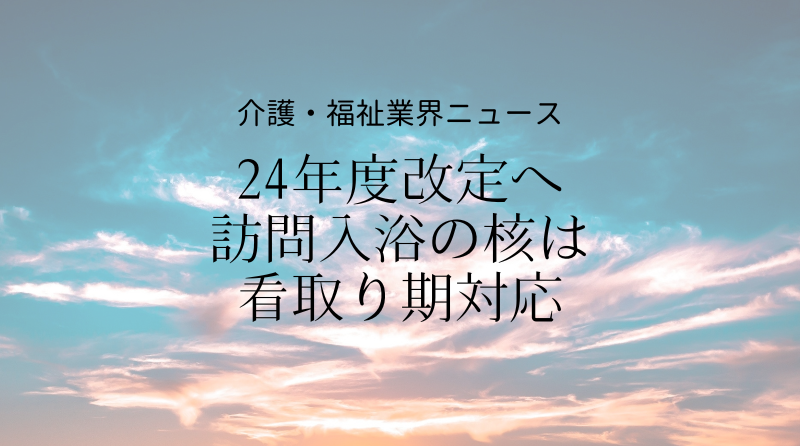社会保障審議会・介護給付費分科会では、2024年度報酬改定に向けて個別サービスの議論が一巡しました。訪問入浴介護を巡っては、看取り期におけるサービス提供が今後の論点となりそうです。
厚生労働省がまとめた近年の動向に関するデータからは、受給者数などについて特徴的な動きも見受けられました。
訪問入浴介護を巡る数値データに特徴的な動き
介護報酬改定に向けた検討に先立ち、厚労省は訪問入浴介護を取り巻く各種最新数値を示しています(第220回社会保障審議会・介護給付費分科会)。
これを見ると、訪問入浴介護の請求事業所数は減少傾向にあり、受給者数も同様の傾向にあります。ただ、近年の「特徴的な動き」として、21年・22年は受給者数が増加に転じています。厚労省はこの変動について、「新型コロナウイルス感染症の影響でデイサービスを利用できず、一定数が訪問入浴介護に流れたのでは」と見立てを示しました。


(【画像】第220回社会保障審議会介護給付費分科会 資料2より(以下・同様))
費用額についても20年度・21年度ともに増加しているものの、収支差率は20年度が6.4%に対し21年度は3.7%と大きく減少しています。厚労省は訪問入浴事業の直近の経営環境について、「コロナ禍の影響を割り引いて考える必要がある」との見解を示しました。

看取り期の利用者に対するサービス提供状況
厚労省はこの日の審議会で、訪問入浴介護の報酬改定での対応について論点を以下の通り示しています。
- (訪問入浴介護の)機能・役割を踏まえつつ、看取り期等においても、利用者の安全を確保しながら、サービスを提供する観点などから、どのような方策が考えられるか。
議論を深めるため、「看取り期」のサービス提供状況についてデータも示されました。22年度の調査研究事業の結果によると、直近1年間において「看取り期の利用者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した人)に対するサービス提供」を実施した訪問入浴介護事業所は、全体の59.5%でした。
また、こうした利用者に対するサービス提供の特徴については、「利用者の身体の状況等に特に留意が必要であり、通常のサービス提供より手順や行為が増えるため、サービス提供に時間がかかる」との回答が79.9%と最多に。さらに、64.3%が「平時とは違った事業所の体制等になる場合がある」と回答も強調しています。

看取り期のサービス内容や事業所の体制に着目
厚労省は看取り期のサービス提供について、そのほかにも詳細データを示しています。まず、通常のサービス提供と比べ看取り期に「増えた行為」について。入浴前は「身体に関する保全行為(褥瘡等の保護、防水処理等)」、入浴後は「褥瘡等へのスキンケア」が最多。入浴中は「呼吸状態や意識状態などの観察」が最多となりました。
「平時とは違った事業所の体制等」としては、「事業所外の医師・訪問看護師等の多職種と連携できる体制を取っている」、「訪問予定日時を訪問診療や訪問看護の訪問日程に併せて調整している」との回答がいずれも7割を超え、多くなっています。


委員からは、訪問入浴介護サービスの重要性に触れる意見があったほか、「看取り期を含め安心してサービスを利用できるよう検討していく必要がある」と、厚労省の示した検討の方向性に賛同する声があがりました。