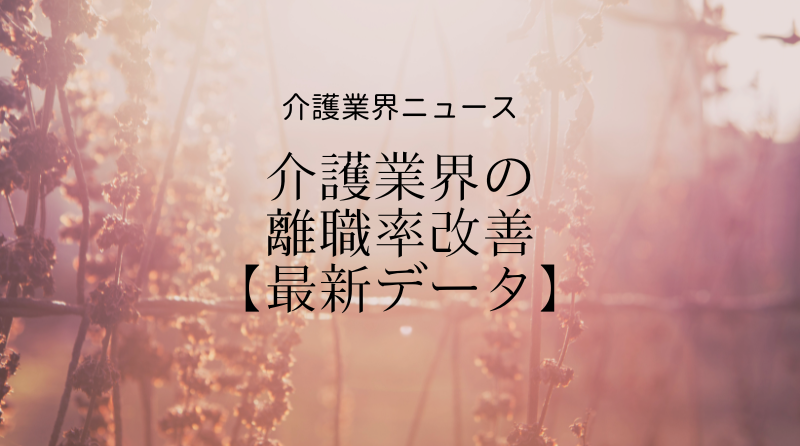介護業界のおよそ6割の事業所が人手不足感を抱いており、特に訪問介護では、「大いに不足している」と感じる割合が過去最大となったことが、介護労働安定センターの直近の調査でわかりました。
こうした人手不足感が根強い一方で、離職率は改善しています。2023年度の介護職の離職率は13.1%となり、05年以降で最も低くなりました。
離職率が改善している背景には、従業員の定着を目指す事業者が、人間関係などの職場環境をより良くしたいと取り組んだ効果が表れているものとみられます。
また、「業務に対する社会的評価が低い」と回答した割合が減るなど、職員の意識の変化もうかがえます。
早期離職を防ぐ取り組みの効果は限定的で、人手不足感の解消には至っていませんが、やりがいを持って働ける環境作りを続けることは、解決に向けた一つの糸口になりそうです。
訪問介護の「大いに不足」は3割超、過去最悪に
介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査」は、労働環境の課題などを明らかにするために、全国の介護サービス事業所から無作為抽出した1万8,000件とその事業所で働く5万4,000人の従業員を対象に、23年10月にアンケートを実施しました。回答率はそれぞれ53.0%と40.3%で、取りまとめた結果を7月に公表しました。
今回の調査結果で特徴的だったのは、依然として続く従業員不足です。

(表1 従業員の過不足状況)
まず、「訪問介護員」や「介護職員」(訪問介護以外の介護事業所で働き、直接介護を行う人)、「介護支援専門員」などを含んだ業界全体について見ていきましょう。
従業員の充足度について、「大いに不足」(12.1%)、「不足」(21.9%)、「やや不足」(30.7%)を合計すると、6割超の事業所が不足を感じているという回答でした。
次に職種別に見ると、訪問介護員が最も顕著に表れています。「大いに不足」の割合は31.3%と、全職種の中で群を抜いて大きく、現在の形態で調査を取り始めた06年以降で最大となりました。 これに「不足」(28.4%)と「やや不足」(21.7%)を合計すると、実に8割を超える事業所が人手不足に悩んでいることがわかりました。 また介護職員についても、「大いに不足」(13.0%)、「不足」(21.7%)、「やや不足」(31.2%)を合わせると6割超に上ります。

(表2 訪問介護の不足感 推移データ)
人手不足の影響 利用者の受け入れ抑制や従業員への負担増に
ではこうした影響は、現場にどういった形で表れているのでしょうか。まず、「訪問系」や「施設系(入所型)」といったサービス系型ごとに見てみましょう。
訪問系では、「利用者の受け入れ抑制」(44.5%)を筆頭に、「業務負担の重さ等」(35.2%)が続きます。
これが「施設系(入所型)」になると、「業務負担の重さ等」(43.5%)の割合が最も高く、次いで「勤務時間の長さ等」(33.2%)となっています。一方、「利用者の受け入れ抑制」(15.8%)は全体の平均よりも下回っています。
次に「事業所規模」で確認すると、「利用者の受け入れ抑制」で当てはまると回答した割合は「4人以下」(43.0%)と「5〜9人」(31.8%)の少人数の事業所が、全体平均よりも5ポイント超上回りました。
それが「50人〜99人」になると18.5%、「100人以上」では15.1%と、規模が大きくなるにつれて割合が小さくなっています。その代わりに「業務負担の重さ」や「介護の質の低下」が増えています。

(表3 介護職員不足が及ぼす影響)
離職率の低下傾向続く、職場の人間関係の改善で
こうしたデータから読み取れるのは、経営基盤の弱い小規模事業所が多い業態の訪問介護を中心に、在宅介護のニーズが高まる中であっても、やむを得ず受け入れを断念するケースが増えている可能性があることです。また、従業員の多い施設系では、利用者の受け入れを続ける代わりに職員への負担が増している状況がうかがえます。
人手不足感が強い介護業界ですが、一方で、昨年度の介護職の離職率は、比較が可能な05年度以降で最も低くなった(13.1%)ことが示されました。
その要因として、国による介護職の処遇改善施策や事業者が職場環境の改善に取り組んだ効果が表れていることが類推できます。
調査では事業者に、早期退職を防ぎ、定着を促進するために取り組んでいる方策について尋ねていますが、「ハラスメントのない人間関係のよい職場づくりをしている」が69.2%でトップでした。
従業員の側にも、働き続ける上で実際に役立っている職場の取り組みについて質問しており、ハラスメントのない職場作りや、仕事内容を変えずに労働時間などを変える取り組みが上位に入りました。

(表4 働き続けるうえで役立っている職場の取り組み)
キャリアアップの機会を重視 医療分野の研修を求める動き
従業員のスキルアップを図りたいという声に応えることも、環境改善で重要なポイントとなっています。医療・介護連携の必要性が増す中で、20代や30代を中心に、専門性を身に付けたいと、研修を重視する気持ちが高まっていることがデータから浮かび上がります(資料2,p76)。
従業員に尋ねた「自分の能力アップに役立った研修」では、感染症や認知症の基礎的理解、終末期ケアという回答が多く見られました。
新型コロナウイルス感染症の対応が長く続いていることや、住み慣れた場所で最期まで過ごしたいという考えにより、看取りケアのニーズが高まっていることなど、現代の潮流が反映されています。
そして、今後受けたい研修では、「薬の知識」(30.6%)がトップで、次いで「精神保健(こころのケア、精神障がい)」(26.6%)、「終末期ケア(ターミナルケア)」(24.0%)、「医学の基礎知識」(22.5%)、「介護における医行為」(20.0%)など、医療分野への関心が高いことが分かる結果となりました。

(表5 今後受けてみたい研修)
介護職へのイメージが近年変わってきたことを実感する従業員も増えているようです。「業務に対する社会的評価が低い」という項目での回答が、この5年間で最も低くなったからです。(資料2,p67)
「介護職としての専門性を身につけて、やりがいを感じたい」
こうした希望を叶える環境をいかに整えられるかが、従業員の定着につながり、介護業界が安定的にサービスを提供できる一つのカギとなりそうです。
参考資料
1:事業所調査「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」結果報告書 本編
https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/2023_jittai_chousa_jigyousya_honpen.pdf
2:労働者調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」結果報告書 本編
https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/2023_jittai_chousa_roudousya_honpen.pdf