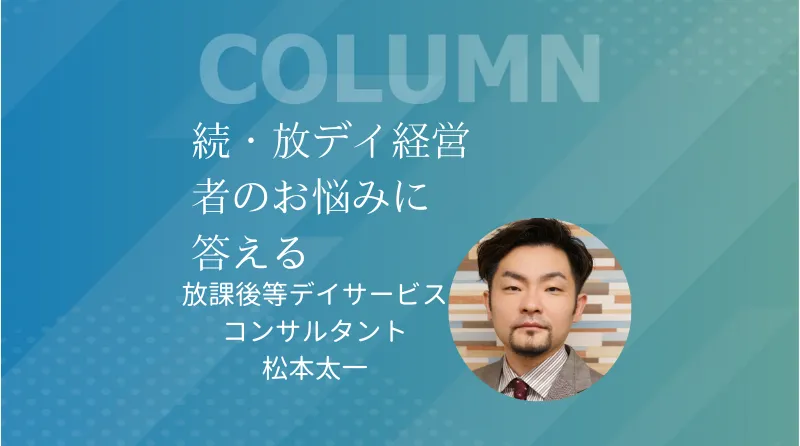放課後等デイサービスコンサルタントの松本太一です。
前回に引き続き、放課後等デイサービスを運営する経営者からよく聞かれる質問やお悩みにお答えします。 今回は、多店舗展開するときの考え方や経営理念の浸透について取り上げます。
*これまでの連載はこちら
Q3「障害程度が重い子と軽い子で事業所を分けたほうが良いか?」
これは1事業所目が軌道にのり、2事業所目の立ち上げを計画している経営者からよく聞かれる質問です。
結論としては、「障害程度ではっきり分けてしまうのはリスクが大きいので、緩やかな分け方にとどめるのがよい」とお答えしています。
こうした質問の背景には、放課後等デイサービスの利用対象が小学生から高校生までの幅広い年代に渡る子どもたちであること、その中には知的な遅れや多様な障害特性を持つ子がいることが関係しています。
これだけ多様な子どもが通う以上、各事業所では様々な支援目標に対応できるよう課題や活動を用意する必要がありますが、一つの事業所がその役割を充分に担うのはなかなか難しいです。 そこで、複数事業所があるなら事業所ごとに対象となるお子さんの発達段階を限定し、その段階にあわせたプログラムや教材を用意することで、法人全体として効率的な支援ができるという対策が浮かぶのではないでしょうか。
例えばA教室は知的な遅れのない通常学級に通う子を主な対象とし、ソーシャルスキルトレーニングや運動プログラムなどの小集団指導を軸とする。B教室は知的な遅れを伴う支援学校に通う子たちを主な対象とし、言葉の理解や身辺自立を狙った個別の療育を中心とする。その中間にあたる支援学級のお子さんは個々のケースに応じてどちらを選ぶか都度判断する、といった具合です。
この方法は、各事業所での支援のしやすさという面では効果的です。事業所で用意する教材や遊具を絞りこみやすく、研修等で支援員の専門性を高めるときも想定する利用児の状態像を明確にしやすいからです。 しかし、グループ全体の経営という観点からは、かなりのリスクがあります。障害程度が重い子たちが通う事業所の支援員の負担が大きくなり、事業所間で不公平感が生まれてしまうためです。
たとえば障害程度が重く、言葉の理解が難しいお子さんが多く在籍する事業所の場合、一人の支援員の指示に従って全体が活動をすることが難しく、その場合支援員が子ども一人ひとりに個別対応する必要があります。
また、身辺自立ができていない子も多く、着替えや食事、排泄といった生活上のニーズを満たすための介助が必要となります。そのため障害程度の重い子を受け入れる事業所の支援員からすると「同じ法人なのに、なぜ私達ばかりが苦労するのか」という不満が生まれ、それがきっかけで離職に至る場合も少なくありません。
もちろん、障害程度の重い子がいる事業所に、支援員を厚く配置することでこうした不公平感はある程度緩和できます。しかし、その分人件費がかかるので、他の系列事業所と比べたときに障害程度が重い子が多い事業所だけ利益があがらず、経営者の評価が厳しくなりがちです。そのことが管理職ひいては支援員との関係悪化につながりかねません。
そこで、複数事業所を運営にするにあたっては、ある程度子どもの障害程度にあわせた事業所の特色づけはしても、支援員の負担に大きな差がでないようバランスを調整していく必要があります。
有効な調整の仕方は一概には言えませんが、例として、A事業所は通常学級所属の子中心、B事業所は知的障害を伴う特別支援学級所属の子を中心とし、主に特別支援学校に在籍して個別対応が必要な重い障害程度の子は両事業所に分散するという方法でバランスを取っている法人もありました。
また、利用児の調整だけでなく、事業所間で定期的に支援員を異動させることで、一部の支援員だけに負担がかからないようにする方法も有効です。
Q4.「法人の理念が浸透せず、従業員がみな自分勝手な考えで働いている。どうしたらよいか?」
組織の理念にまつわる悩みも多く聞かれるところです。
理念とは、組織の構成員すべてが目指すべき目標や仕事に取り組む姿勢を示すものです。経営者であろうと従業員であろうと関係なく、全員がそれを尊重して初めて機能します。
経営者自身が理念を体現できているか?
「理念が浸透していない」という法人にありがちなのは、経営者が従業員を思い通りに動かす手段として理念を使っていて、その経営者自身はその理念に基づいた行動ができていないというパターンです。
経営者が従業員にばかり理念の尊重を求め、自身がその理念を体現できていなければ、誰も理念を尊重しようとはしません。 たとえば「いつも笑顔で接します」という理念を掲げるのなら、経営者自身が従業員や利用者にいつも笑顔で接してきたのでなければ説得力がありません。経営者自身がその姿で示してきたことでなければ、理念に掲げることはできないのです。
みんなで造り上げた「理念」が機能しない理由
もう一つ理念が浸透しないのは、「みんなで話し合って理念を決めた」ケースです。これは民主的な方法ではありますが、こうしたやり方で生まれた理念にはどうしても妥協が入り、誰もがある程度までは納得しているが、ある程度は納得が行っていないものになります。そのため、一人ひとりがそれを全面的に尊重して仕事をすることは難しく、価値観の相違が明らかになった場合には「理念を決めるとき、私は反対したが無視された」といった蒸し返しが起きることになります。
数多くの事業所の運営をサポートしてきた経験から言えることは、「メンバー全員が尊重できる理念を作るには時間がかる」ということです。経営者・管理職・従業員がある程度の時間をかけてそれぞれの仕事に取り組んできた中で、大切だと思ったことを言語化していくというプロセスがなければ、浸透させるのは難しいものです。
目安としては2年から3年の運営経験があり、それを振り返りながら作った理念であれば、それが経営者主導であれ話し合いによるものであれ、現場の支援員にも説得力をもって受け入れられていくと感じています。 それでは、そのような運営経験を積んでいくまでの過程ではどうしたらよいのでしょうか。
理念は会社や事業所の成長とともに変わりゆくもの
法人・事業所の創設の際には、行政に報告する上でも利用者にPRするうえでも理念を掲げる必要がありから、まずは経営者が自分の思いを言葉にして掲げる必要はあります。しかし、それを絶対視するのではなく、いずれ法人として成熟していく過程でその理念は変わりゆくものと捉える必要があります。
そのうえで、創業間もない時期に必要なのは、具体的なルール作りです。組織の運営についても、支援の実施についても、その実践において経営者・管理者・支援員の間で誰がどうするのかが明確になっておらず、曖昧な判断になっている事柄が多々あるはずです。こうしたこと一つ一つを話し合い、明確なルールにしていく過程で、お互いの価値観の違いが明らかになり、それをすり合わせ、実地で実践して、上手くいかなかったことを修正していく。
その過程を数年積み重ねてくると「色々意見の対立はあったけど、この思いだけはみんな共通だったね」「判断の軸はブレたこともたくさんあったけど、この部分だけは揺らがなかったね」とみんなが思える部分がでてきます。それを言葉にしたものが、本当の理念になると考えます。
今回取り上げた質問は、いずれも根本的で抽象度が高いものでしたが、法人を発展させていく過程でどの経営者の方も直面する課題です。ぜひ参考にしていただければと思います。
さて、長く続けてきたこの連載も、次回で一区切りとなります。
最後は、放課後等デイサービス運営上の最大の悩みと言える「人手不足」についてその原因と対策をお伝えしたいと思います。