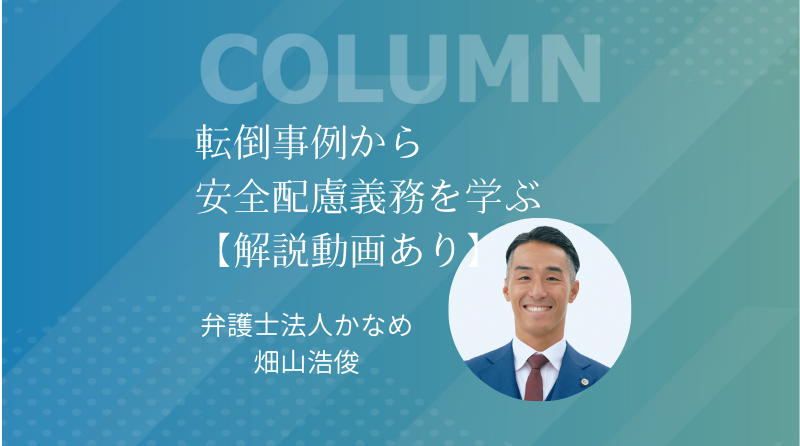今回は、デイサービス内で起きた転倒事故について、職員の利用者に対する安全配慮義務が争われた裁判例を解説します。 この記事を読むことで、
- 安全配慮義務とは何か、基本的なルール
- 「普段と違うときこそ特に注意が必要」
という重要なポイント
を学ぶことができます。
介護現場におけるリスクマネジメントを考える上でも重要な裁判例ですので、是非、現場でも役立ててください。
1.利用者がトイレ内で転倒!その時の状況は?
今回解説する裁判例は、横浜地裁平成17年3月22日の判決です。 まず、転倒された高齢女性の当時の状況をお伝えします。
事故発生当時、女性は85歳。
両足全体に麻痺があるうえ、加齢による筋力低下で歩行が不安定でした。
ふらつきがあり、支えがないと両足で立っている状態を維持できず、杖が必要でした。
室内歩行時も杖を使用していました。
意思能力については、短期の記憶は問題がなく、日常の意思決定を行うための認知能力も自立していました。 自分の意思を伝達することもできていました。
次に、事故当日の状況です。
帰りの送迎を待っている女性利用者が、送迎者がその間にトイレに行こうと思い、杖をついてソファから立ち上がろうとしました。
ここが大きなポイントになるのですが、このトイレは身体障害者用で、車椅子の人でも利用しやすいように中が広く作られていました。 トイレの入口から便器までの距離は約1.8メートル、横幅は約1.6メートルで、入口から便器まで行く間の壁には手すりはありませんでした。
しかも、この女性利用者は、普段は入口から便器までの距離が短く、かつ、壁に手すりがあるトイレを使用しており、この身体障害者用のトイレを使用するのは、帰りの送迎を待っているタイミングのみだったのです。
職員は転倒の危険を感じ、介助しようと考え、「ご一緒しましょう」と声をかけます。女性は「一人で大丈夫」と言いましたが、職員は「トイレまでとりあえずご一緒しましょう」と歩行介助しました。
そして、トイレの中に入った段階で、女性は職員に対し「自分一人で大丈夫だから」と言って内側からトイレの戸を自分で閉めたのです。鍵はかけていませんでした。 このとき、付き添った職員は「あ、どうしようかな。戸を開けるべきか」と迷ったのですが、結局戸を開けず、女性がトイレから出る際に歩行介助をしようと思い、その場から離れました。
その直後です。トイレ内に入った利用者は便器に向かって右手で杖をつきながら歩き始めましたが、2、3歩歩いたところで杖がすべって転倒し、右大腿骨頚部内側骨折の傷害を負いました。
この事故の後、利用者は生活のほぼ全てに全面的な介護を要する状態になりました。
2. .介護事故の責任はどこまで?安全配慮義務の考え方
さて、ここで安全配慮義務についての解説です。 まず、介護サービスの提供に当たって、介護事業者と利用者は、介護利用契約を締結しています。簡単に言うと「利用計画に基づいて、利用者にはこのようなサービスを個別に提供しますね。サービス提供に対して、利用料を支払って下さいね」という内容の契約です。
しかし、このとき介護事業者が利用者に対して負う義務は、サービス提供義務だけではありません。介護事業者は介護利用契約上、利用者の生命、身体、健康を危険から保護するよう配慮する義務、すなわち安全配慮義務も負います。 安全配慮義務を尽くしている中で発生した介護事故に関しては、介護事業者は損害賠償責任を負いません。
そして、安全配慮義務の内容は、個別具体的な事案によって具体的に特定する作業が必要です。 つまり、
- 介護事故の発生が具体的に予見できたのか(予見可能性)
- その結果を回避するために具体的にどのようなことを行うべき義務(結果回避義務)があったのか を考える必要があります。
今回の転倒事故について、裁判所は、デイサービス側の①予見可能性を次のように判断します。
そして、②結果回避義務について次のように判断します。
その上で、今回の転倒事故については、以下のように判断し、デイサービス側の安全配慮義務違反を認めます。
なお、この裁判で、裁判官はもう一つの重要な点を論じています。
それは、今回の事案では、意思疎通が可能な利用者が職員によるトイレ内における介護を拒否したのだから、義務違反は無いのではないか?という点です。
裁判所は以下のように判断しています。
つまり、いくら利用者が介護を拒絶したとしても、簡単には介護義務を免れることはできないと判断している訳ですね。
実際、今回の裁判例の事案では、利用者から「自分一人で大丈夫だから」とトイレ内に入ることを拒絶された際、職員は介護を受けない場合の危険性についても、その危険を回避するための介護の必要性についても説明しておらず、介護を受けるよう説得もしていないので、利用者から拒絶されたことが歩行介護義務を免れる理由にはならないと判断されています。 もっとも、利用者自身が本件トイレを選択したことと、自ら介護を拒絶したことについては、利用者側にも過失があると判断され、3割の過失相殺がなされ、最終的には損害額は1,253万719円と判断されました。
今回の事案は、壁に手すりがついた通常の安全なトイレではなく、入口から便器まで歩行する距離があり、しかも壁に手すりがついていない身体障害者用のトイレを使用するという場面であった点が歩行介護義務違反を認められた大きなポイントでした。
「いつもの環境とは異なるトイレ」を利用する場面において、介護従事者は特に注意が必要であることを確認する上では重要な裁判例だと言えるでしょう。
もちろん、トイレの中に入って欲しくない、という利用者の意思、個人の尊厳を尊重することも大切です。
しかし、今回の裁判例の事実関係を読むと、やはり、便器まで一緒に歩行介助をした上で職員がトイレから出ていくということはできた事案だと思います。
個人の尊厳と利用者の生命・身体という両方とも利用者の大切な権利ですから、個別具体的な状況を見て、しっかりとバランスを取る必要があるなと思います。とても難しい問題ですが、今回の裁判例を元に皆様で普段の介護の在り方を見直すきっかけにしていただければと思います。
*今回のお話を動画でも解説しています。ぜひ事業所内の研修などでもご活用ください。