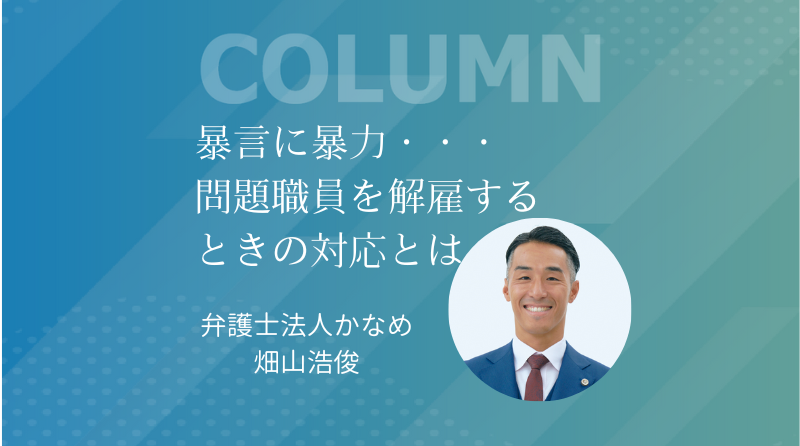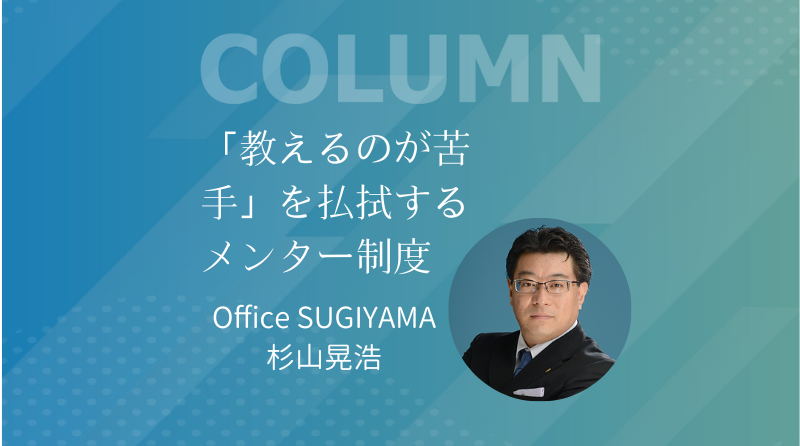今回は、正社員とした採用した職員が、試用期間中に同僚の胸ぐらを掴んだり、上司に暴言を吐いたりといった問題行動を起こした場合、適法にその職員を解雇にする際の注意点や具体的な手順についてお伝えします。
介護現場では、人手不足を背景に「売り手市場」の状況が続き、問題のある職員を採用してしまうリスクも高まっています。 もし、このような“モンスター職員”に出会ってしまった場合、事業者はどう対応すべきでしょうか。 実際の裁判例を取り上げ、動画によるポイント解説も交えながら解説します。
【実際の裁判例】暴力・虚偽報告…職員の適格性が問われたケース
さて、今回は有料老人ホームの施設長からの相談です。
最近採用した男性の職員の素行が悪くて大変困っています。
スタッフがその男性に「おはようございます」と朝の挨拶をしたのですが、返事を返さないので注意したところ、いきなり「お前、やんのか」と胸ぐらを掴んだのです。
採用してまだ2カ月も経っていない頃の出来事です。
社内でも当然問題になり、上司がその男性職員を呼び出して事情聴取しました。
その際、問題の職員は、「以前バイクで交通事故に遭ったことがあって、その影響で記憶が飛ぶことがある」と発言したのですが、実際はバイクの免許も持っておらず、事故に遭ったこともなく、単なる虚偽発言でした。
このほかにも上司を呼び捨てで呼んだり、怒鳴りつけたり、問題行動のオンパレードです。
まだ試用期間中なのですが、この様子を見ていると本採用はできないと思っています。
本採用を拒否しようと思っているのですが、注意点はあるのでしょうか。
どのように手続きをすれば良いでしょうか。
相談内容は作り話ではなく、東京地裁令和3年3月16日判決の事例を元に作成しました。
有料老人ホームで働く男性職員の粗暴な言動を理由に試用期間中で解雇したところ、この問題職員が「不当解雇だ!」と法人を訴えた事例です。
結論として、裁判所は不当解雇ではなく違法性はないと判断したのですが、実際に現場でこのような職員に遭遇した際はどのように対応すれば良いのでしょうか。
今回のポイントは3つです。
- 試用期間中の解雇の性質を理解しよう
- 問題行動については指導した上で記録を残しておこう
- 逆パワハラには臆せず対応しよう
順番に解説します。
対応のポイント①:試用期間中の解雇の性質を理解しよう
試用期間とは、新たに採用した職員について、実際に業務に従事させながら、その人物や能力、勤務態度などが法人に適しているかを評価するために設ける一定期間のことです。
「見習い」のようなイメージですが、実際に働いている点では「内定」とは異なります。
多くの法人が正社員採用時にこの制度を導入していますし、ほとんどの場合は、就業規則や雇用契約書の中で具体的に試用期間に関するルールが定められています。
いわばこの「見習い期間中」に法人として相応しくないと判断されると、雇用契約を解除(解雇)される可能性があるという点で、試用期間中の雇用契約は「解約権留保付き」の雇用契約と解釈されています
そのため、試用期間中に「あれ?採用決定時にはこんな人だとは思っていなかったぞ」というようなケースでは、試用期間中に本採用拒否をする場合は、通常の解雇の場合に比べて法人側には広い範囲における解雇の自由が認められているのです(三菱樹脂事件:最大判昭和4年12月12日参照)。
とは言え、無制限に、あまりにも簡単に解雇を認めてしまうと労働者保護に欠けることになるので、裁判所は以下のように試用期間中の解雇ができる場面を限定しています。
「使用者が、採用決定後における調査の結果により又は試用期間中の勤務状態により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当ではないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に相当であると認められる場合には、さきに留保した解約権を行使することができるものと解すべきである」(東京地裁令和3年3月16日判決)
実はこれは内定取り消しの場面と非常に良く似ています。内定取り消しに関する注意点は以下の動画をご覧ください。
【内定取り消しができる場面とは?事例とポイントを弁護士が徹底解説】
https://youtu.be/tfgQFqb2L0w
なお、今回の相談事例のもととなった裁判例では、同僚の発言に立腹してその胸ぐらをつかみ暴言を吐くなどの感情的な行為に及び、事情聴取においても、これを認めずかえって全く架空の事実を告げるなど不誠実な態度をとっており、職員としての適格性を欠いていること、これらの適格性の欠如は当初知ることができず、また知ることができないようなものであったことから解約権の行使は問題ないものと判断しています。
対応のポイント②:問題行動は指導した上で記録を残そう
二つ目のポイントは、問題行動に対する指導をした上で記録を残すことです。 多くの法人では、試用期間は大体3カ月程度、長くて6カ月程度です。 この期間は意外とあっという間に過ぎてしまいます。
試用期間で本採用を拒否するような適格性を欠くとして「さようなら」を告げるには、きちんと記録に残しておかなければ、後日争いになったときに、「言った言わない」の不毛な言い争いになってしまうリスクが高くなり、ひいては、法人側の解雇が無効になるリスクがあります。 解雇が無効と判断されてしまうと、解雇を言い渡したときに遡って給料相当額を遡って支払うよう命じられたり、場合によっては解雇した職員が職場に復帰したりなど、大きな打撃となってしまいます。
そこで、
- 試用期間中の問題行動は時系列できちんとメモを取っておく
- 指導した内容も記録を残しておく
- できれば指導は書面で行うこと、
- 口頭で指導を行う場合については録音を実施しておく
ことが望ましい対応です。
特に、粗暴な職員の荒々しい言動を記録に残しておくには最後にお伝えした録音が有効です。 この際の録音は無断録音でも問題ありません。無断録音の際の注意点はこちらの動画をご参考にしてください。
【無断録音】こっそり録音することは違法か? https://youtu.be/9ap01gdQlaQ
【無断録音!】実際にあったミス3選!弁護士が解説します! https://youtu.be/JREpEHStEo0
対応のポイント③:最後のポイントは、逆パワハラには臆せず対応することです。
相談事例のように上司を呼び捨てにしたり、上司を怒鳴りつけたりする行為は、いわゆる逆パワハラですね。
こういった場面に遭遇すると、強い恐怖感を抱き、「できれば関わらないでそっとしていこう」と距離を取りたくなると思います。
しかし、放置は厳禁です。
逆パワハラの行為は、組織の秩序を乱す大きな問題行動なので、決して放置せず、注意指導するようにしてください。 逆パワハラの問題については、こちらの動画でも詳しく解説しているので是非ご覧ください。
【逆パワハラ】放置してはいけない逆パワハラ! https://youtu.be/R_OPaRssjs8
最後に補足ですが、相談事例の元となった裁判例では、暴言を吐かれた上司は、電話で問題職員に激怒してついつい「いいか、首を洗って待っていろ。お前の相手は俺だ」と発言してしまいます。あまりにも無礼な態度に切れてしまったのです。
問題職員は、この発言は「不法行為だ!」と裁判で主張しました。
たしかに、上司の方も暴言と言えば暴言ですし、この言葉だけを切り取れば「パワハラ」と思う人もいるでしょう。
しかし裁判所は、この上司のブチ切れ発言は違法ではないと判断します。
というのも、上司がこのような過激な発言をする前に、問題職員が上司に対し、呼び捨てにしたり、「さっきのは何だ」「おい」「誰が悪いと思っているんだ」などと何度も大声で怒鳴っていたことがあり、このような経緯に照らせば、上司の発言がいささか穏当さを欠くとしても、これをもって違法であるということはできない、と判断しているのです。
言葉だけを切り取ってパワハラかどうかを論じるのはあまりにも不毛ですね。 とは言え、このような問題職員に対して怒鳴りつけたくなる気持ちは分かりますが、怒鳴って向き合うのは時間の無駄ですし、エネルギーの無駄なので、そっと電話を切って心を静められると良いですね。この上司は気の毒です。
今回は、試用期間中の問題行動を理由に解雇に処した事例を元に解説をしました。
皆様の事業所でも是非参考になさってください。
*今回のお話を動画でも解説しています。ぜひ事業所内の研修などでもご活用ください。