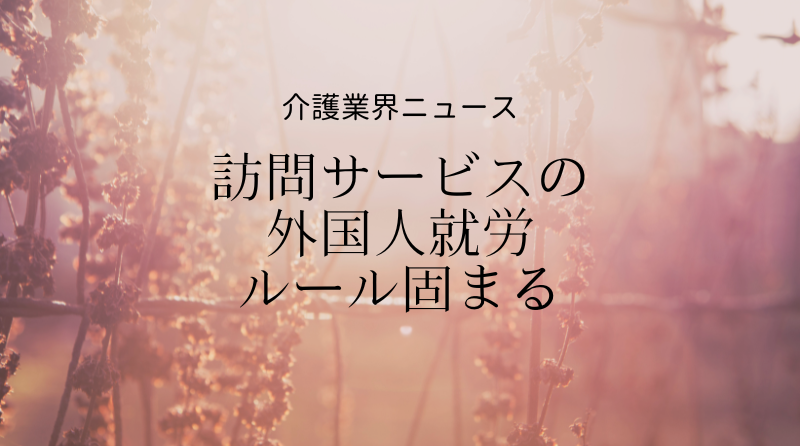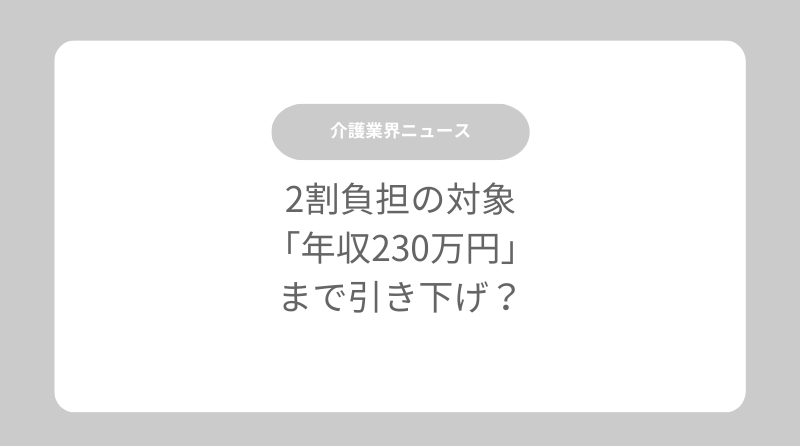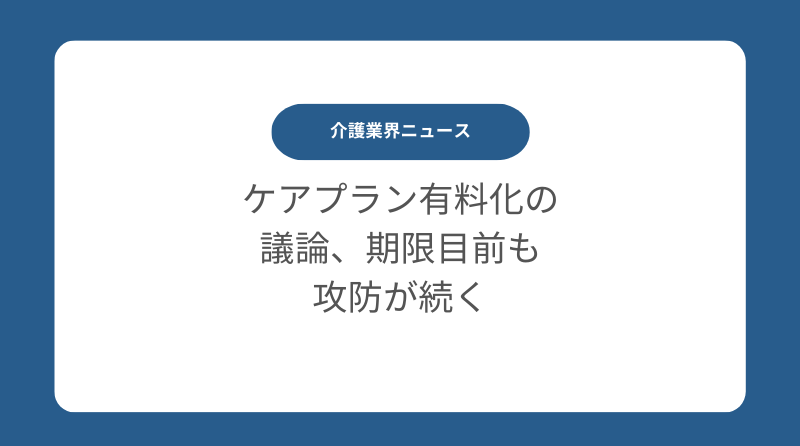外国人材の訪問系サービスへの従事等について話し合ってきた検討会で、厚生労働省が「中間とりまとめ」の原案を示しました。
※(7月5日追記:6月26日に正式な「中間とりまとめ」が公表されています。
訪問介護、定期巡回随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴で技能実習生や特定技能「介護」の資格保有者ら(以下、外国人人材)の従事を新たに認めるにあたって事業者の遵守すべき事項などが盛り込まれています。なお、こうした方針は、障害福祉サービスでも「同様」の考え方が適用されるものとされています。
訪問介護、定期巡回、夜間対応型訪問介護、訪問入浴向けに外国人材従事のルールを記載
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会の「中間とりまとめ」案には、これまでの話し合いから
- 訪問系サービス(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び訪問入浴介護)への従事
- 技能実習「介護」の受け入れを認める”事業所開設後3年要件”の緩和
に向けた運用ルールなどがまとめられました。
このページでは、今回記載された内容のうち、技能実習生や特定技能「介護」資格保有者、EPA 介護福祉士候補者が訪問系サービスの現場で働く場合のルールについてお伝えします。
訪問介護では研修のほかハラスメント対策やICT活用した環境整備が事業者の責務に
まず、とりわけ人材不足が深刻な訪問介護についてです。
訪問介護の現場で従事できる人材は外国人人材であっても介護職員初任者研修を修了した有資格者等に限定し、事業者に対しては遵守事項が定められる方針です。
遵守事項を履行できる体制や計画を整えることを示すために事業者は、「巡回訪問等実施機関」に対して以下5点に関する書類を提出することになっています。
- 外国人介護人材への研修は、訪問介護の基本事項、生活支援技術、利用者、家族や近隣とのコミュニケーション、日本の生活様式等を含むものとする(EPA介護福祉士が訪問系サービスで働く際と同様の規定)
- サービス提供を一人で適切に行えるよう、サービス提供責任者等が一定期間同行するなどにより必要なOJTを行う
- 外国人介護人材に対して業務内容や注意事項等について丁寧に説明を行い、意向等を確認しつつ、外国人介護人材のキャリアパスの構築に向けたキャリアアップ計画を作成する
- ハラスメント対策の実施(未然防止のためのマニュアルの作成・共有、管理者等の役割の明確化、対処方法等のルールの作成・共有、 相談窓口の設置など)
- 負担軽減や不測の事態に適切に対応するための環境整備(介護ソフトやタブレット端末活用による記録業務の支援、コミュニケーションアプリの導入、相談体制の整備など)
このほかにも外国人材を受け入れる事業者に必要な配慮として、
- 外国人人材の従事について事業者が利用者・家族への丁寧な説明を行う
- 施設サービス等での実務経験がなく、訪問系サービスに初めて従事する場合は、利用者・家族にその旨を丁寧に説明そ、サービス提供責任者等が十分配慮しながら徐々に業務に慣れることができるようOJT の期間を通常より長くする
- 面談を定期的に行う
- きめ細かな日本語の学習支援に取り組む
ことなどが挙げられています。
このルールは定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護でも適用されるほか、障害福祉サービスでも準用されることになりそうです。
訪問入浴介護では実務に必要な研修が必要に
訪問入浴介護は、複数人によるサービス提供が必要とされる一方で、従事者の介護職員初任者研修等の修了は必須条件ではありません。
そこで、外国人人材の受入事業者には適切な指導体制等を確保することを求め、その上で職場内で「実務に必要な入浴等の研修等」を受講させ、業務に従事させることになっています。
また、キャリアアップを助けるため、介護福祉士の資格の取得支援など事業所によるきめ細かな支援を行うよう、事業者に対する配慮も求めることとされています。
訪問系サービスでの外国人従事の新ルールと今後の取り扱い
今回の取りまとめ案が示された6月19日の会合では、事業者を代表する委員から記載の内容に対する明確な反対意見はありませんでした。
ただし、労働者の立場からは「(外国人人材の訪問系サービスの現場での従事を認める要件として)施設における実務経験は最低1年とするなど、国において最低基準を設けるべき」「(外国人人材が訪問の現場で働くことについて)利用者やその家族に対しても説明するだけでなく、少なくとも合意を得ることが必要」(松田陽作構成員/連合・総合政策推進局生活福祉局次長)という指摘や、その旨を報告書へ追記するよう求める意見もありました。
議論の内容は後日反映され、後日、厚労省のウェブサイトで正式な報告書として公表される予定です。
また、これらのルールは、他省庁の管轄する制度との調整を経て制度に反映される見通しです。ただし、そのタイミングについては「準備が整い次第」とされています。