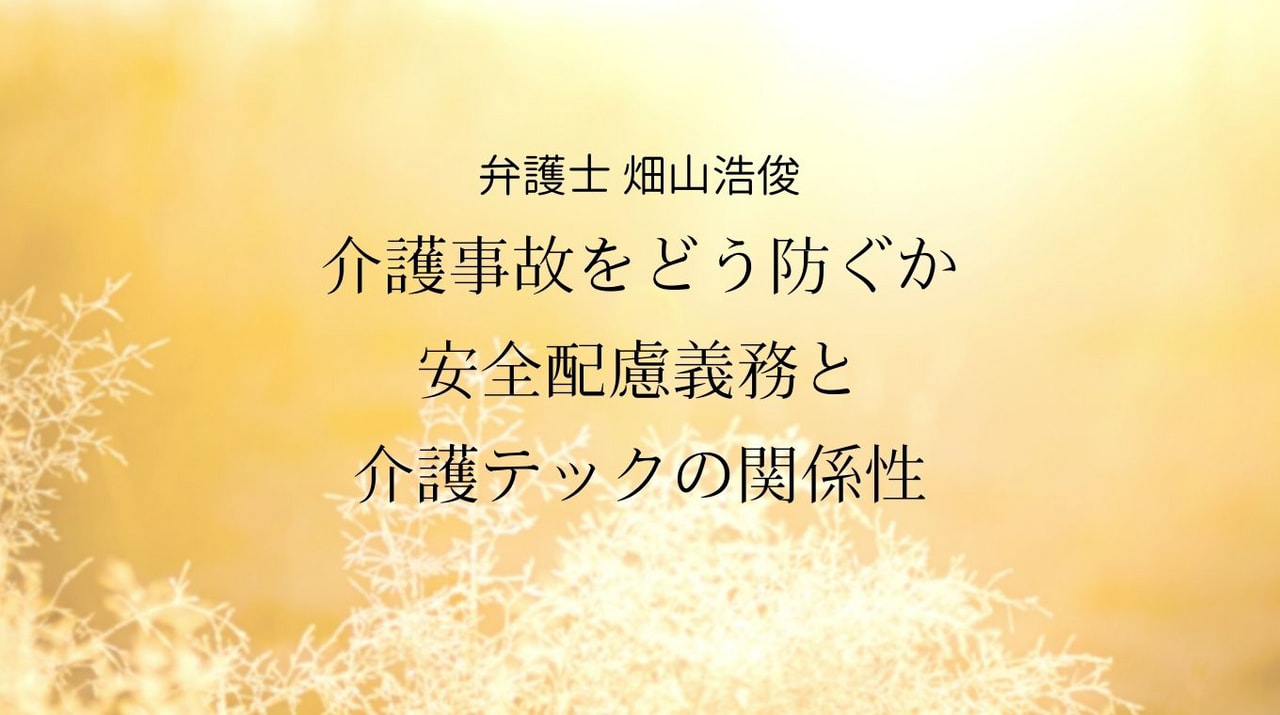1.介護施設内で発生した転倒事故とその法的責任
<ケース>
とある特別養護老人ホーム内のショートステイでの出来事。
太郎(仮名)は79歳、パーキンソン症候群等の影響で転倒リスクの高い利用者。
もっとも、意思能力や判断能力に問題は無い。
介護職員は、太郎に「お手洗いに行く際は、転倒するといけないので必ずナースコールを押して下さいね。」と伝えていたが、太郎は言うことを聞かず、ナースコールを押さずに一人で居室内のトイレで用を足すことが頻繁にあった。
そんなある日・・・。太郎の居室のナースコールが鳴る。
職員「あ、太郎さんの部屋からだ。どうしたんだろう。」
職員が太郎の居室に到着すると、太郎は、洗面所に足を向け、居室入口に頭を向けて仰向けの状態で倒れていた。
職員「太郎さん!どうしたのですか!大丈夫ですか!?」
太郎「トイレから出てきたら、ふらふらして倒れてしまった。こけた時に頭も打った。」
職員「太郎さん、だから言ったじゃないですか。こんな風に転倒する危険があるから、トイレに行く前にナースコールで知らせて下さいって。今度から必ず押すようにして下さいね。」
しかし、1回目の転倒事故からわずか三週間後のある日、またもや転倒事故が発生。
ナースコールが鳴り、職員がかけつけたところ、既に転倒している状態。
1回目の転倒事故と同じような事故であった。
結局、太郎は搬送先の病院で急性硬膜下血腫と診断された。
すぐに開頭血種手術を実施するも、その後、意思疎通は不可能になり植物状態となる。
そして、3年後、太郎は急性硬膜下血腫を原因とした呼吸不全により死亡した。
その後、太郎の遺族は、「2回目の転倒事故が原因で太郎は亡くなった。2回目の転倒事故が発生することは介護事業者として予見できたはずだ!安全配慮義務がある。責任をとれ。」とショートステイを運営する社会福祉法人を相手取って訴訟提起した。
(1)利用者の介護拒否と介護義務の免除
この事例は、大阪地裁平成29年2月2日判決の事案を元に、筆者が一部アレンジしていますが、実際に発生した介護事故事例です。
皆様の介護事業所でも「利用者が介護職員の指示を守ってくれず、介護事故が発生した」というご経験は無いでしょうか。
「職員の指示を理解できるのに、それを守ってくれずに事故が発生したのだから、介護事業者は責任を負わないはずだ!」という意見をお持ちの介護事業者も多くいらっしゃるでしょう。
実際に、私もサポートしている顧問先の介護事業者から同様の質問を受けることが多々あります。
では、利用者が「私はその介護は受けない」と介護を拒否した場合、介護事業者のその利用者に対する介護義務は免除されるのでしょうか。
結論は、介護義務が免除されることはほぼあり得ません。
利用者が介護を拒否したことで、介護義務が免除されるのかが争われた横浜地裁平成17年3月22日判決にて、裁判所は以下のように判示しました。
要介護者に対して介護義務を負う者であっても,意思能力に問題のない要介護者が介護拒絶の意思を示した場合,介護義務を免れる事態が考えられないではない。
しかし,そのような介護拒絶の意思が示された場合であっても,介護の専門知識を有すべき介護義務者においては,要介護者に対し,介護を受けない場合の危険性とその危険を回避するための介護の必要性とを専門的見地から意を尽くして説明し,介護を受けるよう説得すべきであり,それでもなお要介護者が真摯な介護拒絶の態度を示したというような場合でなければ,介護義務を免れることにはならないというべき
介護利用契約を締結している以上、利用者に対する介護義務が免除されることは、上記の判決文を読む限り、ほぼあり得ないと言っても過言ではありません。
介護事業者としては、利用者が介護を拒否するからという理由のみで、簡単に「介護しなくていいや」と考えてはならず、他に何か方法が無いか模索する必要があります。具体的には、介護を受けてもらえるよう丁寧に説得を続ける他、介護が拒否されることを前提とした対策を検討する必要があるのです。
(2) 転倒防止のために何をすべきか
では、冒頭のケースで取り上げた事例では、介護が拒否されることを前提とした場合、転倒防止のために何をすべきだったのでしょうか。
ご遺族側は、以下の3つの主張をしました。
1 ポータブルトイレを設置すべき
2 衝撃吸収マットを設置すべき
3 離床センサーを設置すべき
順に見ていきましょう。
ア ①ポータブルトイレを設置すべきか
ポータブルトイレを設置すれば、ベッドから居室内のトイレまで移動する必要性が無くなるのだから、ポータブルトイレを設置しなかったのは安全配慮義務違反になると主張しました。
しかし、裁判所はこの主張を退けました。
ポータブルトイレへの移乗時に転倒するリスクがあるからです。加えて、太郎さんは自宅ではポータブルトイレを使用していなかったので、ショートステイ利用時にこれを利用することを義務付けることは自宅での生活との連続性を失わせることになり、介護利用契約の目的に反することにもなります。
これらの理由からポータブルトイレ設置義務は否定されました。
イ ②衝撃吸収マットを設置すべきか
次にご遺族側は、衝撃吸収マットを設置していれば太郎の転倒・転倒による被害拡大の防止が可能だったのだから、衝撃吸収マットを設置しなかったことは安全配慮義務違反になると主張しました。
しかし、裁判所はこの主張も退けました。
衝撃吸収マットは,その段差及び弾性により,かえって転倒の危険が増大することもあり得るし、転倒の際に頭部が衝突するのは床に限られません。また、居室の床に衝撃吸収マットを敷き詰めることによって事故の発生を防ぐことができたことの裏付けもありません。
これらを理由から衝撃吸収マットの設置義務は否定されました。
ウ ③離床センサーを設置すべきか
最後に、ご遺族側は、離床センサーを設置していれば、太郎さんがベッドから降りようとしていることに気付き、職員が駆け付け、転倒防止措置が講じることができたはずだから、離床センサーを設置しなかったのは安全配慮義務違反と主張しました。
裁判所はこの主張を認めました。
ケースの事故が発生したのは平成23年9月頃だったのですが、この当時、ナースコールを自己判断により押さない利用者に対して離床センサーを設置することが転倒事故の予防に効果的であるとの学会等の発表があったこと、この施設には未使用の離床センサーが1台あったこと、太郎はナースコールを使わずにトイレに行くことがあったのだから、離床センサーを置くことが効果的であったこと等から、離床センサー設置義務を認めたのです。
離床センサーを設置していても、職員が駆け付けるまでに転倒する可能性があるのではないか、との点も争われましたが、事故発生当時、職員は充分確保されていたこと、他の当該職員が対応していた緊急案件は無かったことから、離床センサーを設置していれば転倒する前に駆け付けることはできた、と結論付けられました。
2.介護テックブーム
ケースで取り上げた裁判例は、平成29年2月2日に判決が言い渡されていますが、実際にこの介護事故が発生したのは、平成23年9月です。
裁判では、その事故が発生した当時の知見に照らして、どのような事故防止義務を講じるべきであったかが議論されます。現段階での知見に基づいてジャッジしてはいけないのです。
平成23年9月から、現在まで、実に約10年の歳月が流れましたが、今、介護業界は空前の介護テックブームです。様々なソリューションが市場に出てきています。
その中でも、報道では、介護用センサーは巨大な未開拓市場であるなどと喧伝されています。
例えば、介護ベッド市場については、介護施設と在宅介護を合わせて年間で200万台弱の介護ベッド市場が存在するものの、本来介護ベッドと併せて供給されることが想定される介護用センサーについては、供給される介護ベッド数の2%程度の供給に留まると指摘している記事もあります(令和3年5月17日刊工業新聞朝刊参照)。
また、厚生労働省の地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボットの導入支援事業も相まって、今、介護テックは空前のブームといって良いでしょう。
ここで、筆者が今興味を持っている商品を2つ紹介します(筆者がこれを推奨する趣旨ではありません)。
(1) 株式会社Magic Shieldsの「ころやわ」
ケースで取り上げた裁判例では、衝撃吸収マットは、その段差及び弾性により,かえって転倒の危険が増大することもあり得ると指摘されていました。
たしかに衝撃吸収マットを敷き詰めると、マットとマットの間、マットにより生じる段差につまずくリスクがあり、介護現場ではその使用に慎重なところも多いです。また、柔らかい衝撃吸収マット上では、利用者が自力で車椅子を操作することが難しく、転倒防止に効果はあるものの、デメリットも多々ありました。
これらのデメリットを見事に解消している商品が株式会社Magic Shieldsの「ころやわ」という商品です。「可変剛性構造体」というメカニカルメタマテリアルの概念を応用して設計・製造した素材で、なんと、転んだときだけ柔らかくなるという特殊な床です。一見すると、普通の床です。固い床であり、一枚の床として設置するものなので、段差及び弾性は生じません。その結果、車椅子も自走できますし、杖も問題無く使用できます。
しかし、転倒して強い衝撃が床に加わった瞬間だけ柔らかくなり衝撃を吸収する仕組みになっているのです。同社のホームページ上に動画が掲載されているので是非ご覧下さい。
https://www.magicshields.co.jp/
(2)インフィック株式会社の「LASHIC-care」
次にインフィック株式会社の提供する「LASHIC-care」という見守りセンサーです。
居室内の「温度」「湿度」「照度」「運動量・動き」をモニターし、居室内の利用者が適切な環境にいるかモニタリングしたり、ベッド上の利用者の状態をデータに基づきリアルタイムで把握することで、離床の可能性を30分前から検知することができるセンサーです。
ケースで取り上げた裁判例では、離床センサーを設置すべきであったと結論付けられました。
しかし、離床センサーを設置していても、センサーが反応して職員が駆け付けた時点で、転倒事故が既に発生していた、という事例は枚挙に暇がありません。
裁判例では、当時の夜勤職員の数、他の緊急事態が無かったことから離床センサーを設置していれば転倒事故は防げたはずだと結論付けましたが、真に結果回避ができたかどうかは疑問です。
現在では、30分後に離床する可能性があることを知らせるセンサーが開発されており、これにより効率的な見守りが可能になれば、より転倒を防止できる可能性が高まります。こちらもホームページのリンクを掲載するので是非ご覧下さい。
3.「システム導入=介護事故ゼロ」ではない
以上のように、介護テクノロジーが進歩していくことで、介護事故の件数が減り、仮に事故が発生したとしても、結果の重大性は軽減していくことになると思います。しかし、「システム導入=介護事故ゼロ」ではありません。それを使うことの意味をしっかりと現場全体で考える必要があります。
どれほど素晴らしい技術であっても、「何のためにそれを導入しているのか」「現場の職員が使いこなせているのか」を考え続けなければ、真の効果は得られず、現場の生産性は向上しないどころか、介護事故が減ることはありません。
思考停止に陥らず、現場全体で介護事故防止を考えていくためには、筆者は、過去の裁判例を分析することが有用だと考えています。
裁判で争われている点を、現在の視点から分析することで、「今この事故が発生したら対応できるか」をしっかりと考えることが大切です。その上で、自分たちの介護事業所において、改善点が見つかれば、それを解消するために介護テクノロジーの導入を検討していくことが効果的です。外部から介護事故に詳しい弁護士を講師として招き、現場職員と裁判例を分析する勉強会の実施をしてみると良いでしょう。
現場全体で考え続けることが習慣化すると、事故リスクは低減し、現場の生産性は向上し、介護サービスの質は益々高まっていくと思います。
以上