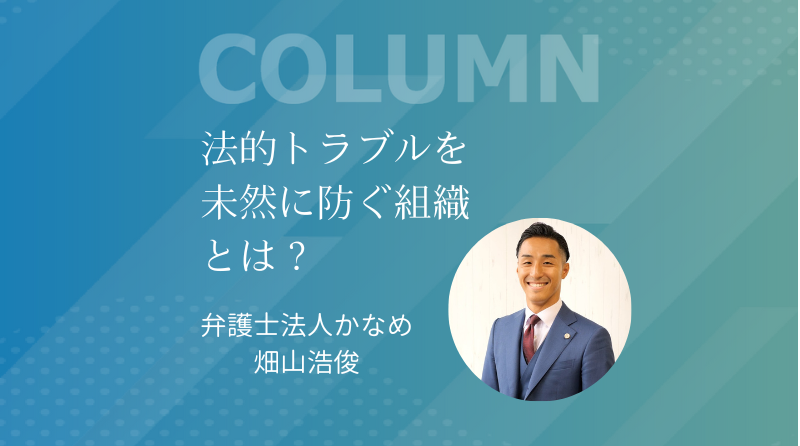1.多種多様な法律相談から見える「組織の問題」について
私が代表を務める弁護士法人かなめは、介護事業者・幼保事業者・障がい福祉事業者等の福祉事業をサポートすることに特化した法律事務所です。日々全国から多種多様な法律相談が寄せられており、問題解決に向けてかなめの弁護士がフル稼働しています。
その中で、「何故、このようなトラブルが起こるのだろうか」という根本原因に立ち戻って思索する機会が多くあります。一概に論じることは難しいのですが、介護現場で生じる労働トラブル(残業代トラブル、ハラスメントトラブル等)、虐待に関するトラブル、利用者やそのご家族との間で生じるカスタマーハラスメントトラブル、クレーム対応等の法律問題は、全て「組織の問題」と捉えることができます。
もっと具体的に分析すると、本来あるべき組織図の構築ができていないがゆえに、適材適所に人が配置できておらず、その結果、あらゆる問題が頻発しているのです。
本稿では、法的なトラブルを未然に防ぐ組織作りの初歩としての組織図の策定法を論じたいと思います。
2.「管理者」の仕事って何だろう―採用活動や請求、利用者獲得…行き過ぎた兼務による落とし穴
介護事業は、事業所ごとに管轄の自治体から「指定」を受けて事業を運営しています。その事業所を統括する職責を担うのが「管理者」であり、その管理者の下に、複数の職員が配置され、日々介護サービスを提供しています。
このように、介護現場における「管理者」とは、その事業所を管理する人なのです。
ですが、実際の管理者は、その事業所の管理業務だけではなく、ほかの業務を兼任している状態が散見されます。
例えば、管理者がその法人の採用活動を担当していたり、請求業務の管理など会計業務を担当していたり、時には、利用者の増加というミッションを与えられ、営業業務も担当しているといったように、業務の重複・兼任の事例は枚挙に暇がありません。
事業所全体を管理する人物が、その他の役割も担うという状況それ自体は、人員配置や適材適所との関係で、やむを得ない場合もあります。しかし、組織のあるべき状態がきちんと可視化できていないと、兼任状態が蔓延化し、優秀な職員は疲弊し、結果として様々な問題が発生する組織になってしまいます。職員の大量離職や、虐待事例の頻発は、誰も組織の在り方を見直さず、ただただ漫然と兼任状態で組織を運営してきたことのしっぺ返しに他ならないのです。
組織全体がどのように成り立っているのかを冷静に見つめ直し、自分たちの組織が今どういう状態にあるのかを分析する機会は中々無いと思います。一度、以下にお伝えする方法で組織を分解して考えてみましょう。
3.組織図を書いてみよう
さて、ここで伺いますが、読者の皆様は自分たちが所属している法人の組織図を書くことはできますか?
組織図など、そもそも作成すらしていない、という法人が数多くあるかと思います。
もしくは、組織図は策定し、ホームページに掲載しているが、それは遥か昔のものであって、現在の組織構成から大きく乖離しているという法人も散見されます。
毎年、組織図を見直している経営者・経営陣はどのくらい存在するでしょうか?
統計データは無いので筆者の感覚になりますが、ほとんどの法人では、自分たちの組織がどのような機能から成り立っているのかを具体的に書き表すことができていません。これでは、組織全体を適切に管理し、成長発展させることはおろか、継続していくことすらも難しくなってしまうでしょう。
毎年書き直されるヤマト運輸の組織図
例えば、クロネコヤマトの宅急便で有名なヤマト運輸株式会社は、組織図をホームページ上に公表していますが、実は、毎年、同社の組織図は変化しています。過去の組織図を見ることはできませんが、毎年確実に組織図を書き直しているのです。筆者の想像にはなりますが、驚くほど変化の速い現代において、次はどのような戦略を打ち立てるべきか、打ち立てた戦略を実行するためにはどのような組織が必要なのかを、日々経営陣が考え、行動に移しているからこそ、組織図が必然的に書き換わっていくのだろうと思います。
「そんな巨大企業と介護事業者を比較されても困る」というお叱りの声が聞こえてきそうですが、敢えて続けます。
全ての事業体、全ての法人にとって、組織図を書くという取組みは絶対に必要です。
上場企業だからできることだ、という精神でいては、待っているのは衰退です。 当事者意識をもって、取り組んでみてください。
手書きでOKです。まずは大きな紙とペンを準備して下さい。
法人のトップに据えられるのは代表者です。社会福祉法人であれば理事長です。その下部組織には何があるでしょうか。理事会でしょうか。皆様の法人では、理事会は適切に機能していますか?実態として、法人本部が法人のあらゆることを統括し、実行しているのであれば、理事長の下の組織図として書き出される組織は「法人本部」となるかもしれません。
では、法人本部は何をとりまとめているのでしょうか。
おそらく、その下部組織には、職員の入退社やあらゆる雑務を司る総務部があり、他には、営業部、人事部、広報部、経理部、法務部などが必要な機能としてあるはずです。
自分たちの法人に必要な組織を可視化する意義
ここで、「うちの法人には人事部や法務部など存在しない。法人本部が全部まとめてやっているのだ」という意見があるかもしれません。
しかし、ここでは法人が備えている、あるいは必要な機能を冷静に分解して考えることが大切です。法人本部は「何でも屋」ではありません。事業を運営していると、人が必要です。採用しなければなりません。採用した人を的確に労務管理することも重要になります。評価もしなければなりません。これらを司る部署・機能が「人事部」です。
法人を運営していると、色々な法的な問題に直面します。例えば、配食委託業者等の事業者と契約を締結しなければなりません。契約内容をチェックする必要があります。職員がハラスメントの被害を訴えています。適切に法人として対応しなければなりません。これらを司る機能が「法務部」です。法人の資金繰りをどうすれば良いだろうか。借入れを起こすべきだろうか。こういった資金繰りに関する戦略を考え、実行する部署が「財務部」です。
法人を適切に運営していこうと思うと、必要な部署が何であるかが自ずと理解できるようになってきます。
「我々の法人に必要な組織って何だろう?」というワークショップを幹部クラスで実践してみて下さい。
最初は他社などの見よう見まねで結構です。一度、大きな模造紙でもホワイトボードでも、書き出して、可視化してみることが大切です。
さぁ、では、出来上がった組織図を見て下さい。
その後に、それぞれの部署に誰を配置するのかを考えて下さい。
大切なことは「特定の人ありきで組織図を考えないこと」です。それをしてしまうと、必要な組織図を書き出すことはできません。法人にとって必要な部署が何であるかをまず書き出し、その後、その部署に誰を配置することができるかを考えるのが正しい順番です。
この作業を進めていくと課題が立ちはだかります。
そうです。その部署に配置できる人がおらず、空白になってしまう、または、一部の「できる職員」に仕事が集中し、その人があらゆるポジションを兼任し、業務過多に陥ってしまうはずです。
これが皆様の組織で実際に起こっている「適材適所に人を配置することができていない」という問題なのです。その空白を埋め、兼任状態を解消していくために必要なことは、必要な人材を外から連れてくる(採用する)、または、内部の人を育てる(育成する)のどちらかです。
4.悲観せずに実践していこう
ここまで作業を行うと、多くの人は悲嘆に暮れます。やらなければならないことが膨大な量に感じるからです。ですが、心配する必要はありません。
介護事業者だけではなく、日本中のあらゆる法人が同じ問題で苦悩しています。
この苦悩は実は経営者が日々直面している課題であり、事業を成長させるために立つべきスタートラインなのです。この苦悩に直面することが「経営すること」と言っても過言ではありません。