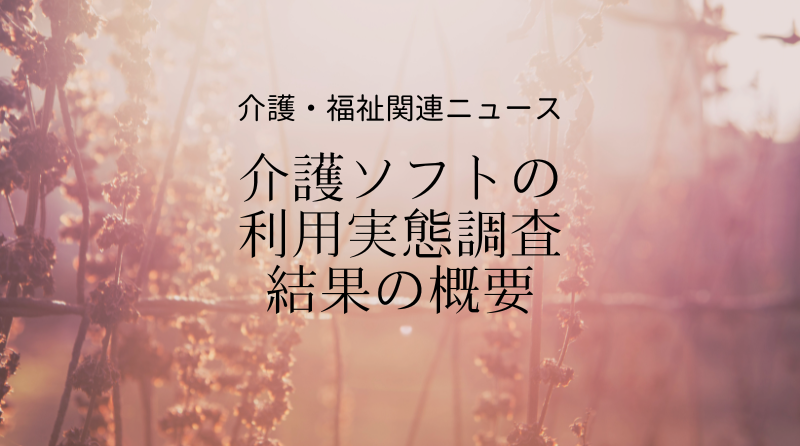現在、社会保障制度全般でDX(デジタルトランスフォーメーション)が推し進められています。介護分野でも、2025年を目標に全国共通のプラットフォームを使って介護情報のやり取りができる仕組みが実現しようとしています。前提となるのが介護事業所のICTインフラ整備です。そこで、このほど、介護等業務等支援ソフトウェア(以降、介護ソフト)の利用状況などに着目した厚生労働省の老健事業による調査結果が公表されました。
それによると、最も需要の高い請求業務だけでなく、アセスメントやサービスの計画、提供に関する記録に活用している事業所は5〜6割であるようです。
調査の概要
この調査(「自身の介護情報を個人・介護事業所等で 閲覧できる仕組みについての調査研究(令和3年度厚生労働省老健事業。三菱総合研究所が実施)」)は、介護現場におけるデータ活用の状況や介護ソフトの導入・利用実態を把握し、情報化を推進するためにアンケート形式で行われたものです。
データは2022年3月時点のもので、サービス種別等の内訳は以下の通りです。

(【画像】自身の介護情報を個人・介護事業所等で閲覧できる仕組みについての調査研究事業「報告書」:三菱総合研究所より(以下同様)
10人未満の事業所でも過半数が請求・勤怠以外の機能を利用
この調査結果によると、約9割の事業所が何らかの形で介護ソフトを導入済みであり、請求や職員の勤怠管理以外にも利用している事業所も6割程度あることが分かりました。
以下の通り、利用者数の多い事業所ほど何らかの業務を支援するソフトを導入している割合が高まる傾向があります。また、10人未満の拠点でも、過半数が請求や勤怠管理以外の用途で利用していました。

介護ソフトのシェア率は上位3種で6割
利用されている介護ソフトの種類は、以下の2グループに分けて分析されています。
- 用途は問わず何らかの形で介護ソフトを利用している事業所(下記図・上)
- 請求や職員の勤怠管理以外にも利用している事業所(下記図・下)
ただし、いずれも上位シェアを占める介護ソフトの顔ぶれは変わらず、上位3種で全体シェアの約6割を占めています。
▼介護ソフトを利用している事業所(上位項目)

▼「請求や職員の勤怠管理以外にも利用している」と回答した事業所のみ(上位項目)

アセスメントやサービス計画の記録は5~6割
介護ソフトの具体的な用途も分析されています。それによると、請求に関する資料等の作成が最も多く、8〜9割程度となっています。アセスメントやサービスの計画、提供に関する記録については5〜6割程度でした。
また、介護ソフトを活用した情報共有の状況については、事業所内や法人内に限ると54.0%で活用されています。しかし、他事業所や他法人、医療機関、利用者家族等との情報共有はいずれも1〜2割程度に留まっています。

介護ソフトを利用していない理由は「コスト」のほか人材への課題意識
いずれの介護ソフトウェアも導入していない事業所(170事業所・分析対象データ全体の11%)には、利用しない理由も尋ねています。それによると、導入にかかる経済的コストの問題を挙げる回答が最も多く、59.4%でした。次いで「現状のまま問題を感じない」が35.9%、「導入するための人的な余力がない」が28.2%、「職員が使いこなせない」が27.1%となっています。
なお、回答時点で介護ソフトを導入していない拠点では、5割以上が「導入検討を予定していない」と回答しています。
介護のICT化に対する関心の度合いは事業所によって大きく分かれているといえるでしょう。


介護ソフトを利用していない場合の情報管理の方法
介護ソフトを導入していない事業所はどのように情報管理をしているのでしょうか。請求関連の情報管理については、「主に電子媒体で行っている」との回答割合が最多で5割弱となっています。これに対し、利用者に関する記録やアセスメント表、シフト表など請求以外の情報は「主に紙媒体で実施している」とする割合が高く、全体の6〜8割程度を占めています。

介護ソフトの乗り換えについての検討状況
本調査では利用している介護ソフトウェアの変更状況についても分析しています。このうち、実際に介護ソフトの乗り換えを検討したことがあるという回答についてご紹介します。
介護ソフトの乗り換えを検討した経験
前提として、介護ソフトを変更するかどうかの意思決定主体は法人本部等であり、調査対象の事業所には権限がないとの回答が最多で約4割となっています。
残りの6割程度の事業所でみた場合、半数弱の事業所で介護ソフトの乗り換え検討経験があることが分かりました。

一方、介護ソフトの変更を検討した結果、実際に変更したことがある事業所は4割程度となっています。

介護ソフトの乗り換えについてを検討したきっかけ
乗り換えを検討したきっかけは、費用面や業務効率の見直しが3割程度でした。
次いで入力項目やカスタマイズの柔軟さ、操作方法の分かりにくさなど機能面に関する項目が2〜3割程度となっており、事業所のニーズに合わせた機能が介護ソフトに求められているようです。

介護ソフトの乗り換えに当たっての課題
介護ソフトの乗り換えを検討する時の課題では、導入費用やランニングコスト等の費用面や変更時の人的負荷等の課題に加え、データ移行を行う手段を課題と回答した割合が約6割でした。

実際に介護ソフトを乗り換え、データ移行を実施した事業所はおよそ85%でした。これらの事業所のうち、利用者の基本情報や要介護認定情報等は5割以上がデータ連携のみで移行できていたものの、請求データのデータ連携ができた割合は約26%に留まり、手作業で行うパンチ入力での移行が約30%、データを移行する意向はあったもののそれができなかったと回答した割合も約23%ありました。

移行できなかったデータは紙に印刷して保存しているという回答が5割以上あります。そして、その結果として、移行前のデータを含む経時的なデータ分析ができなくなったり、介護ソフト以外の紙ベース保管情報を確認する非効率的な業務が発生したりと、なんらかの問題が発生するケースが3~4割程度ある、という課題が明らかになりました。

介護ソフト活用による業務改善は進むものの法人の枠を越えた連携には課題
何らかの形で介護ソフトを利用している事業所は9割程度あり、電子化されたデータによる情報共有を進めていく基盤は整いつつあることがわかりました。
しかし、一方で、情報共有の実態についてはその多くが事業所内もしくは同一法人内でのやり取りに留まっています。さらには、介護ソフトの乗り換え時には、継続的なデータ活用や業務効率化が課題となっていることもわかります。
調査報告書ではこの点について、「介護業務等支援ソフトウェアはカスタマイズ性が高いソフトウェアが多く、すべてのデータ項目を移行することは難しいが、必要な項目についてはデータ定義が統一された上で、データ移行が容易にできるようになることが望ましい」と結論付けています。