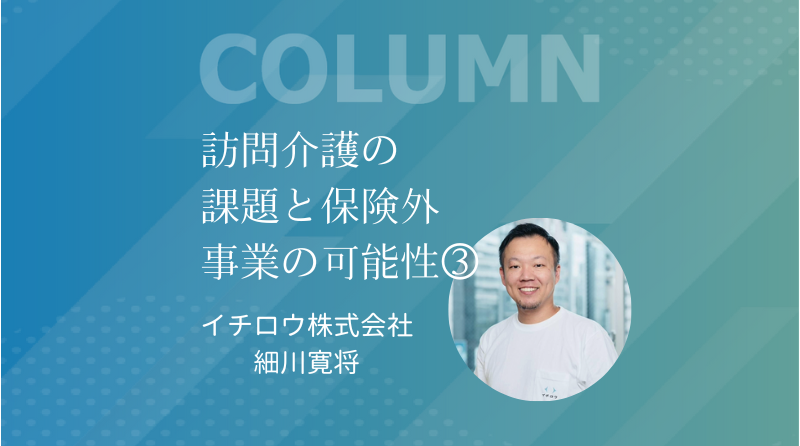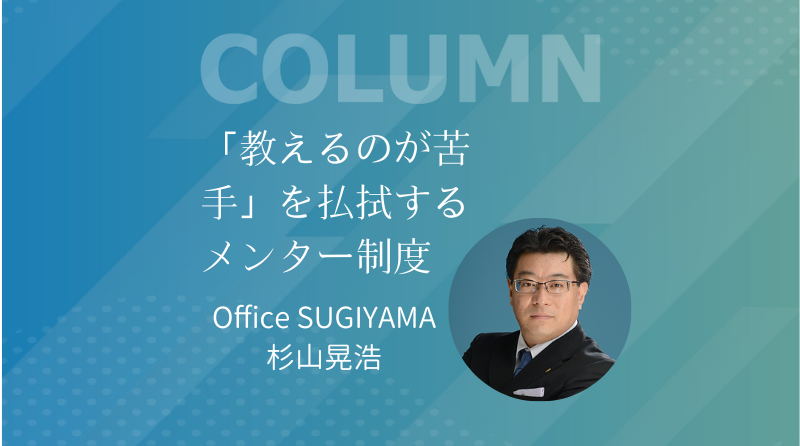この連載では、訪問介護事業の経営者・管理者の皆様に向けて、これからの訪問介護の展望をお伝えしてきました。
第1回は訪問介護事業を取り巻く環境やニーズの変化について取り上げ、第2回では保険外サービスが事業の価値を提供できる領域について考察・紹介しました。
最終回となる今回は訪問介護事業者が将来にわたって地域で必要とされるために、今、取るべきアクションや戦略について、最新トピックスや具体的な事業モデルを交えてまとめます。
持続可能な訪問介護事業所であるには、目先の制度改正への対応では足りません。
取り組むべきは、地域の中における差別化と新しい人材確保・活用戦略の立案、そして収益源の拡張です。ぜひ、今から準備しましょう。
1. 成功する訪問介護事業者の共通点:持続可能な経営に向けたキーワードは「地域密着」と「差別化」
介護保険制度の次期改正に向け、「地域軸を踏まえたサービス提供の在り方」が今、重要なテーマとなっています。
(*関連記事:介護需要に応じて全国のサービスモデルを3つに分類―「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」中間とりまとめ)
全国一律のサービス提供モデルをなぞっているだけでは、もはや生き残れない時代です。
今取り組むべきなのは、地域の実情やニーズを的確に捉えたうえで、独自のサービスやブランドづくりを進めていくことです。
地域密着型サービスにおける「差別化」ブランディングとは
地域に根ざした事業にとって、その価値を効果的に発信しブランド化する戦略が重要です。
成功している事業者の多くは、専門領域に特化したり強みを明確化しています。
例えば「認知症ケア専門の訪問介護ステーション」や「終末期ケアに強いホームヘルプ」といったように、サービス分野をあえて絞り込んで専門性を磨いている事業所があります。
「認知症サポーター養成講座の講師資格を全ヘルパーが保有」「看取りケアの経験件数が地域トップクラス」等の実績を掲げることで、該当ニーズを持つ利用者やケアマネジャーから真っ先に選ばれる存在となっています。
自社の強みを明確にして、それを前面にアピールすることがブランディングの第一歩です。
さらに、地域密着型訪問介護を成功させるには「その土地ならでは」の戦略が求められます。他地域の成功事例を研究しつつ、自社の拠点を置く地域の特性・ニーズ・資源を分析してサービスに反映させ、差別化を目指しましょう。
他事業所と比べて秀でた点を磨き上げ、信頼されるブランドを築くことで、たとえ競合が増えても「この地域にはこの事業所が不可欠だ」と思ってもらえる存在になれるでしょう。
2. これからの訪問介護に求められる人材確保・活用とは
慢性的な人手不足を背景にある訪問介護事業所にとって、経営上の最重要課題は、「人材確保・活用」と言えます。 そこで、これからの現場を支える人材について考えてみましょう。
訪問介護は一人ひとりの負担が大きく、離職率が高い傾向があります。
事業所が継続的に職邊環境を整えるべきでありことは言わずもがなですが、
今回は人材の確保・活用について、新しい制度やサービスに触れていきたいと思います。
訪問介護における人材活用の新潮流:特定技能外国人とスポットワーカー
まず、深刻化する訪問介護の人材不足に対応する手段として、「特定技能外国人材」と「スポットワーク(単発・短時間就労者)」の活用が注目されています。 (*関連記事:「外国人介護人材の業務の在り方」中間とりまとめ案―訪問系事業者の遵守事項は障害福祉も「同様」)
両者は性質が異なるものの、適切に組み合わせることで、事業の柔軟性と持続可能性が高まります。
まず、特定技能外国人材は2025年度より訪問介護でも受け入れが可能となる予定です。 外国人が特定技能1号として来日するには、介護の基礎知識と日本語能力(N4以上)を持っていなければなりません。
事業所がこうした人材を受け入れるには、登録支援機関に委託するか自社で生活支援・言語支援体制を構築する必要があります。
また、受け入れに当たっては、いきなり単独で訪問してもらうのではなく、同行訪問によるOJTを経て段階的に任せていく体制があることが望ましいです。
文化やマナーの違いを補う研修もスムーズな受け入れに必要です。安定した勤務とスキル向上が叶えば、事業所を支えるコア人材としての成長が期待できます。
一方、スポットワークは即戦力を単発・短時間確保できる新しく柔軟な雇用形態です。
マッチングプラットフォームを活用することで、有資格者を短時間で手配できます。
生活援助や買い物代行などの軽度業務はスポットワーカーに任せやすく、欠員対応や繁忙期の支援に効果的です。 さらに、実際に現場で働いてもらったうえで、相性やスキルを見極め、その後の非常勤・常勤登用につなげる“お試し雇用”の場としても機能します。
この二つの新しい仕組みを効果的に活用するには、役割分担と事前準備がカギとなります。
身体介護など責任の重い業務は特定技能人材が担い、軽度の生活援助や補助的業務をスポットワーカーがサポートする運用が理想ではないでしょうか。
こうした人材を受け入れるには、スポットワーカー用の簡易マニュアルや外国人向けの多言語対応ツールなど、現場での混乱を防ぐ支援体制の整備も欠かせません。
いずれにせよ、人材戦略において新しい潮流を受け入れ、柔軟に取り入れていくことも生き残りを図っていく上では重要な要素と言えるでしょう。
3. 訪問介護の持続可能な事業とするための新たなモデルとは
最後に、保険制度上の制約や経営環境の厳しさも増す中で、事業を安定的に継続・発展させるにはどのような戦略が有効でしょうか。 その答えとして、事業の柱を増やすことを提案します。
保険外サービスを活用した収益モデルの構築を
公的介護保険では賄いきれない高齢者のニーズに応えるため、そして事業の収益性を高めるために、保険外サービス(自費サービス)の活用は今後一層重要になるでしょう。
国も経済産業省を中心に、高齢者の生活を支えるための多様なサービス産業の振興策を打ち出しています。
2025年5月には、自治体・介護事業者・民間企業の連携による「産福共創」というコンセプトのもと、経産省の検討会が報告書をまとめました。 これは、保険外サービスを産業として促進するための戦略です。
※リンク:「高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会」の取りまとめについて(経済産業省ウェブサイト)
報告書は、「地域の高齢者福祉における課題解決と事業収益性確保の両立」を目標に掲げ、それを実現させるための具体策として”先進モデル事業の創出”や”ケアマネ等専門職との連携強化”などを示しています。
国が、保険内と保険外のサービスを両立させて、収益源を多角化する道を「目指すべき姿」として示している今こそ、訪問介護事業者が収益モデルの多角化を進めるチャンスです。
保険外サービスを活用した収益モデルの例
保険外サービスを活用した具体的な事業モデルを以下に紹介します。
生活支援・家事代行サービス
- 概要:掃除・洗濯・調理・買物代行・付き添い外出など、介護保険の訪問介護では制限のある生活援助サービスを、柔軟な内容・時間で提供する。
- 強み:有償ボランティアや地元NPOと連携して低価格帯から高付加価値プランまで用意すれば、軽度者から要介護者まで幅広いニーズに応えることができる。
見守り・安否確認サービス
- 概要: 夜間や長時間の独居高齢者の見守り、定期的な電話や訪問による安否確認サービス。
- 強み:ICT機器を設置して遠隔見守りと定期訪問を組み合わせた月額定額サービスなど、介護保険では賄えない安心を提供できる。
介護予防・リハビリ支援
- 概要: 要支援・事業対象者(いわゆる「フレイル」高齢者)向けに、自費でのリハビリトレーニング指導や運動習慣づくり支援、健康チェックサービスを提供する。
- 強み:理学療法士等と連携した訪問リハビリやオンライン運動教室などは、健康寿命延伸ニーズにマッチしたサービスといえる。
その他にも、 福祉用具の購入代行・設置サービス、住宅改修コンサルティング、高齢者向け配食、見守り機能付き住宅セキュリティ(介護大手と警備会社の協業例もあります)など、「生活のトータルサポート企業」として多面的にサービス提供することで、利用者一人当たりのLTV(ライフタイムバリュー)向上を図ることができます。
なお、サービスの多角化は自社で全てカバーする必要はありません。 民間の家事代行会社や配食サービス会社と提携して自社利用者に紹介し手数料収入を得る、地域のタクシー会社と組んで外出支援サービスを共同運営する、といったイメージで異業種や地域資源とウィンウィンの関係を築けるモデルを追求しましょう。
ケアマネジャー等から保険外サービスの情報提供を受けやすくする仕組みづくりも必要です。今後ケアプランに保険外サービスを組み込む動きも進むと考えられます。
このとき重要なのは、既存の保険サービスとのバランスです。 保険収入だけに依存すると報酬改定の影響をまともに受けてしまいますが、自費収入が一定割合あることでリスク分散が図れます。
また利用者も、状態が軽くなって保険サービスが減った場合でも、自費サービスで引き続きサポートが受けられれば安心ですし、逆に重くなったら公的サービスに移行できるといったシームレスなサービスを受けられるようになります。
保険内・外サービスの上手な組み合わせこそが、これからの地域包括ケアシステムにおける持続可能なモデルと言えるでしょう。
おわりに
今回まで3回にわたって訪問介護の未来をテーマに事業の展望についてお伝えしました。
高齢化の進展は、重大な社会課題であると同時に、新たなサービスを生み出し事業を発展させるチャンスでもあります。
経営者・管理者の皆様には、ぜひぜひ将来を見据えた戦略的な視点を持って、それぞれの会社の強みを活かした、持続可能なビジネスモデルを築いていただきたいと思います。
皆様の事業が今後も発展し、地域高齢者の安心な暮らしを支え続けられることを願ってやみません。