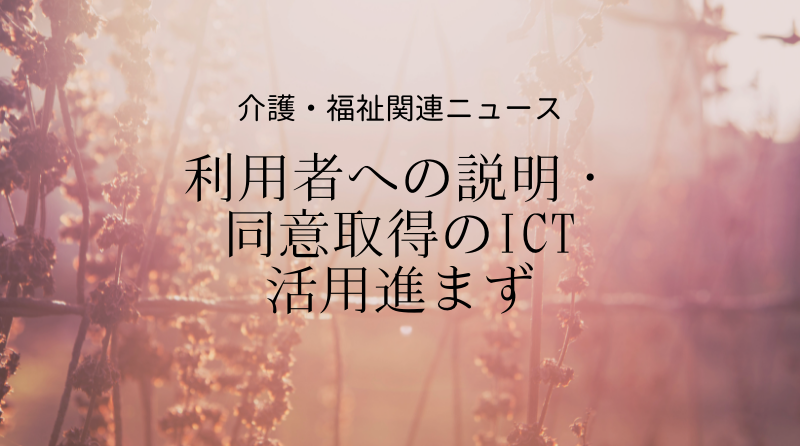2021年度の介護報酬改定の効果検証を行うための調査研究事業によって、介護施設や事業所における文書負担軽減や手続きの効率化に対する実態が明らかになりました。
2021年度の介護報酬改定では、利用者への説明・同意等に係る見直しや記録の保存等の効率化を進めるための運用見直しなどが行われていますが、計画書等について利用者や家族の同意を得る方法として、電子メール等のICT機器を活用していた事業所は6月時点で全体の2.5%以下に留まり、85%の事業所が今後の活用予定も「なし」と回答しています。
文書負担軽減等による介護現場の業務負担軽減に関する調査の目的と概要
2021年秋季に実施した2021年(令和3年)度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査結果の概要案について、3月7日に評価審議が実施され、3月17日の本分科会にて最終の取りまとめがなされました。
このうち本稿では、文書負担軽減や手続きの効率化が介護現場でどの程度進み、課題がどこにあるのか把握するための調査結果について紹介します。
調査対象は、厚生労働省保有の全国の事業所名簿(介護報酬請求事業所)をもとに下表のとおり抽出されており、調査票が郵送されています。

【画像】第209回社会保障審議会介護給付費分科会(2022年3月17日開催)資料1-3より(以下同様)
調査対象のうち、サービス種別の主要な開設主体は下記の通りでした。
・訪問介護…「営利法人」66.9%
・通所介護…「営利法人」47.5%
・地域密着型通所介護…「営利法人」70.7%
・介護老人福祉施設…「社会福祉法人」93.0%
・介護老人保健施設…「医療法人」72.3%
・居宅介護支援…「営利法人」51.6%

パソコンやタブレットの使用状況はサービス種別間で大きな格差
まず、パソコンやタブレット等の業務での使用状況に関する調査をみてみましょう。
常勤の医療・介護職員については、「居宅介護支援」で「(ほぼ)全員」業務で使用している割合が92.3%、「介護老人福祉施設」が71.7%と高い結果となりました。一方、「認知症対応型共同生活介護」では「半数未満」が40.2%、「使用している者はいない」が16.1%と、サービス種別間で導入状況に格差があることが読み取れます。

利用者への説明・同意取得に関するICT導入はいずれのサービス種別でも進まず
計画書等について利用者や家族の同意を得る方法として「電子メール」「事業者のタブレット等へ署名を行う機能」「その他の電子署名」を利用している事業所は、いずれのサービス種別でも2.5%以下と、低水準に留まりました。

電磁的方法を活用していない理由は、「電磁的方法を活用できる機器等がない」が58.3%、「電子署名等の導入にコストがかかる」が46.1%と、ハードウェアの導入に対するハードルが課題として伺えます。
また、「利用者が電子メールやパソコン等を使えない」が48.2%、「利用者に対応してもらうのが難しいと思う」が46.6%と、ICTの活用に際して利用者側の負担を懸念する意見も多くみられました。

ICTを用いた利用者への説明・同意取得については、今後の活用予定でも「特に予定はない」と回答している介護事業所が85.0%を占め、「今後、活用予定である」は8.0%に留まりました。
活用予定がある場合の方法としては、「事業者のタブレット等へ署名を行う機能」が62.3%、「電子メール」が49.4%という結果に。
反対に「特に予定はない」場合、活用したいと思う条件として、「簡単に導入できるソフト・システムがあれば活用したい」が42.6%、「介護ソフトに電子署名等の機能があれば活用したい」が36.6%、「法人が導入してくれれば活用したい」が36.5%、「安く導入できるソフト・システムがあれば活用したい」が36.1%と、導入や簡便性に対する希望が伺える回答結果となりました。

文書保存のペーパーレス化への課題は職員のサポートとシステム導入費用
利用者ごとの記録、介護報酬の請求に係る文書等について、「パソコン等で作成し出力して紙で保存」と回答した事業所が5割以上となり、「訪問介護」「居宅介護支援」ではそれぞれ71.0%に上りました。「パソコン等で作成し、電子でのみ保存」は事業所種類によって1.1%〜3.2%に留まっています。

ペーパーレス化を進めていくために必要なことに関する調査結果では、「パソコンやソフトに対する職員の苦手意識の解消、職員への研修等」との回答(認知症対応型共同生活介護より)が78.0%、「ペーパーレス化のためのシステムの導入」との回答(介護老人保健施設より)で68.9%、「パソコンやソフト、システム等の導入のための費用補助」との回答(介護老人保健施設より)で68.4%と上位を占める結果となりました。