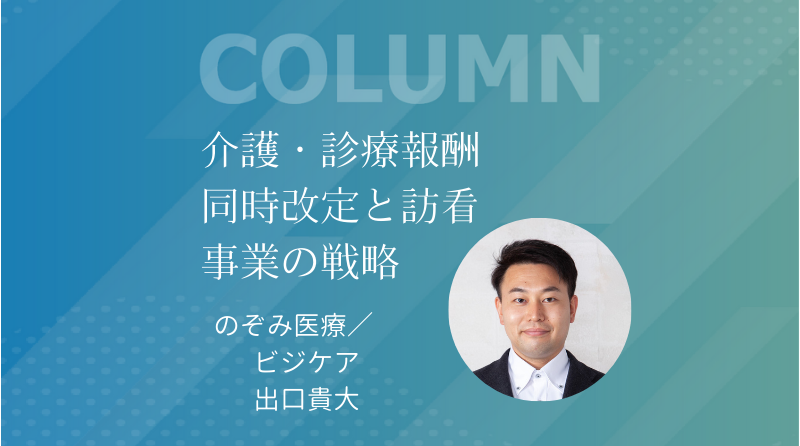「経営できる看護師を増やす」ミッションのもと、訪問看護事業所のコンサルティングや教育事業、経営に関わっております出口貴大と申します。現役取締役かつ看護師の視点から経営に役立つ情報を発信してまいります。
今回は 、2040年以降も見据えた長期的な視点から介護・医療報酬の動向をどのように考え、訪問看護事業所として動き出せばよいか、4つのポイントをお伝えさせて頂きます。
介護・医療の報酬改定の流れを読み解き、早めに動き出せるかどうかは事業所の成長・拡大を行う上で、重要なポイントになってくるでしょう。
1. 介護保険と医療保険の訪問件数のオススメのバランス
まず、介護保険と医療保険の訪問件数のバランスを考えましょう。おすすめするのが、ずばり、介護保険 : 医療保険=5 : 5の割合です。
以下、その理由についてお伝えします。
(1)介護保険ではセラピストの単価が下がり、報酬改定の方針に収入が大きく左右される
リハビリセラピストの単価は介護報酬改定のたびに下がっていて、2021年の報酬改定では2014年度時点の318単位から293単位にまで下がりました(要介護)。
それにより、看護師が80件訪問に行くのとセラピストが100件行くのとでは同じ売上か、あるいはセラピストの方が売上は低くなるという状況が起きています。
下記に、詳しくご説明します。
まず、訪問看護の売上は①平均単価②総訪問件数(または総訪問時間)で構成されています。
今回の件でお伝えしているのは看護とセラピストでは①に差が出てきているため、
同じ売上を上げようとしても②に大きな違いが出てしまうという事です。
なぜ①に差が出てきているのかというと
・セラピストの単価が報酬改定ごとに下がってきているため
・セラピスト単独でつけられる加算が少ないということ
上記2点が大きな要因となります。
加算というのは緊急時訪問看護加算、特別管理加算など、ご利用者様の状態や医療依存度、ケアの体制の状況に合わせて算定できるものです。
現状では看護とセラピストで単位の差が開いてきており、それに加えて加算の算定有無も職種で変わってくるため①の平均単価が大きく異なってくるのです。
表1はとある事業所の看護とセラピストの平均単価の違いを表したものです。
(看護の医療訪問件数比率45%、セラピストの医療訪問件数比率33%)

この単価をもとに100万円を看護とセラピストが達成しようと思うとそれぞれ何件の訪問件数が必要かを表2で出してみます。

事業所ごとのご利用者様の医療度、介護度や体制により違った結果になる場合もあるかと思いますが、多くの事業所でこれに近い状況が起きています。
在宅におけるセラピストの役割や存在は大きく、患者を支える上でも欠かせない存在です。そのため、セラピストの訪問が存続できなくなるような単価まで下がることは考えにくいですが、今後も何らかの形で改定の影響を受けることは念頭に入れる必要があります。
ますは自事業所での看護とセラピストの単価がどうなっているのか、その単価に差が出ている原因は何なのか、を調べてみるところから始めましょう。
(2)医療保険での訪問は単価が上がるが、介護保険よりもサイクルが早いのが欠点
上記のとおり看護師とセラピストの単価は大きく異なっています。
ほとんどの事業所では、看護の平均単価が約10,000円であるのに対し、セラピストは7,000円台後半くらいかと思われます。しかし、事業所によってはセラピストでも9,000円以上の単価を上げている事業所があります。
それは、難病、ターミナル、小児、精神などの医療保険領域での訪問件数が多い事業所です。
私の知っている例では、このような事業所は2021年度の介護報酬改定の影響をほとんど受けていませんでした。
医療保険での訪問は、看護師だけでなくセラピストも介入する場合が多く、多職種間での連携が必要です。
また、難病など、医療保険で介入するケースは公費による助成があり、ご利用者様に金額的な負担をかけずに複数回訪問が出来ることも多いため、介護保険に比べてご利用者様あたりの単価がかなり高くなります。
1人のご利用者様に100万円売上を上げることも多々あります。
医療保険の場合、売上の面でこうしたメリットがありますが、デメリットも存在します。
それは、介護保険に比べてサービス利用が終了となるサイクルが早いという事です。
ターミナルや難病のケースは状態の悪化も頻回にあり、入院を繰り返したりお亡くなりになったりする事も介護保険に比べて多くあります。そのため、医療メインの事業所の売り上げはジェットコースターのような曲線を描きます。安定した売上と収益を得るという観点からは、医療に偏りすぎるのはリスクが高いと言えます。
上に記した(1)と(2)の両面を考慮に入れ介護 : 医療のバランスは=5:5をおすすめします。
2.看護師とセラピストのオススメバランスと必要な対応
職員の配置については、看護師:セラピスト=6:4を意識していく事をおすすめします。
2021年介護報酬改定を巡る議論では、訪問看護事業所の人員基準について、看護職員の割合を6割とする案が、厚生労働省から出されました。
この点にも象徴されますが、今後の人口動態と病院の置かれている状況、訪問看護に本来求められる機能性を考えると、
・看護師が多く医療度の高いケアに対応できる事業所であること・24時間体制が整えられ、かつ看取りができること
というのが訪問看護事業所の必須の条件になってくる、あるいはそれを満たす事業所を増やしていく制度の流れになっていく可能性が大きいです。
そのため、現在セラピストが多い事業所は少しずつ看護師が多い体制にシフトしていく事が課題かと思われます。
しかし、これを達成するためには2つの障害を解決する必要があります。
(1)看護師の採用が難しいが、セラピストは比較的採用しやすい
病院での看護師の需要性は高く、それにコロナ禍が拍車をかけています。一方、在宅で働く看護師の割合は全看護師の3-4%とまだまだ少ない状況です。
一方、セラピストは2040年には病院で働ける場所がなくなり在宅に行くことを強いられると言われるほどの状況で、新卒セラピストの数と病院での求人枠とのバランスが崩れつつあります。そのため看護師に比べセラピストの方が採用しやすいという現状があります。
こうした状況でも看護師を採用していくためには、採用・教育計画、事業所の体制づくりを戦略的に行っていく必要があります。
詳しくはまた別の機会にお話しできればと思いますが、訪問看護事業所の管理者としての勤務経験を経て、現在、訪問看護事業所の取締役として勤務している中で、看護師が在宅領域で働く障害になっていると感じるのは
・一人で訪問をしなければいけないため、経験を積んでなければ働けないという不安や誤解
・事業所単体での経営資源の少なさによる採用や教育にかけられる時間の少なさと質の低さ
などが挙げられます。
これらを踏まえて自事業所が看護師を十分獲得できていなければ、
・なぜ看護師採用がうまく出来ていないのか(HPまでの導線がしっかりとあるのか、応募率は高いか)
・看護師が育たずに辞めてしまっているのか(フォロー体制や教育体制があるのか)
などを確認し、原因ととるべき対策の優先順位を明確にしていきましょう。
(2)看護師のマネジメントは難しい
長く在宅で働く中で、セラピストは論理的思考の方が多いように感じますが、一方、看護師は感情的に考える人が多い印象を受けます。それは、看護師に求められる業務がセラピストに比べ緊急度が高く、またストレス度の高いケースが多い、というところからも来ているものではないかと考えることができます。
そのため、想いや考えが上手く伝わらず、「経営と現場とは全然違う」、「1件1件が忙しく余裕がない」などと看護師に反発されるなど、思い描くように動いてもらえない、といった葛藤を抱く経営者も少なくないのではないでしょうか。
そういった状況を打開するためには
・社内ルールや働き方のルールをしっかりと決めておくこと
・看護師常勤で5名以上のチームを早く作ること
・看護師やチーム全体で話し合える場を毎週しっかりと作っておくこと
が大切な視点となってきます。
このうち、「看護師常勤5名以上のチームを早く作ること」について解説すると、オンコールを回し、緊急対応を行い、コミュニケーションエラーを起こさないようにするためにお勧めしています。看護師が担当するご利用者様の重症度やケアの負担度を均等にしていく事が大切です。
看護師が非常勤だとオンコールを持てない、重症のご利用者様について情報を共有したいのに相手が出勤していない、会議をしても出席できる日にちや時間帯が限られるといった障害が起きてきます。こうなると、連携やナレッジを蓄積していくのが困難となります。
常勤看護師が5名以上いると1人あたりのオンコールの負担が減り、収益を上げながら休みの調整や緊急の対応もグッとしやすくなってきます。
看護師の人数を増やしながら体制づくりにも力を入れていきましょう
3. 地域の中で連携できる事業所を作る
訪問看護は病院と比べて経営資源(教育体制や仕組みづくり、経営に対する知識、スタッフなど)が少なく外部環境の変化による影響を受けやすいという側面があります。
例えば現在は、コロナの影響で休業せざるを得ない事業所も少なくありません。また少ないスタッフで現場を回すことにより皆が疲弊していく、という場面を数多く見てきました。
こうした状況に陥るのは、自分たちの事業所だけで外部環境の変化に対処しようとしているからです。1事業所で対処するのではなく、複数事業所が協力し合うことでより強固な体制を作る事が出来ます。
例えば、
・コロナでスタッフが出勤できずに訪問が出来なくなった場合に一時的に協力し合える事業所を作っておく
・経験の少ないケースを訪問見学させてもらいお互いのスタッフを交換留学させる
・合同勉強会や合同カンファレンスをすることでナレッジの深さと広さを大きくする
・土日祝日休みの事業所は、対応できない日の訪問が発生した場合は対応できる事業所に訪問をお願いして2事業所で介入していけるようにする
などの取り組みが考えられます。
5人の事業所が2カ所あった場合、2カ所が協力し合ってしっかりとしたルールのもと経営資源を共有し合う事が出来れば10人以上の力を発揮する事が出来ます。
コロナ禍を耐え抜くためにも、在宅での基盤を強固とするためにも連携できる事業所を1カ所、2カ所持っているのと持っていないのとでは大きな違いです。
皆さんの地域で連携できる事業所はきっとあるはずです。
4.人口動態を押さえ、訪問看護以外の事業展開を考える
2025年に75歳以上の割合が30%を超えていく2025年問題が騒がれていますが、実は2040年にはもっと恐ろしい状況が控えています。
2025年に75歳以上になった方が2040年に毎日1人ずつ亡くなっていき毎日どこかでお看取りが必要になってきます。
高齢者が増えていた状況から、一気に少なくなる分岐点を迎えます。
経営者が気にしなくてはならないのは、顧客となる層の母数が減ってくるという事です。地域によっては訪問看護だけで事業を大きくしていく、維持していく事が難しくなってきます。自社の顧客層がどういう人なのか、その人数が今後どう変化していくのかを今から知っておきましょう。
もし顧客となる層が減ってくることが分かっているのであれば、1人のご利用者様に提供できる訪問看護以外のサービスをどう増やせるか、どこをキャッシュポイントとしていくかを見極めていきましょう。
訪問看護以外のサービスの増やし方を考えるポイントは
・現在訪問看護を提供しているご利用者様が活用できるサービスであること
・収益性があり、現在の経営資源の延長線上で実現できること
・経営理念との一貫性があること
です。
例えば、リハビリスタッフが多いのであれば、リハ特化型のデイサービスを行うのも視野に入れてもいいかもしれません。
小児特化でやっている事業所では、放課後等デイや施設サービスへ展開する事も可能かと思います。
自社の経営資源となる内部環境を見極めながら、今後自社がどういった外部環境(人口動態や制度の変化など)に直面するのかを今一度しっかりと見極めて対策を取って行きましょう。