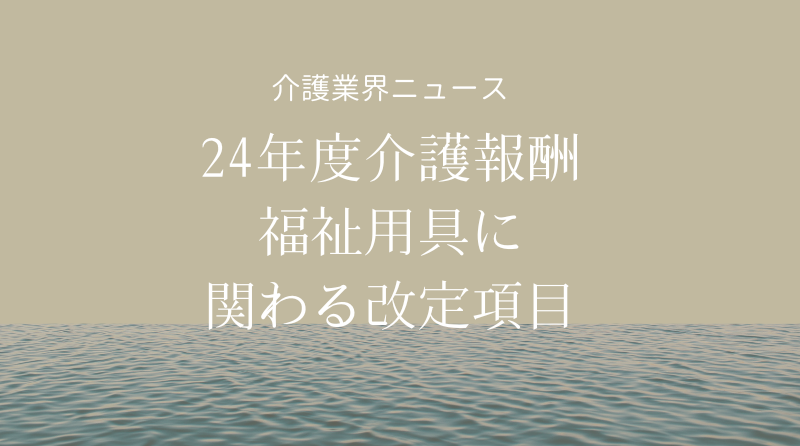2024年度介護報酬改定における「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」の大きな変更点には「貸与と販売の選択制」の導入があり、これに伴い、事業所には新たに様々な対応が義務付けられることになります。こちらについては、利用者への説明・提案に関する必要事項やその後実施すべきモニタリング方法等も3月に入って示された解釈通知で新たに示されました。
また、3月29日に発出された通知によると福祉用具専門相談員のテレワークについても新たに「考え方」が明示されています。
なお、2024年度介護報酬改定の実施日はサービスによって分かれており、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の改定は4月1日に実施されています。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の改定内容
まず、24年度改定における福祉用具貸与・特定福祉用具販売の改定項目をそれぞれ確認しましょう。
福祉用具貸与に関わる改定項目
福祉用具貸与に関わる改定項目は以下の通りです。(★は介護予防を含むもの)
- 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
- 高齢者虐待防止の推進★
- 身体的拘束等の適正化の推進★
- 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入★
- モニタリング実施時期の明確化★
- モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付
- 福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応★
- テレワークの取扱い★
- 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
- 特別地域加算の対象地域の見直し
特定福祉用具販売に関わる改定項目
特定福祉用具販売に関わる改定項目は以下の通りです。(★は介護予防を含むもの)
- 身体的拘束等の適正化の推進★
- 一部単位数の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入★
- 福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応★
- テレワークの取扱い★
両サービスの改定項目にある「福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応」(福祉用具にまつわる事故等の公表、福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直しなど)は主に行政向けの改定項目ですので、以降はそれ以外の事業者向けの改定項目について抜粋します。
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入【福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与】
感染症もしくは災害のいずれか、または両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算となります。
なお、福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)は、 訪問系サービスや居宅介護支援同様に2025年3月31日までの間、減算が適用されません。
| 業務継続計画未実施減算(新設) | |
| 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
| その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
「業務継続計画未実施減算」の適用要件
業務継続計画未実施減算が適用されるのは以下の場合です。
- 感染症や非常災害の発生時において業務継続計画(利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための計画の策定や、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画)を策定していない
- 業務継続計画に従って必要となる措置を講じていない
※ 2025(令和7)年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合は減算適用になりません。
高齢者虐待防止措置未実施減算の導入【福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与】
虐待の発生や再発防止措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の選定)が講じられていない場合、基本報酬が減算となります。
なお、福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)については、3年間の経過措置期間が設けられています。
| 高齢者虐待防止措置減算(新設) | |
| 全サービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数 |
「高齢者虐待防止措置減算」の適用要件
高齢者虐待防止措置未実施減算は、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、「虐待の発生または再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合」に利用者全員に対して適用されます。講じるべき措置とは以下の通りです。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 虐待の防止のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 上記のような高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置くこと。
これらに違反していた場合は速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、違反があった月から3カ月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告しなければなりません。また、違反の事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算されます。
※このほかの改正事項として介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況が追加されます。
身体的拘束等の適正化の推進【福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売】
身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、福祉用具貸与・特定福祉用具販売では、以下が義務化されます。
- 利用者、または他の利用者等の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
- 身体的拘束等を行う場合には、その態様、時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録する。
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入【福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定(介護予防)福祉用具販売】
一部の福祉用具について、貸与と販売の選択制が導入されます。
選択制の対象となる福祉用具の種目・種類は、「要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い」という考え方に基づき、以下の4種目となります。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対応が必要になります。
貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセスについて
選択制の対象となる福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員または介護支援専門員は、利用者に対し、以下の対応を実施する。
- 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
- 利用者の選択に当たって必要な情報(それぞれのメリット及びデメリット等)の提供
- 医師や専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者等)の意見、退院・退所時カンファレンスやサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通し等を踏まえた提案
※なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要があるなど、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない(「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」より)。
貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等について
<福祉用具貸与後のモニタリング・メンテナンス>
- 利用開始後少なくとも6カ月以内に一度福祉用具専門相談員がモニタリングを実施し、貸与継続の必要性を検討する。
※検討に当たっては、 リハビリテーション会議またはサービス担当者会議といった多職種が協議する場を活用するほか、関係者への聴取による方法も考えられる。なお、やむを得ない事情により利用開始時から6カ月以内にモニタリングを実施できなかった場合は、実施が可能となった時点で可能な限り速やかにモニタリングを実施するものとする
<特定福祉用具販売後のモニタリング・メンテナンス>
- 特定福祉用具販売計画の作成後に少なくとも1回、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認する。※目標の達成状況の確認方法は、訪問に限らず、本人や関係者へのテレビ電話装置等の活用による聴取等も含まれる
- 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める。
- 商品不具合時の連絡先を情報提供する。
モニタリング実施時期の明確化【福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与】
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図るため、福祉用具貸与計画の記載事項に「モニタリングの実施時期」が追加されます。
| 改定後の基準(下線部が新設) |
| 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。 |
モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付【福祉用具貸与】
福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することが義務付けられます。
| 改定後の基準(下線部が新設) |
| 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うものとする。
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。 |
福祉用具専門相談員のテレワークの取り扱い【福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売】
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークについて共通しているのは
- 個人情報を適切に管理していること
- 利用者の処遇に支障が生じないこと等
を前提とするということです。
その上で、3月29日発出の通知「介護サービス事業所・施設等における 情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について」によると、福祉用具専門相談員のテレワークについては以下の考え方が示されました(太字は編集部による強調)。
- 福祉用具の選定や納品、提供後の使用状況の確認、使用方法の指導や修理等の業務については、利用者の身体状況や居住環境等を確認しながら適時適切に行われる必要があり、テレワークで実施することは想定されないことから、原則として、テレワークでの実施は認められない。
- 書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる
- ただし、テレワークを実施する場合は、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具の提供に係る突発的な事態等に対応できる体制を事業所において整備しておく必要があることに、留意すること。
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化【福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与】
- 特別地域加算
- 中山間地域等の小規模事業所加算
- 中山間地域に居住する者へのサービス提供加算
上記の算定対象地域に、「過疎地域」として過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定を適用することとされている地域等が含まれることが明確化されます。

※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域
※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島
また、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)及び厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定が改正されます(下線部)。
| <改定後> |
| 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域 |
特別地域加算の対象地域の見直し【福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与】
過疎地域やその他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域は、都道府県・市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しが行われます。