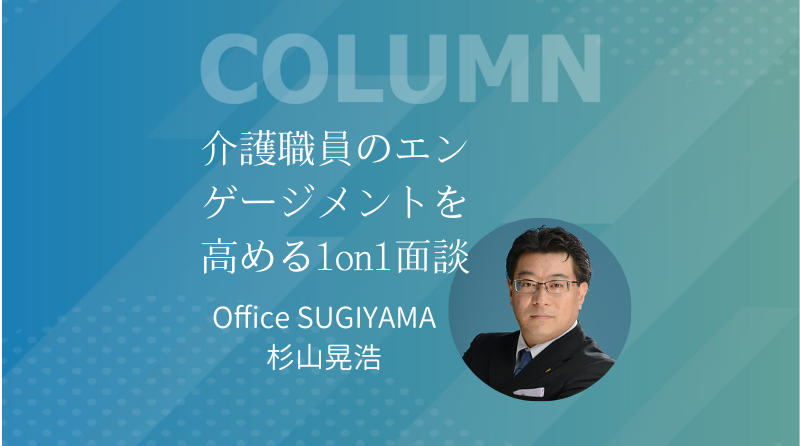4月になると新卒職員が入職してきますね。
若い方にのびのびと働いてもらい、その力を延ばすために、組織内のコミュニケーション強化は重要です。そこで参考にしていただきたいのが、世界的に認知されたリサーチベースのコンサルティング会社・ギャラップ社が公表している「2023年版 ギャラップ職場の従業員意識調査:日本の職場の現状 リーダーのための5つの洞察」です。
今月は、こちらのレポ―トを参考に、介護職員とのコミュニケーションとエンゲージメントの高め方について考えてみます。
1.米ギャラップ社によるエンゲージメント調査結果が示す日本企業の驚くべき実情
アメリカのギャラップ社は、世界的に認知されたリサーチベースのコンサルティング会社です。経営コンサルティング、従業員エンゲージメント調査、世論調査など幅広い分野でサービスを提供しています。
同社は、組織のリーダーがより良い意思決定を行い、従業員の生産性を向上させることを支援するために活動しています。そのミッションは、世界中の職場や社会において、重要な洞察とアドバイスを提供することにより、人々の生活と顧客組織の業績を向上させることです。
冒頭で紹介した同社のレポートには、日本企業にとって驚くべき結果が掲載されています。
まずは、”日本人の72%がエンゲージしていない”という現実です。
従業員エンゲージメントには、従業員の仕事や職場への関与と熱意が反映されます。従業員は、基本的なニーズが満たされ、貢献する機会、帰属意識、学び、成長する機会があるときに、エンゲージした状態になります。
その逆に、エンゲージしていない状況というのは、ただ職場にいて、時計をみつめて終業時間が来るのを待っているような状況を指します。彼らは必要最低限の努力しかせず、会社との心理的つながりが断ち切られています。生産性は最低限で喪失感が強く、職場から分断されていると感じているため、「エンゲージしている従業員」と比べて、ストレスや燃え尽きをより強く感じやすいようです。
働き方改革がなかなか進まない日本の現状を表している結果だと思います。
スタッフの多くがエンゲージメントが低い状況を改善せず何もしなければ、スタッフのエンゲージメントはさらに下がっていくでしょう。なぜなら、これまでの日本では、ずっと下がり続けているからです。
しかし同レポートは、日本再生のヒントを与えてくれています。日本の組織におけるエンゲージメントの低い従業員への対応が、組織の成長と変化を促す大きなチャンスであると伝えてくれています。
エンゲージメントの低い従業員は、もっとコミュニケーションを取り、励ましやインスピレーションを受けることを求めています。リーダーやマネジャーがこのような従業員に対して少し接し方を変えるだけで、彼らはより積極的でエンゲージメントの高いチームメンバーへと変わる可能性があります。
このレポートを受けて、あなたの職場ではどのような行動を選択しますか。ギャラップ社に調査依頼をするのか、それともとりあえずは自社で対応してみるのか、経営者によって考え方の違いはあります。
「あなたならどうするのか」ぜひ、考えて、それを行動に移してください。もしも、エンゲージメントが低いスタッフばかりだったとしたら、あなたの会社の未来はどうなっていくのか想像してみて下さい。

(画像出典:米ギャラップ社「2023年版 ギャラップ職場の従業員意識調査:日本の職場の現状 リーダーのための5つの洞察」より)
2.ギャラップ社のQ12®を介護事業所に当てはめてみると?
このレポートではギャラップ社が開発したQ12®と呼ばれる12個の質問を使って従業員エンゲージメントが測定されています。12個の質問がどのようなものかご覧ください。
【ギャラップ社Q12®】
Q01.私は仕事の上で、自分が何を期待されているかがわかっている。
Q02.私は自分がきちんと仕事をするために必要なリソースや設備を持っている。
Q03.私は仕事をする上で、自分の最も得意なことをする機会が毎日ある。
Q04.この1週間で、良い仕事をしていることを褒められたり、認められたりした。
Q05.上司あるいは職場の誰かが、自分を一人の人間として気遣ってくれていると感じる。
Q06.仕事上で、自分の成長を後押ししてくれる人がいる。
Q07.仕事上で、自分の意見が取り入れられているように思われる。
Q08.会社が掲げているミッションや目的は、自分の仕事が重要なものであると感じさせてくれる。
Q09.私の同僚は、質の高い仕事をするよう真剣に取り組んでいる。
Q10.仕事上で最高の友人と呼べる人がいる。
Q11.この半年の間に、職場の誰かが私の仕事の成長度合について話してくれたことがある。
Q12.私はこの1年の間に、仕事上で学び、成長する機会を持った。
ギャラップ社では、Q12®を活用して、調査企業ごとに従業員エンゲージメントの数値を計算しています。従業員エンゲージメントの数値が高い会社と低い会社を比較して得られた結果のうち、いくつか重要な数字をギャラップ社のサイトから引用してみました。
*出典:ギャラップ社
【従業員エンゲージメントの数値が高い会社と低い会社の比較:ネガティブ指標】
☑欠勤率で81%の差
☑事故率が64%減少
☑品質の欠陥が41%減少
☑高離職率組織では退職率が18%減少 ※年間離職率が40%以上
☑低離職率組織では退職率が43%減少 ※年間離職率が40%以下
☑患者の安全インシデント(死亡および転倒)が58%減少
ネガティブ指標を介護事業所に当てはめてイメージしてみると、次のような推測ができます。
従業員エンゲージメントが高い介護事業所では、欠勤率が大幅に低下し、事故や低品質サービスが減少する可能性があります。介護サービスの品質が向上することにより、利用者の安全が確保される可能性が高まります。また、高いエンゲージメントは従業員の満足度を高め、結果として退職率を大幅に減少させることが期待できます。これにより、熟練したスタッフの維持が可能になり、介護事業所全体の安定性とサービスの連続性が向上します。
理想的な職場のイメージが目に浮かんできますね。
【従業員エンゲージメントの数値が高い会社と低い会社の比較:ポジティブ指標】
☑収益性が23%増加
☑顧客ロイヤリティまたはエンゲージメントが10%増加
☑ウェルビーイング(ギャラップによる「生き生き」している従業員)が66%増加
☑生産性(生産記録および評価)が14%増加
☑組織市民性(参加)が13%増加
ポジティブ指標を介護事業所に当てはめてイメージしてみると、次のような推測ができます。
従業員エンゲージメントが高い介護事業所では、収益性の向上、利用者や家族のロイヤリティやエンゲージメントの増加が見込まれます。従業員のウェルビーイングの向上は、仕事への熱意や生産性の向上につながり、サービスの質を高めます。また、組織市民性の向上により、チームワークが強化され、介護サービスの全体的な効率性が高まる可能性があります。これらはすべて、介護事業所のサービス品質と効率性の向上、そして結果としての利用者満足度の向上に寄与するでしょう。
こちらも、素晴らしい職場のイメージが目に浮かんできますね。
3.ギャラップ社のQ12®を介護事業所で活用してみよう!
それでは、ギャラップ社のQ12®を活用して、介護事業所のスタッフのエンゲージメントを高めるためにはどのようなことをする必要があるのでしょうか。
次の6つのことにチャレンジしてみましょう。
【従業員エンゲージを高める6つのチャレンジ】
①役割と期待値の明確化:従業員が自分の役割と期待される成果を理解できるようにします。
②必要なリソースの提供:業務遂行に必要な設備やサポートを提供します。
⓷強みを活かす機会の創出:従業員が得意とする業務に取り組めるようにします。
④定期的なフィードバックと認知:良い仕事に対しては積極的に褒め、認める文化を育みます。
⑤個人の成長をサポート:研修やキャリア開発の機会を提供します。
⑥組織の使命と個々の貢献の結びつけ:従業員が自分の仕事が組織の目標にどう貢献しているかを理解できるようにします。
このうち、①役割と期待値の明確化を実現するためには、次の4つのステップに基づいて行動してください。
①ジョブディスクリプション(職務記述書)の作成・更新:各職種についての役割、責任、期待される成果を明記したジョブディスクリプションを作成または更新します。
②目標設定のプロセスの導入:個々の従業員との目標設定ミーティングを定期的に実施し、短期・長期の目標を明確にします。
③透明な評価基準:達成すべき目標に対して、どのような基準で評価されるかを事前に共有します。
④継続的なフィードバック:目標に対する進捗状況や成果に関して定期的なフィードバックを提供し、必要に応じて支援や指導を行います。
規模感のある介護事業所や処遇改善加算を受給している介護事業所であれば、①~⓷は既にできていることと思います。
実は最も難しいのが、④継続的なフィードバックです。
その原因として、「フィードバック文化が組織内に根付いていない」、「フィードバックを与えるための具体的なガイドラインやトレーニングが不足している」、「フィードバックを定期的に行うシステムやプロセスが整備されていない」などが考えられます。
課題解決の方法としては、フィードバックの重要性に関する研修やワークショップを実施し、従業員とマネージャーの双方にフィードバックの技術を教育します。フィードバックを簡単に行えるシステムやプラットフォームを導入し、定期的なフィードバックの機会を設ける。また、良いフィードバックを行った従業員やマネージャーを表彰するなどして、ポジティブなフィードバック文化を促進することなどが考えられます。
現実的にフィードバックトレーニングをしようとしても、「誰にお願いしたらよいのかわからない」、「やり方がわからない」、「費用のねん出ができない」、「時間がねん出できないな」ど、いくらでもできない理由が出てきます。
そこで私から、ギャラップ社のQ12®を活用した1on1の実践を提案します。
やり方は簡単です
①部下一人あたり毎月1回15分の時間を確保する
②ギャラップ社のQ12®の問いかけをスタッフにおこなう
③前月の記録と比較し、ポジティブな回答を評価するフィードバックをおこなう
これを毎月実施すれば、【エンゲージを高める6つのチャレンジ】を実施したのと同じような効果が得られるはずです。
もしも悩める管理職がいるようならば、私が考えた「Q12対応質問シート」を活用してください。
希望者にはプレゼントいたします。
◆杉山考案『Q12対応質問シート』のひな形プレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
今月は、杉山が考えた『Q12対応質問シート』のひな形を希望者全員に無料プレゼントします。以下に当てはまる方はぜひご活用ください。
①1on1の際に、どのような質問をしてらよいかわからない方
②個人的な質問内容に踏み込んだときに『ハラスメントだ!』と言ってきそうな部下がいる方
⓷継続的なフィードバックの訓練をしてみたいと考えている方
などのいずれかに該当する方は、お気軽に下記からお申し込みください。