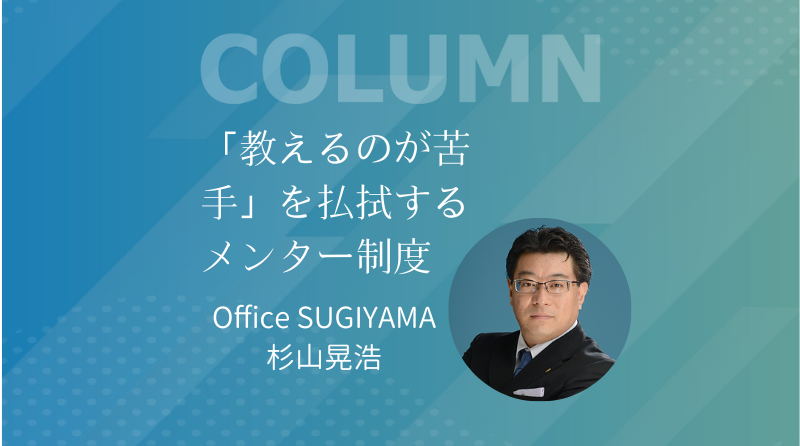「介護の仕事は丁寧で信頼できるけど、新人指導はちょっと苦手そう…」
小規模な介護事業所を運営されている皆様の中には、そんな先輩スタッフの姿に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
一人でも多くの職員に長く働いてもらうことは、どの事業所でも重要な課題です。
特に、スタッフが10名〜15名規模の事業所では、一人の離職がチーム全体に与える影響は決して小さくありません。
その定着の鍵を握るのが、現場でのOJT(On-the-Job Training)、つまり「先輩による育成」です。
しかし、育成の要となる先輩スタッフは、日々の業務で手一杯になりがち。
加えて、「人に教えるのが苦手」という気持ちがあると、管理者としても育成担当を任せにくいものです。
本稿では、”教えるのが苦手”と感じている先輩社員が自信を持って新人を支えるようになれる、メンター制度の仕組みづくりをご紹介します。
これは単なる新人育成策に留まらず、処遇改善加算における職場環境等要件で求められる「新人介護職員の早期離職防止のための取組」を具体化し、実効性を高める重要な取り組みです。
ぜひ自事業所の育成体制づくりにお役立てください。
1.なぜ介護現場では「教える」のが苦手な先輩が生まれるのか?
介護の現場で「新人育成が苦手」「OJTがうまくいかない」と感じる先輩スタッフは少なくありません。
しかしそれは、決してその人の介護スキルや仕事への意欲が低いからではありません。
多くの場合、以下のような背景が関係しています。
理由①:感覚で仕事を覚えてきたから
いわゆる”背中を見て覚える”文化の中での育った世代では、優れた技術や対応を感覚的に身につけてきたケースが多く見られます。
そのため、いざ教える立場になると「どう説明すればいいのか分からない」という壁にぶつかります。
「見て覚えて」というスタイルになりやすいのは、その人が実践を通して一心にスキルを磨いてきた証拠でもあります。
理由②:完璧な先輩でいなければというプレッシャー
「新人のどんな質問にも完璧に答えなければならない」「まちがってはいけない」という強い思い込みも、育成を苦手にする一因です。
「知識の呪い(curse of knowledge)」とも呼ばれるように、熟練者であるほど初心者が何に躓くのかを想像するのが難しくなる、という側面もあります。
結果として、質問されること自体にプレッシャーを感じ、距離を置いてしまうこともあります。
理由③:責任感の強さが重圧になる
「自分が教えた新人がミスをしたら、自分の責任だ」と感じてしまう真面目な先輩ほど、精神的な負担は大きくなります。 このプレッシャーが、育成という役割そのものへの苦手意識を増幅させてしまいます。
理由④:自身の成功体験が、変化への”壁”になることも
「自分たちの若い頃は、厳しい指導の中で必死に技術を盗んで一人前になった」という成功体験を持つ先輩ほど、現代の新人若者に合わせた丁寧なコミュニケーションやサポートの必要性を、頭では理解していても、心から納得しきれできていないこと場合があります。「自分ができたのだから、相手もできるはず」という無意識の思い込みが、教え方のアップデートを阻んでしまうのです。
管理者が理解しておきたいポイント
こうした背景を理解せずに「教えるのが下手だから」「向いていない」と決めつけてしまうと、本来頼れる先輩スタッフの意欲を下げてしまいかねません。 まずは管理者自身が「教えるのが苦手なのは、あなたのせいではない」と共感し、安心して育成役を担える仕組みづくりの土台を整えることが大切です。
2. 成功の鍵は「役割の再定義」。“先生”ではなく“一番の味方”になるメンター育成
介護現場でメンター制度を導入する際に最も重要なのは、「メンター=教える人」という固定観念を捨てることです。管理者も先輩も、そして新人自身も、“教える側・教わる側”という上下の関係から離れ、「メンター=新人の一番の味方」としての新しい役割を共有することが、成功の第一歩になります。
メンターにお願いしたい役割
メンター制度の目的は、「新人を教育すること」ではなく、「新人を孤立させないこと」です。
そのために、先輩スタッフには以下のような役割をお願いしましょう。
- 相談相手:新人が職場で孤立しないよう、最初に声をかけられる“話しやすい人”になる
- 橋渡し役:専門的な質問や答えづらい内容は、他のスタッフや管理者につなぐ
- 聞き役:自分の新人時代の経験や失敗談を交えながら、不安や悩みを受け止める
- 声かけ役:日々の業務中に意識して一言かける
メンターが「しなくていい」こと
メンター制度を形骸化させないためには、「やらなくていいこと」を明確にしておくことも大切です。
- すべての業務を完璧に教える必要はありません
- 新人のミスの責任を一人で背負う必要はありません
- プライベートな相談に無理にのる必要はありません
このように役割を限定することで、「教えるのが苦手」と感じていた先輩も、「これなら自分にもできる」と安心してメンターを引き受けやすくなります。
「一番の味方」が生む心理的安全性
メンターを“先生”ではなく“味方”と位置づけることは、職場の心理的安全性を高めるうえでも非常に有効です。
上下関係の中では、新人は「こんなことも知らないと思われたらどうしよう」と萎縮し、分からないことを聞けない、ミスを隠す―といった悪循環が起こりがちです。
しかし、「味方」という関係性があれば、新人は安心して不安や疑問を話せるようになります。 この「分からない」と言える文化こそが、重大な事故を防ぎ、職員がのびのびと成長できる土壌となるのです。
3.小さな事業所だからできる!自信がつくメンター制度、3つの具体策
「メンター制度」と聞くと、大きな法人や研修体制の整った事業所だけが導入できる仕組みと思われがちです。
しかし、介護現場では小規模だからこそできる温かいサポートが大きな強みになります。
ここでは、明日からでも始められる「シンプルで続けやすいメンター制度」の3つのステップを紹介します。
ステップ①:頼み方を工夫し、安心して引き受けられる形にする
最初のポイントは、メンターを「どうお願いするか」です。
「新人の指導をお願いします」ではなく、“味方になってほしい”という依頼の仕方が重要です。
たとえば、休憩時間など落ち着いたタイミングで個別に声をかけます。
「〇〇さんの丁寧な対応は本当に助かっています。その姿を、新人の△△さんにも一番近くで見せてあげてほしいんです」
「業務の指導はみんなで行うので、あなたには△△さんが気軽に話せる“味方”になってほしいんです」
このように役割を限定し、心理的負担を減らすことで、教えるのが苦手な先輩でも前向きに引き受けやすくなります。
また、メンターと新人のマッチングも大切です。
性格や会話のテンポなど、人柄の相性を重視してペアを組むと、自然に信頼関係が生まれます。
共通の趣味や出身地など、仕事以外の共通点をきっかけに雑談ができる関係が理想です。
ステップ②:「話す機会」を仕組みとして組み込む
「何かあったら相談してね」と伝えるだけでは、多くの新人は遠慮してしまいます。
だからこそ、事業所として“話す機会を仕組み化”することが重要です。
具体的には、次のような方法が効果的です。
- 週1回の5分ミーティング
管理者が「5分だけ話そうか」と声をかけ、メンターと新人が軽く雑談する時間を作ります。
「仕事どう?」だけでなく「週末はどうだった?」といった雑談が、信頼関係の土台を築きます。
毎週決まった曜日・時間に設定することで、自然と習慣化できます。
- 交換ノートの活用
対面で話しにくいことも、文字なら伝えやすくなります。
新人が「今日〇〇様への声かけが難しかった」と書いたら、先輩は「わかる、私も新人の頃は同じだったよ」と共感の言葉を返すだけでOKです。
完璧な答えを出す必要はなく、「共感」こそが新人の安心感を育てます。
管理者が時々ノートを確認することで、双方の様子を把握できます。
ステップ③:管理者が「メンターのメンター」になる
制度を続けるうえで最も大切なのが、管理者がメンターを支えることです。 任命して終わりではなく、定期的に声をかけて努力を認めましょう。
>「〇〇さん(新人)が、先輩のおかげで質問しやすくなったと言っていました。ありがとう。」 >「二人の会話が職場の雰囲気を良くしてくれているね。」
このように具体的な成果をフィードバックすることで、メンター自身の自信が育ちます。
また、メンターからの相談には最優先で対応し、決して孤立させないようにしましょう。
管理者が「支える側を支える」ことで、職場全体の心理的安全性が高まります。
まとめ│小さな積み重ねが“育つ職場”をつくる
小規模な介護事業所でメンター制度を成功させるポイントは、「教えるスキル」ではなく「寄り添う姿勢」にあります。
先輩スタッフには「教える人」ではなく「新人の一番の味方」としての役割をお願いし、コミュニケーションの機会を仕組みとして設けること。そして、その努力を管理者が継続的に承認・支援することが何より大切です。
この小さな取り組みは、若手職員の定着や離職防止といった直接的な成果だけでなく、「教えるのが苦手」と感じていた先輩スタッフにとっても、新しい成長ややりがいを感じるきっかけになります。結果として、職場全体のチームワークが強まり、介護サービスの質向上にもつながります。
制度と聞くと少し構えてしまうかもしれませんが、難しく考える必要はありません。
まずは、あなたの事業所の中で——新人が安心して話せる「一番の味方」を一人つくること。
その一歩が、育つ職場文化づくりの第一歩になります。
◆読者プレゼント:復職可能診断チェックリスト◆
「まず何から始めようか」とお考えのあなたへ。
メンターと新人の最初のコミュニケーションを円滑にするためのツールをご用意しました。
このシートは、メンター(先輩)とメンティー(新人)であるお二人が、リラックスしてお互いのことを知り、最初の会話を楽しむためのツールです。
そこに正解・不正解はありませんので、気軽な気持ちでご活用ください。
希望者全員に無料プレゼントしますので、お気軽に下記からお申し込みください。