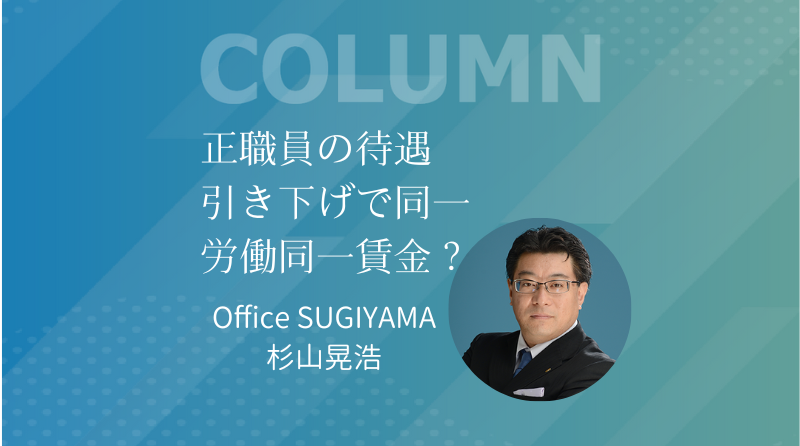正規職員の手当を削って非正規職員と同一労働同一賃金化を図る手法を違法だとして、済生会山口総合病院の正規職員9人が手当減額分の支払いを求めていた訴訟で、山口地方裁判所はこれを、請求棄却としました。2024年5月のことです。請求棄却とは、民事訴訟において原告の請求に理由がないと判断して、請求を退ける判決のことです。
これは、正規職員の待遇を引き下げることによって正規・非正規間の格差を解消する手法を容認する初の司法判断となりました。今回はこの判決が、介護業界にどのような影響を及ぼすのか、人事的な対応をどのようにすればよいのかを検討してみました。
1.正規と非正規職員の待遇格差を是正する同一労働同一賃金の考え方
近年、日本の社会では正規・非正規職員間の待遇格差是正が大きな課題として叫ばれています。そんな中、正規職員の待遇を引き下げることで格差を解消する手法を容認する司法判断が下され、大きな波紋を呼んでいます。特に、慢性的な人材不足に悩む介護業界では、この判決が今後の雇用体制やサービスの質に大きな影響を与える可能性があり、人事関係者を筆頭に注目が集まっています。
介護業界の人材不足の背景には、低賃金、重労働、厳しい労働環境などが挙げられますが、正規・非正規間の待遇格差も大きな要素でしょう。
介護現場では正規職員と非正規職員が共に重要な役割を担っていますが、両者の間には賃金や福利厚生、昇進の機会など、待遇面で大きな格差が存在しています。
しかし、21年に全面施行された「パートタイム・有期雇用労働法」は正社員と短時間・有期雇用労働者の職務や責任の範囲が同一である場合、待遇に不合理な差を設けることを禁止しており、介護事業者も例外ではありません。
2.前例のない判決!正規職員の待遇引き下げを容認した司法判断の中身とは?
今回の司法判断は、正規職員の待遇を引き下げることで非正規職員との格差を解消するという、これまで否定的に見られてきた手法を容認した点で画期的です。この判断は、介護事業所の経営や雇用体制などにも影響を与えると考えられ、最終的には介護サービスの質にも関わる可能性すら秘めています。
そのため、内容を正しく理解し、今後の動向を見守る必要があります。
判決について詳しく見ていきましょう。
(1)訴訟の概要と判決と注目ポイント
今回の訴訟は、正規職員が、非正規職員との待遇格差を解消するための手段として手当削減をしたことを不当として、事業者に手当減額分の支払いを求めたものです。つまり同一労働同一賃金実現のためには、非正規職員に対して正規職員と同様の手当を支払うべきであり、正規職員の手当を減額することは、同一労働同一賃金の趣旨に反するという主張です。
労働者側の弁護士は病院の対応について、『病院は黒字。同一賃金は正職員の手当を非正規に払って実現すべきだ。変更は人件費削減が目的で合理性はない』と主張しています。
一方で、病院側の弁護士は『パートタイム・有期雇用労働法8条で正規・非正規間の不合理な待遇差が禁止された。これを契機に時代に合わない手当を組み替えたもので合理性はある』と主張しています。
今回の判決を出した裁判所は、病院の対応について『職員全体の不利益は小さい』と判断しました。
注目すべきは、裁判所が判決の中で、「制度が根本的に変わる以上、支給条件の大幅な変更もやむを得ず、新しい制度設計を選択する合理性と相当性が認められる」と判断を下したことです。つまり待遇格差を解消するための一つの方法として、正規職員の待遇を引き下げることを容認したということです。
従来の判例では、非正規職員の待遇を引き上げることで格差を解消するのが一般的でしたが、今回の判決は、正規職員の待遇を引き下げることも選択肢の一つであることを示した点が、多くの注目を浴びる理由となっています。
(2)今回の判決のポイントは?同一労働同一賃金に対する従来の考え方との違い
今回裁判所は、病院の対応に「合理性」が有ったかどうかを判断するために、以下のとおり5つの着眼点を示しています。
- 就業規則変更で受ける不利益の程度
- 労働条件変更の必要性
- 変更後の就業規則の相当性
- 労働組合等との交渉状況
- その他の事情
そして、その結果、「パート・有期法8条を契機に正職員のみに手当を支給し続けるか検討することは法の趣旨に添う」と指摘して、労働条件変更の必要性を認めました。ちなみに裁判所は、労働条件変更前と変更後の総賃金原資は0.2%減であり、職員全体の不利益は小さいと判断しました。
つまり、同一労働・同一賃金に対応するために、会社の規定を根本的に見直す過程では、総賃金の原資が現状維持できていれば、正職員の一部に不利益がある規定の変更も適法であるとの見方ができます。
(3) 介護事業所における賃金・待遇格差の実態
厚生労働省の「令和3年賃金構造基本統計調査」によると、介護事業所における正規職員と非正規職員の平均月額賃金は約10万円の差があります。また、賞与や退職金、福利厚生面でも大きな格差が存在するのが実状です。
例として、正規職員には家族手当や住宅手当などの各種手当が支給される一方、非正規職員には支給されないケースが多く見られます。日本では多種多様な手当を使って労働者の待遇に変化をもたらしてきました。その根本には、賞与や退職金の算定基礎額として基本給が利用されることが多く、基本給をできるだけ上げたくないといった事業所側の考え方もあるようです。
また、非正規職員の昇給や昇進の機会も、正規職員に比べて限られているのが現状です。介護事業所のように、就労時間に職員が就労していることが売上(介護報酬)に直結する業態では、役割として同じ仕事をしていても、長時間売上を生み出してくれる正規職員を重視していくことは当たり前だと私は考えています。人材不足が慢性化している介護業界ではなおさらです。
(4) 今回の判決は経営基盤の弱い事業所にとっては朗報か?
今回の判決を受けて、介護事業所は、正規・非正規職員間の待遇格差是正に向けてどのような対策を講じる必要があるのでしょうか。
まず、今回の判決は、特に非正規職員の待遇を引き上げるだけの体力がなく、経営基盤の弱い介護事業所にとって朗報だと私は考えます。、同一労働・同一賃金の理念を実現するために社内制度を整備するうえで、<法人全体で人件費を検討する>という筋道が示されたからです。つまり、正規職員の待遇を見直すことも含めて、総人件費をより効果的に従業員に分配するという選択肢が加わるかもしれません。
具体的な制度設計に際しては、職務内容や責任に応じた公平な賃金体系の構築、非正規職員の正社員化の推進、人材育成の強化などが求められます。
今回の判決は、介護業界の人材不足解消、サービスの質向上に向けた重要な契機となる可能性を秘めています。介護事業所の体力に応じた同一労働同一賃金の実現がやり易くなりました。
なお、当然のことですが、控訴審の行方を見定めることは必要です。
3.今回の裁判例を受けてこれからの介護事業所の人事制度の在り方を考える
今回の裁判例を受けて、介護事業所が処遇制度を設計したり、見直す際には、一般的な注意点に加えて、介護業界特有の事情を考慮する必要があります。
以下に、主な注意点をまとめておきますので、参考にされてください。
(1)介護の仕事の専門性と多様性を考慮する
介護の仕事は、身体介護、生活援助、相談援助など、多岐にわたる業務内容と、利用者一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな対応が求められる専門性の高い仕事です。処遇制度を設計する際には、これらの業務の特性を踏まえ、それぞれの職務に必要な知識、スキル、責任を適切に評価できるような仕組みを構築することが重要です。
例えば、身体介護の経験が豊富な職員、認知症ケアに特化したスキルを持つ職員、コミュニケーション能力に長けた職員など、それぞれの専門性や強みを評価できるような制度設計が必要です。
(2)経験年数だけでなく、能力や成果を重視する
従来の介護業界では、経験年数に基づいた年功序列型の賃金体系が一般的でした。しかし、経験年数だけでなく、職務内容や責任に応じた処遇の必要性がカギとなります。
そのため、経験年数だけでなく、職員の能力や成果を適切に評価できるような仕組みに転換していく必要があります。能力評価、成果評価、多面評価など、様々な評価方法を組み合わせることで、より公平で納得性の高い評価制度を構築することができます。
(3)チームワークと協調性を重視する
介護の仕事は、チームで連携して利用者を支えることが重要です。そのため、個人の能力や成果だけでなく、チームワークや協調性も評価できるような処遇制度を設計することが大切です。
例えば、チーム目標の達成度、他の職員への支援、コミュニケーション能力などを評価項目に含めることで、チームワークを促進し、より質の高いサービス提供に繋げることができます。
(4) 感情労働(emotional labor) の評価
介護の仕事は、利用者との密接な関わりの中で、感情的な負担を伴う労働が大きい仕事です。処遇制度を設計する際には、この感情労働を適切に評価できるような仕組みを検討する必要があります。
例えば、利用者とのコミュニケーション能力、共感性、ストレス耐性などを評価項目に含めることで、 感情労働に対する評価を可視化し、職員のメンタルヘルスケアにも繋げることができます。
なお、Emotional labor(感情労働)とは、利用者(顧客)に対して心理的にポジティブな働きかけをして報酬を得る労働で、肉体労働や頭脳労働に並ぶ労働の分類です。
(5)人材不足と離職率の高さへの対応
介護業界は、慢性的な人材不足と高い離職率が課題となっています。処遇制度を設計する際には、これらの課題を克服し、人材の確保と定着を促進できるような魅力的な制度にする必要があります。
例えば、昇給や昇格の機会を増やす、資格取得支援制度を充実させる、働き方改革を推進することでワークライフバランスを改善する、リファラル採用の結果を評価するなど、職員のモチベーション向上と定着率向上に繋がるような取り組みが必要です。
(6)柔軟性と透明性を確保
介護業界は、高齢化の進展や制度改正など、常に変化が求められる業界です。処遇制度についても、社会情勢や事業所の状況に合わせて、柔軟に見直しできるような仕組みにする必要があります。
また、評価基準や評価プロセスを明確化し、職員に公開することで、制度に対する理解と納得感を高め、透明性を確保することが重要です。
これらの注意点を踏まえ、自事業所の課題やニーズに合わせた処遇制度を設計することで、正規・非正規間の待遇格差是正を効果的に実現し、職員が働きがいを感じ、成長できるような職場環境を構築していくことができます。
4.労働基準監督署の調査に向けた準備はできていますか?
最後に、以下は、23年12月26日に厚労省から発表された資料「同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組の実施状況」から抜粋したスライドです。介護事業所にとっても重要な情報としてお伝えします。

同省では、都道府県労働局のみならず、労働基準監督署による調査を実施して、多数の事業所を指導しています。
もしも、あなたの事業所に労働基準監督署の調査が入ったらどうなるでしょうか?
もしも、あなたの事業所における同一労働同一賃金の実態について是正を求められたら、どれぐらいのコストアップになるのでしょうか?
今のうちに現状把握をしておくことで、将来のリスクを管理し易くなります。
将来のリスクが見える化できれば、優先順位を付けてひとつひとつ対策をすればよいだけです。
今回は、対策を支援するツールとして、『同一労働同一賃金説明シート』を希望者にプレゼントします。
ぜひ、この機会に労働基準監督署の調査に向けて準備をしておきましょう。
◆『同一労働同一賃金説明シート』プレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
今月は、『同一労働同一賃金説明シート』をプレゼントします。
カテゴリーごとにチェック項目や準備に対応するためのサービスなども例示してあり、みなさまの事業所で不足している部分などを簡単に補填できるようにしてあります。
さらに、社員評価欄を付けたことで、より整合性を高め、労使トラブルの防止に繋がる契機となります。
積極的に活用いただくことをおすすめします。
お気軽に下記からお申し込みください。