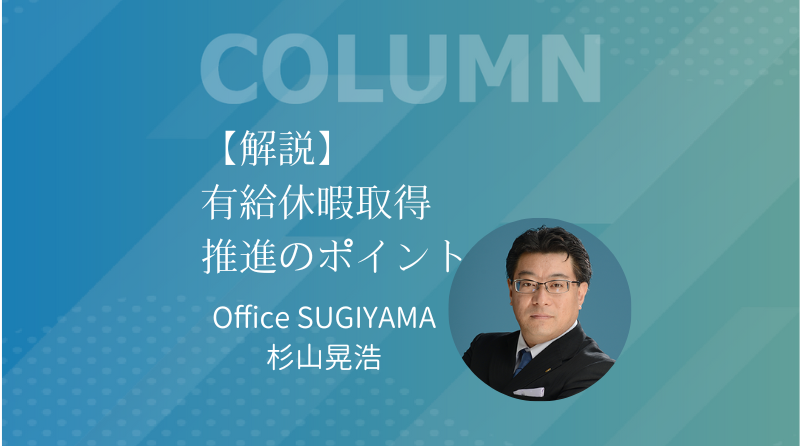介護職員等処遇改善加算を算定するために、介護事業所が満たす必要のある「職場環境等要件」には、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」という項目が含まれています。
2025(令和7)年度以降に適用される予定の「職場環境等要件」と24年度以前のものを比べると、「生産性向上」に関する取り組みと並んで有給休暇の取得推進についても、介護事業者に具体的な取得目標を定めるなどさらに踏み込んだ対応を求めていることがわかります。

そこで今回は、有給休暇休暇の取得しやすい「目標の立て方」や「職員等のコミュニケーション」、「環境整備」について考えてみましょう。
1.介護事業所が有給休暇取得促進に取り組むべき理由と考えられる効果
介護業界は、慢性的な人手不足や業務の負担感から、有給休暇の取得率が低い傾向にあります。しかし、肉体的にも精神的にも負担が大きい介護事業所こそ、従業員の心身の健康を保ちつつ、より質の高いサービスを提供し続けるために、有給休暇の取得促進に取り組むべきです。
介護事業所で従業員の有給休暇取得を推進するメリットとしては、例えば以下のような要素が考えられます。

事業者に課せられた義務だからというだけではなく、事業戦略として有給休暇取得促進に向けた取り組みを行う必要があるといえるのではないでしょうか。
2.有給休暇の具体的な取得目標を考えてみよう
それでは、有給休暇の取得を促す上で、具体的にどのような目標を立てればよいでしょうか。5つの切り口についてその効用を考えてみました。ぜひ参考にしてください。
①「年間取得日数」を指標とした目標
目標の設定例: 年間取得日数10日以上、または付与日数の70%以上取得
ポイント
・全職員に共通の目標を設定することで、有給休暇取得の意識を高めます。
・個人の状況に合わせて、目標値を調整することも可能です。
②「連続休暇」の取得を指標とした目標
目標の設定例: 年に1回は5日以上の連続休暇を取得
ポイント
・長期休暇を取得し、心身のリフレッシュを促します。
・旅行や趣味など、プライベートの時間を充実させることができます。
③「定期的な取得」を促す目標
目標例: 3カ月に1回は有給休暇を取得
ポイント
・定期的な休暇取得を習慣化することで、心身の健康維持を図ります。
・業務が個人に集中することを防ぎ、より効率的な働き方を実現します。
④チーム毎に設定する目標
目標例: チーム全体で年間○○日以上の有給休暇を取得
ポイント
・チーム全体で目標を共有し、協力して達成を目指します。
・チームワークの向上、相互扶助の精神を育みます。
⑤取得理由別の目標設定
目標例: リフレッシュ目的、家族との時間、自己啓発などの目的別に年間○○日以上取得
ポイント
・多様な目的で有給休暇を取得することを奨励します。
・従業員のワークライフバランスを支援します。
こうした目標に加え、半日休暇や時間単位休暇の制度を設けることも有効です。
その他にも実効性を高めるために、目標達成者への表彰制度やインセンティブを設けることも、モチベーション向上に繋がります。
これらの目標設定を通して、従業員一人ひとりが有給休暇を取得することの重要性を認識し、積極的に休暇を取得できる雰囲気づくりを目指しましょう。
3.有給休暇取得を促進するための効果的な取り組みとは
介護事業所において有給休暇取得を促進するためには、従業員が休みを取りやすい環境を作るだけでなく、休暇を取得することのメリットを理解してもらうよう、意識改革を促す必要があります。
例えば、介護スタッフに意識改革を促すための方法として、次のような文章を配布してみましょう。

意識改革と並行して、
①業務の可視化・標準化(マニュアル作成や業務フローの見直しなどが有効)
②情報共有(情報共有システムを導入するなど、スムーズな情報伝達を図り、担当者以外でも業務をフォローできる体制の構築)
③複数担当制の検討(特定の業務に複数の担当者を配置することで、一人が休暇を取得しても業務が滞らないようにする)
④業務の効率化
⑤人員配置の適正化
といった取り組みも必要です。ぜひご自身の施設や事業所において、より有効な手段を考えて実行してみてください。
介護業務の可視化・標準化の具体的方法とは
休みを取りやすい職場づくりの手段に「業務の可視化・標準化」を挙げました。
介護の仕事では、一人ひとり状況の違う利用者さんに合わせた対応が大切です。 でも、「あれ、この業務ってどうやるんだっけ?」「他のスタッフとやり方が違う…」なんて困った経験はおそらくほとんどの方がお持ちでしょう。
日常業務に追われていると、業務の見直しやマニュアル化といった作業は後回しになりがちですが、介護スタッフに理解を促し、実践に落とし込むために、次のフローで作成・導入してください。
①なぜ「可視化」「標準化」が必要?介護職員に対してメリットを伝える
介護の現場では、利用者さん一人ひとりに合わせた丁寧なケアが求められます。
もしかしたら、標準化やマニュアル化には抵抗があるかもしれません。
しかし、これらの取り組みが進んでいれば、新人スタッフもベテランスタッフも、同じやり方でケアができるようになります。手順が明確になることで、ミスやムラが減り、利用者さんに安心してサービスを提供することができます。
また、分かりやすいマニュアルやチェックリストがあれば、業務のたびに「あれ、どうやるんだっけ?」と迷うこともなくなり、時間のムダも減らせます。
さらに、業務の可視化・標準化は、チームワークの向上にも役立ちます。みんなが同じやり方で仕事をすることで、連携がスムーズになり、情報共有も活発になります。お互いに助け合い、協力し合うことで、より質の高いサービスを提供できるようになるでしょう。まずはこうしたメリットを従業員に伝えましょう② 介護職員にマニュアルやチェックリストの具体的な作成方法を伝えてみましょう
可視化・標準化のメリットを伝えたら、次は具体的な方法を教えましょう。
例えば、入浴介助のマニュアルを作成する場合、「脱衣介助」「洗身介助」「洗髪介助」など、それぞれの業務を細かく分けて手順を書き出します。写真やイラストを添えれば、さらに分かりやすくなります。
また、チェックリストを活用すれば、必要な物品の準備や利用者さんの状態確認など、重要なポイントを漏れなく確認することができます。
全体的な流れとしては以下のイメージです。
①業務を書き出す:毎日の業務を、細かく書き出してみましょう。
②業務の流れを図にする:書き出した業務を、順番に並べて図にしてみましょう。
矢印を使って、業務の流れを分かりやすく示すと、より理解しやすくなります。パソコンで「業務フロー図」を作成するのも良いでしょう。
③マニュアル化する:各業務の手順を、細かく書き込んだマニュアルを作りましょう。
写真やイラストを使うと、より分かりやすくなります。
分かりにくい言葉は使わず、誰でも理解できる言葉で書きましょう。
④チェックリストを作る:業務を漏れなく行うために、チェックリストを作りましょう。
各項目をチェックすることで、ミスを防ぐことができます。
最初は少し大変な作業かもしれません。 でも、マニュアルやチェックリストを一度作ってしまえば、その後はずっと役に立ちます。 みんなで協力して、働きやすい職場環境を作っていきましょう!
4.年次有給休暇の運用について法的に注意する点
さいごに、有給休暇について法的に注意する点をいくつかお伝えします。いくら、有給休暇取得促進の仕組みや目標を明確化しても、年次有給休暇の運用方法を間違っていれば、元も子もありません。
①付与日数
・継続勤務年数と出勤率に応じて、法律で定められた日数を付与する必要があります。
・パートタイム労働者にも、勤務日数に応じて年次有給休暇を付与する必要があります。
・正社員からパートタイム労働者になった場合、既に付与されている年次有給休暇はそのまま引き継がれます。
②時季指定
・使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、時季変更権を行使できます。
・時季変更権を行使する場合は、労働者と十分に話し合い、納得を得る必要があります。
・年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、最低年5日以上の取得をさせる義務があります。
③取得
・労働者は、自由に年次有給休暇を取得することができます。
・使用者は、年次有給休暇の取得を理由とした不利益な取り扱いをしてはいけません。
・労働者と合意すれば、時間単位で年次有給休暇を取得することができます。
④その他
・年次有給休暇は、2年間有効です。
・年次有給休暇を取得した日は、賃金を支払わなければなりません。
・年次有給休暇の買い取りは、原則として禁止されています。
・退職する場合は、残っている年次有給休暇をまとめて取得することができます。
⑤罰則
使用者が年次有給休暇に関する規定に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
最近では、勤怠システムを活用して年次有給休暇の管理を行っている介護事業所も増えてきました。一方で、未だにアナログ的な管理をしている介護事業所もあります。特に、労働基準法の規定を超える日数を超えて年次有給休暇を与えている場合には、勤怠システムで管理できないこともあります。
年次有給休暇に関して最も恐れなければならないのは、年休5日取得義務の不履行です。違反者1名あたり罰金最大30万円です。例えば5名が年休5日取得義務を満たしていなければ、150万円もの罰金を支払わなければならなくなります。同時に、経営者や管理者が6か月以下の懲役を受けなければならなくなるかもしれません。
年次有給休暇の管理とは、それほど大切なものなのです。
不安に感じている事業所では、ページ下部でダウンロードできる「年休5日取得を見える化した年次有給休暇管理簿」を活用して、年次有給休暇を管理してみてください。社労士の工夫が詰まった書式となっています。
◆『年休5日取得を見える化した年次有給休暇管理簿』プレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
今月は、労基法違反を防ぐためのツールとして『年休5日取得を見える化した年次有給休暇管理簿』を希望者全員に無料プレゼントします。
お気軽に下記からお申し込みください。